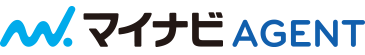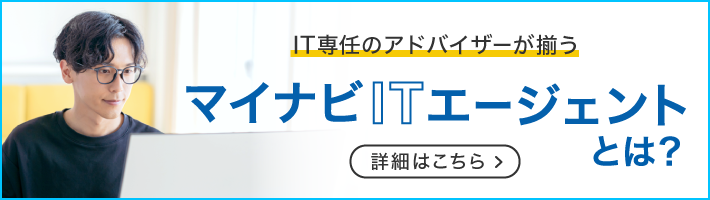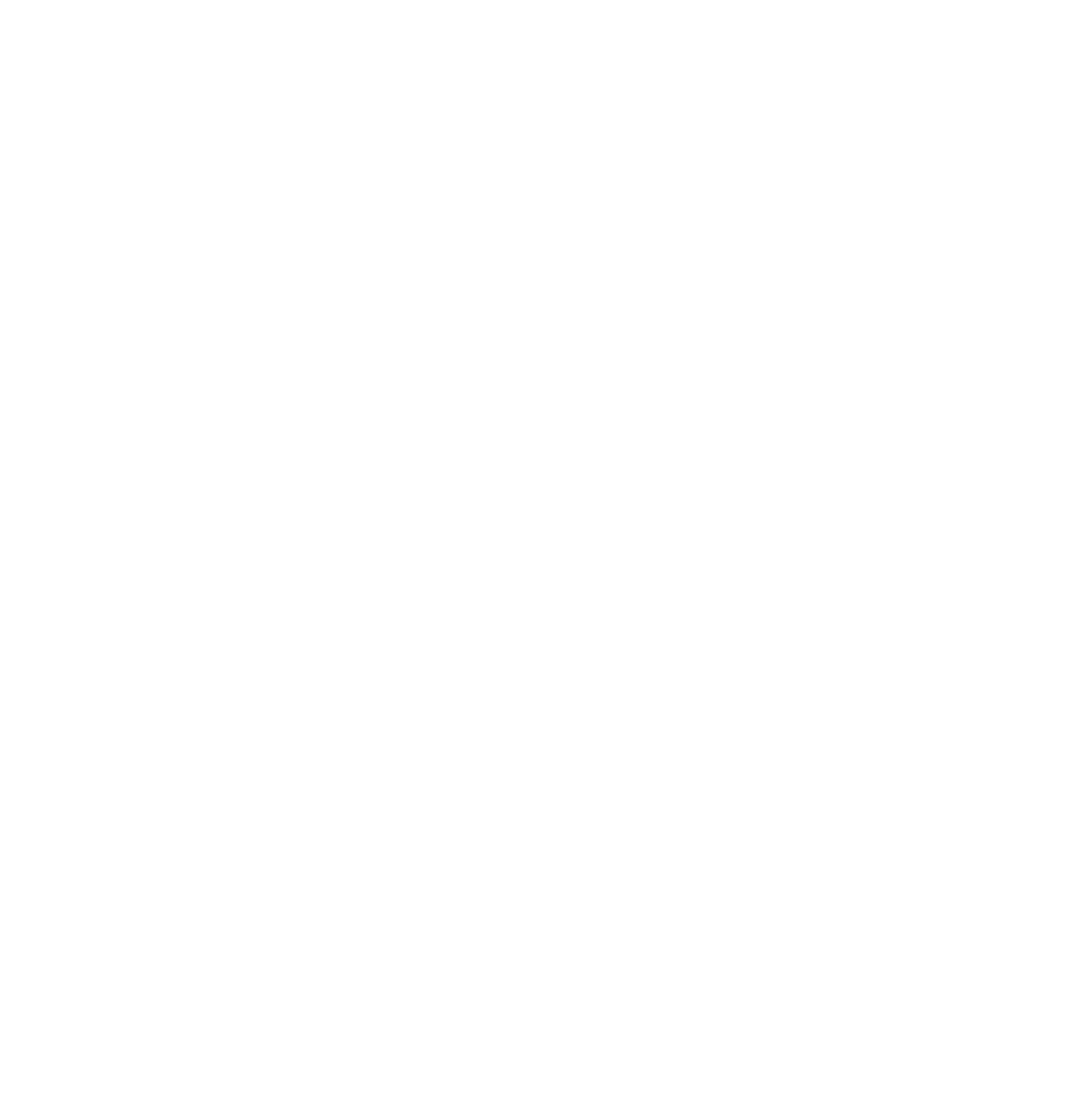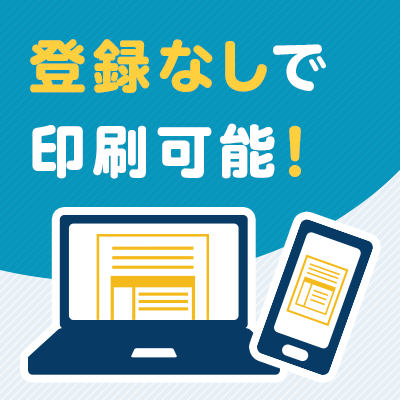インフラエンジニアを辞めたいならどうする?主な理由と対処法、転職先を紹介|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/27
インフラエンジニアを辞めたいならどうする?主な理由と対処法、転職先を紹介

この記事のまとめ
- インフラエンジニアを辞めたいと感じる理由は「夜勤・休日出勤が多い」「人間関係に問題ある」「ルーティンワークにやりがいを感じない」など人によって異なる。
- インフラエンジニアを辞めたいと感じたら、まずは現職で不満を解決できる方法がないかを模索することが大切。
- インフラエンジニアからの転職を検討している方におすすめのキャリアパスには、Webエンジニアや社内SE、プリセールスエンジニア、ITコンサルタントなどがある。
インフラエンジニアとして働いていると、休日出勤や夜勤などで激務が続いたり、報酬を含めた条件面に不満を感じたりすることがあります。このまま働き続けるのが難しいと感じ、辞めたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、インフラエンジニアを辞めたいと思うよくある理由と対処法について解説します。適切な対策を講じることで、辞めたいと悩んでいる現状を打開できるでしょう。
目次
インフラエンジニアを辞めたいと思う主な理由は?

インフラエンジニアとして働いていて転職したいと感じたら、なぜ辞めたいのかを言語化することが大切です。ここでは、インフラエンジニアが「向いていない」「辞めたい」と感じる理由を6つピックアップして紹介します。この機会に、自分が辞めたいと思った理由を洗い出してみましょう。
夜勤・休日出勤がつらい
インフラエンジニアとして運用・保守を担当すると、24時間体制のシフト勤務になるケースが多く、夜間や休日の出勤が必要になる場合があります。夜勤では昼夜逆転の生活リズムを強いられるため、体への負担が大きく、睡眠不足や体調不良に悩まされることも少なくありません。
また、トラブル対応やメンテナンスなどで休日出勤が必要になるケースもあります。休日出勤が多いと、家族や友人と過ごす時間が減り、プライベートを犠牲にしていると感じることもあるでしょう。
単純作業にやりがいを感じない
インフラエンジニアの仕事には、システムやネットワークの安定稼働を維持するために、定期的な点検やログの確認、マニュアルに沿った操作などのルーティンワークが多く含まれます。こうしたルーティンワークは地味で、単調に感じることが少なくありません。
インフラエンジニアとして働くうえで、単純作業をコツコツと正確にこなすことは重要なスキルです。しかし、クリエイティブな仕事や変化の多い業務を求める人にとっては、物足りなく感じることもあるでしょう。
常駐先・パートナー企業との人間関係に問題がある
データセンターや他社のオフィスをはじめとした常駐先で作業する場合、人間関係の悩みが生じがちです。たとえば、常駐先の社員やパートナー企業の担当者との間で、仕事の進め方や認識の違いが生じる場合があります。自分がよかれと思って提案したアイデアや改善策が受け入れられなかったり、逆に、相手のやり方に疑問を感じても指摘しにくい状況が続いたりするとストレスがたまるでしょう。
また、技術的な質問や業務上の相談をしようとしても、常駐先の雰囲気や関係性によっては気軽にできず、孤立感を覚えることもあります。さらに、プロジェクトごとに常駐先が変わることもあり、そのたびに新しい環境に適応し、新たな人間関係を構築することが必要です。人によっては、この状況が精神的に大きな負担になります。
勉強量が多い
インフラエンジニアとして活躍するには、技術の進化や業界のトレンドについていくための継続的な学習が不可欠です。特に、クラウドやセキュリティ・ネットワークなどの分野は日々新しい技術やサービスが登場するため、学習量が多くなります。
業務時間中だけではカバーできない知識を習得する必要があることから、仕事後や休日を使って自己学習に取り組まなければなりません。それによってプライベートの時間が削られることにストレスを感じる人もいます。また、忙しさから勉強時間を確保できなかったり、周囲についていけないと感じたりすることもあるでしょう。
年収に不満がある
IT業界は成果主義の風潮が強く、スキルや経験・成果が年収に反映される傾向にあります。ゆえに、経験の浅いうちは年収の低さに悩むこともあるでしょう。
インフラエンジニアの業務内容は、サーバーやネットワークの運用・保守など、裏方としての役割が多い特徴があります。それゆえ成果が見えにくく、収入に直接反映されにくい点も不満を感じやすい要因のひとつです。年収面の不満を解決する目的で、高収入を得られるほかのITエンジニア職へ転職する方もいます。
将来性に不安がある
インフラの運用・保守業務では、マニュアルに沿ったルーティンワークが多くを占めます。日々の仕事が単純作業の繰り返しに感じられ、「このままでは専門性やスキルが身につかず、自分の成長につながらないのではないか」と不安を抱きがちな環境です。
また、運用・保守業務は成果が見えにくく、キャリアの方向性をイメージするのが難しいと感じる方もいます。「いまの職場でこのまま働き続けても市場価値が上がらないのではないか」といった疑問から、辞めたいと感じることもあるでしょう。
キャリアプランを実現できない
インフラエンジニアとして経験を積みつつ必要なスキルを習得すると、さまざまなキャリアへの道が開かれます。しかし、現職で自分が望んでいるキャリアプランを実現できないこともあるでしょう。「このまま働き続けてもキャリアアップできない」と考え、転職を検討する方もいます。
そのようなときは、キャリアプランを実現できるルートを用意している企業への転職が現実的な選択肢です。転職してさらに経験を積み、スキルアップすれば理想のキャリアを形成しやすくなります。
インフラエンジニアを辞めたいときの3つの対処法

転職すると入社後にミスマッチが生じたり、年収が下がったりする可能性があるなど、一定のリスクが存在します。そのため、インフラエンジニアを辞めたいと感じても、まずは慎重に検討することが大切です。ここでは、インフラエンジニアを辞めたいと思ったときにやっておきたい対処法を3つ紹介します。
1.上司や常駐先の担当者と交渉する
現職の労働環境や報酬などの条件面に不満があるときは、転職を決める前に上司や常駐先の担当者へ相談・交渉しましょう。相談・交渉して改善できれば、ミスマッチのリスクを抱えて転職する必要がなくなるためです。
特に、現職で自分が望んでいるキャリアプランを実現できそうな場合は、まず不満点を解消できないか試してみるとよいでしょう。相談・交渉がうまくいかず解決が難しいのであれば、転職を検討するのは選択肢のひとつです。
2.望むポジションに応募する
インフラエンジニアとしてやりたい仕事に携われないと悩んでいるなら、社内公募制度を利用して臨むポジションに応募したり、希望する部署への異動を願い出たりする対処法が有効です。
現職で自分が希望するキャリアへ挑戦できる環境へと移れれば、辞める必要はありません。社内公募制度の選考に通らない、部署異動が認められないときには転職を考えるとよいでしょう。
3.転職する
現職で悩みや不満が改善できない場合は、転職をするのもひとつの選択肢です。転職することで、現職の悩みや不満を解消できるだけでなく、新たな環境でキャリアを形成できます。
条件面への不満を現職で解決できないときは、自分が納得できる条件を提示してくれる企業に転職しましょう。将来のキャリアを考えてスキルの幅を広げるために転職したいと考えている方は、理想のキャリアパスを実現するための経験を積める企業を選ぶことが大切です。
インフラエンジニアとして働き続けるメリット

インフラエンジニアとして働き続けるか、別の職種に転職するか迷っている方は、まず働き続けるメリットを考えてみましょう。ここでは、インフラエンジニアとして働く3つのメリットを紹介します。
これらの要素を大きなメリットであると感じるのであれば、インフラエンジニアとして働き続けるのがおすすめです。
需要・将来性が高い
多くの業界・企業がDXを推進していたり、最新のIT技術をビジネスに活用したりする動向が見られ、ITの重要性は今後ますます高まることが予測されます。
ITシステムを動かすにはサーバーやネットワークなどのインフラが不可欠で、そのインフラを整備・保守するインフラエンジニアの働きが欠かせません。したがって、今後もインフラエンジニアが重宝される状況が続くと考えられます。経験を積んでスキルアップすると、さまざまなプロジェクトを担当できるようになり活躍の幅が広がるでしょう。
スキルアップで市場価値が高まる
技術の進歩に伴って、インフラエンジニアに求められるスキルも変化します。システムを動かすサーバーとしてクラウドを活用したり、AIを使用して運用業務を自動化したりするなど、新たな技術を積極的に活用するプロジェクトもあるでしょう。
今後もIOWNや6Gなどの新しい通信技術を含め、新たな技術が実用化される見込みです。最新のIT技術を扱えるスキルを習得すると、市場価値を高めることができ年収アップの可能性も向上します。
さまざまなキャリアプランが開かれている
インフラエンジニアとしての経験を積んだ先には、さまざまなキャリアプランが開かれています。具体的なキャリアプランの例を挙げると、以下のとおりです。
- クラウドエンジニア
- ネットワークエンジニア
- サーバーエンジニア
- セキュリティエンジニア
興味を持った分野を深掘りして学び、必要なスキルを習得すれば専門性が高いエンジニアとして活躍できます。
インフラエンジニアを辞めるときの流れ
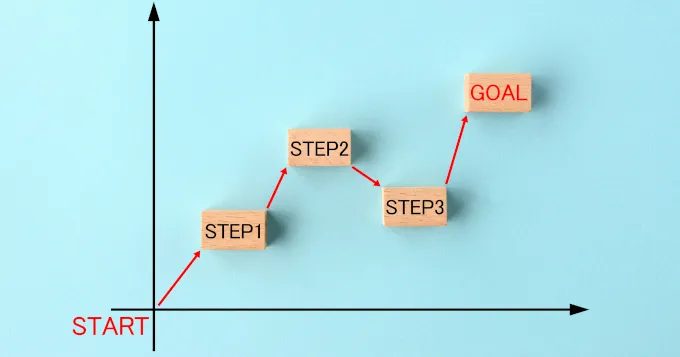
転職を検討し始めてから実際に転職活動を行い、新しい企業に入社するまでの期間にはやらなければならないことが多くあります。スムーズに転職活動を進めるには、一連の流れを把握しておくことが大切です。ここでは、インフラエンジニアを辞めるときの流れを解説します。
辞めたい理由を可視化する
インフラエンジニアを辞める理由が曖昧なまま転職すると、転職先でも同じ理由で悩む可能性があります。そのため、インフラエンジニアを辞めたいと思ったら、不満や悩みを具体的に洗い出すことが重要です。
まずは、「夜勤や休日出勤が多くて体力的につらい」「職場の人間関係がうまくいかない」「同じような業務が多くてやりがいを感じられない」など、自分が感じている問題を言語化してみましょう。そして、それらの問題が「自分自身の適性やスキルの問題」なのか、「会社の体制や環境の問題」なのかを整理します。言語化した問題点が現職では解決できない場合は、転職を決断するとよいでしょう。
転職の方向性を具体的に決める
転職を決断したら、自分が目指す方向性を決めましょう。インフラエンジニアの経験を活かす転職には、主に以下の2パターンがあります。
- ITインフラを扱うスペシャリストを目指し、開発現場で高度なインフラを整備・保守する
- マネジメント層を目指し、ITインフラを扱うプロジェクトのマネージャーとして管理業務を担当する
どちらのルートを目指すかによって、必要なスキルが大きく異なります。スペシャリストを目指すのであれば、最新技術を含めて高度な技術を扱えるようにならなければなりません。マネジメント層を目指すのであれば、マネジメントスキルをはじめとした管理職に求められるスキルが必要です。
スキルアップの方向性が大きく異なるため、できるだけ早いうちに自分がどちらのルートを目指すのか決めましょう。
自分に合った転職先を探す
転職の方向性が決まったら、自分に合った転職先を具体的に探します。転職先を探すときには、以下のポイントを意識しましょう。
- 現職で課題に感じていた問題を解決できるか
- 自分が目指すキャリアを実現できるか
- 条件面に納得ができるか
上記を総合的に考慮することで、ミスマッチが生じるリスクを減らせます。満足度の高い転職を実現するためにも、キャリアの棚卸しや企業研究を通じて納得できる転職先を探すことが大切です。
書類を作成・応募し、面接を受ける
希望する転職先が決まったら、応募に必要な履歴書・職務経歴書などの書類を作成します。それぞれの書類の役割は以下のとおりです。
- 履歴書:基本情報や学歴、職歴、資格等を伝える
- 職務経歴書:具体的なスキルや実務経験をアピールする
どちらも採用を左右する重要な書類のため、応募先企業に合わせて丁寧に作成しましょう。書類作成に不安がある方は、転職エージェントで添削を受けるのもおすすめです。
書類選考通過後は、企業との面接に進みます。自身の意欲や魅力が伝わるように、しっかりと面接対策を行いましょう。面接後に内定をもらったら、指定された期間内に内定承諾を伝えます。
転職が決まったら早めに退職の連絡をする
無事に転職が決まったら、現職の上司にできるだけ早い段階で退職の意思を伝えましょう。退職するときには、業務の引き継ぎや事務手続きなどに時間がかかるためです。
退職の直前に伝えると、引き継ぎなどに充分な時間を確保できず、現職の業務に支障を与えてしまいかねません。スムーズに退職をするためにも、転職が決まったら就業規則に定められた時期に退職の意向を伝えましょう。
インフラエンジニアを辞めたい人が適職を見つけるコツ
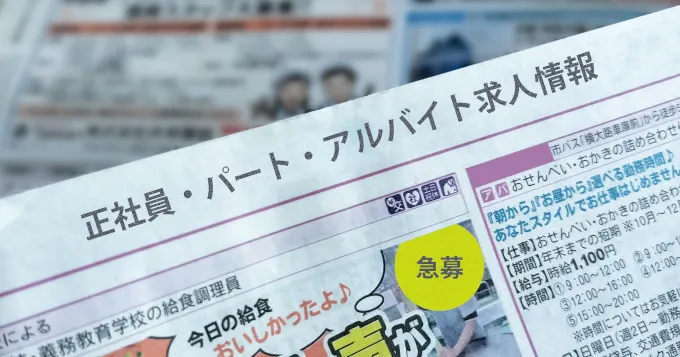
転職経験が少ないと、「どのように転職活動を進めればよいのか」「まず何から始めればよいのか」などと悩むこともあります。転職活動を効率的に進めて採用を勝ち取るためにも、転職成功のポイントを押さえておきましょう。ここでは、転職をスムーズに進めるポイントを5つ紹介します。
キャリアプランを見直す
キャリアプランとは、自分の理想とするキャリアを実現するための計画のことです。定期的にキャリアの棚卸しをしたりキャリアプランを見直したりしておくと、転職活動をする際に自分に合った転職先を見つけやすくなります。
また、キャリアプランは面接でも聞かれる定番の質問であり、スムーズに答えられるようにしておくことは選考対策としても効果的です。
理想の働き方を明確にする
転職活動を始める前に転職先に求める条件を整理しておくと、希望に合った職場を見つけやすくなります。具体的には、給与・年収や労働時間・勤務地・福利厚生・休日・リモートワークの可否など、自分が重視するポイントをリストアップし、優先順位を考えましょう。
たとえば、年収を優先したい場合は、自分のスキルや経験を活かせる高収入の職種や企業を中心に探します。一方で、プライベートの時間や勤務環境の柔軟さを重視したい場合は、残業が少なく働きやすい環境を提供している会社を探しましょう。
自宅にできるだけ近い場所で働きたい場合は、通勤時間がいまより短くなる企業やリモートワークが可能な企業を選ぶといった選択肢が考えられます。
インフラエンジニアの経験が活かせる企業に応募する
転職では即戦力が求められるため、前職の経験が活かせる求人を選ぶのが基本です。インフラエンジニアから別の職種へ転職する場合でも、これまでに培ったスキルや経験を活かせるIT業界を志望したほうが有利に進められます。
とはいえ、未経験でもやりたい仕事があれば、諦めずに挑戦してみることも大事です。好きな仕事に就ければモチベーションを高められ、結果として成長も早くなるでしょう。未経験の職種への転職は年齢を重ねるごとに難しくなるため、早めの行動が大切です。
選考対策を万全にする
インフラエンジニアとして十分なスキルを身につけていても、選考対策が不十分であれば転職は成功しません。そのため、転職する際には履歴書や職務経歴書の作成・面接準備など、選考対策を万全にして臨みましょう。たとえば、履歴書に記載する志望動機は、「その企業でなくてはならない理由」を記載することが大切です。どの企業でも通用するような内容だと、入社意欲が低いと判断されます。
職務経歴書に記載する実績や経験は、数字を用いて具体的に記載しましょう。面接対策では、入退室のマナーを押さえること、定番の質問に対してスムーズに答えられるようにしておくこと、逆質問を用意しておくことがポイントです。
ITに特化した転職エージェントを利用する
転職活動はひとりでも進められますが、転職エージェントを活用することで成功確率を上げられます。転職エージェントは、求人の紹介や応募書類の作成・選考の準備などをサポートしてくれるサービスです。
IT業界に精通した転職エージェントは業界特有の動向や企業の内部事情に詳しく、自分の経験やスキルに合致した求人を見つけるサポートをしてくれます。無料で利用できるため、試しに相談してみるのもよいでしょう。
インフラエンジニアを辞めたい人におすすめのキャリアパス

インフラエンジニアから別職種への転職を目指す場合、どのような選択肢があるのでしょうか。ここでは、インフラエンジニアの経験やスキルを活かせる転職先を5つピックアップして紹介します。興味のある職業が見つかれば、ぜひ挑戦してみてください。
Webエンジニア
Webエンジニアは、Webサイトやアプリケーションを設計・開発・運用する職業です。フロントエンド(ユーザーが直接触れる部分)やバックエンド(サーバー側で処理を担当する部分)など、複数の専門分野に分かれています。
インフラエンジニアとして培ったシステムやネットワークの知識は、Webエンジニアの仕事にも活かせます。「アイデアを形にしたい」「ユーザーの反応を見たい」と感じる方は、ぜひWebエンジニアを目指してみましょう。
社内SE
社内SE(社内システムエンジニア)は、企業内部のIT環境を整備して管理・運用し、社員が効率よく業務を進められるようにサポートする職業です。具体的には、社内ネットワークやサーバーの構築・保守、セキュリティの確保、業務用ソフトウェアの導入やカスタマイズ、IT機器のトラブル対応などを担当します。また、企業のIT戦略に基づき、新しいシステムや技術の導入を検討することも役割のひとつです。
社内SEの業務には、インフラエンジニアとして働いて得たネットワークやサーバーの運用経験、セキュリティの知識などを活かせます。社内SEは多くの場合、勤務時間が比較的安定しているため、ワークライフバランスを充実させたい人におすすめです。
プリセールスエンジニア
プリセールスエンジニアは、IT製品やサービスを提案・販売する際に、営業担当者と協力して技術的な支援をする職業です。具体的には、顧客のニーズをヒアリングして要件に合ったソリューションを設計・提案し、導入のメリットや運用面を説明します。また、プレゼン資料の作成や製品デモの実施、プロトタイプの構築などを担当することもあります。
プリセールスエンジニアはユーザーと直接関わる仕事であるため、技術的なバックグラウンドを活かしながらコミュニケーションスキルを磨ける職種です。また、顧客の課題解決に貢献することで、感謝の言葉を直接もらえる点や、成果が評価されやすい点も魅力です。
プロジェクトマネージャー
プロジェクトマネージャー(PM)は、システム開発プロジェクトの全体を統括する職業です。計画立案・進捗管理・品質管理・コスト管理・人員管理など、プロジェクト全体に対する責任を担います。やりがいと責任が大きいポジションであり、プロジェクトを成功に導くことで達成感や成長を実感できるのが特徴です。
また、調整力やリーダーシップ・課題解決力などのスキルを高められ、IT業界以外でも通用する市場価値が高い人材になれます。さらに、プロジェクトマネージャーはIT業界の中でも比較的年収が高い点も魅力です。
ITコンサルタント
ITコンサルタントは、企業のIT戦略立案やシステム導入・運用改善をサポートする職業です。抱えている課題やニーズを理解し、それに応じた最適なITソリューションを提案します。業務内容には、現状分析・要件定義・技術選定・計画立案などが含まれ、ITを活用してクライアント企業の業績向上を支援するのが主目的です。
ITコンサルタントはクライアント企業の経営層やプロジェクトリーダーと直接関わる機会が多く、ビジネス・経営の視点を培える点が魅力です。また、プロジェクトごとに異なる業界や企業文化に触れることで視野が広がり、多様なスキルを習得できる点もメリットです。
クラウドエンジニア
クラウドエンジニアとは、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azureなどのクラウドサービスを活用してITシステムを設計・構築する職です。クラウドサービス上にシステムを構築するため、オンプレミス環境とは異なる知識やスキルが求められます。実務で活用するサービスは、クラウドサーバーやクラウドネットワークなど多種多様です。
インフラエンジニアとして働いていると、クラウドサービスを使用する機会もあるでしょう。その機会を活用してスキルを習得しつつ、休日を活用して学習に励めばクラウドエンジニアへの転職を目指せます。クラウドの重要性は今後も高まると考えられるため、将来性にも期待できるルートといえるでしょう。
まとめ
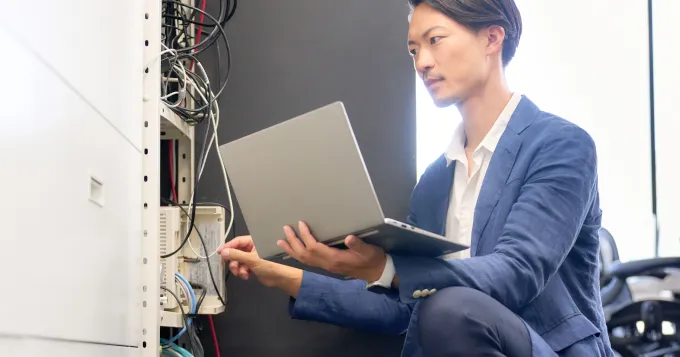
インフラエンジニアとして働いている中で、激務が続いたり条件面に不満を感じたりして転職したいと思うことがあるかもしれません。転職したいと思ったときは、まず現職で状況を改善できないか考えてみましょう。改善が難しいときは、自分に合った企業を探して転職するのがおすすめです。
自分ひとりで転職活動を進めるのが難しいと感じている方は、ぜひお早めにマイナビ転職ITエージェントにご相談ください。マイナビ転職エージェントにはIT業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、あなたの転職が成功するようサポートします。
関連記事:マイナビ転職ITエージェント
-
- 特集コンテンツ
- インフラエンジニアの転職知識まとめ
- 職種図鑑
- インフラエンジニアとは?仕事内容・年収・資格について
- 求人情報
- インフラエンジニアの求人一覧
関連コンテンツ
-

IT業界
プログラマーの将来性が懸念される3つの理由|市場価値を高める方法とは?
-

IT業界
未経験でもWebデザイナーになれる?必要なスキルやポートフォリオの作り方
-

IT業界
女性システムエンジニア|魅力と転職成功のステップを徹底解説