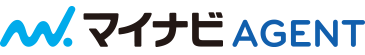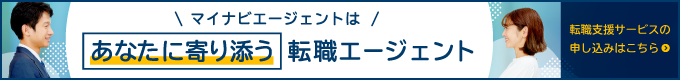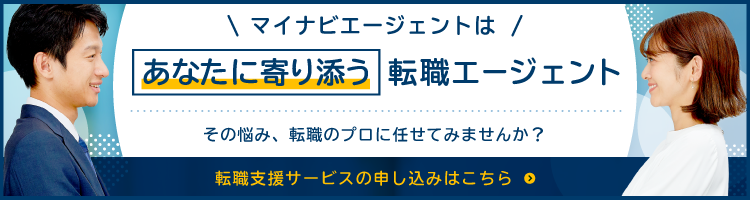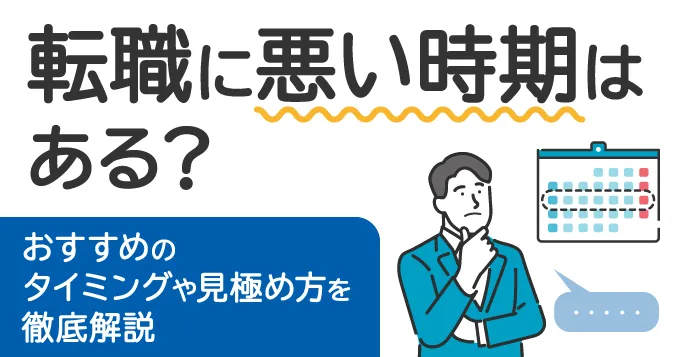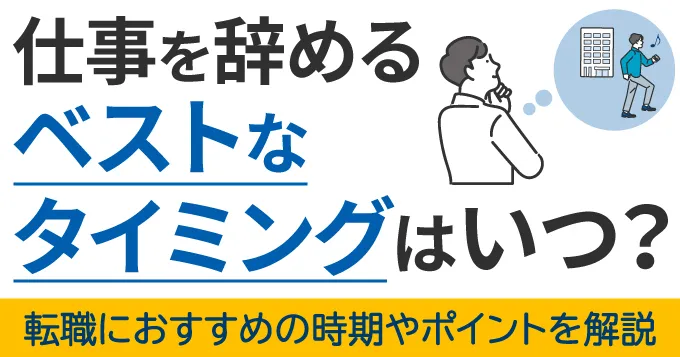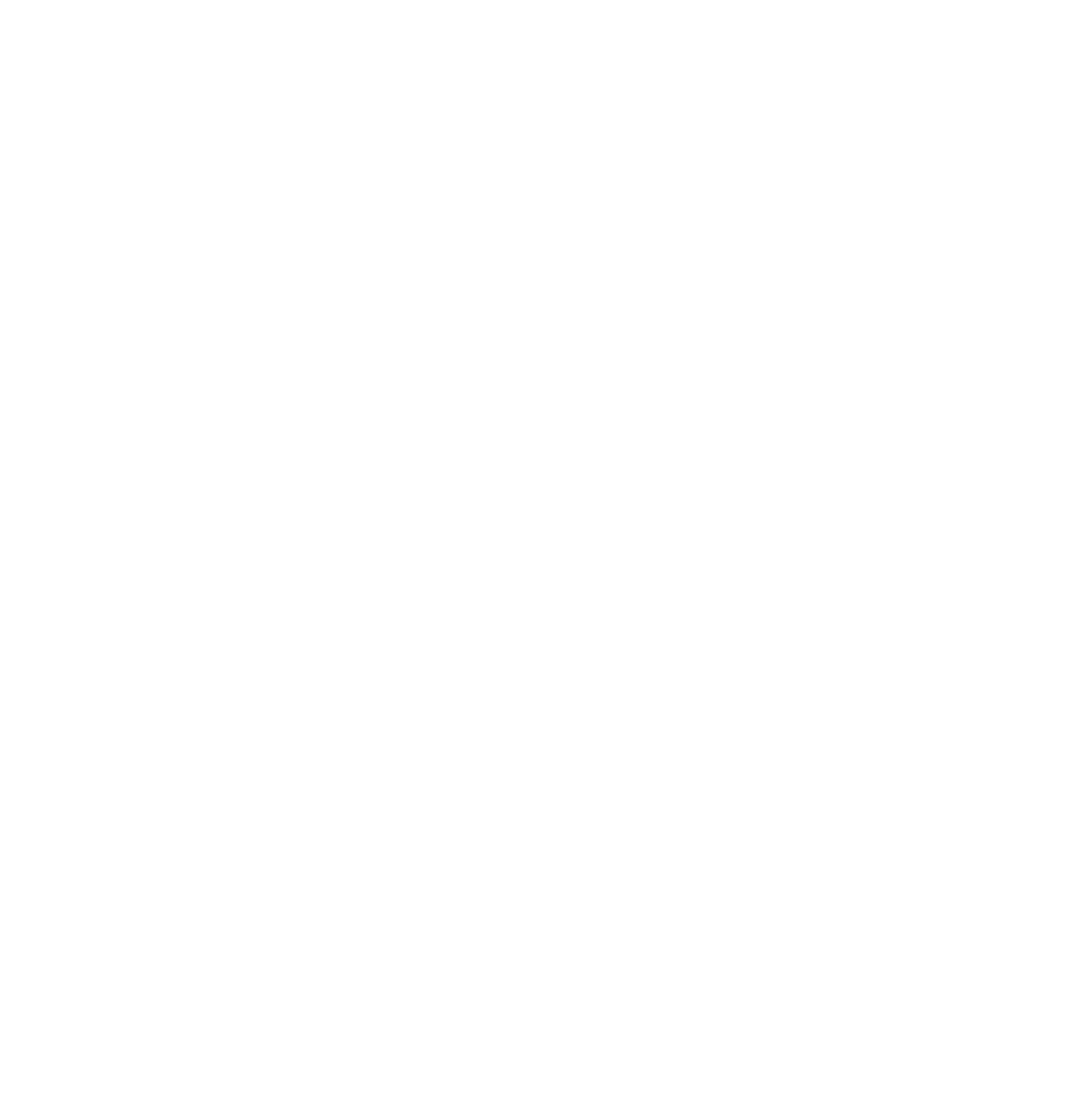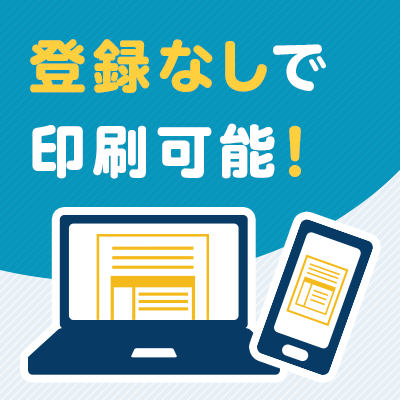転職に最適なタイミングはいつ?年齢別・理由別の見極めポイントも解説|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/08
転職に最適なタイミングはいつ?年齢別・理由別の見極めポイントも解説

この記事のまとめ
- 転職活動を始めるタイミングは、求人が増える2月~3月、8月~9月、賞与支給後の6月~7月、12月~1月がおすすめ。
- 一般的に年齢が上がるにつれて転職のハードルが高くなるため、転職を検討するなら早めに進めることがポイント。
- 転職したい明確な理由がない場合や、繁忙期や参加しているプロジェクトの途中は、転職は避けたほうが無難。
「転職するなら、いつがベストなのだろう」といった迷いを抱えている方は少なくありません。転職に最適なタイミングは、年齢や状況、目的によって大きく異なります。
早すぎる転職は「短期離職」というマイナスイメージを与え、遅すぎれば希望するキャリアパスを実現する機会を逃してしまうこともあるでしょう。この記事では、年齢別・状況別に転職の最適なタイミングとそのポイントを詳しく解説します。
目次
転職活動を始めるタイミングは何月がおすすめ?

転職を成功させるためには、求人が増加するタイミングや企業の採用活動の時期、そして自身のライフプランなどを考慮する必要があります。一般的に転職活動が活発になる時期は、企業の事業計画や人事異動のタイミングなどと密接に関連しています。
では、具体的に何月が転職を成功させやすいのでしょうか。ここでは、転職活動でおすすめの時期について解説します。
求人が増える「2月~3月」「8月~9月」
転職活動を始めるタイミングでおすすめなのは、「2月~3月」「8月~9月」です。この時期は、会社の期が変わるタイミングで人事異動が行われることが多く、中途採用の求人が増える傾向にあります。求人が増える時期に転職活動を始めると、複数の企業を比較検討できます。給与や労働条件など、より自分に合った企業を見つけられるでしょう。
また2月~3月に求人が増える背景には、新年度へ向けて人材を確保し、新卒社員と中途社員へまとめて研修などを行うことで教育コストを抑える狙いもあります。
賞与支給後の「6月~7月」「12月~1月」
日本企業の多くは夏(6月~7月)と冬(12月~1月)に賞与を支給します。そのため、この時期に転職をすると、賞与を受け取ることができるという利点があります。
転職活動には一定のコストがかかるうえに、新しい職場での初月の給与は満額支給されない場合も少なくありません。そのため、賞与を受け取ってから転職することで、生活費や転職活動の資金に余裕を持たせられるというメリットがあります。
年齢別|転職に最適なタイミングはいつ?

転職が成功するかどうかは、個人のスキルや経験だけでなく、年齢にも左右されることがあります。一般的には「異業種への転職は20代が有利になりやすい」「キャリアアップを目的とした転職は経験のある30代以降が有利」と言われています。
転職を成功させたいのなら、自分の年齢を踏まえて転職のタイミングや戦略を練ることが大事です。ここでは、年代別に転職のタイミングやポイントを解説します。
第二新卒
社会人経験3年未満での転職は、一般的に「第二新卒」と呼ばれます。第二新卒は、新卒社員と同じ内容の教育を受ける可能性が高いことから、4月入社を目指して動き出すのがおすすめです。4月に入社できれば、年齢の近い新卒社員と「同期」のような親しい関係を築けるでしょう。
とはいえ、入社してすぐに転職をした場合「我慢強さに欠けるのではないか」「何事も長続きしないタイプなのではないか」などのマイナスイメージを持たれてしまう可能性があります。企業や面接官によるため一概にはいえませんが、新卒で入社した企業に約3年勤めていたり、早期の退職でも理由をきちんと説明できたりすれば、マイナスイメージを持たれずに転職活動を進められるでしょう。
20代
社会人経験を積んでいくと、「より自分に向いている仕事が見つかった」「新しいことにチャレンジしてみたい」「いまの職場が合わないと感じた」など、さまざまな気づきが出てきます。そのため、25歳~29歳で転職をする人は、転職人口全体で見ても多い傾向にあります。
自分の経験・スキルを企業へアピールしたいのであれば、現職で実績を出してから転職するのがおすすめです。特に同業他社や同職種への転職であれば、入社後に活躍できることの説得材料になり、強力なアピールポイントになります。
以下の記事では、20代の転職に関する情報を解説しているので、転職を検討し始めた20代の方はぜひチェックしてみてください。
30代
30代での転職を考えている場合は、できる限り早いうちに転職活動を始めることをおすすめします。なぜなら、30歳を過ぎると中堅扱いとなり、年齢が上がるほど求められるスキルレベルが高くなるためです。
20代とは異なり、30代の転職では「マネジメント経験」や「役職に就いているかどうか」をみられることが多くなります。管理職などに就いているのであれば焦る必要はありませんが、特に役職に就いていない場合は、できる限り早いタイミングで転職したほうが賢明です。
転職を検討し始めた30代の方は、以下の記事も合わせてチェックしてみてください。
40代
40代は、自分の理想とする求人が見つかったタイミングで転職するとよいでしょう。転職市場では40代の転職の難易度が高まるため、応募するタイミングを逃さないことが大切です。また、企業側は40代の人材に対して「管理職や専門職として即戦力で活躍してほしい」と考えているため、転職を成功させたいのならマネジメント経験や専門的なスキルをしっかりとアピールすることが重要です。
さらに、40代には柔軟な姿勢と謙虚さも求められます。過去の経験に固執せず、新しい環境で学ぶ意欲を示すことで、企業からの評価は高まります。転職を少しでも有利に進めるために、転職エージェントを活用するのもおすすめです。
50代
50代も40代と同様に、自分の希望に合った求人が見つかったタイミングで転職するとよいでしょう。50代の転職では、これまでのキャリアを総括し、自身の強みを活かせる職場を見極めることが重要です。一般的に管理職や専門職としての採用が多く、リーダーシップやマネジメント経験が評価される傾向にあります。
しかし、40代と比較して転職のハードルがさらに高くなるため、より慎重な戦略が求められます。50代の転職においては、年収やポジションに過度にこだわらないことが大切です。また、長期的な視点で、退職まで安定して働ける環境を優先するとよいでしょう。
理由別|転職を検討したいタイミング

転職を考える理由は人それぞれですが、タイミングを間違えると後悔することもあります。転職のタイミングに正解はないため、自身の状況を踏まえながら慎重に第一歩を踏み出しましょう。ここでは、転職を検討してもよいタイミングについて解説します。
入社後すぐに「合わない」と感じた
入社後すぐに「合わない」と感じることは珍しくありません。仕事内容、職場の雰囲気、企業文化など、入社前に想像していたイメージと現実とのギャップに悩む人は多くいます。このような場合、早い段階で転職を検討することで、キャリアを無駄にせずに済みます。
次の転職先を選ぶ際には「合わない」と感じた原因を分析し、同じようなミスマッチが起こらないよう情報収集を徹底しましょう。企業のWebサイトや口コミサイトだけでなく、実際に働いている人の話を聞くことも有効です。
資格を活かせる職場で働きたい
取得した資格が活かせない環境では、仕事のやりがいや成長につながりにくいといえます。資格を活かせる職場に転職することで、専門知識を発揮できるだけでなく、資格手当による給与アップや昇給の可能性が高まるでしょう。
また、専門職や資格必須の職種では、経験を積むことで市場価値が向上し、キャリアの選択肢が広がる可能性があります。たとえば、働きながら社会人向けのビジネススクールに通ってMBA(経営学を修めた方に対して授与される学位)を取得すれば、コンサルティング関係の企業や経営関係の業務ができる会社への転職が有利になります。
年収アップ/キャリアアップを目指したい
長年携わった業界で経験を積んだ場合には、年収アップやキャリアアップ、新たなチャレンジのために転職するのもよいでしょう。
キャリアアップを目指す場合は、これまでの経験を活かせる同業界・同職種への転職が有利になります。一方で、年収アップを狙う場合は、業界や企業による年収水準の違いを理解し、より高い給与が見込める職場を選ぶことが重要です。
-
- 関連記事
- 平均年収ランキング【2020年版】
他業界へキャリアチェンジしたい
これまでとは異なる業界へ転職し、キャリアチェンジを狙うのもよいでしょう。特に、現職での仕事が自分に向いていない、あるいは激務すぎるといった場合に、キャリアチェンジは有効な選択肢です。
とはいえ、未経験の業界へ転職する場合は、年齢が若いほど有利な傾向があります。年齢が上がるほど即戦力が求められるケースが増えるためです。早い段階でキャリアチェンジを決断することで、新しい分野での経験を積みやすくなり、長期的なキャリア形成につながります。
事業方針や体制が変更した
事業方針や体制の変更に伴って仕事内容や待遇が大きく変化した場合も、転職を考えるタイミングといえます。新たな仕事内容や待遇に不満があれば、現職を続けることにストレスを感じるでしょう。また、業績悪化や事業方針の転換により、企業が多くの社員をリストラをされるような状況下も、転機となりやすいでしょう。
転職を検討する際は、今後どのようなキャリアを築きたいのかを明確にすることが大切です。加えて、新しい職場でミスマッチが起こらないよう、入念に企業研究を実施して、事業戦略や職場環境をしっかり確認することが重要です。
労働環境に不満がある
長時間勤務や休日出勤が多いなど、労働環境に不満がある場合も、転職を検討するタイミングといえます。長時間労働は多くの企業での課題となっていますが、すぐに解決できないケースもあります。まずは現職で状況を改善できないか検討し、改善が見込めない場合は、転職を視野に入れることをおすすめします。
転職をする際は、転職先の労働環境をしっかりとチェックしておきましょう。また、転職理由を伝える際にはネガティブな表現を避け、「スキルを活かして新しい環境で挑戦したい」など前向きな理由に置き換えることも大切です。
人間関係がうまくいかない
職場の人間関係がうまくいかず、業務に支障をきたすほどであれば、転職もひとつの選択肢でしょう。まずは信頼できる上司や同僚に相談し、問題解決を試みるのが先決です。社内で異動の希望を出すことも検討しましょう。相談や異動を試みても改善の見込みがなく、人間関係の悩みが長期化している場合は、転職を検討する適切なタイミングといえるでしょう。
ライフスタイルが変化した
結婚や育児、介護などによって現在の職場での勤務が難しくなった場合は、ライフスタイルに合った職場へ転職したほうがよいでしょう。ライフイベントにより働き方の優先順位が変わるのは自然なことです。問題なく働けていた環境でも、ワークライフバランスを考慮して環境を変える必要に迫られることもあります。
転職を検討する際は、まず希望する働き方を明確にしましょう。リモートワークやフレックスタイム制を導入している企業や、育児支援制度のある企業などの情報収集をし、自分に合った働き方が可能な職場を選ぶと満足度高く働けます。福利厚生や休暇制度など、長期的に働きやすい環境が整備されているかを確認することも重要です。
転職を避けたほうがよいタイミングは?

転職にはメリットが多くありますが、待遇が悪くなったりミスマッチが発生したりするリスクもあります。現職に不満がある場合でも、転職するかどうかの判断は慎重に行うことが大事です。ここでは、転職を待ったほうがよいケースについて解説します。
転職したい明確な理由がない
転職活動を始める際、「なぜ転職したいのか」という明確な理由を持つことが重要です。まずは現在の職場に対する不満や希望を具体的に書き出してみましょう。曖昧な動機のままでは転職先でも同じ問題に直面する恐れがあります。
「給与が低い」「スキルアップの機会がない」「ワークライフバランスが取れない」など、項目別に整理をし、それらの問題が現職で解決できるのか、転職でしか解決できないのかを冷静に分析しましょう。現職で解決できるかもしれない理由の場合は、安易な転職を避けることをおすすめします。
現職に就いて間もない
早期退職をした人は、「忍耐力のない人」「転職を繰り返す可能性が高い人」と見られやすく、選考で不利になる可能性があります。可能であれば実績や経験を積んでから転職活動を始めるのがおすすめです。
とはいえ、現職で働き続けるのが困難な事情がある場合など、状況によっては早めに転職したほうがよい場合もあります。
繁忙期や参加しているプロジェクトの途中
プロジェクト進行中や繁忙期は、転職を避けたほうがよいでしょう。プロジェクトの途中で退職すると、チームメンバーへの負担が増大するだけでなく、引き継ぎに多くの時間を要することがあります。また、完遂していないプロジェクトは面接で実績としてアピールしづらく、転職先での評価にも影響を与えかねません。
また、企業の繁忙期に退職を申し出ると、慰留が強くなることも想定されます。予定していた退職時期が遅れると、転職先との入社日調整に支障をきたす可能性があるため注意が必要です。
転職タイミング決定のために知っておきたいスケジュール
転職活動には3ヵ月~6ヵ月程度かかるのが一般的です。転職活動のスケジュールの目安は以下のとおりです。
- 自己分析や情報収集(1週間~2週間程度)
- 応募書類の作成および応募(1週間~2週間)
- 面接と選考(4週間~5週間)
- 内定および入社(4週間~5週間)
転職活動のタイミングを決める際は、希望入社日から逆算してスケジュールを組むことが重要です。無理なく転職活動を行えるよう、余裕をもって計画を立てましょう。特に在職中の場合は、退職時期や引継ぎ期間も考慮に入れた戦略的なスケジューリングが転職成功の鍵となります。
転職のタイミングに関するよくある質問

転職に関する疑問は、さまざまなシーンや状況で生じます。転職は人生設計に大きく影響するため、疑問や不安を解消したうえで最適なタイミングを見極めましょう。
Q.入社してすぐに転職してもよい?
入社してすぐの転職は可能ですが、いくつか考慮したい点があります。まず、就業規則を確認し、試用期間中の退職手続きや退職予告期間を把握することが重要です。一般的に2週間前の退職予告が必要ですが、企業によって異なる場合もあります。また、短期間での退職を繰り返すと、転職市場での評価が下がるリスクがあります。
Q.住宅の購入を考えている場合、ベストな転職のタイミングは?
住宅購入を検討している場合、住宅ローンの審査に大きく影響することから、転職のタイミングには慎重な判断が求められます。住宅ローン審査では安定した収入と勤続年数が重視されるため、最適な転職タイミングは「融資が実行された後」といえます。
多くの金融機関では審査基準に勤続1年以上といった条件を設けています。転職すると勤続年数はリセットされ、短期間では審査に通りにくくなります。また、転職後の収入は実績ではなく見込み金額であるため、安定性の面でも評価が下がる傾向にあります。
さらに住宅ローン申込後から融資実行までの期間に転職すると、申込内容と実態が異なるとみなされ、審査が取り消されるリスクがある点にも注意しましょう。
Q.ボーナス支給後すぐに転職してもよい?
ボーナスは過去の労働に対する正当な対価であるため、支給後すぐに退職しても道義的な問題はありません。ただし、一部の企業では支給日に在籍していても、直後の退職が決まっていると減額される場合があります。就業規則に条件が明記されていることが多いため、事前に確認しておきましょう。
円満退職のためには、ボーナス支給後に退職の意思を伝えるのが望ましいといえますが、支給直後では「ボーナス目的」と思われる可能性があります。そのため、数週間空けてから退職を申し出るとよいでしょう。ただし、心身の不調など深刻な問題を抱えている場合は、ボーナスにこだわりすぎず健康を優先することも大切です。
転職のタイミングに悩んだら「マイナビ転職エージェント」へご相談ください
マイナビ転職エージェントには転職のノウハウを熟知したキャリアアドバイザーが在籍しており、あなたのキャリアプランや希望に応じて適切な転職のタイミングをアドバイスできます。
また、求人の紹介や応募書類の作成、面接対策のアドバイス、内定後の条件交渉など、転職に関するサポートも充実しています。マイナビ転職エージェントのサービスはすべて無料であり、相談だけの利用も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ

転職のベストタイミングは、求人が増える2月~3月・8月~9月や、賞与支給後の6月~7月・12月~1月が適しています。また20代・30代・40代など年齢によっても最適な時期は異なり、キャリアアップやキャリアチェンジなど目的別に考慮したい点もあります。一方で、理由が曖昧な場合や入社間もない時期、プロジェクト途中での転職は避けたほうがよいでしょう。
転職を成功させるには、目標から逆算したスケジュール管理が重要です。悩んだ際はマイナビ転職エージェントに相談することで、あなたに合った転職タイミングを見つけられるでしょう。

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。
関連コンテンツ
-

転職全般
転職したいけど何がしたいかわからない人へ|自分に合う仕事の見つけ方
-
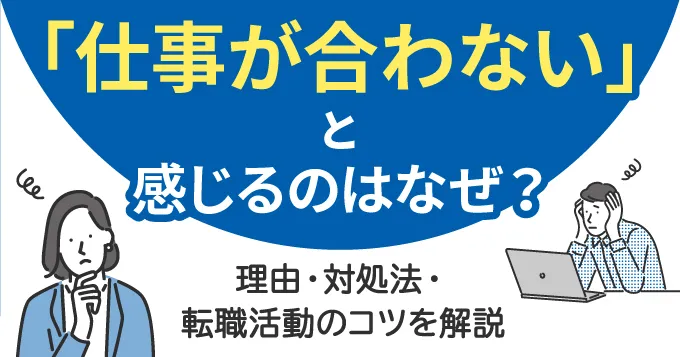
転職全般
「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説
-

転職全般
転職して後悔する理由は?後悔しない再転職を実現するポイントも解説!