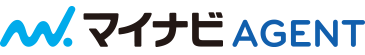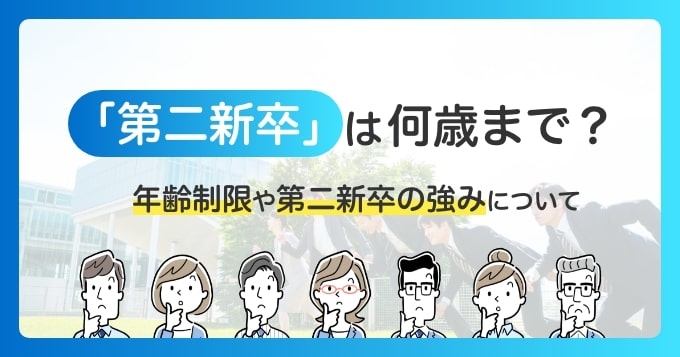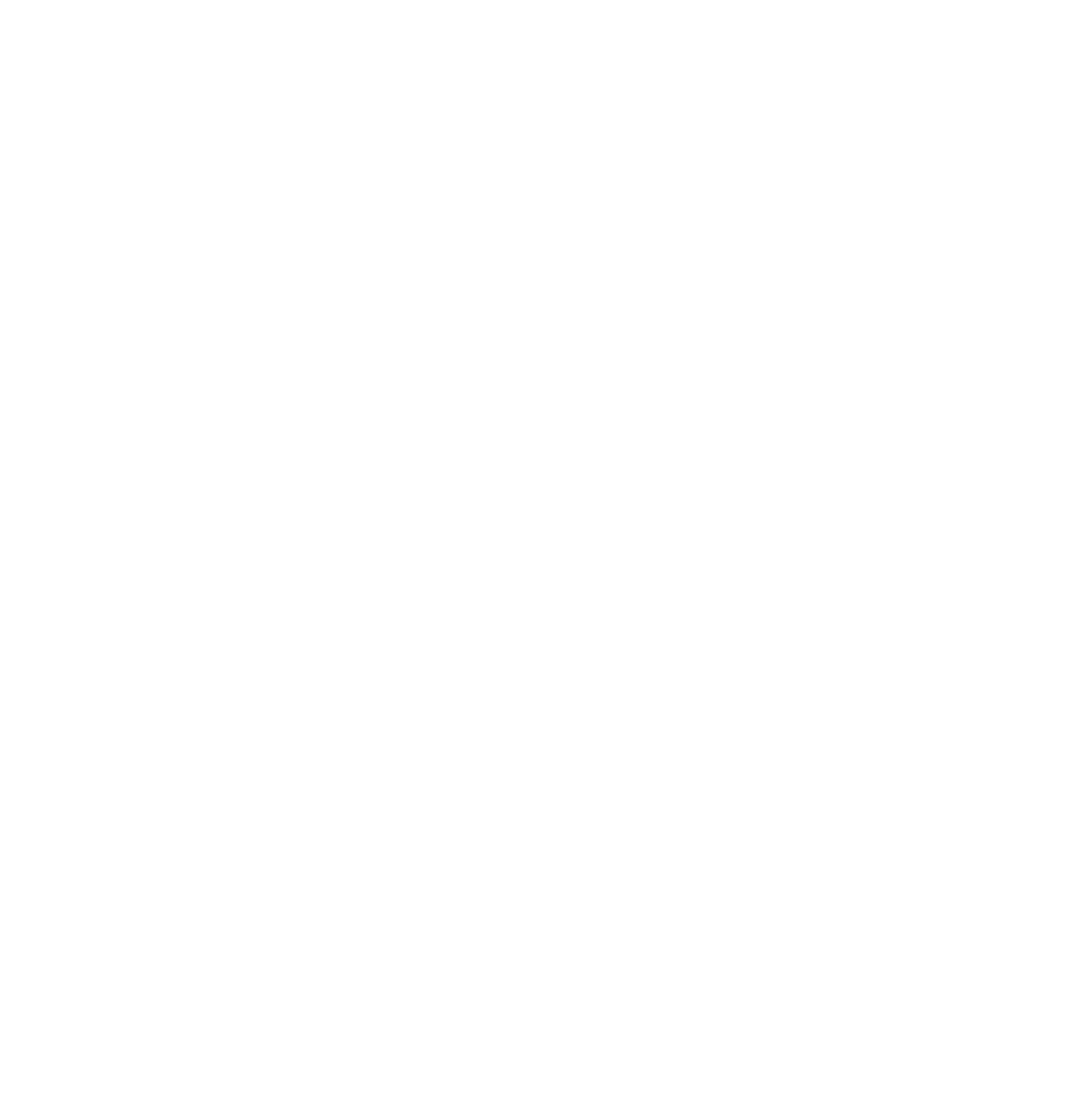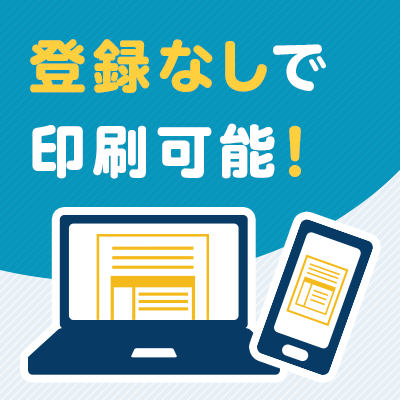第二新卒から公務員に転職するには?向いている人の特徴や採用難易度を解説!|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/08
第二新卒から公務員に転職するには?向いている人の特徴や採用難易度を解説!

この記事のまとめ
- 第二新卒が公務員になるメリットとして、「福利厚生が充実していて働きやすい」「雇用が安定している」点が挙げられる。
- 公務員に向いているのは、社会貢献にやりがいを感じ、コミュニケーションスキルが高い人。
- 第二新卒から公務員を目指すには、希望する職種を絞り、試験勉強へ集中することが重要。
公務員は安定した雇用と給与が魅力で、第二新卒にとっても有望なキャリアのひとつです。しかし、公務員になるには試験を受ける必要があるだけでなく年齢制限もあるため、誰でも目指せるわけではない点に注意しましょう。
この記事では、公務員を目指している第二新卒に向けて試験の難易度や向いている人の特徴を解説します。公務員への転職方法や転職事情を押さえたうえで試験勉強を進めると、より採用される確率を上げられるでしょう。
目次
第二新卒が知っておきたい公務員の基本情報

公務員は民間企業と仕事内容や転職の仕方、給与システムなどが異なります。第二新卒で公務員を目指すのであれば、まず公務員の基本情報をしっかりと押さえておきましょう。ここでは、公務員への転職で知っておきたい情報をピックアップして紹介します。
民間企業との違い
公務員は国や地方自治体に雇用され、公務に従事します。安定性があり、終身雇用が一般的です。一方、民間企業は営利を目的とした組織であり、市場競争の影響を受けます。雇用形態は正社員や契約社員、派遣社員などさまざまです。
また、公務員は国民や地域をよりよくする行政業務が主な仕事・目的であるのに対し、民間企業は利益追求のビジネスであり、特定の顧客に対して商品やサービスの提供を行います。
待遇面においても違いがあり、公務員は国や自治体が決めたルールに従って給与が支払われます。それに対して民間企業は、企業ごとのルールや業績に基づいて給与が支給される形が一般的です。
公務員の種類
公務員は「国家公務員」「地方公務員」「公安系公務員」の3つに大別でき、それぞれ次のような特徴があります。
- 国家公務員:国の政策に関わる分野を担当。総合職、一般職、専門職に細分化される
- 地方公務員:地域の行政に携わる行政職や技術職のほか、資格・免許が必要となる職種も存在する
- 公安系公務員:自衛官や警察官、消防士など街の安全を守る職種
自分が将来どのようなキャリアを歩みたいかを明確にしたうえで、適切な進路を探しましょう。
公務員の給与システム
公務員の給与は等級に基づいて決まります。地方公務員を例に挙げると、職務内容や複雑さ、責任の度合いなどを表す「級」と、職務経験年数を表す「号給」の組み合わせによって給与が決まります。
また、公務員は「扶養手当」「特殊勤務手当」「時間外勤務手当」「夜間勤務手当」「地域手当」「住居手当」「通勤手当」などの手当が充実している点も特徴です。中でも地域手当は最高で俸給などの20%となる地域もあり、給与総額に大きな影響を与えます。公務員の年収は地域によって大きく異なるため、どこで働くかも重要です。
公務員試験の受験可能年齢
公務員になるには試験に合格する必要があります。しかし、公務員試験には年齢制限があり、一定の年齢を超えた人は受験できません。また、受験可能年齢は試験種によって異なります。
国家公務員試験では30歳を上限としているケースが多く見られ、地方公務員試験は30歳前後を上限としている自治体が多くあります。しかし地方公務員試験で26歳前後を上限としている自治体もあり、第二新卒でも年齢によっては受験できない可能性がある点に注意が必要です。
公務員の試験内容
公務員試験は、教養・専門・論文などを問う一次試験と、面接・討論などの様子を評価する二次試験に分かれています。
まずは一次試験で、自然科学や人文科学といった教養が試されます。続く専門試験では経済学や法律、論文試験では行政が力を入れているテーマから出題されるのが特徴です。いずれも膨大な試験範囲の中から出題されるため、入念な準備が欠かせません。
二次試験では個別面接や集団討論など、コミュニケーションスキルを試されます。あらゆるテーマで会話ができるように、事前準備を徹底しましょう。
社会人が公務員へ転職する際の採用枠は主に2つ
公務員への転職には、「一般枠」と「社会人枠」の2種類があります。一般枠は従来の公務員試験のことで、ほとんどの試験が30歳前後を年齢制限としています。しかし年齢要件さえ満たしていれば、高卒でも専門学校卒でも受験可能です。一般枠は社会人枠よりも受験科目が多いことから、膨大な勉強時間を確保する必要がある点には注意しましょう。
一方で社会人枠は民間企業で勤務している社会人向けの中途採用試験となっており、59歳まで受験可能としている自治体がほとんどです。しかし、一部を除いて30歳以上という年齢要件があります。加えて民間企業での一定の勤続年数が求められるため、第二新卒が社会人枠で受験するのは難しいといえるでしょう。
第二新卒から公務員への転職に向いている人の特徴

公務員と民間企業とでは仕事内容に大きな違いがあり、人によって向き不向きがあります。自分に公務員の適性があるかどうかを知っておくことで、転職後のイメージもしやすく、目指すうえでのモチベーションにもつながるでしょう。ここでは、公務員への転職に向いている人の特徴を4つ紹介します。
社会的貢献度の高い仕事がしたい人
地域の活性化や地方創生といった活動に興味を持っている方は、公務員に適性があるといえます。公務員の仕事は人々の生活を支えることに直結し、社会貢献度が高いと考えられるためです。
公務員は、ビジネスで利益を追求し続ける民間企業の活動とは異なり、市民の安全やよりよい生活に寄り添った業務が中心です。公益のための活動にやりがいを感じたい方におすすめの職種といえるでしょう。
コミュニケーションスキルがある人
公務員では、コミュニケーションスキルを持つ人材が重宝されます。業務では、部署内のメンバーと連携を図るのはもちろん、市民や部署が異なるメンバーとの折衝も必要になるためです。
受付窓口や電話口で市民から寄せられる質問・意見によっては、複数の職員と共同で作業を進める意識が欠かせません。細やかな連携や丁寧なコミュニケーションを心掛けられる方に適性があるといえます。
ルーティンワークの精度が高い人
書類作成や資料整理といった日々のルーティンワークが得意な方も、公務員の業務に適性があるといえるでしょう。部署によっては日々同じような作業や連絡をこなす機会も多く、仕事の速さと正確さが重視されるためです。
したがって仕事を通じた成長やスキルアップを感じたい方は、入職後にギャップを感じる可能性があるため注意しましょう。
環境の変化に柔軟に対応できる人
公務員は特定の個人・団体との癒着防止や幅広い業務経験を積んでもらう目的から、人事異動が頻繁に行われます。職種にもよりますが、頻度は2年〜4年に1回、早くて半年で異動となるケースもあります。
そのため、部署や仕事内容が変化しても柔軟に対応できる人が向いているといえるでしょう。部署移動によって、新たな人間関係の構築や新しい仕事を覚えることに大きなストレスを感じる人は、公務員の仕事が向いていない可能性があります。
第二新卒が公務員になる3つのメリット

第二新卒は公務員を目指すことで、働くうえでの条件を改善できる場合があります。現職では達成できない、やりがいを感じられる業務も少なくありません。ここでは、第二新卒が公務員になる3つのメリットを紹介します。いずれも転職後のイメージを膨らませる際に役立つ情報です。
1.社会への貢献度が高くやりがいを感じやすい
公務員は、街に住む人々の生活基盤を支える仕事です。社会的な意義も大きく、仕事を通じたやりがいも感じやすいのが特徴といえます。
現職で仕事へのモチベーションを見いだせない方にとって、公務員は転職先候補のひとつとしておすすめです。民間企業への転職は多くの選択肢がある一方、仕事の充実度まで保証されているとは限りません。自分の仕事が人々の役に立っていると実感したい方は、ぜひ公務員を目指してみてください。
2.福利厚生が充実していて働きやすい
福利厚生を重視している方にとって、公務員は働きやすい環境だといえます。なぜなら公務員は育児休業や介護休暇といった福利厚生が充実しており、ライフイベントをサポートしてくれる制度が整っているためです。
出産・育児に関する制度が整っていない企業で働くと、休職中のサポートに物足りなさを感じたり、職場復帰しにくいと感じたりするでしょう。将来を見据えて長く働くためにも、公務員になるメリットは十分あるといえます。
3.雇用が安定している
公務員は雇用が安定している点がメリットです。収入が国の経済状況に左右されにくいため、生活を安定させたい方におすすめのキャリアといえるでしょう。民間企業の中にも条件がよく働きやすい企業は多く存在しますが、社会情勢によってやむを得ず倒産してしまう会社も少なくありません。
第二新卒が公務員を目指す際の3つの注意点

第二新卒から公務員を目指す場合、事前に知っておきたい情報があります。働きやすい環境を目指して公務員を志しても、後悔してしまう可能性があるためです。ここでは、第二新卒が公務員を目指す際の3つの注意点を解説します。
1.転居を伴う異動を言い渡されることがある
公務員は、職種によって転居を伴う異動のリスクがあります。地方公務員の場合は、県内や市内といった自宅からも十分通える範囲の異動が大半です。しかし国家公務員の場合は、県外への異動も少なくありません。
特に将来的に結婚して家庭との両立を考えている方は、慎重に判断する必要があるでしょう。転居によって家庭環境が変わると、その後のライフプランにも大きな影響がおよぶと予想されます。異動のメリットとデメリットを考慮し、転職するかどうか検討してみましょう。
2.副業ができない
公務員になると副業ができません。民間企業に勤めている方は、働き方改革によって副業や兼業が認められるようになってきました。しかし公務員の場合は、本業に支障を来してはならないという理由から、副業や兼業が禁止されています。
ただし、条件つきでできる副業も存在します。たとえば小規模農家に携わる場合です。一定の手続きや許可を得る必要はありますが、条件をクリアすれば兼業農家として事業に携われます。一方で、実際に取り組むかどうかは慎重な判断が必要です。
3.定時で帰れない部署がある
公務員として働く際に、一定の残業が生じる場合もあります。総務省の「地方公務員における働き方改革に係る状況―令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要― 」によると、令和3年度における職員ひとりあたりの残業時間は月に12.4時間、年間148.2時間であり、前年度よりも15.4時間増えている現状にあります。
ただし、規定時間以降の打ち合わせや追加業務の禁止、資料作成の効率化といった定時内で業務を終える取り組みに取り組んでいる自治体は増えつつあります。
第二新卒から公務員への採用難易度

公務員試験は、職種によって難易度が変化します。採用されるには、自分が希望する職種に向かって十分な対策を練ったり、採用枠が広い職種を狙ったりする戦略が必要といえるでしょう。ここでは、公務員の職種別難易度を解説します。
公安系職種は採用枠が多く狙い目
警察や消防といった公安関連の職種は、多くの人数を必要とします。そのため採用枠も多く、比較的採用されやすい傾向にあるのが特徴です。
実際に神奈川県における令和4年度警察官採用試験では、採用予定人数の約2倍近い人材を合格にしています。倍率は高い反面、十分な採用枠が用意されていることを考慮すると、少しでも公務員になるチャンスをつかみたい方におすすめです。
事務系職種は倍率が非常に高い
事務系職種は人気が高い傾向にあります。例年20倍近くの倍率の中で競争が行われており、狭き門をくぐり抜ける覚悟が必要です。
たとえば2021年度の国家公務員採用総合職試験では、大卒程度試験の申込者数が1万2,799人に対し採用者数は374人です。年度や区分によっても多少の違いはあるものの、データで確認しても人気の職種であることは間違いありません。これから事務職種を目指す方は、明確な対策スケジュールを立ててから挑戦しましょう。
第二新卒から公務員に転職する方法

第二新卒から公務員を目指すには、綿密な対策を練って採用試験に臨む必要があります。ただし、どのような手順で公務員になるのが効率的か、イメージが難しい方もいるでしょう。ここでは、第二新卒から公務員に転職する方法を紹介します。
目指す職種を確定する
公務員の職種は「国家公務員」「地方公務員」「公安系公務員」に分かれており、自分が将来どの職種で働きたいのか、具体的にイメージすることが最初のステップです。
実際に公務員の職種は総合職や行政職、技術職のように細分化されています。どの職種を目指すか明確にしておかないと、試験対策が難しくなってしまうため注意しましょう。
十分な学習時間を確保する
公務員試験対策にかかる時間は、約1,000時間ともいわれています。したがって最低でも1年程度の学習期間を確保しておきましょう。
すでに社会人として業務に携わっている第二新卒にとって、学習時間の捻出は重要な課題のひとつです。自分で学習計画を立てるのが難しい場合は、公務員試験対策を実施している予備校を利用したり転職エージェントによるアドバイスを受けたりするのもよいでしょう。
試験勉強に集中する
採用試験当日までの期間は、試験勉強に集中しましょう。勉強する際は、現職を続けつつ業務後や休日を利用して学習を進める方法がおすすめです。不合格になった場合のリスクも考慮しつつ、学習に専念するのが安全な方法と考えられます。
実際に現職を退職してから試験勉強を続けた結果、不合格になってしまうと収入源が確保できなくなります。キャリアにも空白期間ができてしまうため、やむを得ない事情を除いて、現職を続けながら学習を続けたほうが無難といえるでしょう。
第二新卒から公務員への転職をマイナビ転職エージェントで成功させよう!
第二新卒から公務員を目指すのであれば、マイナビ転職エージェントの活用がおすすめです。マイナビ転職エージェントでは、第二新卒がスムーズな転職活動が実現できるように、転職先の情報収集や転職プランの検討などをサポートします。
これから公務員を目指す方にも役立つ二次試験の面接対策も提供しているため、転職活動が初めての第二新卒の方でも安心してご利用いただけます。
まとめ
第二新卒から公務員に転職することは可能ですが、試験には年齢制限がある点に注意しましょう。公務員試験に合格するには約1,000時間以上の膨大な勉強時間も必要であるため、年齢制限が近づいている場合は早めに行動することが大切です。
転職に関する悩みや不安のある方は、ぜひマイナビ転職エージェントにご相談ください。マイナビ転職エージェントには、第二新卒の転職ノウハウを持ったキャリアアドバイザーが在籍しています。あなたのスキルや希望に合った求人の紹介や転職成功のアドバイスなどを通じて、転職を成功に導くサポートをいたします。

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。
関連コンテンツ
-

第二新卒
新卒と第二新卒の違いは?第二新卒が転職を成功させるポイントを解説!
-

第二新卒
「第二新卒の転職はやめとけ」は本当?5つのメリットと成功のコツを紹介
-

第二新卒
第二新卒で転職するメリットとは?強みを活かして内定獲得を目指そう!