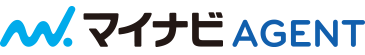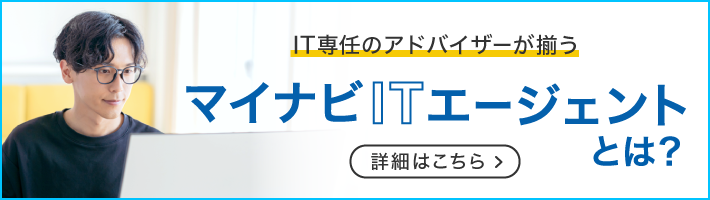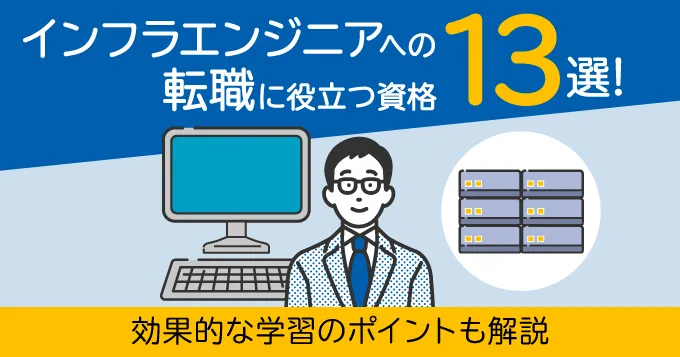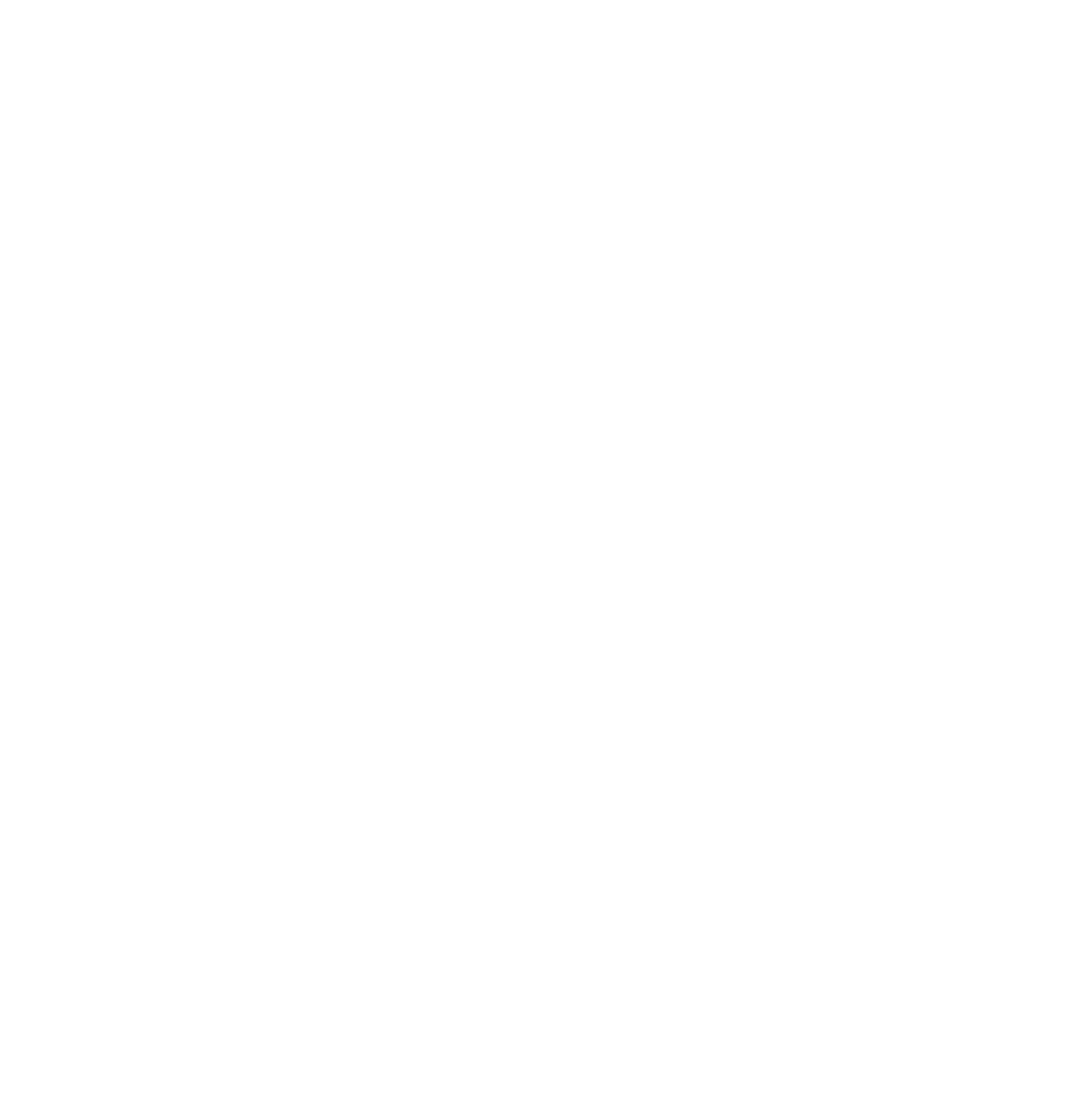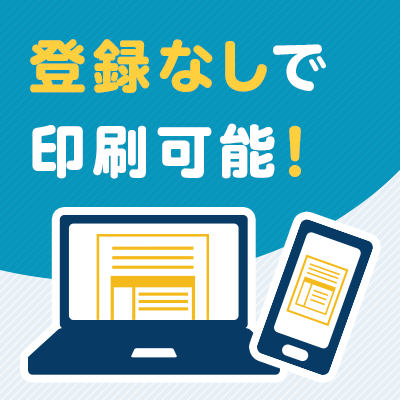インフラエンジニアは将来性がある職業!転職するメリットや注意したいこと|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/28
インフラエンジニアは将来性がある職業!転職するメリットや注意したいこと

この記事のまとめ
- インフラエンジニアに将来性がある理由として、「AI・ロボットに仕事を奪われにくい」「慢性的な人手不足により需要が安定している」ことが挙げられる。
- インフラエンジニアは未経験者でも挑戦できる職業であり、年収が高く、キャリアパスが豊富にある点が魅力。
- インフラエンジニアとして長期的に活躍するには、クラウドの知識を身につけたり、資格を取得したりすることが大切。
インフラエンジニアは企業の業務を支えるITインフラの整備・運用を担う存在として、DXやクラウド化の進展に伴い注目度が高まっています。将来性があり、スキルしだいで高収入も狙える職種ですが、夜勤があるなど人によっては働き方が合わない可能性がある点に注意が必要です。
この記事では、インフラエンジニアへの転職を検討している方に向けて、将来性や転職するメリット、あらかじめ知っておきたい注意点などを解説します。自分に合ったキャリアを描くために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インフラエンジニアとは

インフラエンジニアとは、ITサービスを支える基盤となる「インフラ」を設計・構築・運用・保守する技術者のことです。ITインフラには、サーバー、ネットワーク、データベース、OS、セキュリティなどが含まれ、これらが正しく動作しなければWebサービスや業務システムは機能しません。
たとえば、企業のメールシステムや社内ネットワーク、ECサイトのバックエンドなど、一般ユーザーには見えない部分を支えるのがインフラエンジニアの仕事です。障害発生時には原因を特定して迅速に復旧する必要があるため、技術力だけでなく、冷静な対応力や責任感も求められます。
インフラエンジニアには将来性がある!その3つの理由とは

ITシステムの基盤となるインフラ環境の構築や運用に携わるインフラエンジニアは、IT社会が進展する中で重要な役割を担っています。テクノロジーの変化に柔軟に対応できるインフラエンジニアは、今後ますます求められる存在となるでしょう。ここでは、インフラエンジニアに将来性がある3つの理由を紹介します。
需要が安定している
インフラエンジニアは、企業のIT基盤を支える存在として、安定した需要があります。年々DXの推進が加速しており、製造業や流通業、サービス業などのあらゆる業界でITシステムの導入が進んでいます。システムを安定稼働させるには、サーバーやネットワーク、クラウド環境などの構築・運用に携わるインフラエンジニアの存在が欠かせません。
また、IT業界全体が慢性的な人手不足に陥っており、特に高度なスキルを持つインフラエンジニアは引く手あまたです。クラウド化が進んでも、ITインフラの構成や運用には専門知識が必要なため、機械的に自動化することは難しい領域といえます。
加えて、クラウドとオンプレミスを併用する企業も多く、どちらの環境にも対応できるインフラエンジニアの価値は高まり続けています。将来的にも、需要が大きく減少する可能性は低いといえます。
新技術の開発・活用が進んでいる
IT分野では技術革新のスピードが速く、新しい仕組みやシステムが次々と登場しています。たとえば、クラウドコンピューティング、AI、IoT、5G、光電融合技術による次世代通信「IOWN」など、ITインフラの形も進化し続けています。こうした技術を実際に活用するには、それを構築し、安定して稼働させるインフラエンジニアの存在が必要不可欠です。
また、オンプレミスからクラウド環境への移行、ハイブリッド構成の導入などの複雑なインフラ環境が主流になりつつあり、設計や運用の知識が求められる場面が増えています。つまり、新しい技術の導入が進むほど、それを理解し、実務に活かせるインフラエンジニアの重要性は高まるでしょう。
AI・ロボットに仕事が奪われにくい
世の中のいくつかの仕事はAIに取って代わられるといわれていますが、AIを支えるITインフラ自体がなくなることはなく、インフラエンジニアの仕事が減少する可能性は低いといえます。ただし、AIがインフラエンジニアの仕事をサポートするツールとして活用されることは考えられるでしょう。
-
- 関連記事
- インフラエンジニアの求人を見る
インフラエンジニアになるメリット

インフラエンジニアは将来性が高いだけでなく、転職先として多くの魅力を持つ職種です。特に年収水準の高さや未経験からでも挑戦できる門戸の広さ、そして将来的なキャリアパスの多さが、エンジニア職の中でも注目されている理由です。
IT業界に興味があり、安定した環境でスキルを磨きたい人にとって、インフラエンジニアは理想的な選択肢といえます。ここでは、インフラエンジニアになるメリットを3つ紹介します。
年収が高い
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、インフラエンジニアの平均年収は752万6,000円とされており、年収水準が高い点が魅力です。年収が高い理由としては、ITインフラの設計や運用に高度な専門性が求められることが挙げられます。
ただし、年収は個人のスキルレベルによって大きく異なります。たとえば、ITSS(ITスキル標準)でレベル1~レベル2の初級者では年収400万円~600万円台が一般的ですが、レベル5以上のように高度なスキルとマネジメント力を備えた人材であれば、年収900万円以上も珍しくありません。
このようにスキルに応じて年収が上がる業界であるため、努力と成長がそのまま収入に直結します。地道にスキルアップを続けることで、長期的に高収入を目指せる職種です。
参照:システムエンジニア(基盤システム)|職業情報提供サイトjob tag|厚生労働省
未経験でも転職できる
インフラエンジニアは専門的な知識が必要な職種ですが、未経験からでもチャレンジできる点が魅力です。特に企業の中には、運用・監視業務からスタートして徐々に構築や設計へとステップアップできるようなキャリア育成制度を整えているところもあります。
人手不足が続くIT業界では、ポテンシャルを重視して採用する傾向があり、インフラ分野でも「未経験OK」「研修あり」などの求人が多く見られます。
キャリアパスが豊富にある
インフラエンジニアとしてのキャリアを積めば、さらなるキャリアパスが開かれます。インフラエンジニアの経験を活かせるキャリアパスの例は、以下のとおりです。
- ネットワークスペシャリスト
- セキュリティスペシャリスト
- プロジェクトマネージャー
- ITコンサルタント
まずは自分が技術面を極めたいのか、マネジメント職を目指したいのかを明確にしましょう。技術面を極めたい方は、その分野のスペシャリストを目指せます。マネジメント職を目指したいのであれば、リーダー業務に積極的に挑戦して経験を積みつつプロジェクトマネージャーに転職し、その後ITコンサルタントや経営職を目指すのがおすすめです。
-
- 関連記事
- インフラエンジニアの転職知識まとめ
インフラエンジニアを目指すうえで知っておきたい注意点
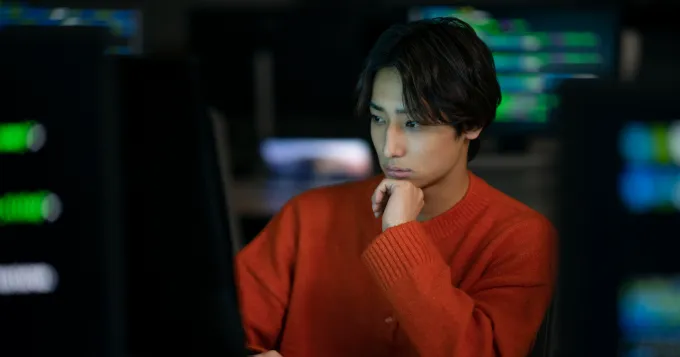
インフラエンジニアはやりがいのある職種ですが、事前に知っておきたい注意点もあります。特に勤務形態や働き方の面では、一般的なオフィスワークとは異なる部分があるため、事前に理解しておくことが大切です。ここでは、インフラエンジニアを目指す際に押さえておきたい注意点を3つ紹介します。
シフト制・夜勤の勤務形態がある
インフラエンジニアは24時間365日止められないシステムを扱うため、特に運用・監視の現場ではシフト制や夜勤が必要になることがあります。初めて夜勤を経験する人にとっては、生活リズムが乱れるなど体調面で不安を感じる場合もあるでしょう。
ただし、シフト制ならではのメリットもあります。たとえば、平日の昼間に休みを取れることから銀行や役所の手続きがスムーズにできたり、休日の混雑を避けて出かけられたりします。夜勤に慣れれば、ワークライフバランスの調整がしやすくなる可能性もあります。
現場によってはリモートワークが難しい
IT業界全体ではリモートワークが広がっていますが、インフラエンジニアの中には現場対応が必要なケースも少なくありません。特に、ハードウェアの設置やメンテナンス業務、物理サーバーの運用・保守などでは、データセンターや現地オフィスに出向く必要があることから、リモートワークが難しい傾向です。
一方で、クラウド環境や仮想サーバーの監視業務など、物理機器を扱わない業務であれば在宅勤務が可能な場合もあります。配属先の業務内容や企業の方針によって働き方は大きく異なるため、求人を探す際には「リモート可」「出社あり」などの条件をよく確認しておきましょう。
運用・監視業務はルーティンワークが多い
インフラエンジニアのキャリアは、まず運用・監視業務からスタートすることが一般的です。このフェーズでは、システムの稼働状況を監視し、トラブルがないかを確認したり、決められた手順に沿ってメンテナンス作業をしたりといったルーティン業務が中心になります。
そのため、中には手応えや達成感を感じにくいと感じる人もいるでしょう。しかし、この段階で基礎知識を身につけ、障害対応の流れを経験することで、次のステップである構築・設計フェーズへの足掛かりになります。
インフラエンジニアに向いている人
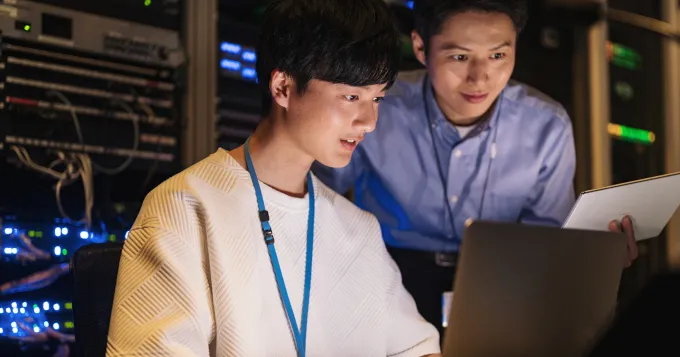
インフラエンジニアは専門的な知識やスキルが求められる職種ですが、理系出身である必要はなく、適性があれば誰でも目指せる分野です。それでは、どのような性格や志向の人がインフラエンジニアに向いているのでしょうか。ここでは、現場で求められる能力や姿勢から、インフラエンジニアに適している人物像を紹介します。
トラブルに冷静に対応できる人
インフラエンジニアの業務では、システムの障害やネットワークトラブルなど、緊急事態への対応が避けられません。特に24時間365日稼働しているシステムに関わる場合、深夜や休日でもアラート対応を求められることがあります。そのようなとき、慌てずに原因を分析し、最短で復旧に導くための判断が必要です。
パニックになってしまうと誤った対応をしてしまい、被害を拡大させるおそれもあります。そのため、常に冷静さを保ちながら、論理的に物事を考えられる人がインフラエンジニアには向いています。
チームでの連携ができる人
インフラエンジニアは、ひとりで黙々と作業するだけの仕事ではありません。プロジェクトを円滑に進めるためには、アプリ開発チーム、セキュリティチーム、運用部門、ベンダーなど、さまざまな関係者と連携を取りながら業務を進める必要があります。
特にインフラは「裏方」でありながら、ほかのチームの作業にも密接に関わる存在です。自分の考えを分かりやすく伝える力や、相手の要望を的確にくみ取る力が求められます。トラブル時や仕様変更の調整などでは、関係者とのスムーズな連携が重要になるため、一定のコミュニケーション能力を持ち、チームプレーを大切にできる人に向いているといえます。
学習意欲が高い人
IT業界は技術革新のスピードが速く、インフラの分野でも新しい技術やツールが次々と登場しています。クラウドサービスの進化やセキュリティ対策の高度化、AIや自動化の導入など、日々知識をアップデートしていかなければ、時代に取り残されてしまいます。
そのため、インフラエンジニアとして長く活躍するためには、常に新しい技術に興味を持ち、学び続ける姿勢が欠かせません。資格の取得や、勉強会・セミナーへの参加、最新情報のキャッチアップを習慣化できる人は、将来性のあるインフラエンジニアとしてキャリアアップもしやすいでしょう。
将来性のあるインフラエンジニアになる方法|スキルを磨く
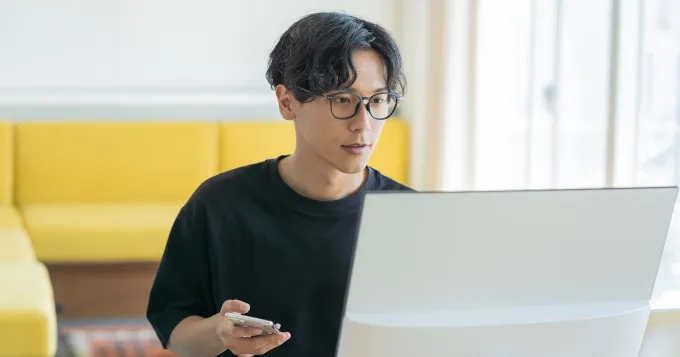
インフラエンジニアとして転職を成功させたいと考えている方にとって、「スキルを磨くこと」は避けてとおれない道です。企業のIT基盤を支える役割を担う以上、一定レベルの知識・技術を身につけておく必要があります。将来性の高いインフラエンジニアになるためにも、以下で紹介するスキルレベルを磨きましょう。
クラウドの知識・スキル
ITインフラの構築でクラウドを活用するケースがあるため、AWS(Amazon Web Services)やGoogle Cloud、Microsoft Azureなどの代表的なクラウドサービスの知識の習得が欠かせません。主要なサービスとその機能を正しく理解し、設定・運用できるように学んでおきましょう。また、それぞれのクラウドサービスの特徴やメリット・デメリットを把握しておくと、設計時の比較検討に役立ちます。
プログラミングスキル
従来、インフラエンジニアにプログラミングスキルは必須ではありませんでした。しかし、ITインフラがクラウドに変化しつつあることでコードによる環境設定が主流となり、インフラエンジニアにもプログラミングスキルが求められています。
また、インフラ設定をコード化することで、設定ファイルの作成や複数サーバーへのファイルコピーなど業務の効率化にもつながります。まずは、覚えやすく利用しやすい軽量プログラミング言語の「Python」や「Ruby」の習得がおすすめです。
サーバーの設計・運用スキル
インフラエンジニアはサーバーを扱う機会が多く、設計や構築・運用を担当します。設計ではITシステムを動かすのに必要なスペックを見積もり、適したハードウェアを調達・設置します。構築では要件にしたがってOSやミドルウェア・ソフトウェアをインストールし、予定どおりに動くように設定するのが主な仕事です。
運用ではサーバーが正常に稼働しているかを常時監視し、障害が発生したら復旧作業を実施します。ほかにも、定期的なメンテナンスやアップデート、必要に応じてハードウェアの交換を担当するのもインフラエンジニアの仕事です。
上記の業務を担当するには、サーバーに関する広範なスキルに加えて設計面の知識が求められます。クラウドサーバーを使用するケースもあるため、クラウドに関する知見も深めておきましょう。
ネットワーク関連のスキル
ITシステムを動かすには、データを送受信するためのネットワークが欠かせません。ネットワークを設計・構築・運用するのも、インフラエンジニアの重要な仕事です。想定される負荷を計算して適したスペックのネットワークを構築し、安定してシステムにアクセスできるようにします。
構築段階ではリピーターやLANスイッチ・ルーター・ロードバランサーなどの機器を用意し、それらをケーブルで接続します。また、機器が正常に動作するように設定するのもインフラエンジニアの役割です。
ネットワーク全般に関するスキルが求められるため、使用されている技術や設計・構築方法を学習しておきましょう。サーバーのときと同様にクラウドサービスを使用してネットワークを構築することもあるため、併せて学習しておくのがおすすめです。
将来性のあるインフラエンジニアになる方法|資格を取得する

未経験からインフラエンジニアを目指す場合、スキルの証明として「資格取得」は効果的な手段です。特に国家資格や業界で評価されているベンダー資格は、転職時のアピール材料にもなります。将来性のあるインフラエンジニアになるためにも、自身のレベルに合った資格から挑戦していきましょう。
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験は、「独立行政法人情報処理推進機構(IPA)」が主催している国家試験です。情報処理技術者試験の中でもITエンジニア向けの基礎的な資格に位置づけられていて、規格や要件定義・システム構築などに関するスキルを証明可能です。
合格率はおおむね40%台後半~50%台前半であり、未経験者が試験に合格するには計画的に学習を進める必要があります。試験はCBT方式で随時実施しているため、学習の進捗状況に応じて適したタイミングで受験可能です。
参照:統計情報(基本情報技術者試験)|独立行政法人情報処理推進機構
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験は「独立行政法人情報処理推進機構(IPA)」が実施する国家試験のひとつで、高度IT人材を対象にした試験です。システムの企画や要件定義・設計・開発・運用に必要なスキルだけでなく、マネジメント分野や経営分野のスキルも問われます。
そのため、いずれプロジェクトマネージャーとして活躍したいと考えている方にもおすすめの試験です。合格率はおおむね20%台後半で、合格するには十分な勉強が求められます。基本情報技術者試験とは異なり試験が年2回と限られているため、試験日から逆算して計画的に勉強することが必要です。
ネットワークスペシャリスト試験
ネットワークスペシャリスト試験も、「独立行政法人情報処理推進機構(IPA)」が主催する情報処理技術者試験のひとつです。ネットワークに関する幅広い知識が問われ、ネットワークエンジニアやインフラエンジニアに適した国家試験といえます。
合格率はおおむね15%前後と難度は高めです。未経験から合格するのは容易ではありませんが、インフラエンジニアとして市場価値を高めるうえでおすすめの資格です。
参照:ネットワークスペシャリスト試験|独立行政法人情報処理推進機構
Linux技術者認定 LinuC
Linux技術者認定 LinuCは、サーバーOSのLinuxに関する知識を問う資格です。Linuxに関する資格には、「LPIC」と呼ばれる全世界に対応している国際的な資格もあります。LinuCは日本国内向けに作られているため、取得しやすい資格といえます。
LinuCは、レベル1~レベル3、システムアーキテクトの4つの難度に分かれています。未経験者は取得しやすいレベル1から挑戦するのがおすすめです。
シスコ認定
シスコ認定は、アメリカの大手ネットワーク機器メーカーであるCisco Systems社が認定するベンダー資格です。認定レベルは4つあり、エントリー・アソシエイト・プロフェッショナル・エキスパートの順に難度が上がっていきます。
また、セキュリティ・サービスプロバイダーなど認定技術も8つに細分化されており、自分の学びたい分野に合わせて受験できる点が魅力です。高度なネットワーク技術の知識を学びたい方は、シスコ認定の受験を検討するとよいでしょう。
AWS認定・Google Cloud認定
クラウドサービスを活用したインフラ構築に携わる機会もあるため、クラウド関連のスキルを証明しておくのもおすすめです。クラウドベンダーが実施している認定試験に、AWS認定やGoogle Cloud認定があります。いずれもそれぞれのクラウドサービスを使うのに必要なスキルを有していることを証明可能です。
まずは頻繁に使用するサービスに関連する試験を受験するとよいでしょう。その後、学習を重ねつつさまざまな分野の試験に合格すれば、対応できるプロジェクトの幅を広げられます。
参照:AWS認定
将来性のあるインフラエンジニアになる方法|選考対策を万全にする

スキルや資格を身につけても、選考対策を万全にしておかなければ転職活動の成功は勝ち取れません。特に未経験からインフラエンジニアを目指す場合は、書類や面接で自身の強みや意欲をしっかりと伝える工夫が大切です。ここでは、自己PR、志望動機、面接の3つの観点から選考対策のポイントを解説します。
自己PR
自己PRでは、単なる経歴紹介にとどまらず、「自分はどのような価値を企業にもたらせるのか」を明確に伝えることが重要です。未経験の場合は、前職で培ったスキルや姿勢をインフラエンジニアという職種にどう活かせるかを具体的に述べましょう。
たとえば、「前職で複数部署を調整しながら業務を進めた経験があるため、ITプロジェクトでも周囲と連携しやすい」といったように、再現性や応用力をアピールすると効果的です。さらに、自主的に学習している内容や、資格取得に向けた努力も加えることで、成長意欲の高さが伝わります。自分の強みをインフラ業務と関連づけて伝えましょう。
志望動機
未経験からインフラエンジニアを目指すときには、志望動機で「なぜインフラエンジニアなのか」「なぜ応募先企業を志望したのか」の2つの軸を明確にすることが基本です。「IT業界に興味がある」ではなく、ITインフラに興味を持ったきっかけや、応募先企業の技術領域に共感した点をしっかり伝えましょう。
たとえば、「貴社が注力するクラウド技術に魅力を感じ、資格取得と並行して実践経験を積みたいと考え志望しました」など、その企業で働く意義を言語化できると評価につながります。自分の成長と企業のビジョンが合致していることを伝えられれば、説得力のある志望動機になるでしょう。
面接
面接では、事前準備が結果を大きく左右します。自己紹介や志望動機に加え、「将来どうなりたいか」「ストレスにどう対処するか」などの定番の質問への回答はスムーズに話せるよう練習しておきましょう。
また、逆質問を用意することも重要です。たとえば、「チームの構成や雰囲気を教えてください」といった前向きな質問をすることで、入社意欲をアピールできます。未経験者でも「企業や職種についてしっかり調べてきた」ことが伝われば、好印象を持たれやすくなります。
まとめ

インフラエンジニアは、今後ますます社会から求められる職種です。将来性のあるインフラエンジニアとして活躍するためには、クラウドやネットワークなどのスキルを磨き、自分の価値を高めることが不可欠です。
将来性のあるインフラエンジニアとして活躍したい方、転職活動に悩みのある方は、IT業界に特化した転職支援サービスのマイナビ転職ITエージェントにご相談ください。業界事情に精通したキャリアアドバイザーが、スキルレベルに合った求人の紹介から選考対策までサポートします。
関連記事:マイナビ転職ITエージェント
-
- 特集コンテンツ
- インフラエンジニアの転職知識まとめ
- 職種図鑑
- インフラエンジニアとは?仕事内容・年収・資格について
- 求人情報
- インフラエンジニアの求人一覧
関連コンテンツ
-

IT業界
未経験でもWebデザイナーになれる?必要なスキルやポートフォリオの作り方
-

IT業界
システムエンジニアのキャリアパス|全体像と進路・スキル・資格を解説
-

IT業界
女性システムエンジニア|魅力と転職成功のステップを徹底解説