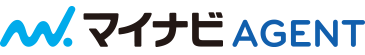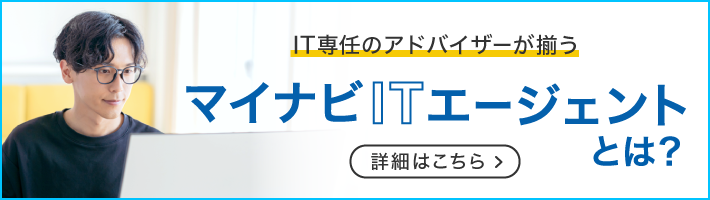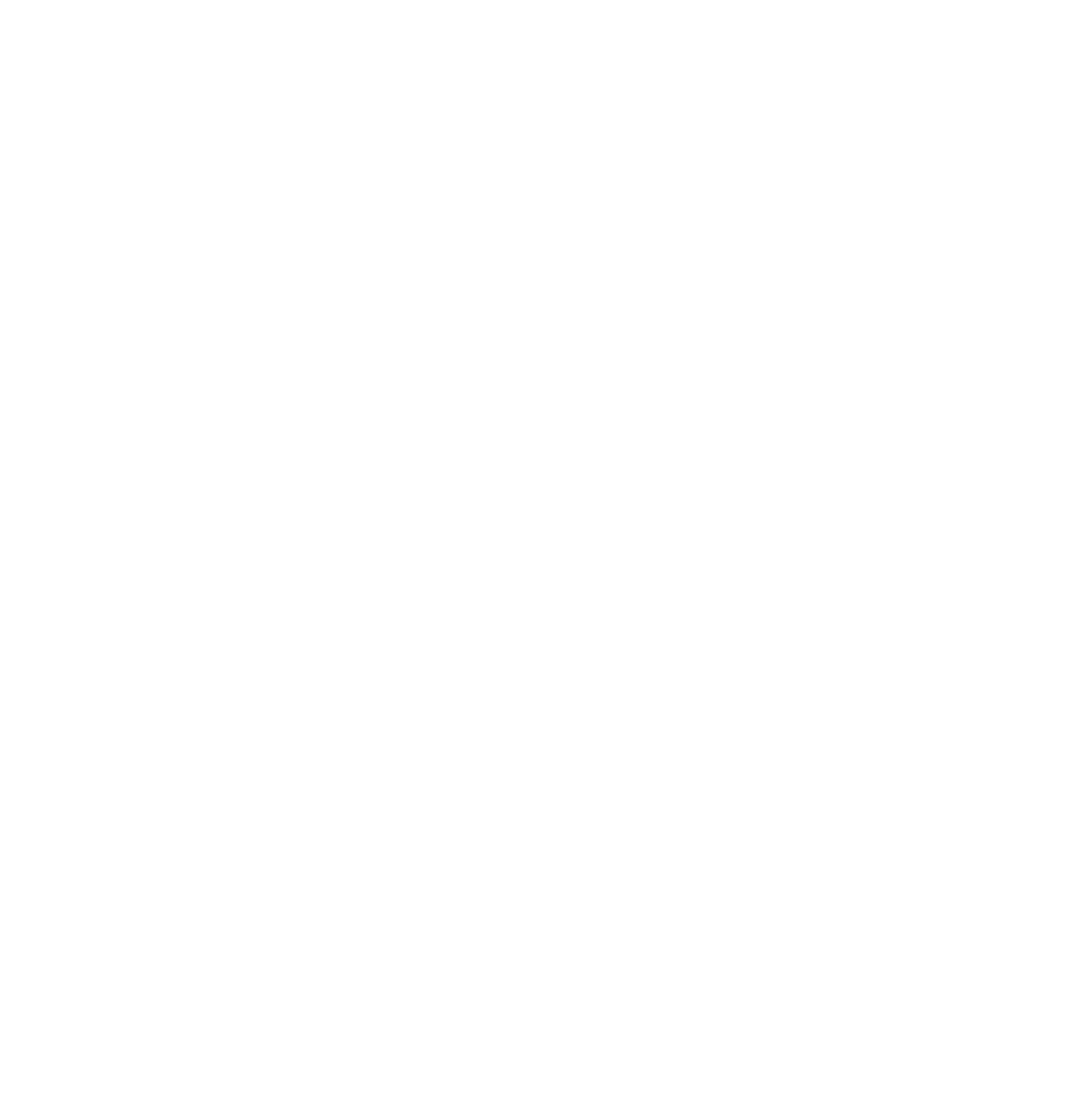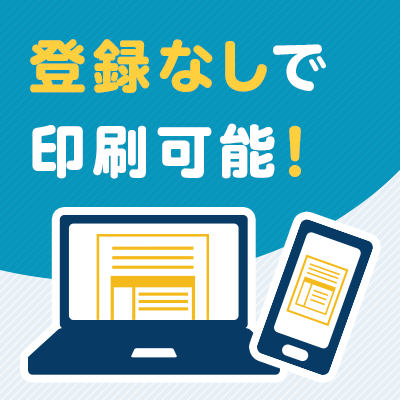ITコンサルタントに資格は有用?キャリアアップのポイントも紹介|求人・転職エージェント
更新日:2023/10/17
ITコンサルタントに資格は有用?キャリアアップのポイントも紹介

この記事のまとめ
- ITコンサルタントとして活躍するには、高度なエンジニアリングスキルに加えてマネジメントスキルやコンセプチュアルスキルが欠かせない。
- 資格を取得すると自分のスキルレベルを客観的に証明でき、より有利に転職できる可能性が高まる。
- ITコンサルタントになるには、ITエンジニアとしてのスキルを高めながらコンサルティングファームへの転職を目指すとよい。
ITコンサルタントになるために必要な資格はありません。しかし、これからITコンサルタントを目指すにあたり、またITコンサルタントとしてキャリアアップするために有利な資格があるのかが知りたい方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ITコンサルタントへの転職やキャリアアップに役立つ資格を紹介します。経験を積みながらスキルアップに励み、関連資格を取得すればより有利な条件で転職しやすくなるでしょう。
目次
ITコンサルタントが担当する業務

コンサルタントは経営面で何らかの課題を抱えているクライアントに対して、その課題を解決するためのサポートを提供する職です。ITコンサルタントは、経営課題を解決する手段としてIT技術を活用します。
適切な解決策を考えて施策に落とし込み、 実行をサポートするにはIT分野に関する深い知識やスキルだけでなく、ビジネスや経営に関する知識も必要です。ITコンサルタントとして活躍することを望むのであれば、ITだけではなく経営面にも関心を抱きましょう。
ITコンサルタントになるために資格は必要?
ITコンサルタントの主な仕事は、企業の課題をITの力で解決することです。特定の資格がなければ業務に携われないわけではなく、無資格でもITコンサルタントに転職できます。
しかし、クライアントの課題を解決するためのサポート業務には、経営方針に沿ったIT戦略の提案やプロジェクトの進行管理などが含まれます。導入するシステムの提案・開発や運用など、多くの業務を担当するのが特徴です。資格を取得していればその分野に精通していることをアピールでき、より顧客からの信頼を得られるでしょう。
ITコンサルタントには高いスキルが必要とされるため、難易度の高い資格がほとんどです。そのため、取得すると十分なスキルレベルに達していることを客観的に証明できます。資格の勉強を通じて経営の知識を習得すれば、ITスキルだけでなく経営スキルが高く評価されることもあるでしょう。
転職に有利な資格1 ITコーディネータ

「ITコーディネータ(ITC)」は、2001年に国家プロジェクトの一環として設けられた経済産業省が推進する資格のひとつです。内容は「ITストラテジスト」と重なる部分がありますが、ITコーディネータは毎年更新が必要な資格である点が異なります。
ITコーディネータの資格を更新するには、更新前年度の実践力ポイントが10以上、更新前年度の実務活動報告書を提出、3年ごとのフォローアップ研修受講、更新手続料の入金が必要です。
ITコーディネータ取得による「メリット」
ITコーディネータ試験では、経営やマネジメントに関する知識も問われます。資格を取得すると「ITの知識に加えてビジネスの知識も深く知っている」人であることを証明できるでしょう。
さらに毎年資格の更新が必要になるため、常に「最新のスキル」を持っている(勉強を続けている)という信頼も得られます。
ITコーディネータ試験の「対策」
ITコーディネータ試験の出題形式は、複数の選択肢から選ぶ「多肢選択式」です。試験時間は120分ありますが、問題数が100問と多いため熟考する時間はありません。素早く、かつ正確に答えていくことが求められます。
なお、「公認会計士」「中小企業診断士」「PMP」などの有資格者は一部の選択問題が免除され、60問の試験(制限時間は80分)をクリアすれば資格が得られます。
ITコーディネータ試験の概要
|
(2023年9月時点)
転職に有利な資格2 ITストラテジスト

「ITストラテジスト」は、経済産業省が認定し独立行政法人情報処理推進機構が実施している国家試験です。
経営方針に基づくIT戦略を立案、システム全体の計画を立てて開発プロジェクトを支援する役割を担うCIO(Chief Information Officer/最高情報責任者)やCTO(Chief Technology Officer/最高技術責任者)向けの資格で、ITコンサルタントを目指す人にとってもスペシャリストであることを示すにふさわしい資格といえます。
ITストラテジスト取得による「メリット」
ITストラテジストの試験に合格するには、経営戦略を正確に捉え、課題を把握し分析するスキルが必要です。併せてITに関する幅広い知識や経験も要求されます。経営とITの両面を高いレベルで理解していることを客観的に示せるため、本資格を取得しているITコンサルタントは企業から高い評価を得られるでしょう。
IoTやビッグデータ、AIなどITに関する技術は飛躍的に発展しており、ビジネスを伸長させるには積極的に活用することが求められます。ITの技術と経営戦略を高次元で描けるITストラテジストの需要は、今後も高まるでしょう。
ITストラテジスト試験の「対策」
試験は午前中に多肢選択式問題(30問・50分と25問・40分の2回)が出題され、午後は記述・論述試験(最低2,000字・90分と120分)が実施されます。市販の参考書での学習が前提ですが、試験ではIT関連の細かい知識は問われません。
また、論述試験では文章力が重視されます。ITの知識を踏まえたうえで物事を筋道立て、論理的な文章を書くことが重要です。過去問を解くだけでなく、文章を書く訓練を重ねましょう。
なお、以下の条件を満たす受験者は、最初の試験(選択問題30問)を免除されます。条件を満たしてから2年間は免除されるため、該当する方は忘れずに申請しましょう。
- 「応用情報技術者試験(AP)」「情報処理技術者試験(高度試験)」「情報処理安全確保支援士試験」の合格者
- 「情報処理技術者試験(高度試験)」もしくは「情報処理安全確保支援士試験」の午前I試験で基準点以上の成績を修了
ITストラテジスト試験の概要
|
(2023年9月時点)
転職に有利な資格3 中小企業診断士

「中小企業診断士」は、中小企業支援法の第11条に基づいて実施される経営コンサルタントに関する国家資格です。ITに特化した資格ではないものの、中小企業の経営診断や助言を担当できるため業務の対象は幅広く、有資格者は大企業からも高く評価されます。
中小企業診断士取得による「メリット」
中小企業診断士を取得すると、「企業経営に関するコンサルティングのエキスパート」であることを証明できます。
経営課題の洗い出しや解決に向けた提案などの業務を行うITコンサルタントに人気の資格で、持っていると顧客から大きな信頼が得られるでしょう。有資格者は経営コンサルタントとして独立したり、企業内診断士として働いたりすることも可能です。
中小企業診断士資格を取得し、ITスキルに加えて経営関連のスキルを有していることを証明すれば、よりITコンサルタントとしての自分の価値を高められます。
中小企業診断士試験の「対策」
資格を取得するには、1次・2次試験通過後に15日以上の実務補習もしくは実務従事を行う方法と、1次試験通過後に指定の養成講座を受講する方法の2とおりがあります。
ここでいう実務補習とは、国の登録実務補習機関である中小企業診断協会が実施する補習を受けることをいい、実務従事は既定の中小企業の診断・助言を担当し、その企業から証明をもらうことを指します。
なお、1次試験はマークシートによる多肢選択式試験、2次試験は筆記・口述試験で、マーケティングや運営管理をはじめとする幅広い知識を問われます。
中小企業診断士試験の概要
|
(2023年9月時点)
転職に有利な資格4 PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)

「PMP(Project Management Professional)」とは、PMI(米国プロジェクトマネジメント協会)が認定しているプロジェクトマネジメントの国際資格で、日本ではPMI日本支部が試験を実施しています。
法的な資格や免許ではありませんが、資格の保有者はプロジェクトマネジメントに関する経験・知識・教育を有している人材と認められるなど、ITのみならずさまざまな業界から注目されている資格のひとつです。
PMP取得による「メリット」
後述するプロジェクトマネージャ試験と重なる部分が多いものの、国際資格のため海外企業や外資系企業への転職でも役立ちます。
受験資格を得るには事前に「実務経験」および「研修の受講」が必須となっていることも、より高いスキルを持っている証明になるといえるでしょう。体系的な仕事の進め方を身につけ、効率よく業務を進められる人材として、あらゆる場面で高い評価を得られるようになります。
PMP試験の受験資格と「対策」
PMP試験の対策として、さまざまな参考書が発売されています。 PMPを受験するには、下記の条件をクリアしなければなりません。なお、実務経験としてカウントできるのは過去8年以内のものに限定されている点に注意が必要です。
<PMP試験 受験資格>
- 高校卒業、または大学卒業以上
- 実務経験(高卒の場合は7,500時間、大卒の場合は4,500時間のプロジェクトマネジメントの実務)
- PMIが認定した全35時間のプロジェクトマネジメント教育の研修を受講
試験のベースになるのは「PMBOKガイド」という書籍(電子書籍やPDF版もあり)です。まずはこれをひととおり読みましょう。PMBOKガイドに書かれている内容は難解であるため、ほかの教材や参考書も利用しながら勉強していくことをおすすめします。
PMP試験の概要
|
(2023年9月時点)
転職に有利な資格5 プロジェクトマネージャ試験

「プロジェクトマネージャ試験」は、独立行政法人情報処理推進機構が行う国家試験「情報処理技術者試験」の一区分です。情報処理関連の応用知識やシステム戦略の知識が問われるもので、ITコンサルタント志望者は取得しておくことで有利に転職できる可能性を高められます。
プロジェクトマネージャ試験合格による「メリット」
プロジェクトマネージャ試験に合格すると、プロジェクト全体を統括するプロジェクトマネージャーとしてのスキルを有していることを証明できます。上位職といわれるITコンサルタントへのキャリアアップにもつながるでしょう。
情報処理技術者試験の中でも難度が高い試験として知られているため、合格者は転職活動においても高い評価を受けやすくなります。特に官公庁などのシステム開発においては「プロジェクトマネージャ試験合格者がいることが入札の条件」となっていることもあるため、高く評価されやすいでしょう。
プロジェクトマネージャ試験の「対策」
プロジェクトマネージャ試験には選択式2種類(30問と25問)と記述式の問題に加え論述式の問題もあり、論理を破綻させない文章力が求められます。
論述式の問題は2つの問題からひとつを選び、3つの設問に対して800字以内、800字以上1,600字以内、600字以上1,200文字以内で論文を書きます。試験時間は120分です。決められた時間できちんとした論文を書かなければいけないため、十分なトレーニングが必要といえます。過去問のテーマに沿って模擬試験的に書いてみるなど、仕事の合間に論文を書く訓練をしておきましょう。
また、働きながら勉強をする場合、合格するために必要な期間は一般的に半年~1年以上といわれ、諦めずに学習し続けることが必要です。専用の講座や通信教育も多数開講されているため、独学では無理と判断したときは利用するのもひとつの方法でしょう。
プロジェクトマネージャ試験の概要
|
(2023年9月時点)
ITコンサルタントの転職・キャリアアップに役立つそのほかの資格

ITコンサルタントへの転職で役立つ資格にはさまざまなものがあります。ここからは、将来有望なITコンサルタントとして活躍するために役立つ5つの資格を見ていきましょう。データベースやクラウドなど、IT分野において重要度が高いスキルを証明する資格も含まれます。
応用情報技術者試験
|
(2023年9月時点)
IT分野において、システムの企画・設計・開発・運用に関する広範な知識を有していることを証明するのが「応用情報技術者試験」です。国家試験である情報処理技術者試験のひとつで、高度IT人材として活躍するために取得しておくとよいといわれています。
ITエンジニアなどのプロジェクトメンバーとして活躍する人材を対象としていますが、習得できる知識・スキルはITコンサルタントとして働くときにも役立つでしょう。試験は多肢選択式と記述式の問題で構成されています。
ORACLE MASTER
|
(2023年9月時点)
IT業界で活躍するうえで、データベースに関する十分な知識・スキルは欠かせません。ORACLE MASTERはデータベースを扱うのに必要なスキルを有していることを証明する資格で、Bronze・Silver・Gold・Platinumに分かれています。
合格するにはランクに応じたレベルのデータベーススキルが求められるため、SQLを含めてデータベース全般について学習することが大切です。試験を受ける場合、受験料が高額なのがデメリットといえるでしょう。
AWS認定
|
(2023年9月時点)
Amazonが提供しているAWSは、数あるクラウドサービスの中でもシェア率が高いのが特徴です。AWSを扱うのに必要なスキルを有していることを証明できるのが、ベンダー資格のAWS認定です。
資格はFOUNDATIONAL・ASSOCIATE・PROFESSIONAL・SPECIALTYに分けられており、それぞれさらに細かく分類されています。データエンジニアを対象としたものやテストエンジニアを対象にしたものなど多種多様な資格があるため、経験がある分野や得意分野から取得するとよいでしょう。
Microsoft Azure認定資格
|
(2023年9月時点)
AWSに次いでシェアが高いクラウドサービスが、Microsoft Azureです。MicrosoftもMicrosoft Azure関連のスキルを証明するためのベンダー資格を運営しており、取得するとクラウドを活用するためのスキルを十分なレベルで有していることを証明できます。クラウドを活用するプロジェクトは今度も増えていく可能性が高いため、Microsoft Azureのスキルも高めておくとよいでしょう。
Microsoft Azureを使用したプロジェクトも多いことを考えると、担当できる分野を広げればクライアントに合ったサポートを提供できるようになるでしょう。クライアントがMicrosoft Azureをメインで活用している可能性が考えられるためです。
CompTIA Project+
|
(2023年9月時点)
CompTIA Project+は、プロジェクトの管理・運営に携わるプロジェクトマネージャーを対象にした資格です。メンバーとのコミュニケーションやリソースの適切な管理など、プロジェクトをスムーズに進めるためのスキルを証明するもので、10種類以上の資格があります。エンジニアリングスキルだけでなく、交渉スキルやイレギュラーに対処するスキルも必要です。
プロジェクトマネージャーに求められるスキルは、ITコンサルタントとして活躍する場合にも求められます。サポートの一環として、プロジェクトの管理・運営に携わるケースがあるためです。
-
- 関連記事
- ITコンサルタント|求人一覧
ITコンサルタントには資格同様に3つのスキルが重要

ITコンサルタントになるための資格はないものの、資格の有無は評価基準のひとつになります。ただし、資格を持っていても仕事に活かせないと意味がありません。ここでは、専門分野の知識にプラスして培っておきたいITコンサルタントに重要なスキルをご紹介します。
スキル1.コミュニケーション能力
ITコンサルタントとして求められるものは、「人見知りをしない」「初対面でも話ができる」などの一般的なコミュニケーション能力だけではありません。適切な質問を用いて相手の意図や要望を正しく理解する能力が重要といえます。
クライアントは課題や問題点を認識していないこともあるため、状況を正しく聞き出して現状の課題を正確に把握できるかがITコンサルタントとして活躍するうえで重要です。
スキル2.論理的思考能力
プレゼンテーション能力に通ずるところもあり、ITコンサルタントにとって論理的思考能力は欠かせないスキルです。一朝一夕で培えるスキルではないため、メールや議事録の作成など、普段の業務でも論理的に考えることを意識し、スキルアップに励みましょう。
相手の経験や状況によって言葉の受け取り方が異なるため、相手の立場になって考えることも重要です。必要に応じて、論理的に考えるためのフレームワークも学習しましょう。
スキル3.問題解決能力
直面する課題の原因や適切な解決策は、すぐに見えてくるわけではありません。簡単に答えが出ないことも多いでしょう。さまざまな課題を解決するには「どの方向からアプローチしたらよさそうか」を見極めるスキルが欠かせません。問題解決能力を培う必要があるといえるでしょう。
問題解決を導くのに有用なものとして、「MECE」「仮説思考」「ロジックツリー」などのフレームワークがあります。最初は考え方を知ることからスタートしましょう。
ITコンサルタントを目指すルート

新たにITコンサルタントを目指す場合、ITエンジニアやプロジェクトマネージャーの経験を積んでキャリアアップするのが一般的です。ここでは、具体的にどのような形でITコンサルタントを目指せるのかを解説します。スキルや経験を活かしてITコンサルタントとして活躍したいと思っている方は、ひととおり確認しておくとよいでしょう。
ITエンジニアの経験を積む
ITコンサルタントとして活躍するにあたって、ITエンジニアの経験は強力な武器になります。そのため、まずはプログラマーやシステムエンジニア・Webエンジニア、インフラエンジニアなどの経験を積むことをおすすめします。
ITエンジニアとしての経験を積むと、プロジェクトの進め方やIT技術を活用して課題を解決する方法が見えてくるでしょう。その経験は、ITコンサルタントとしてクライアントをサポートするときに役立ちます。ITのスペシャリストとして最前線で活躍するために必要なスキルの習得という意味でも、ITエンジニアの経験は大切です。
経験を積みつつスキルアップに励む
実務経験を通じてスキルアップに励むことも、ITコンサルタントに転職するには欠かせません。開発に必要なエンジニアリングスキルに加えて、上流工程を担当するのに必要なマネジメントスキルやコンセプチュアルスキルを培うことも意識しましょう。
リーダーやマネージャーとして活躍する機会が開かれたのであれば、積極的に挑戦するのがおすすめです。自ら進んでスキルアップすることで、ITコンサルタントとして有用な人材へと成長していけるでしょう。
コンサルティングファームへの転職を目指す
ITコンサルタントが活躍する職場は、大きく事業会社とコンサルティングファームに分けられます。ITコンサルタントとしてさまざまな案件に携わりたいのであれば、コンサルティングファームへの転職がおすすめです。コンサルティングファームは、ITに関するコンサルティングを専門に提供することで収益を得ているためです。
ただし一口にコンサルティングファームといってもさまざまな企業があるため、IT分野に強いところを選ぶようにしましょう。また、これまでの経験やスキルを高く評価してくれる企業を選ぶことで、より有利な条件で転職しやすくなります。
まとめ

ITコンサルタントは、IT分野のスペシャリストとして多くの企業の経営課題を解決する職です。ITコンサルタントになるには十分な経験と高度なスキルが求められるため、学習活動の一環としてスキルレベルを証明する資格を取得するのもよいでしょう。
転職活動に取り組むときは、自分のスキルや経験、保有資格を高く評価してくれる企業を探すことが大切です。自分だけで探すのは難しいこともあるため、早い段階でぜひマイナビITエージェントにご相談ください。マイナビITエージェントにはIT業界に強いキャリアアドバイザーが多数在籍しており、スキルや経験を発揮して活躍できる職場探しや選考対策を入念にサポートします。
関連記事:マイナビITエージェント
-
- 職種図鑑
- ITコンサルタントとは?仕事内容・年収・資格について
- 平均年収ランキング
- システムコンサルタント
- 求人情報
- ITコンサルタントの求人一覧
- 関連記事まとめ
- いま取得すべきIT業界の資格まとめ!役立つ資格を職業別にご紹介
関連コンテンツ
-

IT業界
未経験でもWebデザイナーになれる?必要なスキルやポートフォリオの作り方
-

IT業界
システムエンジニアのキャリアパス|全体像と進路・スキル・資格を解説
-

IT業界
女性システムエンジニア|魅力と転職成功のステップを徹底解説