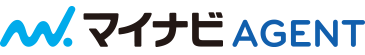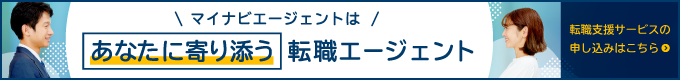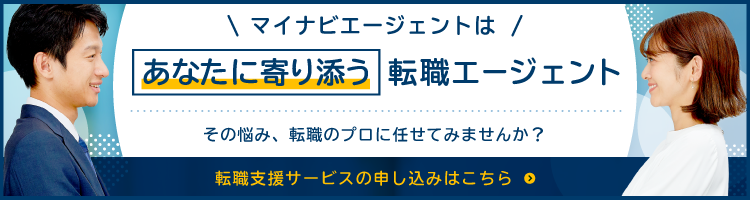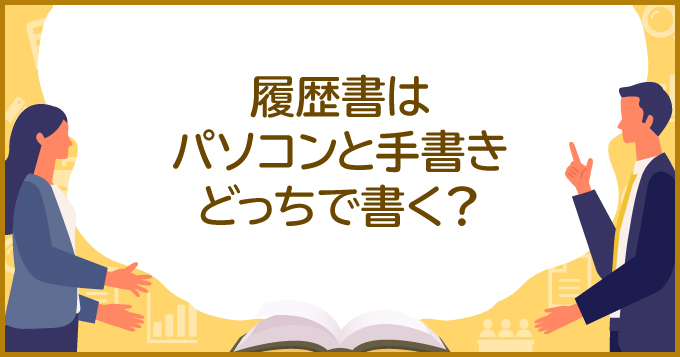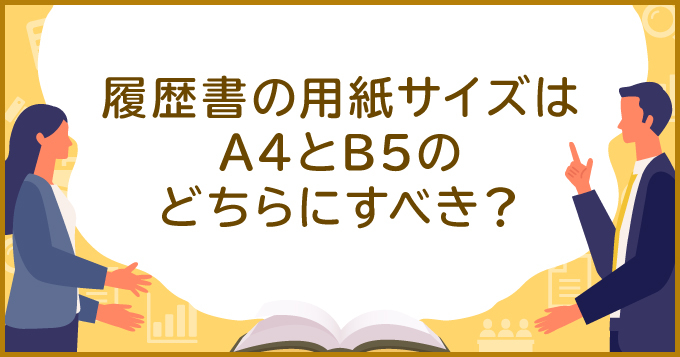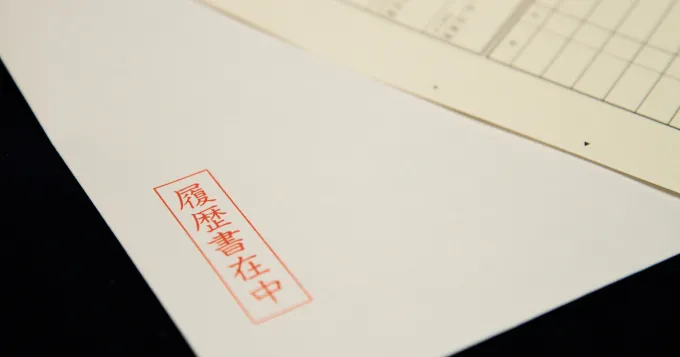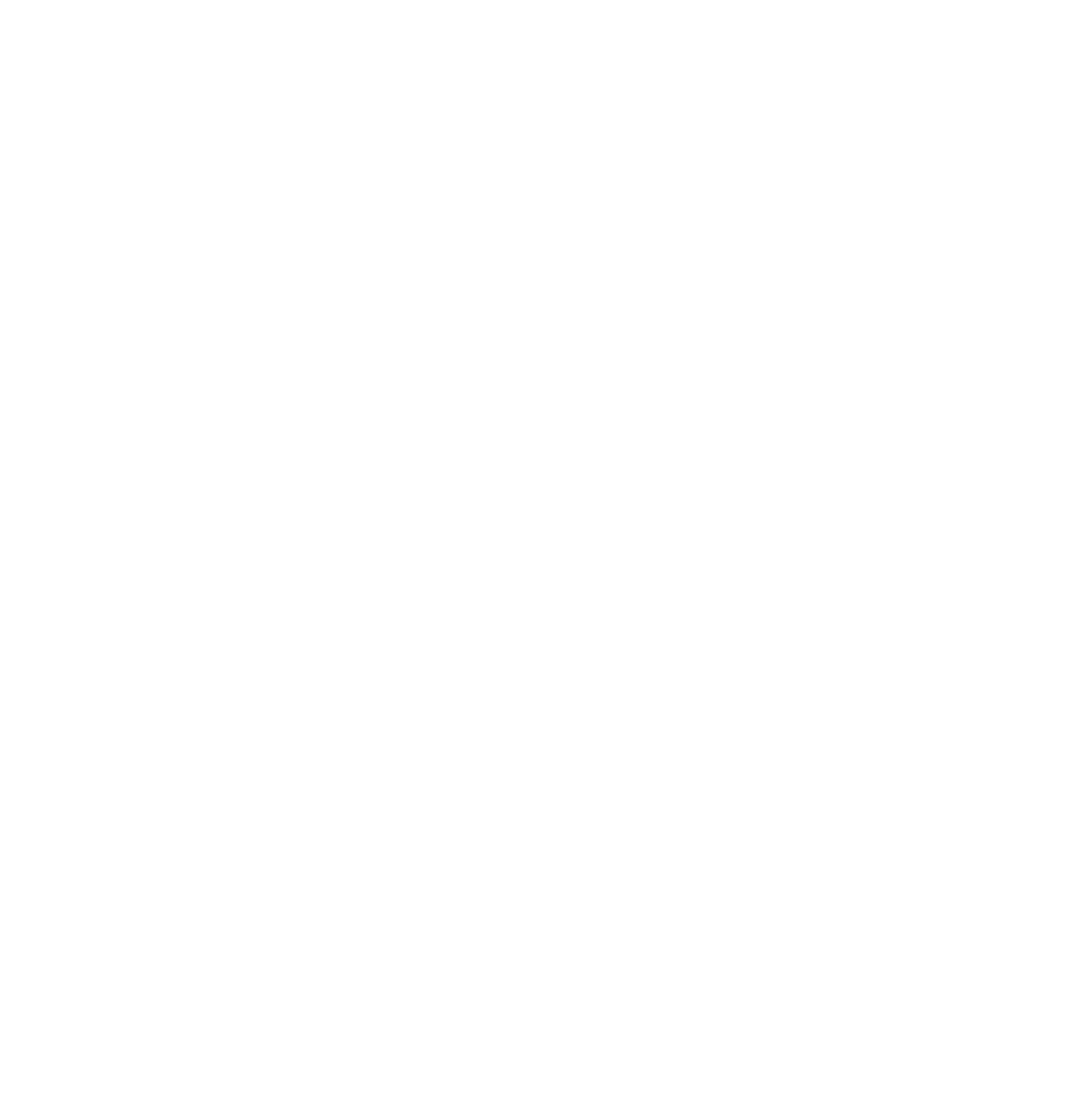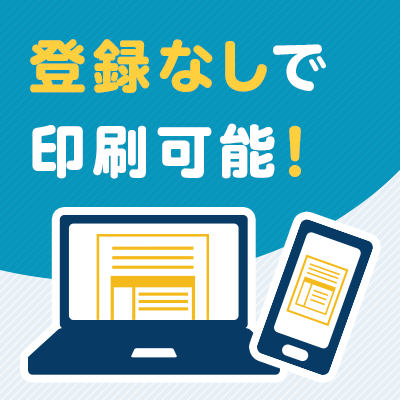【サンプルあり】履歴書郵送時の送付状(添え状)の書き方!作成時の注意点やポイントもあわせて紹介|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/08
【サンプルあり】履歴書郵送時の送付状(添え状)の書き方!作成時の注意点やポイントもあわせて紹介

この記事のまとめ
- ビジネスシーンにおいて、何らかの書類を郵送する際には送付状を添えるのがマナー。
- 送付状は同封している書類の概要を説明するものであることを意識し、シンプルかつ読みやすいものに仕上げることがポイント。
- 送付状を作成したら、誤字脱字がないかどうかを確認することが大切。
求人情報を見て選考に応募すると、応募書類を郵送するように指示されることがあります。そのようなときには、履歴書や職務経歴書とセットで送付状を添付するのが一般的です。
履歴書や職務経歴書は作成できたものの、送付状をどのように作成すればよいか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、送付状の作成方法と基本的なマナーを紹介します。
送付状はビジネス文書のひとつです。基本的なルールを押さえ、応募先企業に好印象を与えられるものに仕上げましょう。
目次
履歴書の送付状が果たす役割
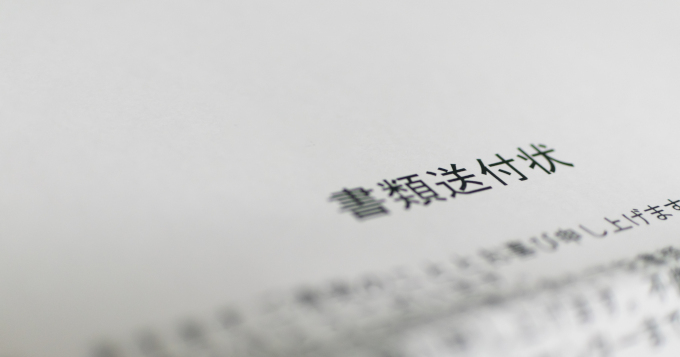
応募書類を送付する際に、あわせて送付するあいさつ状を送付状や添え状、カバーレターと呼びます。送付状は、誰から誰に対してどのような目的で何の書類を送付したのかを簡潔にまとめた書類です。選考に応募する段階においては、求人を見て応募したことと応募書類を送付したことを伝える役割を果たします。
ビジネスにおいて何らかの書類を送付するときは、送付状を添えるのが一般的なマナーです。応募書類だけを送付するのではなく、送付状を添えることで基本的なマナーを理解していることを示せます。
履歴書の送付状に書くことと基本的な書き方

送付状に書かなければならない内容は、ある程度決まっています。ここでは、書く内容や位置、より丁寧な印象を与えるために必要な頭語、結びのあいさつなどについてひとつひとつ解説します。これらのポイントを押さえたうえで、伝えたい内容もきちんと記載するようにしましょう。
日付
日付は最上行に右寄せで記載します。表記は和暦と西暦のどちらでも問題ありませんが、同封する履歴書や職務経歴書と統一することが大切です。
宛名
宛名は、日付の次の行に少しフォントを大きくして左寄せで書きます。会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載しましょう。
敬称は、個人が宛名の場合は「様」、部署が宛名の場合は「御中」とします。担当者の名前が不明の場合は「(部署名) 採用ご担当者様」と書いても構いません。
自分の連絡先・氏名
自分の連絡先や氏名は、宛名から1、2行下げて右寄せで書きます。郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、氏名を改行しながらコンパクトにまとめます。
タイトル
送付状のタイトルは自分の連絡先から1、2行下げて、中央に「応募書類の送付につきまして」などと書き、送付内容がひと目で分かるようにします。
頭語・時候のあいさつ
「こんにちは」のようなあいさつにあたる頭語は、「拝啓」を使用するのが一般的です。続けて「新春の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」など、時候のあいさつを加えます。
時候のあいさつは送付する時期に応じたものを使用します。相手に送付した書類が届く時期にあわせて、言葉を変えるようにしましょう。以下、各月における時候のあいさつ例を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
- 1月:新春の候・寒中の候・大寒の候
- 2月:立春の候・梅花の候・向春の候
- 3月:早春の候・春色の候・春分の候
- 4月:桜花の候・春風の候・春陽の候
- 5月:新緑の候・薫風の候
- 6月:初夏の候・深緑の候・梅雨の候
- 7月:盛夏の候・暑中の候
- 8月:立秋の候・残暑の候・晩夏の候
- 9月:初秋の候・涼風の候・秋涼の候
- 10月:秋色の候・紅葉の候
- 11月:晩秋の候・落葉の候・霜秋の候
- 12月:師走の候・寒冷の候・歳末の候
応募書類送付の旨
時候のあいさつに続いて、「この度、◯◯にて貴社の採用情報を拝見し、応募書類一式を送らせていただきます」など、応募書類を送付したことを伝える一文を明記します。
なお、履歴書・職務経歴書に書いた志望動機や自己PRを補いたい場合は、志望動機やアピールポイントを強調する一文を入れても構いませんが、簡潔にまとめるように心掛けましょう。
結びのあいさつ
最後は「ご検討の上、面接の機会をいただけましたら幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます」などと結び、改行して右詰めで「敬具」と記載します。
記、以上
送付書類の具体的内容は、最後に「記」として箇条書きで書いて「以上」で締めます。「記」は文書の中央に、「以上」は文書の最後、右下に記載するのがルールです。「以上」は締めの言葉であるため、その後に文章を続けないようにしましょう。
履歴書の送付状のテンプレート

ここからは、送付状作成時の基本的なポイントをテンプレートとともに紹介します。これから応募書類の送付を控えている方は、テンプレートを参考にしつつ、状況に応じてアレンジすることをおすすめします。基本的な送付状と簡潔な自己PRを盛り込んだ送付状の2パターンをチェックしていきましょう。
基本となるシンプルな送付状
|
【例文】 (日付) 株式会社○○○○ 人事部 御中 (自分の連絡先) 応募書類の送付につきまして 拝啓 時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 この度、貴社のシステムエンジニアの採用情報を拝見し、応募したく以下の書類を提出いたします。 ご検討の上、ぜひ面接の機会を頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具 記 添付書類 1. 履歴書 1通 2. 職務経歴書 1通 3. ポートフォリオ 1通 以上 |
上記のテンプレートでは、どの求人に応募したのかを明確に示しつつ応募書類を送付したことを簡潔に記述しています。シンプルに必要事項が盛り込まれているため、送付状として適切な形です。選考担当者もスムーズに読め、内容を理解しやすいでしょう。
簡単に自己PRを盛り込んだ送付状
|
【例文】 (日付) 株式会社○○○○ 人事部 採用担当者 様 (自分の連絡先) 応募書類の送付につきまして 拝啓 時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 この度、貴社のWebデザイナー職の採用情報を拝見し、下記の応募書類を提出いたします。 私は前職で2年間、企業のWebサイト制作を請け負うチームにて設計やマークアップ、フロントエンド開発を担当していました。前職の経験を活かして、貴社の事業拡大に貢献したいと考えております。 ご検討の上、ぜひ面接の機会を頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具 記 添付書類 1. 履歴書 1通 2. 職務経歴書 1通 3. ポートフォリオ 1通 以上 |
上記の例では、前職で携わっていた職種と経験を2行で簡潔に記しています。送付状は経験やスキルを長文でアピールする場ではないため、この程度の記述で問題ありません。具体的な内容は職務経歴書やポートフォリオなど、応募書類でアピールしましょう。
-
- 関連記事
- 履歴書の書き方
履歴書の送付状を作成するときの6つの注意点

送付状は、書き方を誤ったり間違いがあったりすると、かえって印象を悪くしてしまう可能性があります。相手に失礼がないように、また受け取る側の読みやすさを考慮して作成しましょう。ここでは、送付状を書く際に注意したい5つのポイントについて解説します。
1. 過剰な自己PRを書かない
送付状は、あくまでも応募書類への布石です。応募先企業に対する熱意や思いを長々と書き連ねると、「送付状の意味合いを理解していない」と判断される可能性があります。送付状はシンプルにまとめるのがベストです。
2. 給与など希望条件を書かない
給与や勤務地、勤務時間への希望は、それがたとえ転職における譲れない条件であったとしても、送付状に書くことは避けましょう。
送付状に希望条件を書くことは社会人としてのマナー違反であり、「ルールを守らず自分の主張ばかりする人物なのでは」といったよくない印象を持たれてしまう恐れがあります。
3. 定型文だけにしない
シンプルな送付状がよいといっても、定型文だけで済ませるのも避けたほうがよいでしょう。定型文をつなげて作成した場合、応募先企業への熱意が伝わりにくいばかりではなく、「ほかの企業へ送った送付状の使い回しなのでは」「手抜きをしているのではないか」といったマイナスな印象を与えてしまう可能性も考えられます。
4. ネガティブな経歴について理由を書かない
「人間関係がうまくいかない」「スキル不足で業務についていけなかった」などの理由ですぐに仕事を辞めてしまったり、転職回数が多くなったりすることもあるでしょう。そのような場合、応募先企業がマイナスの印象を受けるような書き方は避けたほうが無難です。
送付状では転職にいたった理由や、これまでの経歴でアピールしたい点などを簡単にまとめる程度にとどめ、ネガティブな印象を与えかねない経歴については必要以上に書かないことが基本です。
5. 誤字・脱字・衍字(えんじ)に注意する
書類作成の基本として、誤字・脱字・衍字(不要な文字)には注意を払いましょう。送付状は応募書類ではありませんが、誤字・脱字・衍字があると基本的な書類作成スキルに問題があると判断される可能性があります。
経験やスキルと関係ないところで評価を下げる必要はないため、作成後には複数回見直すのがおすすめです。作成した文章を音読したり、ブラウザのテキスト読み上げシステムを活用したりするとよいでしょう。
6. パソコンで作成する
送付状は、基本的にはパソコンで作成しましょう。書く際に修正がしやすく、受け取る側も書式や文字がそろっていることで読みやすく感じるためです。また、一般的なルールにしたがった送付状がきちんと作成されていれば、一定のパソコンスキルがあることのアピールにもつながります。
好印象を与える履歴書の送付状を作成する3つのポイント

履歴書や職務経歴書とあわせて提出する送付状は、直接の選考には関係ないかもしれませんが、「この方の話を聞いてみたい」「この方と一緒に働きたい」といった好印象を与えるきっかけになります。ここでは、採用担当者に好印象を持ってもらえるよう、送付状の作成時に意識したいポイントを4つ紹介します。
1. 礼儀正しさ、丁寧さを意識する
送付状の文体は「ですます調」にして、礼儀正しさ、丁寧さを意識して書きましょう。送付状の内容がよかったとしても、言葉遣いが適切でなかったり、誤字・脱字があったりしては、採用担当者に好印象を与えられません。
2. 分かりやすく簡潔に記載する
送付状の内容は、分かりやすく簡潔に書くことを心掛けましょう。採用担当者が時間をかけずに添付状を読めるように配慮することがポイントです。
3. A4用紙で作成する
送付状のサイズは、職務経歴書と同じものを選択します。ビジネスではA4用紙を使用するのが一般的なため、履歴書や職務経歴書のサイズをA4にそろえたうえで添え状もA4で作成しましょう。
サイズが統一されていると、受け取った採用担当者も扱いやすくなります。反対に、付箋のような小さい紙で送付状を作ってしまうと、何らかの原因で剥がれたり、受け取った側に意図が伝わらなかったりすることがあります。
また、送付状は1枚に収まるように作成しましょう。あいさつや自己紹介、履歴書などに書き切れなかったPR文を複数枚にまとめることは避け、あくまでも概要を伝える程度にとどめるのが基本です。
履歴書の送付状を封入する方法
応募書類の郵送を指示されたら、必要な書類を封入した状態で送付します。封入の仕方にも一定のルールがあるため、ここでチェックしておきましょう。
最初に、送付状・履歴書・職務経歴書の順になるように応募書類を重ねます。ほかに指示された書類がある場合は、職務経歴書の下に配置しましょう。適切な順番で重ねたら、クリアファイルに収納します。
最後に封筒を用意し、応募書類を収納したクリアファイルを封入すれば完了です。封筒の表側に送付状が来るようにしましょう。封筒には宛先とともに「応募書類在中」と記したうえで指定された方法で送付します。
「応募書類在中」と書く位置は、住所や宛名などが縦書きの場合は封筒の左下、横書きの場合は右下です。文字は赤字で目立つように記載し、定規を使って周りを四角で囲むのがルールです。
履歴書を手渡しするなら送付状・添え状は不要
履歴書や職務経歴書を面接などのタイミングで直接手渡す場合は、送付状を用意する必要はありません。対面で渡す際、口頭で内容を説明して中身の確認ができるためです。
送付状の役割は、口頭で伝えられない場合に送付した旨を明確にしてその概要を紹介することです。そのため、採用担当者や面接官に直接提出する際は、送付状の代わりに「応募書類を提出いたします」「履歴書と職務経歴書を提出いたします」などとひと言説明したうえで手渡します。履歴書などを手渡しする場合は、封筒やクリアファイルに入れましょう。
まとめ
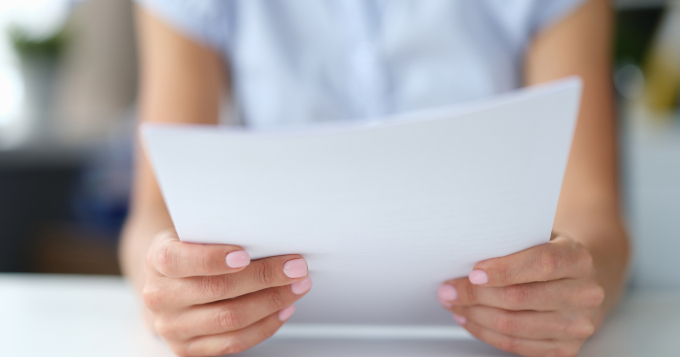
応募書類を郵送する際に送付状を添えるのは基本的なビジネスマナーです。送付状は同封している書類の概要を示すものであることを意識し、シンプルかつ読みやすいものに仕上げましょう。
応募書類の作成や自分に合った求人の選択など、転職活動においては考えなければならないことがほかにも多数あります。自分ひとりで転職活動を進めていると、悩んだり不安を感じたりすることもあるでしょう。
転職を成功させるためにも、早い段階でプロのサポートを受けることをおすすめします。マイナビ転職エージェントでは非公開求人の紹介や応募書類の添削など、転職を成功させるためのサポートを提供しています。後悔しない転職を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
-
- 履歴書について
- 【決定版】履歴書の書き方マニュアル|テンプレートのダウンロード
- 職務経歴書について
- 職務経歴書の書き方マニュアル|【職種別】テンプレートのダウンロード
- 面接について
- 面接で抑えておくべき基本マナー|転職の面接対策完全ガイド
- 自己PRについて
- 【自己PR完全ガイド】例文集・書き方や面接での伝え方

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。
関連コンテンツ
-

履歴書
転職の書類選考通過率はどのくらい?通過率アップの工夫を紹介
-
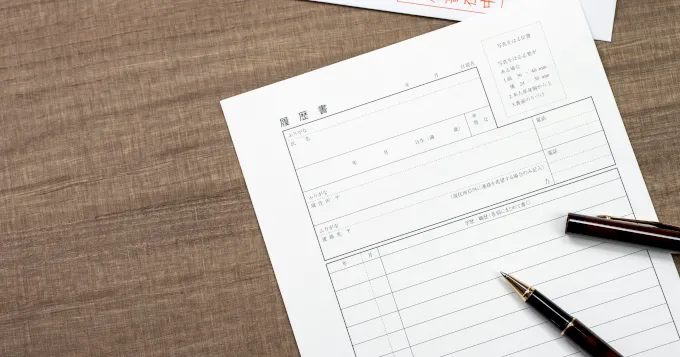
履歴書
履歴書の電話番号の書き方ガイド|ハイフンやカッコの正しい使い方とは
-
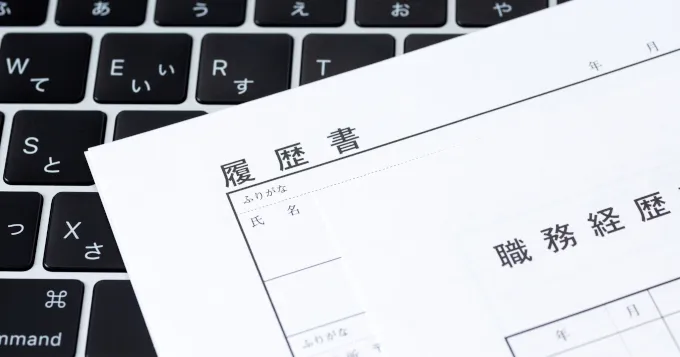
履歴書
【業務委託経験者の履歴書|例文あり】効果的な書き方のコツを解説