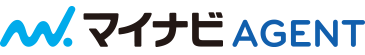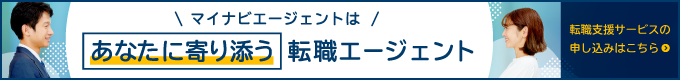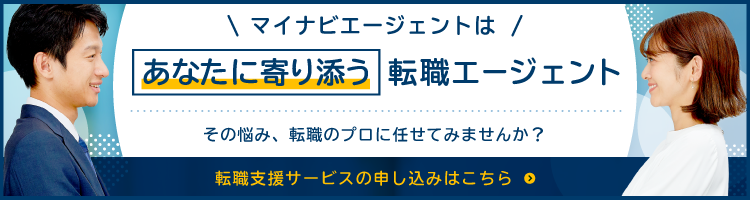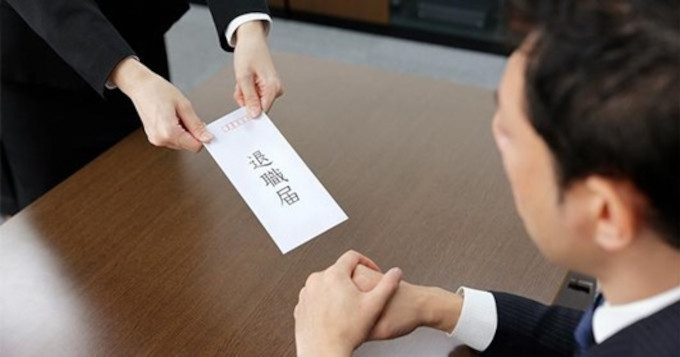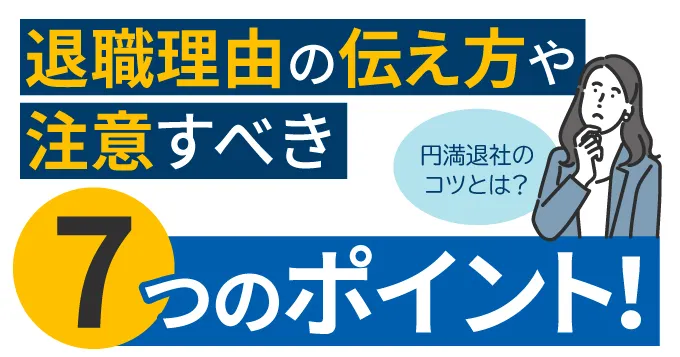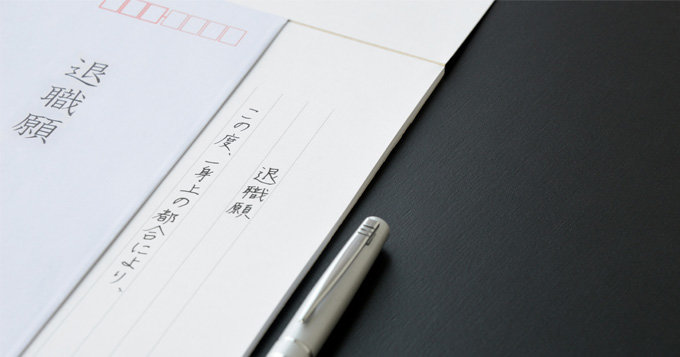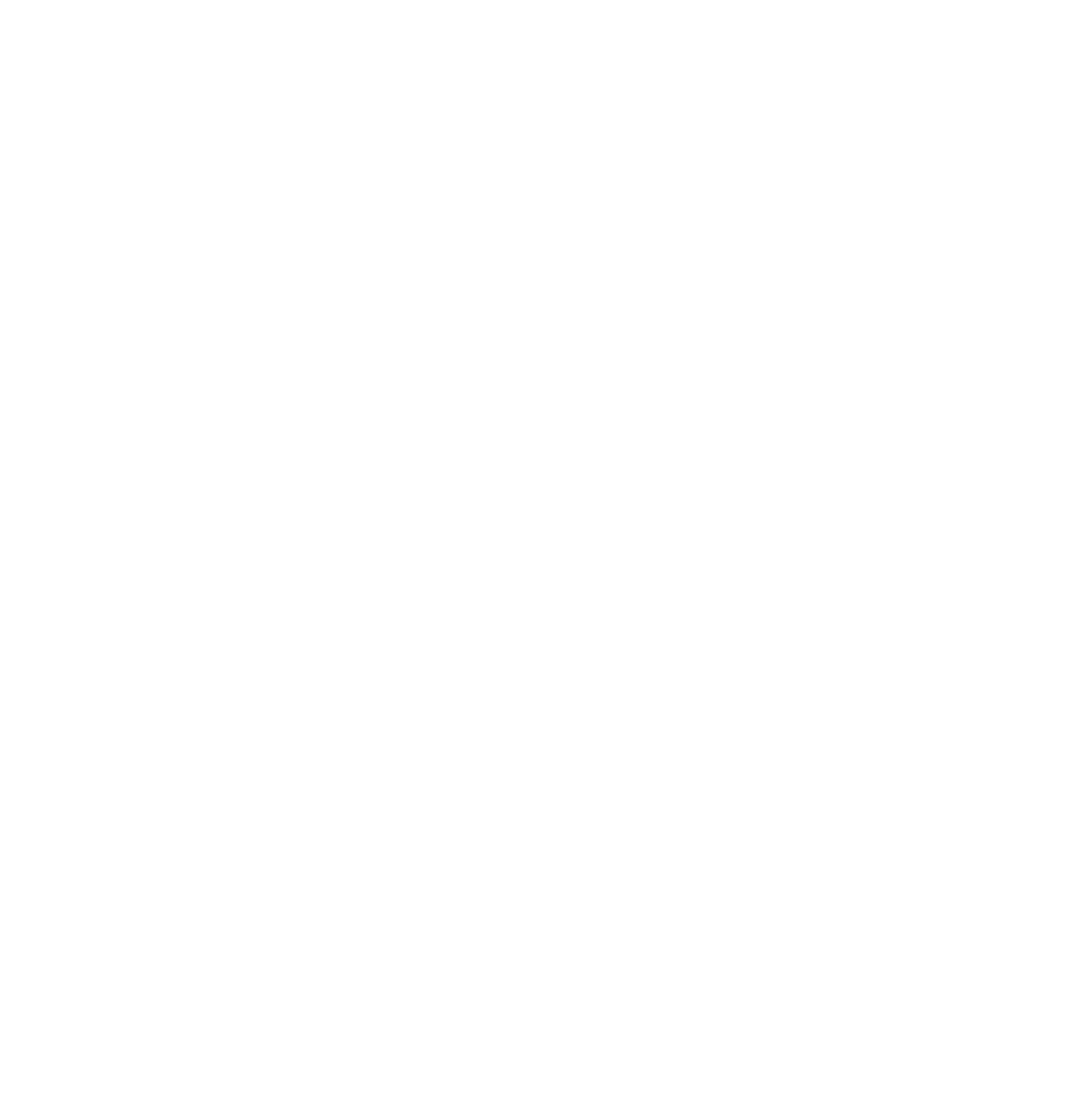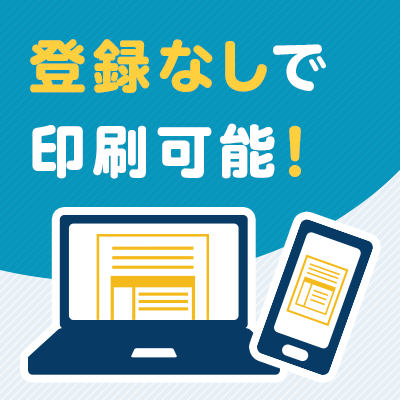退職を伝えるベストなタイミングとは?円満退職のコツも伝授|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/08
退職を伝えるベストなタイミングとは?円満退職のコツも伝授

この記事のまとめ
- 円満退職を望むのであれば、希望退職日の2ヵ月前~3ヵ月前に退職の意思を伝えるとよい。
- 退職を伝えるタイミングは、繁忙期や有給休暇の残日数、引き継ぎにかかる期間などを考慮して決めることがポイント。
- 退職を伝えるタイミングで転職先が決まっていれば、退職の意思が固いことを示せる。
転職するためには、退職のプロセスは避けてとおれません。しかし、退職の意思をどのタイミングで伝えればよいのか、迷っている人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、退職を伝えるベストなタイミングについて解説します。退職の意思を伝えるタイミングと気をつけておきたいポイントが分かれば、不要なトラブルを避けられるようになり、円満退職を実現できます。
目次
退職を伝えるタイミングとは

退職意思は退職希望日の1ヵ月前~3ヵ月前に伝えるのが一般的とされていますが、その理由が分からないまま退職のタイミングを決めるのは避けたほうが無難です。退職の意思をいつ伝えるかを決める前に、押さえておきたい法的根拠や退職をスムーズに進める要素について整理しておきましょう。
退職理由や職場の雰囲気はそれぞれ異なるため、自分にとってベストな退職のタイミングを見極めることが必要です。
法的なタイミング
民法627条によると「解約の申入れ」、つまり退職を伝えるタイミングは退職日の2週間前までと定められています。ただし、これは「期間の定めのない雇用」となる正社員のケースです。「期間の定めのある雇用」である契約社員の場合には、決められた雇用期間を満了した後、契約更新をしない形での退職となります。
ただし、病気・介護など緊急を要する事情がある場合はケースバイケースです。また、契約期間が5年を過ぎている場合には、契約社員であっても2週間前の申し出で退職できます。2週間前というタイミングは法的には有効ですが、現実的にはかなり急な申し出になるため、特別な事情がない限りは避けたほうが賢明でしょう。
就業規則に準じたタイミング
会社の就業規則で退職を伝えるタイミングが明記されているケースも少なくありません。就業規則よりも法律のほうが強い拘束力があります。しかしトラブルを避けるためにも、事前に就業規則を確認し、それに準じたタイミングで退職の意思を伝えるほうが得策です。
会社によって異なりますが、多くは退職の1ヵ月前~3ヵ月前の間で設定しています。就業規則には退職を伝えるタイミングだけでなく、退職金や退職に関わるほかのルールも記載されているため、退職を考え始めた段階で、まずはチェックしてみることをおすすめします。
円満退職のタイミング
円満退職を望むのであれば、退職希望日の2ヵ月前~3ヵ月前に退職の意思を伝えるとよいでしょう。退職の意思を伝えた後は、社内での承認や手続き、業務の引き継ぎ、取引先への連絡などさまざまなプロセスがあります。退職までの期間がタイト過ぎると、十分に引き継ぎができなかったり、会社が予定していたプロジェクトに影響を与えたりしかねません。
気持ちよく送り出してもらうためにも、上司には前もって退職の意思を伝えることが重要です。
退職を伝えるタイミングを決める4つのステップ

退職の意思を伝えるタイミングは、職種や業種、社内での責任、企業規模などにも左右されます。自分の状況を冷静に理解したうえで、最適なタイミングを見極めましょう。ここでは、退職の意思を伝えるタイミングを決めるうえで押さえておきたい4つのステップを紹介します。自分の状況に当てはめながら、退職日と退職を伝えるタイミングをいつにするのか考えてみましょう。
1.迷惑がかかるタイミングを避ける
仕事が忙しくなる繁忙期は、避けたいタイミングです。忙しさのあまり、上司に話を聞いてもらえないこともあります。気持ちに余裕がないため、退職を聞き入れてもらっても冷遇されたり、手続きなどについて冷静に話ができなかったりするかもしれません。
大きなプロジェクトに関わっているのであれば、一段落するタイミングまで待ちましょう。人事異動の打診があった場合には、引き受ける前に退職の意思を伝えると、現場を混乱させることなく退職できます。
2.引き継ぎにかかる期間を計算する
業務の引き継ぎをしっかりとしてから退職すれば、会社に迷惑をかけることがないため、円満退社につながります。引き継ぎにかかる期間は職種や企業規模によって異なります。業務を共有する社員が複数人いる場合には、そう時間はかからないかもしれません。一方、顧客を多く抱える営業職のように、後任を連れてあいさつに行く必要があるケースではかなりの時間がかかります。
そのため、退職の意思を伝える前に、自分のケースで引き継ぎにどれくらいの時間がかかるか、現実的に見積もってみましょう。必要な情報をリスト化する、作業手順を表にするなど引き継ぎをスムーズに進める方法を考えることで、引き継ぎ期間を短縮できる可能性があります。
3.転職先を見つける期間を見積もる
働きながら転職先を探しているのであれば、転職活動の期間をある程度決めておくことで、より集中して取り組めるようになります。転職のゴールを決めておくと、それに合わせたスケジュールを立てられます。
転職活動や業務引き継ぎのスケジュール、会社の繁忙期などを逆算していけば、退職を伝えるベストなタイミングを見定められるでしょう。
4.有給休暇を消化する
有給休暇を取らないまま退職すると、その権利は消滅してしまいます。有給休暇の取得は従業員の権利であるため、急な退職となった場合でも基本的には認められます。とはいえ、何かと理由をつけて、退職間際の有給休暇を会社が認めてくれないケースがあるのも事実です。こうなると労働基準監督署への相談など煩雑な手続きが必要になります。余計な仕事を増やさないためにも、計画的に有給休暇を消化しましょう。
まずは、有給休暇の残日数や有効期限を確認します。退職日の前にまとめて消化する、数ヵ月かけて少しずつ消化するなど、どのタイミングでどれくらいの日数を消化するか計算することで退職スケジュールも立てやすくなるでしょう。
退職を伝えるタイミングが早過ぎると

退職の意思は十分な余裕を持って伝えたほうがよいとはいえ、あまりにも早過ぎると、思いがけないトラブルを引き起こしてしまいかねません。中には退職が先延ばしになったり、退職そのものができなくなるなど最悪のケースが起こる可能性があります。なぜそのようなことが起こるのか、詳しく見ていきましょう。
転職先が決まっていないとズルズル辞められない
転職先も決まらないまま早々に退職の意思を伝えてしまうケースでは、「結局辞められない」パターンに陥りかねません。退職の意思を伝えると、「転職先はもう見つかっているのか」と聞かれるのはよくあることです。転職先が決まっていないことが分かると本気度が低いと判断され、責任のある仕事を任されたり、「まだ時間があるから」と退職手続きを先延ばしにされてしまったりするかもしれません。
そうこうしているうちに退職の意思が揺らぎ、結局退職できないというわけです。
引き留めの理由を与えてしまう
退職希望日までに時間があると、「まだ説得する余地がある」と引き留めされるケースは少なくありません。具体的には不満点の改善や、待遇アップを持ち出されて説得されるなどです。
また、同僚からの引き留めにあう可能性もあります。上司や同僚などから長期間にわたって引き留めにあう中で思うように退職日を決められず、転職のタイミングを逃してしまう恐れがある点には注意が必要です。
待遇面でのマイナスも
あまりに早いタイミングで退職の意思を伝えると、仕事がしにくくなることもあります。責任のある仕事を任せてもらえなくなったり、露骨に文句を言われたりするかもしれません。「期待していたのに」「頼りにしていたのに」といったネガティブな雰囲気で職場の人間関係がぎくしゃくすることもあります。ボーナス査定の前に退職の意思を伝えたケースでは、不当な減額や不支給というトラブルが発生する可能性も否めません。
退職を伝えるタイミングが遅過ぎると

法律では2週間前までに退職の意思を伝えれば退職できることになっています。とはいえ、ギリギリのタイミングで退職を伝えることには大きなリスクがあります。会社は人と人との関わり合いの中で機能しているため、法律があるからといって、簡単に割り切れることばかりではありません。退職を伝えるタイミングが遅過ぎる場合のデメリットを確認しておきましょう。
引き継ぎが間に合わない
退職の意思を伝えるのがギリギリになると、業務の引き継ぎが間に合わない事態が起こり得ます。誰がどれだけの業務を引き継ぐのかを決め、必要な資料やマニュアルを作成するのには時間がかかります。引き継ぎの情報が不十分だと、残された業務を複雑にしてしまうだけでなく、場合によってはビジネスに損害を与えることにもなりかねません。
転職後にも何らかの形でつながりがあるケースは少なくないため、悪い印象を残さない意味でも業務の引き継ぎはおろそかにしないようにしましょう。
希望日に退職できない恐れがある
ギリギリのタイミングで退職を伝えた場合、法律的には問題なくても「就業規則では認められない」という理由で、手続きをなかなか進めてくれないことが起こり得ます。すでに転職先の入社日が決まっているケースでは、希望日に退職ができないと大きな問題となりかねません。
一方で、単純に退職手続きに時間がかかるケースもあります。希望日に退職したいのであれば、手続きに相応の時間がかかることを理解して申し出るタイミングを見定めましょう。
有給休暇を取らせてもらえないトラブルも
就業規則違反という理由で、有給休暇を取らせてもらえないトラブルも起こり得ます。業務を引き継ぐ時間が足りず、有給休暇を取らずに最後まで働いてもらいたいと言われることもあるでしょう。「消化できない有給は会社に買い取ってもらおう」と思っていても、拒否されるかもしれません。
どのケースも法的に対処する方法はありますが、一度トラブルに発展してしまうと時間や手間が取られるだけでなく、精神的にもストレスになります。
円満退職を実現する4つのポイント

退職を伝えるタイミングは、円満退職を実現するひとつの要素です。しかし、気持ちよく退職し新たなステージへと旅立つうえでは、ほかにも外せないポイントがあります。ここでは、退職を伝える際に心しておきたい4つのポイントを解説します。
1.相談ではなく意思であることを示す
退職について最初に話す相手は直属の上司です。メールなどでアポイントを取り、個室など1対1で話せる環境を作りましょう。このときにNGなのは「退職を考えている」という表現です。「退職しようかどうか迷っている」とも受け取れるため、上司は相談されていると勘違いしかねません。引き留めにもつながります。
はっきり「退職させていただきます」と決定事項であることが分かる表現にすると、誤解を生まずに退職の意思を伝えられるでしょう。
2.ネガティブな退職理由は言わない
人間関係や待遇に不満があっても、退職前に口にすることは避けましょう。「不満が解消すれば退職せずに済む」というメッセージとも受け取られかねません。よかれと思った上司が改善策を提示し実際に動き始めると、「それでも退職します」とは言い出しにくくなってしまいます。
退職理由を聞かれたら、「新たなキャリアで頑張ってみたい」など、未来志向の答えが返せるよう準備しておくとよいでしょう。
3.まずは直属の上司に話す
退職の意思を伝えるうえで避けたいのが、直属の上司よりも先にほかの人に相談をすることです。上司よりも上の役職の方に退職の意思を伝え、それが上司の耳に入ってしまうと、話し合いがスムーズにいかなくなる可能性があります。直属の上司の管理能力が疑問視されるなどの事態にもつながりかねません。
直属の上司が原因で退職する場合でも、個人的な感情は抑え、マナーをわきまえて退職の意思を伝えるようにしましょう。
4.転職先を見つけてから退職する
転職先が見つからない状態で退職日を決めた場合、引き留めにより退職が先延ばしになったり、退職の意思が揺らいで結局退職できなかったりすることがしばしば起こります。上司や同僚に対して本気度が伝わらないだけでなく、将来への不安から退職の決意が弱まることもあるからです。転職先が決まっていると、自信を持って退職の意思を伝えられるでしょう。
転職先について尋ねられた場合、具体的な企業名を答える必要はありません。「新たな業界で働くつもりです」「後日改めてご報告させていただきます」など、転職先があることをそれとなく伝えると、退職の意思の固さを示せます。
退職を伝えるタイミングでよくある疑問
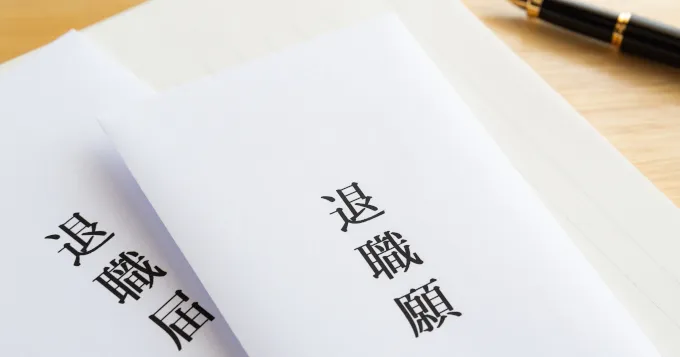
円満退職を目指して退職準備をしていると、さまざまな疑問が浮かんでくるかもしれません。取り越し苦労に終わることもありますが、できるだけ情報を集めて、特殊なケースに備えておくと安心です。ここではよくある3つの疑問について取り上げます。
疑問1.引き留めにあったらどうすればよい?
引き留めに使われる正攻法は「説得する」「お願いする」「不満点を改善する」の3つです。どの場合でもまず大切なのは、自分の意思が固く、退職は決定事項であるとはっきりと伝えることです。引き留められるということは、自分を評価してくれている裏返しでもあるため、感謝の気持ちは伝えるようにしましょう。とはいえ、情に流される素振りを見せないことが重要です。
疑問2.転職先について話したほうがよい?
転職先を根掘り葉掘り聞かれることもあります。転職先を話すかどうかはケースバイケースであり、転職先と現職の関係性などを慎重に考慮したうえで決めることがポイントです。
たとえば、新たな転職先でもビジネス上のつながりがあるケースでは伝えるメリットがあるといえます。一方で、競合他社への転職の場合、上司や同僚との関係がぎくしゃくしたり、転職に際して誓約書へのサインを求められたりすることもあるため、話すかどうかは慎重に判断することが重要です。
疑問3.「退職願」と「退職届」の違いって?
「退職願」は退職の希望を伝え、社内承認をお願いするものです。口頭で申し出ることもできます。「退職届」は、社内承認が出た後、退職の意思表示として書面にするものです。法的には口頭での意思表示も可能ですが、トラブル回避のためにも書面にして記録に残すのが一般的です。「退職届」は一度提出すると、基本的に撤回できません。
なお、企業の役員や公務員が出す場合には「辞表」と表書きし、退職ではなく辞職、辞任となります。
円満退職を目指すならマイナビ転職エージェントを活用しよう!
円満退職を実現するには、退職を伝えるタイミングや伝え方を工夫することが欠かせません。転職活動をスケジュールどおりに進めることも重要です。
退職を伝えるタイミングが分からない、働きながら転職活動をする時間が取れないとお悩みなら、マイナビ転職エージェントへ一度ご相談ください。専任のキャリアアドバイザーがあなたの状況を把握したうえで、現実的な転職スケジュールを提案します。求人の紹介や選考対策だけでなく退職交渉もサポートするため、円満退職と新たなキャリアのスタートを同時に実現可能です。
まとめ

退職の意思を伝える最適なタイミングは業種や職種、企業規模によって異なります。繁忙期や有給休暇の残日数、ボーナス査定のタイミング、業務の引き継ぎにかかる期間などを計算し、余裕を持って退職の意思を伝えることが円満退職につながります。また転職先が決まっていると、退職の意思が固いことを示せるでしょう。
マイナビ転職エージェントは、あなたの転職活動を全面的にバックアップします。あなたに最適な転職先を紹介するだけでなく、円満退職のコツもアドバイスします。円満退職とスムーズな転職を実現したい方は、お気軽にご相談ください。

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。
関連コンテンツ
-

転職全般
転職したいけど何がしたいかわからない人へ|自分に合う仕事の見つけ方
-
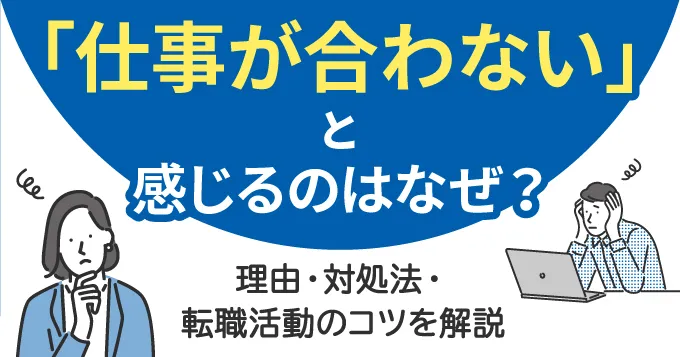
転職全般
「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説
-

転職全般
転職して後悔する理由は?後悔しない再転職を実現するポイントも解説!