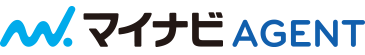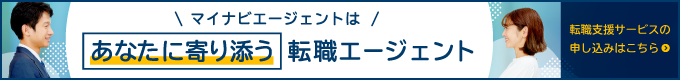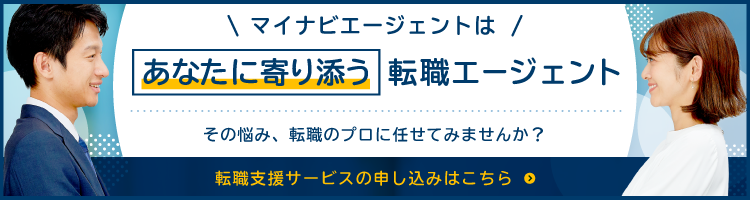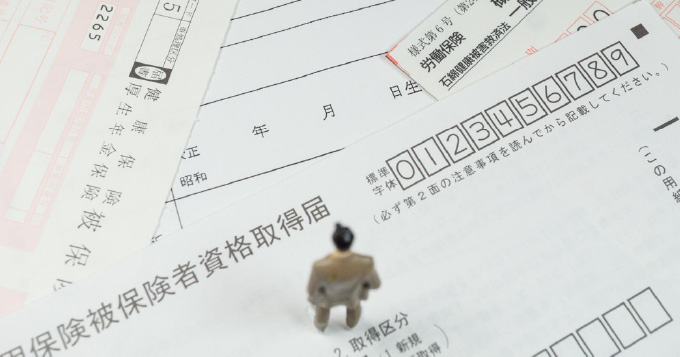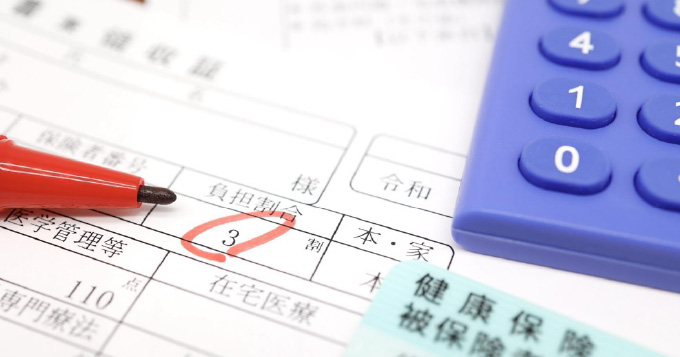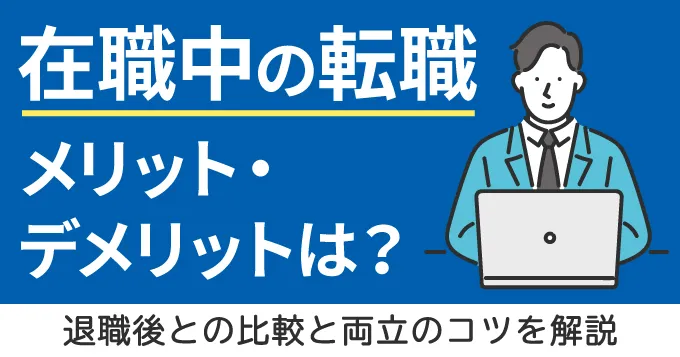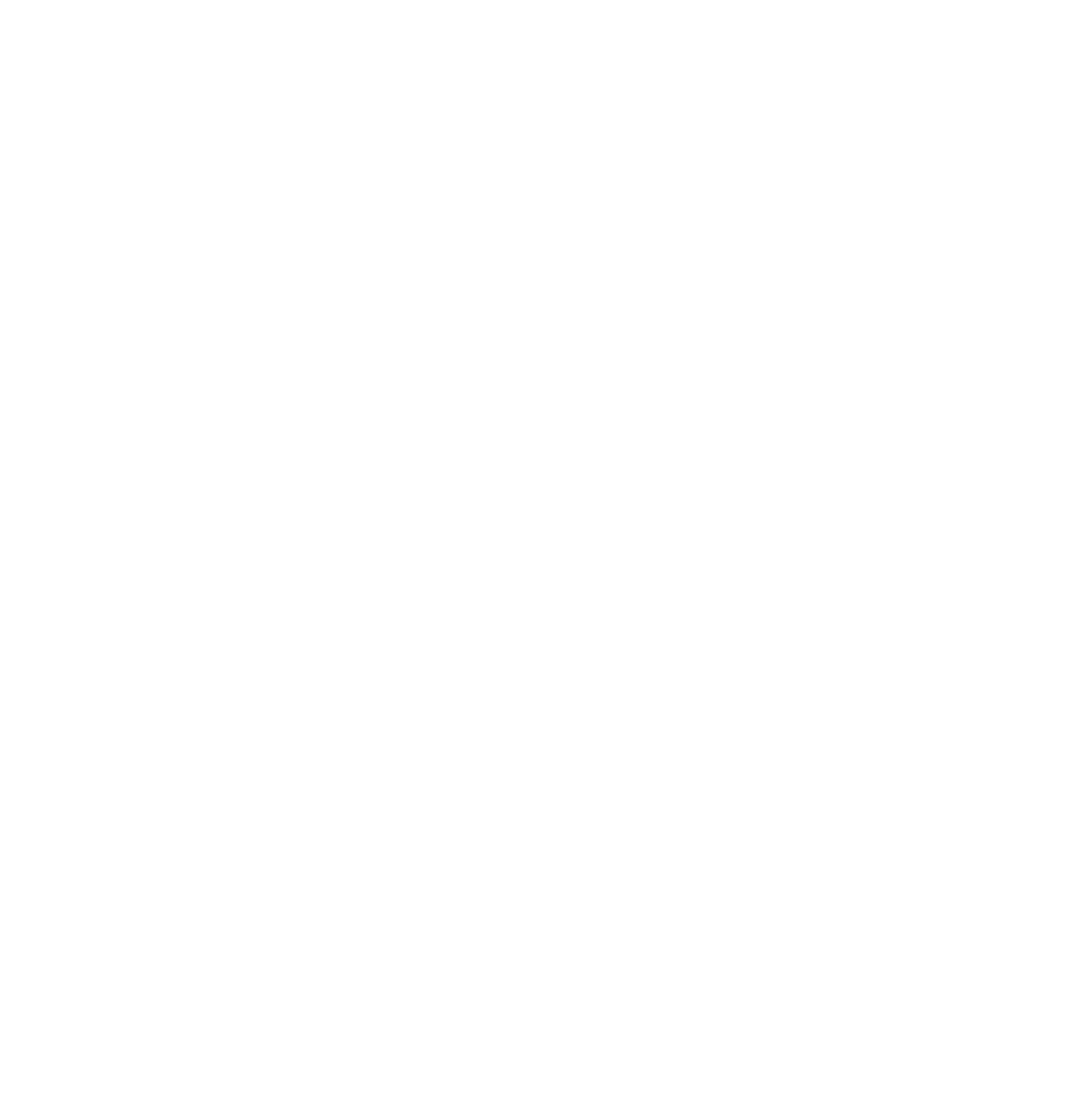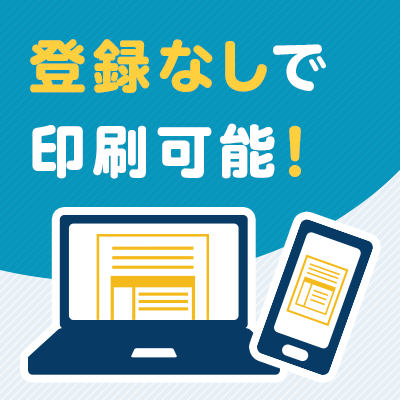転職時に必要な社会保険の手続きとは|保険証の切り替えはどうする?|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/08
転職時に必要な社会保険の手続きとは|保険証の切り替えはどうする?
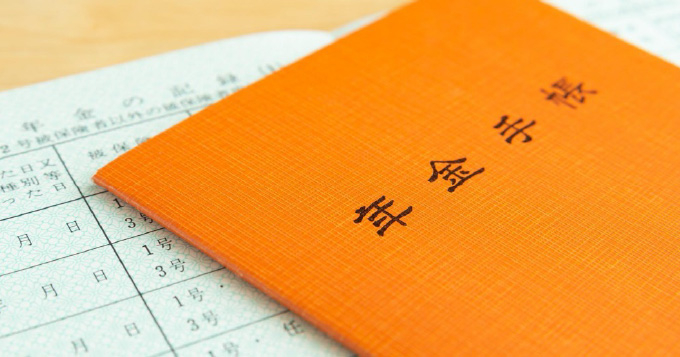
この記事のまとめ
- 労働者が加入する社会保険には、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類がある。
- 社会保険を切り替える手続きが必要となるのは、退職後、次の会社に入社するまでの期間が空くとき。
- 転職時には、社会保険以外にも住民税・所得税の納付手続きが必要となるケースもある。
転職するときには退職・入社に伴い、さまざまな手続きが発生します。そのひとつが、社会保険関連の手続きです。転職は頻繁にするものではないため、具体的にどのような手続きが必要なのかが分からず、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、社会保険の種類と転職に伴う手続きの内容、注意点などを紹介します。この機会にひととおりチェックしておくことで、さまざまな手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。
目次
社会保険の種類は5つ
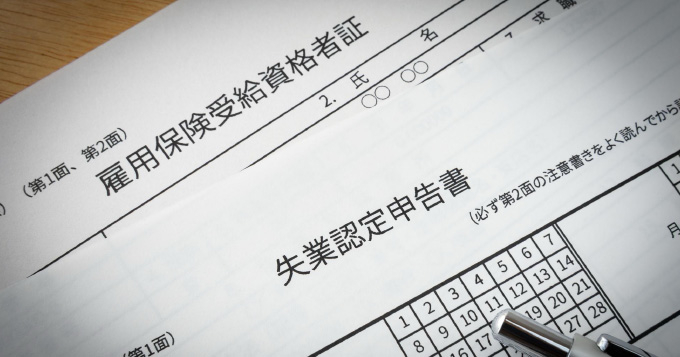
社会保険は病気やけが・失業などの社会的なリスクに備えることを目的として、国や地方自治体などの公的機関が運営している保険制度です。具体的には、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類を指します。ここでは、それぞれの社会保険がどのようなものかを見ていきましょう。
1.健康保険
健康保険は、病気やけがをした際に医療費の負担を軽減してくれる制度です。健康保険に加入することで、医療費の1割~3割の自己負担額で医療サービスを受けられます。会社員の場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、会社の健康保険組合に加入するのが一般的です。一方で、自営業や学生・無職の人は国民健康保険への加入が義務づけられています。
2.厚生年金保険
厚生年金保険は、老後や障がいを負ったときなどの生活を支える社会保障制度です。一般的に70歳未満の会社員や公務員は、厚生年金保険への加入が義務づけられています。個人事業主の場合も、常時従業員を5人以上雇用している場合は、加入を求められるケースがあるでしょう。厚生年金保険には、老後に支給される年金以外にも障害年金や遺族年金といった種類があり、受給要件を満たすと受け取れます。
厚生年金保険の加入対象者以外は、国民年金にのみ加入します。そのため、退職してから転職するまでに期間が空く場合は、国民年金に種別変更する手続きが必要なことを覚えておきましょう。
3.介護保険
介護保険は、介護が必要になった際に利用できる制度です。要介護認定や要支援認定を受けた場合など、給付対象になった際に、介護サービスを受けられます。40歳になると介護保険の被保険者となり、保険料の徴収が始まります。会社員の場合は健康保険と一体化されているため、健康保険の加入に合わせて介護保険の手続きも行われるのが一般的です。
4.雇用保険
雇用保険は、失業した際に生活の安定を図るための制度です。雇用保険に加入することで、失業時や収入が減った際に一定条件を満たすと就職支援や給付金の支給を受けられます。受け取れる給付金には再就職を支援する基本手当のほか、就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付などの種類があります。受給を希望する際は、ハローワークでの手続きが必要です。
5.労災保険
労災保険は、仕事中や通勤途中に事故に遭った際などに、治療費や休業補償を受けられる制度です。業務との因果関係が認められた場合は、けがだけでなく疾病も給付の対象です。労災保険は正社員・パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者の加入が義務づけられており、保険料は事業主が負担します。
転職時には自分で社会保険の手続きが必要?

転職するときには、社会保険の手続きを自分で行う必要があるのでしょうか。ここからは、自分で手続きが必要な場合と不要な場合をケース別に解説します。自分で手続きが必要な場合、忘れることなくスムーズに手続きができるようにきちんと確認しておきましょう。
自分で手続きが必要なケース
前職の会社を退職してから次の会社に入社するまでに期間が空く場合、自分で社会保険の切り替え手続きを行う必要があります。退職後14日以内に健康保険を「国民健康保険」に切り替えたり、厚生年金を「国民年金」に切り替えたりといった手続きが必要です。家族の扶養に入る場合にも、同じく14日以内に手続きを済ませましょう。
また、離職期間中の生活費を補うために、希望する場合には失業手当の受給手続きも早めに行うことをおすすめします。
自分で手続きが不要なケース
前職を退職してすぐに新たな会社に入社する場合は、社会保険の手続きを自分で行う必要はありません。この場合は、前職の会社から次の会社へ社会保険の資格が継続されます。
退職時に渡される源泉徴収票や雇用保険被保険者証などを、新しく入社した会社の担当者に提出しましょう。また、前職の健康保険組合から交付された健康保険証や資格確認書は、退職日までしか使えません。退職時に忘れずに返却しましょう。
転職時の健康保険関連の手続きは3パターン

離職期間中の健康保険はどのようにすればよいのでしょうか。ここでは、「任意継続」「国民健康保険への加入」「家族の扶養に入る」という3つの選択肢を解説します。自分の状況に応じたプランを選んで、転職までの間も安心して過ごせるよう準備を進めましょう。
1.健康保険任意継続制度を利用する
離職後もこれまでと同じ健康保険に加入し続けたい場合は、任意継続被保険者制度を利用できます。これは、退職前の健康保険を最長2年間継続できる制度です。ただし、これまで会社が負担していた分も含め、保険料は全額自己負担です。
手続きは退職日から20日以内に、前の勤務先の健康保険組合などに申し出る必要があります。また、任意継続制度の加入条件として、資格を喪失する日の前日までに2ヵ月以上の被保険者期間が必要です。転職までの期間が短い場合や、次の会社の健康保険に加入するまでのつなぎとして活用できるでしょう。
2.国民健康保険に加入する
離職期間が長引きそうな場合は、国民健康保険への加入を検討しましょう。国民健康保険は、職場の健康保険に加入していない人が対象です。そのため、健康保険の任意継続制度を利用しなかった場合は国民健康保険への加入が必要です。
国民健康保険に加入するときは、本人確認書類やマイナンバーを確認できる書類・退職の事実を確認できる書類を用意し、住所地を管轄する自治体の窓口で手続きしましょう。保険料は前年の所得に応じて決まります。収入が減るなどの理由で支払いに不安を感じる方は、保険料の減免制度について自治体の担当者に相談してみましょう。
3.家族の扶養に入る
家族の健康保険に扶養として入るのもひとつの選択肢です。扶養に入るには、「被保険者の3親等以内の親族で、被保険者に生計を維持されている」「年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/3未満」など、いくつかの条件を満たす必要があります。手続きする前に、条件を満たしているか確認しておきましょう。手続きは、扶養者の勤務先の健康保険組合などで行います。
なお、国民健康保険には扶養の概念はありません。したがって、家族が国民健康保険に加入している場合はこの方法を利用できず、国民健康保険料の負担が発生します。
転職時に新しい資格確認書が届くまではどうする?

転職によって加入する健康保険が変わると、新しい健康保険組合から交付されるまで資格確認書が手元にありません。それまでの間、医療機関を受診する場合はどのようにすればよいかを紹介します。なお、マイナンバーカードを健康保険証として使用するための登録を済ませている方は、連携手続きが完了したらすぐに受診可能です。
切り替えおよび資格確認書の交付にかかる期間
健康保険の切り替えにかかる期間は、新たに加入する健康保険の種類によって異なります。入社した会社で健康保険組合に加入する場合、会社を通じて手続きする必要があり、資格確認書の交付やマイナンバーカードの連携完了までに1週間~1ヵ月程度かかることもあります。
国民健康保険に加入する場合は、必要な書類がそろっていれば自治体の窓口で資格確認書を即日交付してもらえるケースが一般的です。
資格確認書の到着前に病院にかかる場合の対処法
もし健康保険証の到着前に病院にかかる必要がある場合は、「健康保険被保険者資格証明書」を医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けられます。健康保険被保険者資格証明書は、事業主や年金事務所などに申請書を提出することで発行が可能です。
健康保険被保険者資格証明書がない場合は、病院の窓口で事情を説明して、いったん自費で受診します。後日健康保険証が届いてから加入している健康保険組合や自治体の窓口などで手続きすると、後日支払った自己負担分の払い戻しを受けられます。
転職時のその他社会保険関連の手続き

転職時には、健康保険以外に公的年金や雇用保険の手続きも必要です。ここでは、それぞれどのような手続きが必要なのか、どこで手続きすればよいかを紹介します。いずれも重要な手続きであるため、忘れず速やかに済ませましょう。
【公的年金】国民年金の資格取得・種別変更手続き
退職に伴って厚生年金の資格を喪失したときは、国民年金への種別変更が必要です。国民年金への種別変更は、マイナポータルから電子申請で行えます。そのため、電子証明書が登録されたマイナンバーカードを保有している方は、電子申請するとスムーズです。
電子申請を利用できない場合は、基礎年金番号通知書と本人確認書類を持って住所地を管轄する自治体の窓口で手続きします。この手続きは、退職してから14日以内に済ませましょう。
【雇用保険】失業給付の受給手続き
失業給付を受給する場合は、住所地を管轄するハローワークでの手続きが必要です。退職してからハローワークに行き、求職を申し込みます。その後、窓口に離職票を提出することで失業給付を受給できる仕組みです。
失業給付を受けるには、離職した日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヵ月以上あることが条件です。ただし、すでに転職先が決まっている場合は受給できません。また、待機期間や給付制限期間がある点にも注意が必要です。
転職に伴い必要になる可能性がある社会保険以外の手続き

社会保険の手続き以外にも税金や失業手当など、転職時にはさまざまな手続きが必要です。ここでは、転職時に発生する可能性のある社会保険以外の3つの手続きについて解説します。転職のタイミングによって必要な手続きが異なるため、きちんと確認しておきましょう。
住民税の納付
転職時の住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は、勤務先の会社が毎月の給与から住民税を天引きして納付する方法です。一方、普通徴収は、自分で納付書を使って納付する方法です。年の途中で転職する場合、退職前に所定の手続きを済ませれば、特別徴収を継続できます。
しかし、退職してから入社まで空白期間がある場合は、一度普通徴収に切り替わります。ただし、年末に転職する場合は、前職の会社が1年分の住民税を特別徴収で納付するため、自分で納付する必要はありません。転職のタイミングによって、住民税の納付方法が変わることを覚えておきましょう。
所得税の申告・納付
所得税の申告は、通常1年間の所得に対して行います。しかし、年内に転職した場合は、新しい勤務先で年末調整をしてもらえるので、自分で確定申告をする必要はありません。一方、離職期間のまま年を越した場合は、確定申告が必要です。
退職後に確定申告が必要になるのは12月30日以前に退職した場合や、給与所得以外の所得が一定金額を超える場合などです。
転職するときの保険関連の手続きの手順
社会保険や税金に関する手続きには期間が決められていることが多いため、効率よく順番に済ませる必要があります。基本的には、期限が近いものから手続きしましょう。以下の順番で進めるのがおすすめです。
- 退職翌日以降:公的年金の種別変更(厚生年金から国民年金への切り替え)
- 退職日の翌日から14日以内:健康保険の切り替え(任意継続または国民健康保険への加入)
- 退職日の翌日から2ヵ月以内:失業給付の請求
- 退職翌年の2月16日~3月15日:所得税の確定申告
社会保険の手続きは期限が短いため、退職したらすぐに行うとよいでしょう。特に健康保険の切り替えが遅れると、医療機関を受診した際に医療費が全額自己負担になるリスクがあります。
転職で離職期間をなくすためのポイント

転職時の社会保険手続きを円滑に進めるには、離職期間をできるだけ短くすることが重要です。ここでは、離職期間を短くする具体的なポイントを3つ紹介します。スムーズな転職と社会保険の手続きにつなげるためにも、事前に確認しておきましょう。
1.在職中に転職活動を行う
転職活動を在職中から始めることで、離職期間を短くできます。現在の仕事を続けながら、空き時間を使って求人情報をチェックしたり、応募書類を準備したりしましょう。面接日程も有給休暇を活用するなどして調整すれば、スムーズに転職できるでしょう。ただし、転職活動には思った以上に時間がかかります。余裕を持ったスケジュールを立て、焦らず着実に進めていきましょう。
2.逆算スケジュールを立てる
転職したい日から逆算してスケジュールを立てる方法もおすすめです。まずは、転職希望日から逆算して、内定獲得目標日を決めます。そこから面接日や書類応募などの具体的な日程を設定します。この際、選考の期間や具体的な日程は企業によって異なることを念頭に置きましょう。
スケジュールどおりに進めるには、複数の企業に応募するのがおすすめです。万が一、志望していた企業から不採用通知が届いても、ほかに選択肢があれば余裕を持てます。
3.転職エージェントを活用する
転職エージェントを活用するのも賢明な判断です。転職サポートのプロであるキャリアアドバイザーに相談すれば、スキルや経験・希望条件に合った求人を紹介してもらえます。また、企業に応募した後には、書類作成のアドバイスや面接対策といった手厚いサポートが期待できます。面接日の調整などのスケジュール管理も任せられるため、在職中の転職活動の心強い味方になってくれるでしょう。
転職に関する悩みはマイナビ転職エージェントに相談しよう!
「離職期間を短くしたい」「在職中の転職活動をスムーズに進めたい」という方は、ぜひマイナビ転職エージェントをご活用ください。マイナビ転職エージェントでは、転職に関する知識が豊富なキャリアアドバイザーが、一人ひとりの希望条件に合わせて最適な求人をご紹介します。
書類作成のお手伝いや面接対策、スケジュール管理などもお任せいただけます。在職中の転職活動を効率よく進められるよう、丁寧にサポートします。転職を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ

転職するときには、入退社に伴って健康保険や厚生年金保険をはじめとした社会保険に関する手続きが発生します。決められた期間内に手続きを済ませる必要があるため、いつまでに何をしなければならないかを正しく理解しておきましょう。
また、転職活動には求人探しや応募書類の準備・面接対策など、さまざまな準備が必要です。ひとりで転職活動を進めるとスケジュールが長引きやすいため、早めに転職エージェントに相談することをおすすめします。
マイナビ転職エージェントでは、各業界の転職事情を熟知したプロのキャリアアドバイザーが求人選びから選考対策、条件交渉までサポートします。より有利に転職活動を進めたい方は、ぜひマイナビ転職エージェントにご相談ください。

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。
関連コンテンツ
-

転職全般
転職したいけど何がしたいかわからない人へ|自分に合う仕事の見つけ方
-
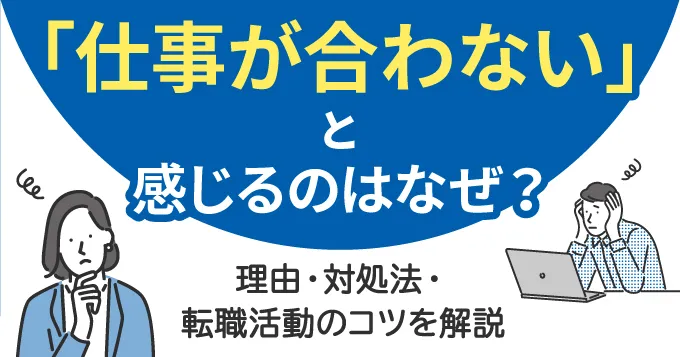
転職全般
「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説
-

転職全般
転職して後悔する理由は?後悔しない再転職を実現するポイントも解説!