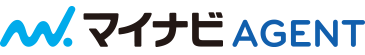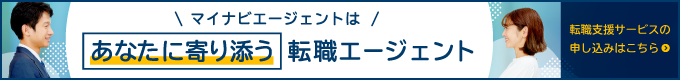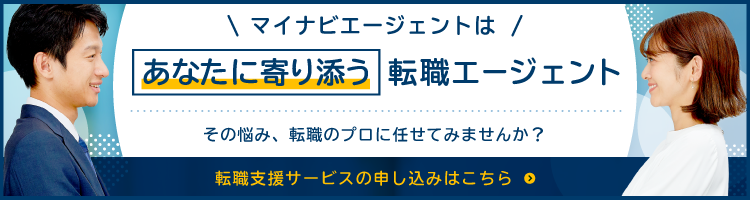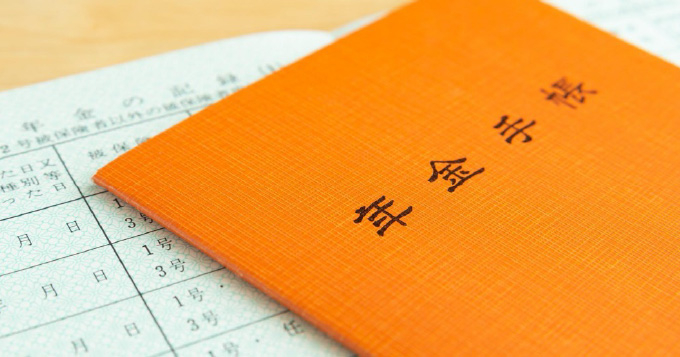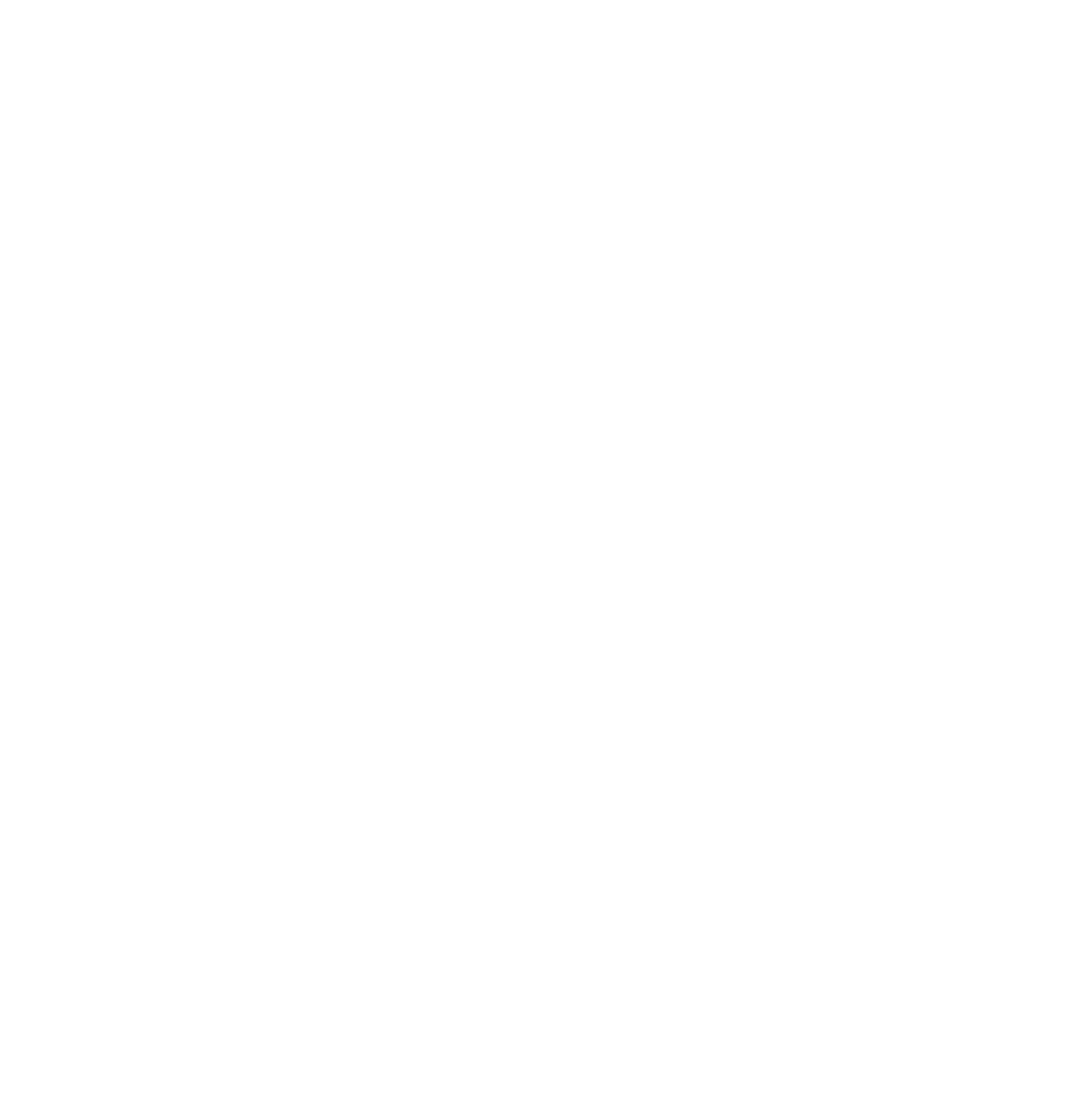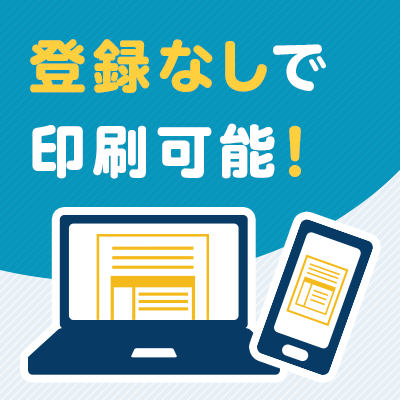退職したら保険証の返却は必要?返却方法や健康保険への加入方法を解説|求人・転職エージェント
更新日:2026/01/08
退職したら保険証の返却は必要?返却方法や健康保険への加入方法を解説
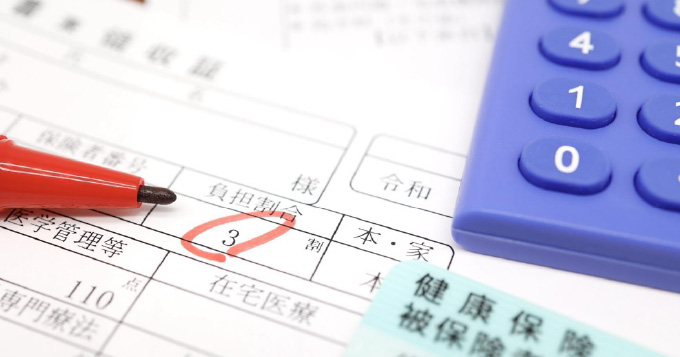
この記事のまとめ
- 転職すると健康保険組合から脱退するため、健康保険証や資格確認書の返却が必要になるが、マイナンバーカードを利用している場合は返却する必要はない。
- 転職先の企業で健康保険に加入したら、新しい健康保険組合から資格確認書が交付される。
- 退職日の翌日以降に前職の健康保険証や資格確認書を使用すると、無資格受診として後日医療費の返還を求められる。
転職に伴う手続きのひとつに、健康保険関連のものがあります。健康保険の手続きは頻繁にするものではないため、どのように進めればよいか迷いがちです。これから転職するにあたり、具体的にどのような手続きが必要なのか分からずに不安な方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、退職時に健康保険証や資格確認書の返却が必要なのか、どのように新たな健康保険に加入するのか、マイナンバーカードの保険証機能はそのまま使えるのかを紹介します。スムーズに手続きを進めるためにも、この機会にひととおりチェックしておきましょう。
目次
【退職時】退職する会社の健康保険証・資格確認書は返却する

転職に伴って現在在籍している企業を退職するときには、健康保険証や資格確認書を返却します。しかし、状況によってはスムーズに返却できなかったり、すぐに返却すると困ったりするケースもあるでしょう。ここでは、よくある4つのケースを例に挙げて返却時のポイントを紹介します。
被扶養者がいる場合
配偶者や子ども・両親などが健康保険の被扶養者となっている場合があります。被扶養者がいる場合は、全員の健康保険証や資格確認書を返却する必要があります。なお、被保険者・被扶養者がマイナンバーカードを保険証として利用している場合は資格確認書の発行はなく、カードもそのまま利用できるため返却する必要はありません。
家族と離れて暮らしているなどの理由で保険証の回収に時間がかかることが予想される場合は、早めに連絡をして受け取っておきましょう。
紛失した場合
健康保険証や資格確認書を紛失して返却できない場合は、すぐに会社に相談しましょう。早めに申告することで後のトラブルを回避できます。退職間際になって慌てないためにも、日頃から健康保険証や資格確認書をきちんと管理することは大切です。
なお、在職中に健康保険証を紛失した場合、健康保険証の再交付はできません。加入している保険組合から新たに資格確認書が交付されるため、医療機関を持参するときは資格確認書を持参しましょう。
持って行くのを忘れた場合など
病気やケガはいつ起きるか分からないものです。そのため多くの場合では、健康保険証や資格確認書は勤務最終日に返却します。しかし、最終日に持って行くのを忘れたり、有給休暇の取得により最終勤務日と退職日に開きがあったりすることもあるでしょう。そのような場合は、退職の翌日以降に後日郵送で返却します。
退職日に使いたい場合
健康保険証の資格失効日は退職日の翌日です。つまり、退職日にはまだ健康保険証を使用できます。退職時に健康保険証や資格確認書を返却できない場合は、持って行くのを忘れたときと同様に、退職日の翌日以降に郵送で返却します。
【転職後】転職先の会社で健康保険に加入する
転職先の会社で健康保険に加入するには、前の会社から発行される「健康保険資格喪失証明書」の提出を求められることがあります。受け取れなかった場合は以前の会社で加入していた健康保険組合に請求しましょう。ただし、全国健康保険協会に加入していた方は、年金事務所に請求する必要があります。
新しい会社に転職したら、その企業の健康保険組合に加入します。入社後に会社の指示にしたがって手続きすると、新たな健康保険組合から資格確認書が交付されます。なお、健康保険証の新規交付はありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を済ませている場合は、加入手続き後にそのまま手持ちのマイナンバーカードを使用できます。この場合、資格確認書は交付されません。
退職後に健康保険に加入する方法

日本には国民皆保険制度があり、退職後も何らかの健康保険に加入する必要があります。退職後における代表的な選択肢は、「任意継続する」「家族の被扶養者になる」「国民健康保険に加入する」の3つです。ここでは、それぞれの選択肢について解説します。
任意継続健康保険の場合
任意継続健康保険とは、退職後2年間に限り退職前と同様の健康保険を継続できる仕組みです。任意継続すると会社負担分が加算され、保険料の負担が増加します。ただし、上限額が設定されているため、人によっては単純に従来の金額の2倍とはならない可能性もあります。
多くの企業が加入する保険組合「協会けんぽ」の場合、任意継続健康保険に加入するには退職日から20日以内に各都道府県に設置されている協会けんぽ支部への申請が必要です。なお、退職日までの間に継続して2ヵ月以上の被保険者期間がない場合は加入できません。
任意継続における保険料は、自ら納付します。1日でも納付期限を超過すると自動的に資格を喪失するため、十分に注意しましょう。なお、任意継続健康保険に加入した後に国民健康保険に切り替えたい場合は、届出が必要です。
被扶養者として家族の健康保険の場合
家族が加入している健康保険の被扶養者となる場合、保険料は被保険者である家族分に含まれるため、個人の負担を抑えられます。協会けんぽにおける被扶養者の認定範囲は以下のとおりです。いずれにしても被保険者が主に生計を維持する者であり、一部を除き同一世帯に属している必要があります。
【被扶養者の認定範囲】
-
被保険者の3親等以内の親族
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
- 上記配偶者が亡くなった後における父母および子
- 被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)、兄弟姉妹、配偶者、子、孫 ※同一世帯でなくても可
上記で示した範囲のうち、さらに以下の収入基準を満たしている際に被扶養者として認められます。
被保険者と同一世帯の場合
・年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
・60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
被保険者と異なる世帯の場合
・年間収入が130万円未満、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合
・60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合
なお、加入手続きは家族の勤務先担当者が行います。健康保険組合によっても条件が異なり、手続きにも準備や時間を要するため、被扶養者となることが判明した段階ですぐ確認しましょう。
国民健康保険に加入する場合
退職してから入社までの期間が空いていて、任意継続せず家族の被扶養者にもならないときは、国民健康保険に加入します。該当する場合は、以下の書類を用意して住所地を管轄する自治体の窓口で加入手続きを済ませましょう。
- 本人確認書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 退職日が分かる書類
国民健康保険に加入する場合の資格取得日は、退職日の翌日です。この場合も、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続きを済ませていれば、そのまま利用可能です。登録していない場合は資格確認書が交付されます。なお、一定の条件を満たしていれば、即日で交付を受けることが可能です。
任意継続と国民健康保険はどちらがよい?
任意継続保険と国民健康保険のどちらがよいかはそれぞれの状況により異なるため、一概には言い切れません。協会けんぽの任意継続保険の場合は保険料額表が定められており、在職中の標準報酬月額に一律の保険料率を掛け合わせて算出します。
一方の国民健康保険は、被保険者の年齢や収入だけでなく家族構成などが影響するため、人によって大きく変動します。どちらを選択するか迷ったときは、双方の保険料を試算したうえで判断しましょう。
新たな資格確認書が届くまでに受診する場合の流れ

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を済ませていないものの、急病などの理由で、資格確認書が届く前に医療機関を受診したいと思う方もいるでしょう。ここでは、上記に該当するときにどのような形で受診すればよいのかを紹介します。主な方法には2種類あるため、それぞれチェックしておきましょう。
健康保険被保険者資格証明書を使用して受診する
新しい会社で加入手続きを済ませているのであれば、健康保険被保険者資格証明書を使用して受診できます。本書を必要とするときは、転職先の企業に請求して発行してもらいましょう。
発行された書類を持参して医療機関を受診すれば、資格確認書を持参したときと同様の自己負担割合で医療を受けられます。ただし、従業員が会社に発行を請求した後に会社が健康保険組合に申請する必要があるため、即日交付されるわけではありません。そのため、転職後にすぐ医療機関の受診を予定しているときは、できるだけ早く健康保険被保険者資格証明書の発行を求めましょう。
自費で負担して後日返還請求する
資格確認書・健康保険被保険者資格証明書の交付や、マイナンバーカードの連携が間に合わないときは、いったん自費で診療を受けて後日請求する方法があります。
上記の方法で受診する場合、医療機関から交付される診療内容明細書と領収書をはじめとした必要書類をそろえ、健康保険組合や自治体が指定する方法で療養費を請求しましょう。必要な書類は受けた診療の内容や請求する保険組合・自治体によって異なるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
療養費の請求を済ませると、数ヵ月後に保険給付相当額が指定した口座に振り込まれます。そのため、最終的な負担額は受診時に資格確認書を提示したときと同等です。
転職で健康保険証・資格確認書を返却するときの注意点

転職に伴ってこれまで加入していた健康保険証・資格確認書を返却するときには、いくつか注意しておきたいことがあります。うっかりしていると金銭的に大きな負担を求められることもあるため、注意しましょう。ここでは、健康保険証・資格確認書の返却で特に注意が必要な2つのポイントを紹介します。
1.退職日の翌日以降に使用しない
退職した企業で加入していた健康保険組合の保険資格は、退職日の翌日に喪失します。そのため、手元に健康保険証や資格確認書があっても、それを使って医療機関を受診できません。
間違えて前職の健康保険証や資格確認書を使用して受診すると、無資格受診に該当します。そのときは保険を適用した負担額で医療を受けられるものの、後日健康保険組合に返還しなければなりません。そのため、前職の健康保険証・資格確認書は退職翌日に郵送で返還し、間違えて使用しないようにするのがおすすめです。
2.手続きが遅れるとさかのぼって保険料を徴収される
前職の保険資格を喪失したときは、喪失してから14日以内に手続きして新たな健康保険に加入する必要があります。何らかの理由で上記の期間内に手続きしなかった場合、届出までにかかった医療費をすべて自分で負担しなければなりません。
さらに、保険料は資格取得日である退職日の翌日にさかのぼって発生し、納付することが求められます。そのため、手続きは決められた期間内に済ませましょう。
年金の切り替えにも注意しよう
退職後すぐに再就職しない場合は国民年金の切り替えも必要です。会社に在職中は第2号被保険者に属していますが、以下のいずれかに種別変更手続きを行わなければなりません。
-
- 第1号被保険者
- 20歳以上60歳未満の自営業者や家族、学生、無職など、第2、3号に該当しない人
- 第3号被保険者
- 20歳以上60歳未満で第2号被保険者の被扶養者である配偶者(年収130万円以下)
退職日から14日以内に、年金番号を確認できるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書)、退職日を確認できるもの(離職票、退職証明書)、本人確認書類を持参して住所地を管轄する自治体の窓口で手続きしましょう。
保険料に関しては、第3号被保険者の場合は個別で納付する必要はありませんが、第1号被保険者は自ら納めます。万が一収入が少なく納付が難しい場合は、免除や納付猶予の申請も可能です。なお、2025年2月時点の国民年金保険料は、1ヵ月1万6,980円です。
転職に関する疑問やお悩みはマイナビ転職エージェントに相談しよう!
転職するときには、健康保険に関する手続き以外にもやることがいくつもあります。自分の経験やスキルを振り返って方向性を決め、キャリアプランを実現できる転職先を探すことも大切です。
転職に伴うさまざまな作業や手続きをスムーズに進めつつ、自分に合った企業を探すためにも、ぜひマイナビ転職エージェントにご相談ください。マイナビ転職エージェントには経験豊富なキャリアアドバイザーが在籍しており、一人ひとりに合った企業に転職できるようサポートしています。転職活動に伴う応募先企業とのやりとりや日程調整などのサポートも受けられるため、転職活動に集中できるのも魅力です。
まとめ

転職すると前職で加入していた健康保険の保険資格を失うため、所持している健康保険証や資格確認書を返却する必要があります。また、転職先の企業では新たな健康保険に加入する手続きが必要です。退職から入社までの間が空くときは、任意継続の選択や国民健康保険への加入などが必要になります。
実際に転職するときには、健康保険関連の手続き以外にも企業探しや選考の準備など、やらなければならないことが多岐にわたります。転職に関する悩みを抱えることもあるでしょう。
そのようなときは、ぜひマイナビ転職エージェントにご相談ください。プロのキャリアアドバイザーによるサポートを受ければ、ひとりで転職活動に取り組むより効率的に進められます。

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。
関連コンテンツ
-

転職全般
転職したいけど何がしたいかわからない人へ|自分に合う仕事の見つけ方
-
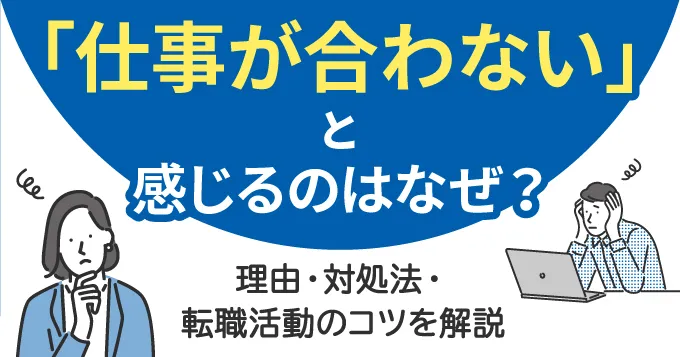
転職全般
「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説
-

転職全般
転職して後悔する理由は?後悔しない再転職を実現するポイントも解説!