一般的に、民間企業におけるボーナスは夏と冬の年2回支給されることが多いです。企業によって支給額の基準は異なりますが、新卒一年目の場合、夏のボーナスは寸志程度、冬のボーナスは基本給1ヵ月分程度となる可能性があります。
本記事では、新卒ボーナスの平均額を夏と冬、また企業規模や学歴別で詳しく紹介します。手取り額の計算方法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」
【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉の相場と年収アップの交渉をするコツをご紹介」
【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」
【テーマ別】平均年収ランキング
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 新卒一年目のボーナス平均額はいくら?
多くの企業では、夏と冬の年2回ボーナスが支給されており、給与以外のまとまった収入を楽しみにしている方も多いでしょう。
ボーナスの金額は企業によってさまざまですが、4月入社の新卒一年目の場合、夏のボーナスは査定期間が入社後2〜3ヵ月程度と短いため、支給額は寸志程度になります。
冬のボーナスは4月〜9月頃の勤務状況が反映され、平均で基本給の1ヵ月分程度となるのが一般的です。令和6年の場合、新卒者が多いとみられる20~24歳の1ヵ月の平均賃金が23万円程度であったことから、それに近い金額になる可能性が高いでしょう。
では、これらのボーナスの金額は具体的にどのような基準で決められているのでしょうか。また、そもそもボーナスを支給しない企業があるのは問題ないのでしょうか。
【出典】厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況(第2表 性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差)」
【関連記事】「転職のおすすめ時期はいつ?タイミング別のメリットや成功のコツを紹介」
1.1. そもそもボーナスとは
ボーナスとは毎月の固定給以外に、定期的または臨時的に支給される賃金のことです。昭和22年9月13日の労働次官通達には、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。」と記載されています。
一方、労働基準法にはボーナスに関する定義はなく、支給の有無や金額は会社が自由に決められます。
【出典】厚生労働省「発基第一七号|都道府県労働基準局長あて労働次官通達」
【関連記事】「ボーナスとは?一般的な支給時期や支給額の基準、平均額などを紹介」
1.2. ボーナスの金額はどうやって決まるのか
ボーナスには最低賃金などの基準はなく、金額の決め方は企業に委ねられており、一般的には、基本給に一定の支給月数をかける「基本給連動型」や、業績に応じて金額が変わる「業績連動型」を採用している企業が多いです。
また、職歴や等級、役職で一律に支給する企業もあるため、勤務先のボーナス制度に関しては、労働協約や就業規則、労働契約などで確認しておきましょう。
【関連記事】「年収とは?手取りとの違いや確認方法、年齢・業種別の平均額を紹介」
1.3. ボーナスがある会社は何割?新卒はもらえる?
令和6年度では夏季ボーナスが全業種の73.0%、冬季ボーナスが77.8%の企業で支給され、約7割の企業がボーナス制度を採用しているため、ボーナス制度がある企業では新卒社員でももらえる可能性が高いです。
また、株式会社マイナビの夏と冬のボーナス額と転職に関する2つの調査によると(※1)、理想の賞与額と現実の差がどちらも37〜38万程度あり、転職検討中や転職経験者の69.1%(※2)がボーナスの少なさを理由に転職していることがわかりました。
このようにボーナスに関する不満がある場合は、思い切って転職を検討することも一つの方法です。
(※1 20-50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3ヵ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)
(※2 20-50代の正社員のうち、2024年10月に転職活動を行った人と、今後3ヵ月で転職活動を行う予定の人計1,369人を対象に実施)
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要」
【出典】株式会社マイナビ「「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」を発表」
【出典】株式会社マイナビ「「2024年冬のボーナスと転職に関する調査」を発表」
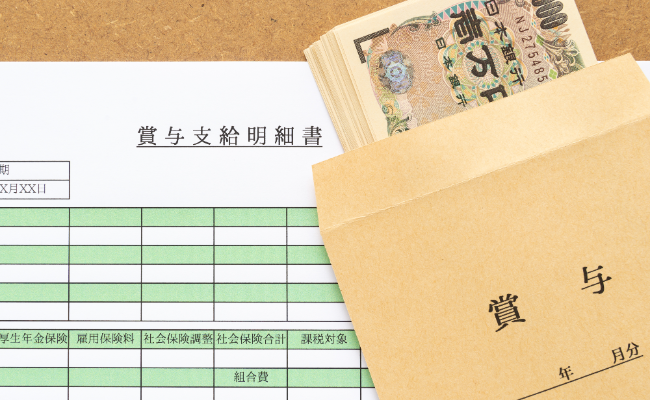
【関連記事】「ボーナスがない会社は何割?賞与なしの会社で働くメリットや注意点」
【関連記事】「転職の平均回数はどれくらい?年代別の傾向から転職成功の秘訣までまとめて解説」
【関連記事】「夏のボーナス後の転職は「早めの転職活動」がポイント!」
「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビエージェント』にご相談ください。
【マイナビエージェントのご利用方法はこちら】
【年収300万円以上の求人はこちら】
2. 【夏・冬】新卒のボーナス平均額
民間企業の場合、ボーナスは夏と冬の年2回支給されることが多いですが、新卒のボーナスは夏と冬でどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの平均額を紹介します。
2.1. 夏の新卒ボーナスは寸志程度の可能性がある
多くの企業で、夏のボーナスは6月〜7月頃に支給されますが、新卒社員にとっては入社からわずか2〜3ヵ月しか経過していない時期にあたります。会社によっては、この時期を本採用の前の「試用期間」とみなしている場合もあり、満額のボーナスを支給する会社は多くありません。
また、ボーナスの金額は、あらかじめ設定された査定期間に基づいて決定されることがあります。通常、夏のボーナスの査定期間は、新卒採用前の10月〜3月頃であり、新卒社員の場合その時期の実績はないため、適正な金額を算出できません。
このことから、新卒の夏のボーナス平均額は、気持ち程度の寸志になる可能性もあることを理解しておきましょう。
2.2. 冬の新卒ボーナス平均は「給料の1ヵ月程度」
冬の新卒ボーナスは多くの企業で通常通り、または通常に近い額が支給されます。冬のボーナス査定期間は4月~9月頃が一般的であり、新入社員の査定も問題なくおこなえることが理由の1つです。
業種によって異なりますが、冬のボーナスは基本給の1ヵ月分となるのが一般的とされています。前述のとおり新卒のボーナスは、1ヵ月の賃金約23万円(令和6年度)程度になると予想されます。
【出典】厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況(第2表 性、年齢階級別賃金、対前年増減率及び年齢階級間賃金格差)」
【関連記事】「夏・冬のボーナスはいつ支給される?一般企業と公務員の支給日や平均額を紹介」
【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」
【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?平均支給額と給与に対する割合を紹介」
【年収400万円以上の求人はこちら】

3. 【企業規模別】新卒のボーナス平均額
ここでは、大手企業と中小企業に分けて、新卒のボーナス平均額を見ていきます。
令和6年度の年間賞与について、勤続年数0年・20~24歳のデータを基に、従業員数が1,000人以上の大手企業と従業員数が10〜99人の中小企業の企業規模別に、新卒ボーナス平均額を以下の表にまとめました。
なお、これらの数字はボーナスを支給しない企業も含まれており、学歴による区別もありません。
| 企業規模 | 新卒ボーナス平均額(勤続年数0年・20~24歳) |
|---|---|
| 大手企業(従業員数1,000人以上) | 35,900円 |
| 中小企業(従業員数10〜99人) | 22,700円 |
ちなみに、勤続年数1〜2年目になると、ボーナス平均額は大手企業で588,800円、中小企業で361,200円とどちらも大幅にアップしますが、支給額は大手企業の方が高い傾向にあります。
【出典】厚生労働省「令和6年度賃金構造基本統計調査に関する統計表」
【出典】e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類」

【関連記事】「中小企業のボーナス平均額は?何ヶ月分?支給なしの割合や大企業との差も解説」
【関連記事】「働きながらの転職活動期間はどのくらい?長引かせないための成功のコツ6選」
【年収500万円以上の求人はこちら】
4. 【学歴別】新卒のボーナス平均額
次に、学歴別の新卒ボーナス平均額を見ていきましょう。
従業員数100〜999人企業の令和6年度年間賞与について、勤続年数0年・18〜24歳のデータを基に、高卒・大卒・大学院卒の学歴別に、新卒ボーナス平均額を以下の表にまとめました。
なお、これらの数字にはボーナスを支給しない企業も含まれています。
| 学歴 | 新卒ボーナス平均額(勤続年数0年・18〜24歳) |
|---|---|
| 高卒 | 42,300円 |
| 大卒 | 27,600円 |
| 大学院卒 | 31,400円 |
ちなみに、勤続年数1〜2年目になると、ボーナス平均額は高卒で430,600円、大卒で634,300円、大学院卒で506,500円にアップします。
学歴を問わず、一般的には新卒のボーナスは寸志程度であることがわかります。
【出典】厚生労働省「令和6年度賃金構造基本統計調査に関する統計表」
【出典】e-Stat 政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類」

【関連記事】「20代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【関連記事】「30代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【年収600万円以上の求人はこちら】
5. ボーナスの手取り額は約6〜8割!計算方法は?
ボーナスからは、所得税と社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上のみ))が引かれます。これらの税金や保険料を差し引いたものが手取りとなり、その額は支給額の約6〜8割です。それぞれの計算方法を簡単に紹介します。
【所得税】
①前月の給与-社会保険料=基準額
②基準額と扶養人数を使用し、国税庁の「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」から所得税率を確認
③(賞与-社会保険料)×所得税率=所得税
ボーナスにかかる所得税は、前月の給与や扶養人数によって変化します。
【出典】国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 7 年分)」
【健康保険料】
標準賞与額×健康保険料率=健康保険料
標準賞与額とは、賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた額です。健康保険料率は加入している保険組合によって異なります。また、健康保険料は企業と従業員が折半で納付するため、実際の金額は計算で算出した金額の半分です。
【厚生年金保険料】
標準賞与額×厚生年金保険料率(18.3%)=厚生年金保険料
厚生年金保険料率は現在18.3%で固定されており、こちらも健康保険料と同様に、企業と従業員の折半です。
【雇用保険料】
賞与総支給額×雇用保険料率(0.55%)=雇用保険料
従業員が負担する令和7年度の雇用保険料率は0.55%です。また、雇用保険料を計算する際は、1,000円未満を切り捨てる標準賞与額ではなく、賞与の総支給額を使用します。
【出典】厚生労働省「令和7年度の雇用保険料率について」
【関連記事】「手取りとは?額面との違いや計算方法、年代(年齢)別の平均額を紹介」
【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」
【関連記事】「【早見表】年収と手取りの違いは?簡単な計算式や早見表、シーンの使い分け方を紹介」
【年収700万円以上の求人はこちら】
6. ボーナスが多い業種は?
紹介したとおり、ボーナスは勤続年数が長くなるにつれてアップすることが多いです。では、ボーナスが多いのはどのような業種でしょうか。
6.1. 公務員
公務員のボーナスは、地域や職種、階級によってさまざまです。民間企業の平均ボーナス額と比較してそれほど高いわけではありませんが、公務員には安定した給与と福利厚生が提供されています。
国や地域の予算状況によってボーナス額に影響が出る可能性はあるものの、支給額は比較的安定していると言えます。
6.2. 資格を要する仕事
高度な専門知識とスキルを要する仕事は、ボーナスの額も高くなることが多いです。例えば、医師や歯科医、薬剤師などの医療専門職、データサイエンスに関する知識やプログラミングスキルを要するIT職、弁護士や法律専門家などの法律専門職がそれにあたります。
6.3. 上場企業
前述したように、従業員数が多い大企業のボーナスは、中小企業よりも多い傾向にあります。このことから、事業規模が大きく業績も安定している上場企業のボーナスは、一般企業と比べて高めです。
また、企業によっては優秀な従業員を獲得するため、ボーナスを高めに設定している場合もあります。近年は人材不足が深刻化しつつあり、このような企業が増えることが予想されます。現在のボーナスに不満や疑問を感じている方は、転職を検討するのも1つの方法です。
【関連記事】「地方公務員に転職するには?種類や給料、成功のコツなどを詳しく解説」
【関連記事】「年収はボーナス含む?計算方法や手取り・年俸との違いを解説!」
【10~12月限定】
年内の転職を目指す!「秋の無料個別相談会」
7. ボーナスの使い道
新卒一年目の新入社員が初めてもらうボーナスは、どのように使われるのでしょうか。ここでは、新入社員のボーナスの使い道をいくつか紹介します。
7.1. 貯蓄・資産形成
初めてもらうボーナスは、将来に備えて貯蓄や資産形成に回すケースが多く、特に貯金用の口座に預けて、大きなライフイベントや突発的な支出などに充てることが一般的です。
また、資産を増やす手段として、投資信託や積立NISAを活用し、少しずつ投資を始める人も増えています。
このように貯蓄以外で資産を増やすことで、将来に向けて経済的な安定を目指せます。ただ、投資には元本割れのリスクがあるため、投資先については十分な注意が必要です。
7.2. 自己投資
ボーナスの使い道として、自己投資する人も増えています。自己投資には、スキルアップや資格取得のための学費や書籍代、オンライン講座の受講料などが含まれます。こうした投資は、将来的なキャリアアップや仕事の幅を広げるためにも重要です。
また、自己投資を通じて自分の成長を実感できるため、モチベーションを維持しやすく、仕事に対する意欲も高まります。
7.3. 両親へのプレゼント
ボーナスを両親へのプレゼント購入費に充てる人も多いです。新入社員がまとまった金額を用意するのは難しいことが多いため、ボーナスを活用して感謝の気持ちをプレゼントという形で伝える人もいます。
例えば、両親が欲しがっていた家電製品や旅行券などを贈るケースが挙げられます。自分で働いたお金で感謝を伝えられることで達成感が得られ、仕事へのモチベーションが高まるきっかけにもなります。
【関連記事】「資格なしの20代後半は転職できる?おすすめの転職先や選考対策も紹介」
【関連記事】「30代の転職が厳しいといわれる3つの理由|おすすめの転職先も紹介」
【関連記事】「大手企業への転職は難しい?有利になる条件と3つのポイント」
【離職中の方限定】今すぐ転職したい!最短で転職するための「無料個別相談会」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】
8. 新卒のボーナスでよくある質問
最後に、新卒のボーナスについてよくある質問を紹介します。
8.1. ボーナスが出ないのはどんなとき?
ボーナスは支給が定められているものではなく、雇用契約や労働協約においてボーナスの支給条件が定められていない場合、ボーナスは支給されません。ボーナスの有無に関しては、契約時に必ず確認が必要です。
また、会社の業績が悪い場合や、個人の業務遂行に問題があると判断された場合は、ボーナスが支給されなかったり、カットされたりすることもあります。
【関連記事】「ボーナス(賞与)は退職予定でももらえる?損しないタイミングを解説」
【関連記事】「育休中でもボーナスはもらえる?減額されるケースや控除についても解説」
8.2. ボーナスの額をアップさせるには?
ボーナス査定に関しては、会社ごとに独自のルールがあります。そのため、まずはどの要因がボーナスの支給に影響を与えるかを把握しましょう。
その上で、自身の成果や価値を上司に積極的に伝えて、評価されるよう努力することが大切です。しかし、ボーナス額が増えるかは会社の業績によるところが大きいため、仕事のスキルを上げて会社の業績アップに貢献することが、将来のボーナスアップにつながります。
【関連記事】「ベースアップ(ベア)とは?定期昇給との違いや役割について解説」
【関連記事】「昇格とは?昇進・昇給との違いや昇格試験合格のポイントを解説」
【関連記事】「昇給とは?昇給制度の種類や仕事選びでの注意点を紹介」
【関連記事】「ボーナスの使い道ランキングを紹介!年代別おすすめの使い方や無駄遣いを防ぐコツは?」
【関連記事】「【エッセイ連載#3】この冬のボーナスはどこへ行く!|額賀澪の『転職する気はないけど求人情報を見るのが好き』」
年収アップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビエージェントについて詳しく知る >
9. まとめ
現在、約7割の企業がボーナスを支給しており、新卒一年目の社員でも受け取れる可能性があります。新卒一年目のボーナス平均額は確かに少ないものの、勤続2〜3年目になると徐々にアップしていく場合が多いです。
一方、ボーナスの支給がない企業が3割存在するのも事実です。ボーナスの支給がない代わりに、毎月の給与額を多めに設定しているケースもありますが、やはりボーナスの支給がないことは、仕事のモチベーションが下がる要因にもなりえます。
「新卒の頃のままボーナス額がなかなか上がらない」「そもそもボーナス制度がない」などボーナスに関する不満がある方は、転職を考えてみてもよいかもしれません。ご自身の市場価値を知りたい場合は、マイナビエージェントのキャリアアドバイザーにご相談ください。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビエージェントに無料登録して
転職サポートを受ける



