退職時に気になることの一つに、「ボーナスはもらえるのか」という点が挙げられます。ボーナスは退職するタイミングによって支給の有無が変わることがあるため、損をしないよう、支給条件を事前に確認しておくことが大切です。
本記事では、ボーナスをもらって退職するのにベストなタイミングや注意点を詳しく紹介します。
【関連記事】「ボーナスとは?支給日や計算方法、平均額(2024年版)を紹介」
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 退職を伝えたあとのボーナスはどうなる?
会社を退職する際、ボーナスは受け取れるのか気になる方は多いでしょう。ボーナスは半年間頑張ってきた証(あかし)でもあるので、せっかくなら受け取りたいものです。
しかし、退職を伝えるタイミングによっては損をしたり、手続きが煩雑になったりすることもあるので注意が必要です。
1.1. 退職後はボーナスが支給されないこともある
多くの企業では、ボーナスの支給要件として「支給日に在職していること」を定めており、退職後はボーナスが支給されない場合があります。
企業によって支給条件は異なるため、転職を検討する際は「支給日在籍要件」の有無を必ず確認しましょう。
1.2. ボーナスの支給条件は企業ごとに異なる
実は、ボーナスは法律による支給義務はありません。給与は労働基準法により支払いが義務付けられていますが、ボーナスは企業の裁量に委ねられています。
そのため、勤続年数・個人の業績・会社の業績といった支給条件や、支給時期、回数、金額などは企業によって異なります。
1.3. ボーナスの支給条件は「就業規則」などを確認する
ボーナスの支給義務はないものの、ボーナス制度を設ける場合は、就業規則・労働契約・労働協約などで支給条件を明記する必要があります。
退職する際のボーナス支給条件についても、通常はこれらの規則に記載されているので、しっかり確認しておきましょう。
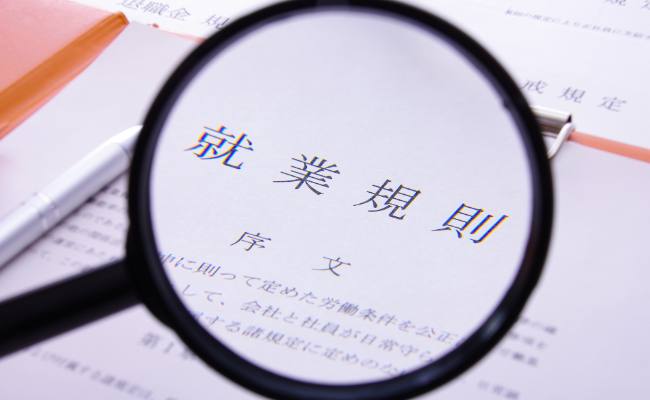 【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」
【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」
2. 退職の意思表示はボーナス支給後がベスト
ボーナスを受け取ってから辞めたいのであれば、退職はボーナス支給後がベストなタイミングです。また、もらってすぐ辞めるのは良い印象を持たれないため、支給後2〜3週間以上は空けると無難でしょう。
ただし、ボーナスの支給に関しては会社によってルールが大きく異なるので、支給後の退職であっても確実に満額受け取れるとは限りません。
2.1. ボーナス額が転職理由となる人は7割
ボーナスが思ったよりも低く、働くモチベーションが下がったことがある人は少なくないのではないでしょうか。
マイナビが実施した「【2025年夏ボーナス調査】夏ボーナスと転職の関係性について」(※1)によると、転職経験者の約7割がボーナスの少なさを理由に転職したと回答しており、ボーナス額が仕事のモチベーションに直結しやすいことがわかります。(※2)
単なる賞与にとどまらず、働きがいや評価の指標として捉えられていることがうかがえます。ボーナス額に満足できない場合、不満が転職意欲につながりやすい傾向があると言えるでしょう。

(※1:20〜50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3カ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)
(※2:(「1番大きな転職理由だった」(32.1%)と「1番ではないが転職理由だった」(37.0%)の合計)
【出典】マイナビ「【2025年夏ボーナス調査】夏ボーナスと転職の関係性について」
2.2. 転職検討者の6割が「夏のボーナス後に退職」を選択
多くの企業では、ボーナスの支給要件として「支給日に在職していること」を定めているため、ボーナスを受け取ってから退職する人が多い傾向にあります。
前項で紹介したマイナビの調査によると、転職を検討している人のうち「夏のボーナス支給後に退職する予定」と回答した割合は、およそ6割にのぼっています。このことから、夏のボーナスを受け取った後、秋から心機一転して新たな仕事に踏み出す人が多いことがうかがえます。

【出典】マイナビ「【2025年夏ボーナス調査】夏ボーナスと転職の関係性について」
 【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」
【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」
【関連記事】「新卒のボーナス平均額は?社会人一年目の夏・冬はいくらもらえる?」
3. ボーナスで損をせずに円満退職するには?
ここでは、ボーナスを受け取りつつも、同僚や上司に悪い印象を与えず円満に退職するためのスケジュールを紹介します。
3.1. ①事前に「支給日在籍要件」を確認する
「支給日在籍要件」とは、従業員が給与やボーナスを受け取るために、一定の期間会社に在籍している必要があるという条件を指します。例えば、「賞与は支給日の当日に在籍している従業員に支払われる」「賞与は在籍〇日以上の従業員に支給される」といった形です。
この要件は企業ごとに異なり、雇用契約や就業規則に記載されています。退職後のトラブルを防ぐためにも、事前にボーナスの支給条件をしっかり確認しておくことをおすすめします。
3.2. ②ボーナス支給前には退職を伝えない
企業によっては支給前に退職の申し出があった場合、「一切支給しない」もしくは「減額する」といったルールを定めている場合があります。先述した通り、ボーナスの支給に関しては法律による定めはなく、企業ごとに独自の規定が存在します。
そのため、ボーナスを受け取ってから退職したい場合は、支給前ではなく支給後に退職の意志を伝えましょう。
3.3. ③引き継ぎの期間を十分考慮する
大きな仕事を抱えている場合は、仕事を完結させたり引き継ぎを行ったりするのに、2〜3カ月必要な場合もあります。会社や同僚に迷惑をかけないよう、退職日までを逆算して余裕を持つことが重要です。
この場合、例えば6月のボーナス支給後に辞める場合は、7月頃退職を申し出て、実際退職するのは9月頃が適当となります。12月のボーナス支給後に辞める場合は、1月頃に退職を申し出て、実際の退職は3月頃とするのがいいでしょう。
また、転職を検討している方は転職活動にかかる期間も考慮して、退職を申し出る時期を決定するようにしましょう。
 【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」
【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」
【関連記事】「年収とは?手取りとの違いや確認方法、年齢・業種別の平均額を紹介」
4. ボーナスをもらって退職する際の注意点
ここでは、ボーナスをもらって退職する際の注意点を説明します。退職を申し出る前に、注意すべき点をしっかり把握しておきましょう。
4.1. 会社によっては減額の可能性がある
就業規則や労働契約書に「ボーナス支給後〇日以内に退職を申し出た場合は、〇割減額する」といった記載がある会社もあります。減額の割合は会社の規定によって異なります。
退職時のボーナスは、支給されない・減額されるといったケースもあるため、事前に就業規則や労働契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
4.2. 大きな業績があるなら要注意
会社の売上に大きく貢献したような業績があったとしても、査定期間を考慮せずに退職してしまうと、その業績が反映される次回のボーナスを受け取れなくなる可能性があります。
例えば、4月〜9月を冬のボーナスの査定期間としている場合、10月の業績は冬のボーナスではなく、翌年夏のボーナスに反映されることがあります。そのため、夏のボーナス前に退職すると、せっかくの成果が評価されず、もったいない結果になることもあります。

【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?それぞれの平均支給額と給与に対する割合を紹介!」
5. 退職時のボーナスでよくある質問
ここからは、退職時のボーナスでよくある質問を紹介します。有給休暇消化中にボーナスが支給される場合の扱いや、年俸制のボーナスについても解説します。
5.1. 退職後にボーナスは請求できる?
ボーナスは会社ごとの規定に則って支給されます。退職後でもボーナスを支給するという明確な規定が就業規則などで定められていれば、会社はその通り従業員へ支給しなければなりません。
会社が定める「支給日在籍要件」をしっかり確認して、要件に当てはまっているのであれば請求は可能です。
5.2. 有給休暇消化中でも在籍日として認められる?
残った有給休暇を消化してから退職しようと考える方も多いでしょう。
通常、有給休暇消化中であっても会社には籍がある状態ですので、在籍日として認められることが多いです。そのため、有給休暇消化中でも「支給日在籍要件」の対象となるケースが多いと言えます。
とはいえ、会社独自の規定を設けている場合もあるので、就業規則などで会社のルールを確認することが大切です。
5.3. 退職を理由にボーナスが支払われないこともある?
会社が定める「支給日在籍要件」に当てはまっているにもかかわらず、退職だけを理由にしてボーナスが支払われない場合、違法になる可能性があります。
まずはボーナス支給に関する規定を就業規則でしっかり確認して、不当に支払われていないのであれば、上司や労働組合、都道府県の労働局などに相談しましょう。
5.4. 年俸制の場合ボーナスは出ない?
年俸制の場合は、あらかじめ年収額が決められており、毎月の給与だけでなく、ボーナスもその年収の中から支給されるのが一般的です。そのため、会社は従業員が在籍していた期間に応じてボーナスを支払います。
ただし、こちらももらえる条件や金額の算出方法は企業ごとに大きく異なるため、就業規則や雇用契約で確認しておきましょう。
5.5. 退職後にボーナスの返還を要求されることはある?
会社が退職者に対して支給済みのボーナスを返還するよう義務付けたり、強制的に返還を迫ったりすることは法律違反にあたります。そのため、既に支給したボーナスについては従業員に返還を求めることはできず、仮に求められたとしても返還する必要はありません。
ただし、就業規則などで退職予定者に対するボーナスを減額する旨が明記されており、退職の予定があるにも関わらずその意思を伝えていなかった場合などは、満額を受け取ったあとに法的にも認められる範囲で一部返還を要求される可能性もあります。
5.6. ボーナスをめぐって会社側と揉めたらどうする?
退職とボーナスをめぐって、会社側とトラブルになってしまうこともあります。例えば、「労働契約や就業規則に書いてあることと会社の主張や支給された金額が違う」「労働契約や就業規則には明記されていないが不当な扱いを受けた」といったトラブルです。
このような問題が発生した場合は、泣き寝入りはせず、先に紹介した労働組合や労働局、または弁護士に相談するようにしましょう。
【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」
【関連記事】「転職エージェントの使い方は?上手に活用して転職を成功させる方法」
年収アップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
6. まとめ
退職を申し出るタイミングによっては、もらえるはずのボーナスが満額もらえない場合があります。ボーナスの支給ルールは会社ごとに異なるため、損をしないよう事前に就業規則を確認しておくことが大切です。
近年、多くの会社でボーナスが支給されていますが、その扱いや金額には差があります。「もっと多くボーナスをもらいたい」「ボーナスの支給回数を増やして欲しい」などの希望がある場合は、転職を検討するのも一つの方法です。ぜひ、マイナビ転職エージェントのキャリアアドバイザーにご相談ください。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける

