通常の給料とは違ってボーナスには法的な支給の義務はなく、実際にボーナスがない会社も約2割ほどあります。これには、企業規模や給与の制度などが関係していると考えられます。ボーナスがないことが一見デメリットに思えるかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。
この記事では、ボーナスがない会社の割合を紹介するとともに、そこで働くメリットやデメリット、ボーナスがない会社に転職する際の注意点などを詳しく解説します。
【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」
【関連記事】「転職で年収アップの相場は?交渉の相場と年収アップの交渉をするコツをご紹介」
【テーマ別】平均年収ランキング
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. ボーナスがない会社は約22%、その特徴は?
民間企業ではボーナスの支給に法的な義務はなく、支給条件は企業の判断に委ねられているため、中にはボーナスがない会社もあります。厚生労働省によると、令和6年度の夏にボーナスが支給されたのは全業種の73.0%、同年の冬に支給されたのは77.8%で、約22%の企業では年間を通してボーナスが支給されていません。
ボーナスがない理由はさまざま考えられますが、ボーナスなしになりやすい会社の特徴としては、以下のような点が挙げられます。
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要」
【関連記事】「業績悪化・不振は転職理由になる?|伝える際の例文とコロナ禍に言及する際の注意点」
1.1. 規模の小さい零細企業
事業規模の小さい零細企業は、市場変動や競争の影響を受けやすく、売上高や内部留保が少ないことがあります。このような背景から、給与以外の報酬を支払うのが難しくなり、ボーナスが支給できなくなることも考えられます。
1.2. スタートしたばかりのベンチャー企業
ベンチャー企業とは独自のアイデアや技術を用いて、事業の成長や拡大を目指す新興企業のことです。スタートしたばかりのベンチャー企業は、まだ経営が安定していないことも多く、経営が波に乗るまではボーナスを後回しにする企業もあるでしょう。
また、事業の立ち上げには多額の資金が必要になる場合もあり、ボーナスを支給できる資金的余裕がない可能性も考えられます。
1.3. 業績が悪化している会社
業績が悪化すると、企業の売上高や利益は減少し、資金繰りが厳しくなることがあります。そうなった場合、企業はコスト削減や効率化を図るため、組織の合理化を検討します。その一環として、ボーナスの支給が見送られることもあるでしょう。
1.4. 年俸制を導入している会社
年俸制では1年間の給与総額が決まっており、その給与を月々定額で支給するのが一般的です。そのため、月給制のように別途ボーナスが支払われるのではなく、毎月の給与にボーナスが含まれているという考え方になります。
つまり、定額支給の年俸制は「ボーナスはないが、毎月の給与に分割されたボーナスが上乗せされている」と言えます。
1.5. 労働組合がない会社
労働組合とは、賃金などの労働条件の改善を図るために従業員で組織する団体です。従業員たちの意向を会社に伝えやすいため、一般的に労働組合がある会社の方が、ボーナス制度を導入していることが多いと言われています。
【関連記事】「新卒のボーナス平均額は?社会人一年目の夏・冬はいくらもらえる?」
【関連記事】「20代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【関連記事】「30代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【関連記事】「中小企業のボーナス平均額は?何ヶ月分?支給なしの割合や大企業との差も解説」
【関連記事】「育休中でもボーナスはもらえる?減額されるケースや控除についても解説」
【関連記事】「夏のボーナス後の転職は「早めの転職活動」がポイント!」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】

「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。
【マイナビ転職エージェントのご利用方法はこちら】
2. 業種別のボーナスの支給傾向
ボーナスの支給については、業種によっても傾向が異なります。主な業種におけるボーナスを支給している事業所の割合を見てみると、最も割合が低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の54.8%です。また、「生活関連サービス等」も61.3%と、比較的低い数字になっています。
一方、「鉱業・採石業等」は100%と最も高く、「複合サービス事業」が97.7%、「電気・ガス・水道業」が95.9%と続きます。
※令和6年年末賞与の支給状況
(事業所規模5人以上)
| 業種 | 支給事業所数割合 |
|---|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 100.0% |
| 建設業 | 81.6% |
| 製造業 | 80.6% |
| 電気・ガス・水道業 | 95.9% |
| 情報通信業 | 81.8% |
| 運輸業、郵便業 | 80.4% |
| 卸売業、小売業 | 76.6% |
| 金融業、保険業 | 91.2% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 83.1% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 84.3% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 54.8% |
| 生活関連サービス等 | 61.3% |
| 教育・学習支援業 | 83.2% |
| 医療、福祉 | 85.6% |
| 複合サービス事業 | 97.7% |
| その他のサービス業 | 80.1% |
【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」
【関連記事】「夏・冬のボーナスはいつ支給される?一般企業と公務員の支給日や平均額を紹介」
【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?平均支給額と給与に対する割合を紹介」
【年収500万円以上の求人はこちら】

【関連記事】「転職におすすめの業界&未経験OKの職種9選|転職成功のコツも解説」
【関連記事】「新卒1年目の転職は可能?相談先や転職を成功させる4つのコツを解説」
【関連記事】「未経験からIT業界への転職を成功させる方法|役立つスキルや注意点も解説」
【在宅勤務可の求人はこちら】
3. ボーナスがない会社で働くメリット
全体的に見るとボーナスありの会社が多いものの、ボーナスがない会社には収入面などでいくつかのメリットも期待できます。
3.1. もともとの給与が高い場合がある
ボーナス制度を導入していない企業では、月々の給与を高く設定している場合があります。毎月の基本給が高ければ、ボーナスありの人と年収は同等、もしくは上回ることも考えられます。
3.2. 年収が安定する可能性がある
例えばボーナスを支給しない年俸制の場合は、1年間の給与総額が決まっているため、企業の業績によって年収が減ることはなく、安定した収入を得やすくなります。
ボーナスは企業の業績に大きく左右される面もあるため、業績が悪化すれば、大幅な減額になったり不支給になったりすることもあり、その影響で年収が減ることもあります。
3.3. 福利厚生が手厚い場合がある
ボーナス制度がない代わりに、福利厚生を充実させている企業もあります。企業が独自に設けている法定外福利厚生には以下のようなものがあります。
- 住宅手当・家賃補助
- 育児・家族・介護手当
- 資格手当・資格取得補助
- 医療・健康関連補助
- 社員食堂
- 法定外の休暇制度
福利厚生が充実していれば、結果的にボーナスをもらった場合と同等のメリットを享受できる可能性があります。
3.4. 退職時期に迷う必要がなくなる
転職などを理由に退職しようと思ったとき、ボーナス制度がある場合は「せっかくならボーナスを受け取ってから辞めたい」と考える方が多いでしょう。退職を申し出るタイミングに悩む方もいるのではないでしょうか。
一方、ボーナス制度がない会社であれば、ボーナスの支給時期に左右されることなく退職を申し出ることができます。
【関連記事】「福利厚生とは? 種類の例・メリット・デメリットをわかりやすく解説」
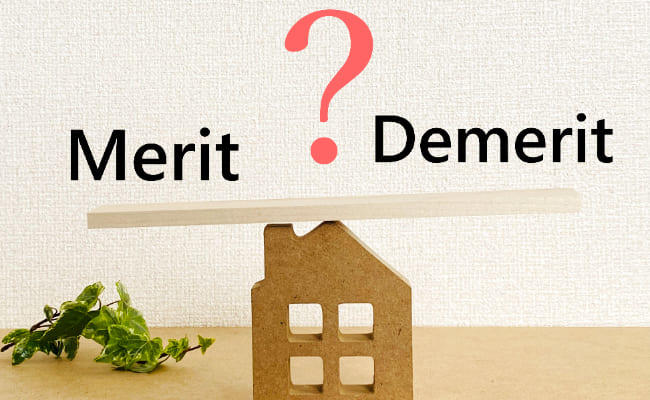
【関連記事】「地方公務員に転職するには?種類や給料、成功のコツなどを詳しく解説」
【関連記事】「資格なしの20代後半は転職できる?おすすめの転職先や選考対策も紹介」
【関連記事】「大手企業への転職は難しい?有利になる条件と3つのポイント」
【年収500万円以上の求人はこちら】
4. ボーナスがない会社で働くデメリット
上記のようなメリットがある一方で、「ボーナスがない会社はきつい」「収入が減るからやばい」など、ネガティブな声が聞かれることもあります。実際には、以下のようなデメリットが考えられるでしょう。
4.1. 貯蓄がしづらくなる可能性がある
臨時収入として受け取れるボーナスはできるだけ貯蓄にまわすという方も多いですが、ボーナスがない場合は毎月の給与から貯蓄していかなければならず、貯蓄計画を立てて着実に積み立てていかないと、なかなか貯蓄額が増えない可能性があります。
4.2. 大きな買い物をしづらくなる
まとまった金額が手に入るボーナス支給のタイミングは、高額な家具や家電、住宅や自動車の頭金などにお金を使う好機でもありますが、ボーナスがない場合は臨時収入を当てにできないため、こうした大きな買い物をする際も毎月の給与から支出しなければなりません。
4.3. モチベーションが低下することがある
ボーナスは通常の給与とは異なる臨時収入であり、個人の業績を評価してボーナス額を決定する場合もあるため、従業員のモチベーションの維持に繋がります。しかし、こうしたイベントがないと「目標がない」「やる気が出ない」など、仕事へのモチベーションが低下してしまう可能性も考えられます。
【関連記事】「【早見表】年収と手取りの違いは?簡単な計算式や早見表、シーンの使い分け方を紹介」
【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」
【関連記事】「IT業界とは?5つの業界別に職種やメリット・向いている人を紹介」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】
5. ボーナスなしでも収入をアップさせる方法
現在の職場でボーナスがないことで、収入に不安を感じている方もいるかもしれません。そこで、ここではボーナスなしでも収入をアップさせる方法を3つ紹介します。
5.1. スキルを磨いて昇進を目指す
収入は昇進するごとにアップしていくのが一般的です。企業によっては昇給に加えて、一定の役職以上に「役職手当」を支給している場合もあります。そのため、高度なスキルや知識を身につけて、昇進を目指すことが収入アップの近道と言えます。
5.2. 副業を行う
空いている時間を利用して、副業を行うことでも収入アップが目指せます。例えば自宅でできる副業としては、Webライター・動画編集・ブログ運営・出品代行などさまざまなものがあります。自分の得意なことを活かせば、楽しみながら副収入を得られるでしょう。
ただし、企業によっては副業を禁止している場合もあります。違反が見つかると懲戒処分を受ける可能性もあるため、しっかり確認してから始めましょう。
5.3. 資産運用を行う
月々の給与から資産運用を行って、利益を作り出すのも一つの方法です。例えば2024年からスタートした新NISAは、非課税期間の無期限化や非課税上限額の拡大などもあり、さらにメリットが大きくなっています。
大きな利益を期待するなら、株式を購入してみるのもおすすめです。少額から始めれば、リスクを抑えた運用が可能です。ただし、資産運用は必ずしも元本が保証されているわけではなく、損失が出る可能性もあることは十分把握しておく必要があります。
【関連記事】「ベースアップ(ベア)とは?定期昇給との違いや役割について解説」
【関連記事】「昇格とは?昇進・昇給との違いや昇格試験合格のポイントを解説」
【関連記事】「昇給とは?昇給制度の種類や仕事選びでの注意点を紹介」
【年収600万円以上の求人はこちら】
6. ボーナスがないなら転職も選択肢になる
ボーナスのない企業でも、基本給が高い、福利厚生が充実しているなどのメリットが存在する場合もありますが、これらのメリットを感じられない場合は、思い切って転職を検討してみるのも一つの選択肢です。
実際に、株式会社マイナビが実施した「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」(※1)によると、現在転職を検討していて転職経験がある人のうち、過去にボーナスが少ないことが理由で転職したと回答した人は69.1%(※2)と、ボーナスの額が転職理由になった人が約7割いることが分かりました。
(※1 20-50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3カ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)
(※2 (「1番大きな転職理由だった」(32.1%)と「1番ではないが転職理由だった」(37.0%)の合計)
ただし、給与面のみに注視するのではなく、自分にとって何が優先事項なのかを整理した上で判断することが大切です。まずは情報収集から始めて、自分の価値観に合った働き方を考えてみましょう。
【出典】株式会社マイナビ「「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」を発表」
【関連記事】「面接日程メール返信の基本|ケース別例文10選とNG行為」
6.1. 規則違反や契約違反が疑われる場合は対処が必要
民間企業ではボーナスは法的に義務付けられているものではありませんが、以下のようなケースでは規則違反や契約違反が疑われるため、適切な対処を図りましょう。
- 就業規則などに明記されているボーナス支給条件を満たしているにもかかわらず、ボーナスが支給されなかった
- 不支給に関する記載や説明がないのに、突然ボーナスがなくなった
- 育休や産休を理由に支給を拒否された
会社に直接相談するか、場合によっては労働基準監督署や労働局などに相談する方法もあります。
【出典】厚生労働省「都道府県労働局」
【関連記事】「転職のおすすめ時期はいつ?タイミング別のメリットや成功のコツを紹介」
【関連記事】「ボーナスとは?一般的な支給時期や支給額の基準、平均額などを紹介」
【年収400万円以上の求人はこちら】
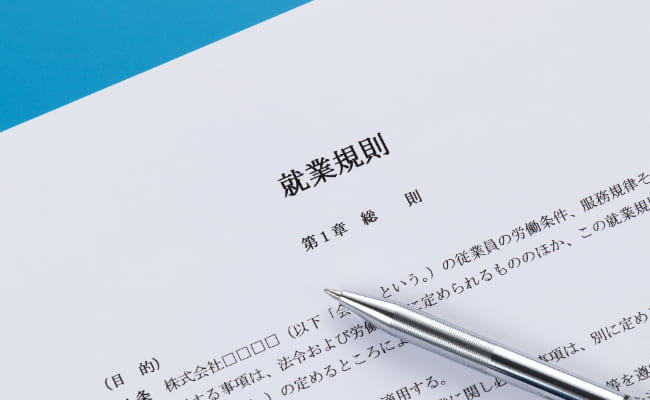
【関連記事】「人材紹介会社とは?利用するメリットや選び方のポイントを詳しく解説」
【関連記事】「職務経歴書の添削を転職エージェントで受けるべき理由とは?準備や注意点も紹介」
【関連記事】「マイナビ転職エージェントだからできる面接対策」
7. ボーナスがない会社への就職・転職で注意すべきこと
これから就職・転職しようと思っている会社にボーナスがなかった場合、ボーナスがない分ほかのメリットがあるかどうかを確認すべきでしょう。
7.1. 基本給が高く設定されているか
ボーナスがない分、基本給が高く設定されているかを確認しましょう。入社直後の時期も含め、「基本給で実際にいくらもらえるのか」「その水準はボーナスありの会社と比較して高いのか」といった点をしっかり確認することが大切です。
7.2. 成果に対するインセンティブはあるか
インセンティブ制度を導入している企業では、一定の成果や目標達成に応じて、従業員に報酬が支払われます。ボーナスのように定期的な報酬ではないものの、頑張り次第ではボーナスありの場合よりも高い収入を得ることができるかもしれません。
7.3. 福利厚生の内容は十分か
ボーナスがなくても、独自の手当てや休暇など自身の働き方やライフスタイルと合う福利厚生が充実していれば、ボーナス以上のメリットを得られる可能性があります。
福利厚生が充実している企業は、従業員の満足度も高く、業績も安定していることが多いため、年収とともにぜひチェックしておきたいポイントです。
7.4. 昇給実績は十分か
ボーナスがない企業で給与アップを目指すには、昇給の有無や頻度をしっかり確認することが重要です。
昇給実績の確認方法は、企業の口コミサイトをチェックしたり、転職エージェントに相談したりする方法があります。実際に働いている・働いていた人の声や、第三者の意見を参考にすることで、求人情報だけでは見えにくい企業の実態を確認しやすくなります。
【関連記事】「面接結果の連絡が遅いのは不合格のサイン?遅くなる理由と対処法を紹介」
【関連記事】「ボーナス(賞与)は退職予定でももらえる?損しないタイミングを解説」
キャリアアップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
【卒業年早見表はこちら】
8. まとめ
日本国内では、約2割の企業がボーナスを支給していません。ボーナスを支給しない理由としては、業績の悪化や年俸制の導入などが挙げられますが、ボーナスがないこと自体に違法性はありません。
ボーナスがない会社には、もともとの基本給が高かったり、年収が安定しやすかったりするメリットがある一方で、大きな買い物がしづらく、モチベーションを保ちにくいといったデメリットもあります。ボーナスがない会社を選ぶ際は、生活にどういった影響があるのかを確認し、納得したうえで判断しましょう。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける



