育休(育児休業)中は給与の支払いがないケースもありますが、それでもボーナスについては支給するという場合もあります。支給なし、満額支給、一部のみ支給など、企業や契約内容ごとに条件はさまざまです。
そこで、本記事では育休中のボーナスについて詳しく解説します。育休中のボーナス有無の確認方法から、計算方法、控除項目、もらえる手当まで細かく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」
【関連記事】「転職で年収アップの相場は?交渉の相場と年収アップの交渉をするコツをご紹介」
【テーマ別】平均年収ランキング
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 育休中でもボーナスはもらえる可能性がある
ボーナス(賞与)は、会社に在籍していれば育休(育児休業)中であってももらえる可能性があります。ただし、ボーナスは法的に支払いの義務があるわけではないため、育休中にもらえるかもらえないか、どの程度もらえるかは会社の就業規則や契約内容によります。
とはいえ、他の従業員にボーナスが支給される場合は、多くのケースで育休中の従業員にも支給されることになるでしょう。これは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で「婚姻・妊娠・出産などを理由に女性労働者に不利益を与えない」と定められているためです。
男性の場合も同様に、育休を理由にボーナスなしとすることは不当な扱い・違法行為とみなされる可能性が高いです。
【出典】e-GOV法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条」
【出典】e-GOV法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
【関連記事】「転職のおすすめ時期はいつ?タイミング別のメリットや成功のコツを紹介」
【関連記事】「ボーナスとは?一般的な支給時期や支給額の基準、平均額などを紹介」
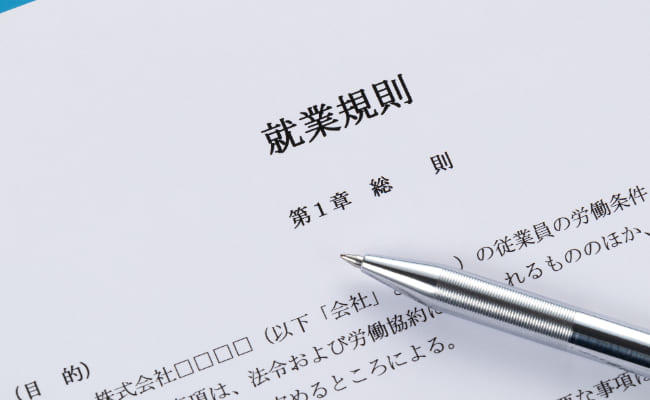
【関連記事】「ボーナスがない会社は何割?賞与なしの会社で働くメリットや注意点」
【関連記事】「夏のボーナス後の転職は「早めの転職活動」がポイント!」
「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。
【マイナビ転職エージェントのご利用方法はこちら】
2. 育休中にボーナスがもらえるケース
育休中でもボーナスはもらえる可能性があると説明しましたが、全ての人がボーナスをもらえるとは限りません。そこでまずは、育休中にボーナスがもらえるケースについて解説します。
2.1. 就業規則などにおけるボーナスの支給条件に当てはまる場合
ボーナスについては、就業規則や雇用契約書などに「ボーナスの支給基準」「ボーナスの支給期間」といった支給条件が明記されています。育休中の方でも、これらの条件に当てはまる場合は他の従業員と同様にボーナスを受け取ることができます。
特に以下のような場合は、育休中でもボーナスの満額が支給されるでしょう。
- 育休中の従業員も支給対象であることが明記されている
- 支給基準が「会社業績」や「固定額支給」となっている
前述したように、育休中であることを理由に支給されない場合や、就業規則などに「育休中の従業員へボーナスは支給しない」といった文言がある場合は、法律違反である可能性が高いです。
2.2. ボーナス算定期間中に勤務していた場合
ボーナス算定期間とは、ボーナス額決定のための査定対象期間です。夏のボーナスは10~3月、冬のボーナスは4~9月を算定期間としている企業が多く、この期間の勤務状況や業務成績などを評価してボーナス額を算出しています。
そのため、ボーナス受給時期に育休を取得していたとしても、査定期間中に勤務していたのであれば、通常通りボーナスが受け取れる可能性が高いでしょう。
【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」
【関連記事】「ボーナス(賞与)は退職予定でももらえる?損しないタイミングを解説」
【関連記事】「転職におすすめの業界&未経験OKの職種9選|転職成功のコツも解説」
【関連記事】「「転職したいけど何がしたいかわからない」ときはどうすればいい?解決策や転職先の見つけ方をご紹介」
【年収400万円以上の求人はこちら】

3. 育休中のボーナスが減額される・もらえないケース
育休中でもボーナスをもらえるケースは多いものの、支給基準によっては減額されるケースもあります。また、会社との契約などによってはそもそもボーナスがもらえないこともあるでしょう。
3.1. ボーナス算定期間中に育休を取得した場合
先述した通り、ボーナス額は算定期間中の勤務状況や業務成績などによって決まることが多いです。そのため、算定期間中に育休を取得した場合、ボーナスが減額されるかもしれません。
例えば、10~3月が夏季ボーナスの査定期間である場合、1月から育休を取得すると、10~12月しか査定対象にならないため、減額されてしまう可能性があります。
3.2. 企業の業績が悪化した場合
企業によっては、就業規則や雇用契約書に「業績が悪化した場合は減額する、または不支給となる」といった内容が記載されていることもあります。その場合、業績の悪化などを理由にボーナスが減額になったり、なくなったりする可能性があります。
これは、育休中の従業員のみならず、すべての従業員に当てはまる減額や支給無しのケースです。
3.3. 年俸制の場合
年俸制では1年間の給与総額が決まっており、その給与を月々定額で支給するのが一般的です。毎月の給与にボーナス分も含まれているケースが多く、通常、育休中は給与が支払われないため、実質ボーナスが減額・支給なしとなる可能性があります。
以下に月給制・年俸制の違いの例を挙げます。
【年収600万円・月給制の例】
・給与40万円×12カ月
・ボーナス120万円
【年俸600万円・年俸制の例】
・給与50万円(うち10万円はボーナス分)×12カ月
詳しい支給基準は企業ごとに異なるので、事前に就業規則や雇用契約書で確認することが大切です。
【関連記事】「新卒のボーナス平均額は?社会人一年目の夏・冬はいくらもらえる?」
【関連記事】「新卒1年目の転職は可能?相談先や転職を成功させる4つのコツを解説」
【関連記事】「20代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【関連記事】「30代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【関連記事】「中小企業のボーナス平均額は?何ヶ月分?支給なしの割合や大企業との差も解説」
【年収500万円以上の求人はこちら】

4. 育休中のボーナスはいくらもらえる?計算方法は?
ボーナスの支給基準は企業によって異なりますが、ここでは査定期間中の勤務日数に応じて支給額を決定しているケースを例に挙げて紹介します。
例えば、満額で40万円のボーナスをもらえる場合、査定期間180日のうち、45日勤務してそれ以降は育休を取得したケースでは、日割り計算で40万円×(45日÷180日)=10万円となります。
ただし、実際は企業の業績や個人の成果なども加味されて、単純な日割り計算での支給にはならないことも多いため、ボーナスの支給基準に関しては就業規則や雇用契約書などでしっかり確認しておきましょう。
4.1. 育休に入る時期や復帰時期を検討しておこう
これから出産や子育てについて計画を立てる方は、可能な範囲で育休に入るタイミング、復帰するタイミングを検討しておくことをおすすめします。会社のボーナス支給条件に合わせて上手に育休を取ることで、ボーナスを少しでも多く受け取れるでしょう。
夫婦で育休を取る時期をずらしたり、家族にサポートを依頼したりといった工夫で収入を安定させられる場合もあります。
4.2. より安心できる環境を探すのも一つの方法
もし今の職場で今後の育休中の収入の不安などがある場合、転職をしてより安心できる環境を探すのも一つの方法です。転職することで、よりボーナスの制度や福利厚生が整った職場に身を移すことができ、家庭とも両立しやすくなることが期待できます。
実際に、株式会社マイナビが実施した「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」(※1)によると、現在転職を検討していて転職経験がある人のうち、過去にボーナスが少ないことが理由で転職したと回答した人は69.1%(※2)と、ボーナスの額が転職理由になった人が約7割いることが分かりました。
(※1 20-50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3カ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)
(※2 (「1番大きな転職理由だった」(32.1%)と「1番ではないが転職理由だった」(37.0%)の合計)
また、年代別でみると、20代ではボーナスが少ないことが「1番大きな転職理由だった」割合が46.0%と、ボーナスの額の少なさが転職の動機となる割合がほかの年代と比べて大きいことが分かります。
【出典】株式会社マイナビ「「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」を発表」
【関連記事】「夏・冬のボーナスはいつ支給される? 一般企業と公務員の支給日や平均額を紹介」
【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?平均支給額と給与に対する割合を紹介」
【関連記事】「未経験からIT業界への転職を成功させる方法|役立つスキルや注意点も解説」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】

【関連記事】「資格なしの20代後半は転職できる?おすすめの転職先や選考対策も紹介」
【関連記事】「大手企業への転職は難しい?有利になる条件と3つのポイント」
【離職中の方限定】
今すぐ転職したい!
最短で転職するための「無料個別相談会」
5. 育休中にボーナスを不当に減額された・もらえなかった場合
他の従業員にはボーナスが支給されているのに、育休中の自分だけもらえなかったなど、育休を理由にボーナスを不当に減額された・もらえなかった場合、以下のような対処法が考えられます。
5.1. 会社に申し出る
まずは会社に申し出て、ボーナスが支給されなかった理由や減額された原因を確認しましょう。場合によっては、就業規則などに記載されている条件を見落としていたり、育休以外の理由があったりすることも考えられます。
育休を理由にしたボーナスの不支給や減額は違法にあたる可能性があるものの、ボーナス自体は必ずしも支給が義務付けられているものではないため、慎重に確認することが大切です。
5.2. 労働基準監督署や労働局に相談する
「会社に確認を求めても明確な理由が提示されない」「明らかに不当な扱いにもかかわらず、会社が対応してくれない」などの場合は、労働基準監督署や各都道府県の労働局に相談することも考えましょう。その際は、就業規則や雇用契約書をコピーしたり、会社とのやり取りをメモしたりしておくのがおすすめです。
【出典】厚生労働省「都道府県労働局」
【関連記事】「【ベースアップ(ベア)とは?定期昇給との違いや役割について解説」
【関連記事】「昇格とは?昇進・昇給との違いや昇格試験合格のポイントを解説」
【関連記事】「昇給とは?昇給制度の種類や仕事選びでの注意点を紹介」
6. 育休中のボーナスに対する社会保険料はどうなる?
ボーナスにかかる社会保険料は、ボーナス支給月の末日を含んだうえで、連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
例えば、7月にボーナスが支給される場合、7月31日を含んで連続1ヶ月以上の育休を取得すれば、社会保険料が免除になります。一方、7月1日~7月30日など末日を含まない場合や、7月20~8月15日など1ヶ月を超えない場合は免除になりません。なお、所得税や雇用保険料は通常通り控除の対象です。
6.1. 育休中に報酬があると社会保険料は免除されない?
育休中は、上記のように一定の条件を満たすことで社会保険料が免除されますが、この間に短期的な就労による報酬を得た場合、内容によっては免除の対象外となることがあります。
免除の対象になるかどうかは、実際の就労日数や報酬額、勤務内容などによって変わります。社会保険料への影響が考えられる就労の予定がある場合は、事前に勤務先に確認しておきましょう。
【出典】日本年金機構「育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます」
【関連記事】「ボーナス(賞与)から社会保険料はどれくらい引かれる?社会保険の仕組みを知ろう」
【関連記事】「社会保険とは?公的医療保険と公的年金について詳しく解説!【社会人のためのお金の勉強】」
【関連記事】「【早見表】年収と手取りの違いは?簡単な計算式や早見表、シーンの使い分け方を紹介」
【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」
7. ボーナスをもらうと育休中の手当は減額される?
育休中には以下のようにさまざまな手当が支給されることがありますが、ボーナスをもらうことでこれらの手当が減額されたり不支給になったりすることは基本的にはありません。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 出生時育児休業給付金・育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金
ただし、給与の受け取り状況によっては、減額や不支給の対象となる場合がありますので、各手当の支給条件をしっかりと確認しておくことが大切です。
【出典】全国健康保険協会「子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます」
【出典】全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
【出典】厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」
【出典】厚生労働省「育児休業等給付について」
【出典】厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました」
【出典】厚生労働省「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設しました」
キャリアアップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
【卒業年早見表はこちら】
8. まとめ
就業規則や雇用契約書に記載されている支給条件を満たせば、育休中でもボーナスを受け取れる可能性は高くなります。また、ボーナスを受け取ることで、もらえるはずの手当がもらえなくなったり減額されたりすることはありません。
ただし、育休の取得時期によってはボーナスに影響が出る場合があります。また、会社の業績によっては、そもそもボーナスが支給されないことも考えられます。まずは、自分の会社のボーナスがどういった条件のもと支給されるのか、しっかり確認しておくことが重要です。
【関連記事】「人材紹介会社とは?利用するメリットや選び方のポイントを詳しく解説」
【関連記事】「職務経歴書の添削を転職エージェントで受けるべき理由とは?準備や注意点も紹介」
【関連記事】「マイナビ転職エージェントだからできる面接対策」
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける



