20代のボーナス平均額は年間約54万円です。ただし、入社したての20代前半と業務に慣れてきた20代後半では職場での立ち位置が変わるため、同じ20代でもボーナス平均額には差が生じる可能性があります。
本記事では、業種・男女・学歴・企業規模・都道府県などの項目ごとに、20代前半と20代後半に分けてボーナスの平均額を細かく紹介するので、20代のボーナスについて知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
【関連記事】「今よりも年収を上げたい!年収アップのための転職準備と企業の選び方」
【関連記事】「転職で年収アップの相場は?交渉の相場と年収アップの交渉をするコツをご紹介」
【テーマ別】平均年収ランキング
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 20代のボーナス平均額は年間約54万円
20代の年間ボーナス平均額は約54万円です(※)。ただし、ボーナスは経験やスキルを積み重ねることでアップしていく傾向にあるため、まだ入社したての20代前半と、仕事に慣れてきた20代後半では差が生じる可能性があります。
(※令和6年賃金構造基本統計調査の年齢別年間賞与その他特別給与額から算出した平均値)
30代~50代を含めた年間ボーナスの平均額は以下のとおりです。
企業規模計(10人以上)
| 年代 | 年齢区分 | 年齢別 年間賞与その他特別給与額 | 年代別 年間賞与その他特別給与額(※) |
|---|---|---|---|
| 20代 | 20~24歳 | 39.6万円 | 約54万円 |
| 25~29歳 | 68.6万円 | ||
| 30代 | 30~34歳 | 83.0万円 | 約91万円 |
| 35~39歳 | 99.1万円 | ||
| 40代 | 40~44歳 | 111.0万円 | 約115万円 |
| 45~49歳 | 118.6万円 | ||
| 50代 | 50~54歳 | 123.7万円 | 約125万円 |
| 55~59歳 | 126.7万円 |
【出典】厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」
【年収300万円以上の求人はこちら】
1.1. 全年代のボーナス平均支給額は約82万円
厚生労働省の公表によると、令和6年の全業種・全年代(従業員5人以上の事業所)におけるボーナス平均支給額は約82万円でした。
なお、夏と冬を比較した場合、夏が414,515円、冬が413,277円と大きな差は見られません。
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要」
【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」
1.2. ボーナス支給額は企業などにより差がある
そもそもボーナスが支給されない企業もありますし、支給される場合も金額は企業の取り決めによります。同じ企業内でも、基本給の額や役職、業績などによって支給額が異なる場合もあるでしょう。
ボーナスについては法的な定めがなく、企業に支給義務もありません。厚生労働省の公表によると、令和6年度にボーナスが支給されたのは全業種(従業員5人以上の事業所)のうち7割を超えていますが、支給の有無や条件、金額などは企業が自由に決めて良いものとされています。
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要」
【関連記事】「ボーナスがない会社は何割?賞与なしの会社で働くメリットや注意点」
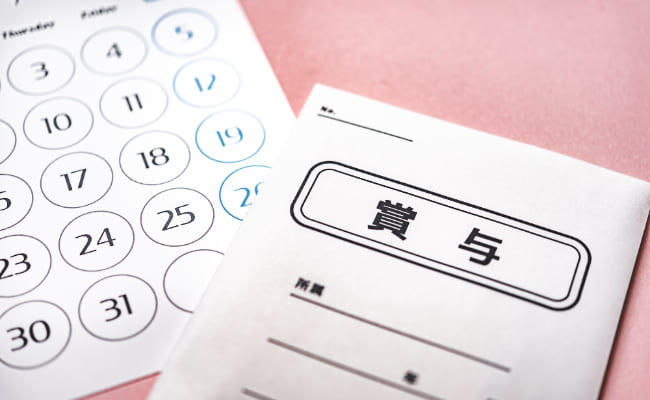
【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」
【関連記事】「夏・冬のボーナスはいつ支給される?一般企業と公務員の支給日や平均額を紹介」
【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?それぞれの平均支給額と給与に対する割合を紹介!」
【関連記事】「新卒1年目の転職は可能?相談先や転職を成功させる4つのコツを解説」
「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。
【年収400万円以上の求人はこちら】
2. 【項目別】20代のボーナス平均額
ここからは、厚生労働省が公表した令和6年のデータから、20代のボーナス平均額を項目別に紹介します。入社後まだ間もないことが多い20~24歳と、少しずつ仕事に慣れ始める25~29歳に分けてまとめました。
【出典】厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査(学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額)」
2.1. 【業種別】20代のボーナス平均額
まずは、業種別に20代のボーナス平均額を見てみましょう。
令和6年 年間賞与その他特別給与額
(事業所規模10人以上)
| 業種 | 20~24歳のボーナス平均額(千円) | 25~29歳のボーナス平均額(千円) |
|---|---|---|
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 798.7 | 1304.6 |
| 建設業 | 467.9 | 836.8 |
| 製造業 | 503.0 | 753.7 |
| 電気・ガス・水道業 | 596.9 | 991.6 |
| 情報通信業 | 365.3 | 799.9 |
| 運輸業、郵便業 | 454.0 | 649.3 |
| 卸売業、小売業 | 348.4 | 705.1 |
| 金融業、保険業 | 413.2 | 1006.2 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 387.0 | 919.6 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 392.2 | 860.9 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 194.2 | 331.6 |
| 生活関連サービス等 | 129.2 | 361.6 |
| 教育・学習支援業 | 467.7 | 740.9 |
| 医療、福祉 | 409.0 | 575.4 |
| 複合サービス事業 | 580.9 | 792.3 |
| その他のサービス業 | 242.9 | 389.2 |
ボーナス平均額が最も多い職種は「鉱業・採石業・砂利採取業」で、20~24歳では約79万円、25~29歳では約130万円でした。また、どの業種でも20代前半より20代後半の方が支給額は増えています。
2.2. 【男女別】20代のボーナス平均額
次に、男女別の20代ボーナス平均額を見てみましょう。
令和6年 年間賞与その他特別給与額
(事業所規模10人以上)
| 性別 | 20~24歳のボーナス平均額(千円) | 25~29歳のボーナス平均額(千円) |
|---|---|---|
| 男性 | 435.1 | 755.1 |
| 女性 | 356.2 | 602.4 |
男女別の年間賞与平均額を見ると、20代前半、後半ともに男性の方が上回っています。
2.3. 【学歴別】20代のボーナス平均額
次に、学歴別の20代ボーナス平均額を紹介します。
令和6年 年間賞与その他特別給与額
(事業所規模10人以上)
| 最終学歴 | 20~24歳のボーナス平均額(千円) | 25~29歳のボーナス平均額(千円) |
|---|---|---|
| 中学 | 223.9 | 243.2 |
| 高校 | 522.2 | 585.3 |
| 専門学校 | 328.5 | 524.2 |
| 高専・短大 | 476.2 | 660.7 |
| 大学 | 372.1 | 827.0 |
| 大学院 | 53.4 | 1045.9 |
20代前半では、18~20歳頃から働き始める高卒の方の平均額が最も高く、次いで短大卒の方の平均額が高くなっています。しかし、20代後半になると、最も高い平均額は大学院卒の方で、次に大卒の方が続きます。
2.4. 【企業規模別】20代のボーナス平均額
続いて、従業員数による企業規模別の20代ボーナス平均額を紹介します。
令和6年 年間賞与その他特別給与額
| 従業員数 | 20~24歳のボーナス平均額(千円) | 25~29歳のボーナス平均額(千円) |
|---|---|---|
| 10~99人 | 303.1 | 485.8 |
| 100~999人 | 393.4 | 689.8 |
| 1000人以上 | 461.7 | 807.6 |
従業員が1000人を超える大企業は、ボーナス平均額も多いことがわかります。ただし、従業員が少ないベンチャー企業などの中には、賞与が少ない分毎月の給与額を高く設定しているところもあります。そのため、賞与が少ないからといって、一概に年収が低いとは言い切れません。
2.5. 【都道府県別】20代のボーナス平均額
最後に、都道府県別の20代ボーナス平均額を紹介します。ここでは、全年代におけるボーナス平均額が高い上位5つの都道府県(東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫)についてまとめました。
令和6年 年間賞与その他特別給与額
(事業所規模10人以上)
| 従業員数 | 20~24歳のボーナス平均額(千円) | 25~29歳のボーナス平均額(千円) |
|---|---|---|
| 東京 | 361.8 | 727.6 |
| 神奈川 | 385.8 | 750.9 |
| 愛知 | 459.9 | 765.0 |
| 大阪 | 382.7 | 724.7 |
| 兵庫 | 376.0 | 676.0 |
上記5つの都道府県における20代のボーナス平均額は、愛知県が最も高い値です。ただし、全年代のボーナス平均額を比較すると、東京都が約123万円と最も高くなっています。
【関連記事】「20代の平均年収は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく解説」
【関連記事】「20代の平均貯金額はいくら?中央値や理想の貯金額、賢い貯め方も紹介」
【関連記事】「20代で年収1000万円を稼ぐには?目指せる職種や稼ぐ方法を紹介」
【年収500万円以上の求人はこちら】

【関連記事】「新卒のボーナス平均額は?社会人一年目の夏・冬はいくらもらえる?」
【関連記事】「30代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」
【関連記事】「中小企業のボーナス平均額は?何ヶ月分?支給なしの割合や大企業との差も解説」
【関連記事】「育休中でもボーナスはもらえる?減額されるケースや控除についても解説」
【関連記事】「今よりも年収を上げたい!年収アップのための転職準備と企業の選び方」
【在宅勤務可の求人はこちら】
3. 20代のボーナスに関するQ&A
ここでは、ボーナスに関してよくある質問を紹介します。支給額の決め方や、手取り額、中央値についても解説します。
3.1. 支給額の決め方は?
前述のとおりボーナスに法的な定めはなく、支給額の決め方は各企業に委ねられています。一般的には「基本給与連動型賞与」といって、「半期の経常利益率が〇%以上であった場合、支給月数を給与の2カ月分にする」など「給与の〇ヶ月分」という基準を設定しているケースが多い傾向です。
そのほかにも、等級や役職、個人の業績に応じて独自のボーナス額算出基準を設けている企業も存在します。このように、ボーナス額の決め方は企業によって異なるため、気になる場合は就業規則や雇用契約書をチェックしましょう。
【関連記事】「ボーナス(賞与)は退職予定でももらえる?損しないタイミングを解説」
3.2. ボーナスは給与何ヶ月分?
「給与の〇ヶ月分」という基本給与連動型賞与を導入している企業が多い中、実際に平均何ヶ月分の給与額がボーナスとして設定されているのでしょうか。令和6年の給与に対するボーナスの支給割合は以下の通りです。
令和6年夏季・年末賞与の支給状況
(事業所規模5人以上)
| 業種 | 【夏季賞与】きまって支給する 給与に対する支給割合 (ヵ月分) | 【年末賞与】きまって支給する 給与に対する支給割合 (ヵ月分) | 【年間】きまって支給する 給与に対する支給割合 (ヵ月分) |
|---|---|---|---|
| 鉱業、採石業等 | 1.12 | 1.12 | 2.24 |
| 建設業 | 1.12 | 1.16 | 2.28 |
| 製造業 | 1.03 | 1.10 | 2.13 |
| 電気・ガス業 | 1.82 | 1.93 | 3.75 |
| 情報通信業 | 1.32 | 1.27 | 2.59 |
| 運輸業、郵便業 | 0.97 | 0.98 | 1.95 |
| 卸売業、小売業 | 1.03 | 1.02 | 2.05 |
| 金融業、保険業 | 1.61 | 1.62 | 3.23 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 1.50 | 1.48 | 2.98 |
| 学術研究等 | 1.28 | 1.35 | 2.63 |
| 飲食サービス業 | 0.39 | 0.42 | 0.81 |
| 生活関連サービス等 | 0.71 | 0.75 | 1.46 |
| 教育・学習支援業 | 1.52 | 1.63 | 3.15 |
| 医療、福祉 | 0.89 | 1.00 | 1.89 |
| 複合サービス事業 | 1.63 | 1.71 | 3.34 |
| その他のサービス業 | 1.16 | 1.09 | 2.25 |
業種別に見ると、電気・ガス業の3.75ヵ月分が最も高い割合でした。
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査」
【関連記事】「年収はボーナス含む?計算方法や手取り・年俸との違いを解説!」
3.3. 手取り額や中央値はどれくらい?
給与と同様に、ボーナスからも「所得税」と「社会保険料」が控除されます。そのため、実際に受け取る手取り額は、額面の約7~8割程度になることが多いでしょう。
20代のボーナス平均額54万円で計算すると、手取り平均額は約38万円~43万円になります。
また、ボーナスの中央値は公表されていないものの、厚生労働省が調査した令和5年の結果によると、全世帯における平均所得金額が約536万円なのに対し、中央値は約410万円と平均額よりも126万円ほど少ない金額となっています。
そのため、20代のボーナス中央値も、平均よりも少し少なくなる可能性があります。
【出典】厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査 Ⅱ各種世帯の所得等の状況」

【関連記事】「【早見表】年収と手取りの違いは?簡単な計算式や早見表、シーンの使い分け方を紹介」
【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】
4. 20代におすすめのボーナスの使い道
比較的自由にお金を使うことのできる20代ですが、ボーナスをどのように使用すべきでしょうか。ここでは、20代におすすめのボーナスの使い道を4つ紹介します。
4.1. 自己投資に使う
社会人として歩み始めたばかりの20代は、将来のために自己投資をすることで、さらなるキャリア発展や収入アップが目指せます。例えば、新しいスキルや資格を習得するための書籍を購入したり、トレーニングプログラムに参加したりするのがおすすめです。
また、ジムに通って体を鍛えたり、健康診断を受けて生活指導をしてもらったりするのも、将来に向けた自己投資の一種です。今だけでなく先のことを考えた上で、知識の向上や健康の維持を目的に自己投資するのは、ボーナスの賢い使い道と言えます。
4.2. 投資資金にする
新NISAの登場をきっかけに、日本では投資への注目が集まっています。ボーナスを株式、債券、不動産などの投資に回すことで、将来のリタイアメント資金を増やせるかもしれません。20代であれば、30年、40年という長期投資も可能であり、場合によっては十分なリターンも期待できます。
ただし、投資には元本割れのリスクがあることを理解したうえで、慎重に行う必要があります。
4.3. 家族へのプレゼントを買う
両親やきょうだいなど、家族へプレゼントを贈るのもおすすめです。身近な人に喜んでもらえることは、自分への投資とはまた違った満足感があります。普段は言えない感謝の気持ちを、ボーナスという機会に伝えるのも良いでしょう。
4.4. 旅行へ行く
旅行へ行くのも満足度の高いボーナスの使い道です。旅行に行くことで、普段の生活では味わえない非日常の体験を味わえます。
社会に出て間もない20代は、学生時代とのギャップに疲れを感じる年代です。そのため、旅行に行き日常を忘れてゆっくりリフレッシュすれば、「また仕事を頑張ろう」という前向きな気持ちになれるでしょう。
【関連記事】「ボーナスの使い道ランキングを紹介!年代別おすすめの使い方や無駄遣いを防ぐコツは?」

【関連記事】「資格なしの20代後半は転職できる?おすすめの転職先や選考対策も紹介」
【関連記事】「30代の転職が厳しいといわれる3つの理由|おすすめの転職先も紹介」
【関連記事】「大手企業への転職は難しい?有利になる条件と3つのポイント」
5. 20代がボーナスを増やす方法
20代の方の中には、「思ったよりボーナスが少ない」「なかなかボーナスが増えない」と不満や不安を抱えている方がいるかもしれません。そこで、ここではボーナスを増やすための方法を紹介します。
5.1. 成果を出して昇進する
ボーナスの支給額には個人の業績や役職、基本給を加味する企業が多いため、仕事で成果を出して昇進し責任ある役職などに就くことで、さらなるボーナスアップが期待できます。
平均額の項目でお伝えした通り、基本的にボーナスは20代前半よりも20代後半の方が多くなる傾向です。これは、社会人としての経験値とスキルがアップし、より重要な仕事を任されるようになったことが理由の一つと考えられます。
5.2. 運用する
ボーナスの支給額アップが期待できないときは、もらったボーナスを運用で増やす方法があります。ただし、投資にはリスクがつきものであるため、いきなり大きな額を運用し、短期で大きなリターンを得ようとするのは危険です。不安な場合は専門家に相談しつつ、少額から始めるのがおすすめです。
5.3. 転職する
ボーナスの額に納得がいかない場合は、思い切って転職するのも一つの選択肢です。特に、業績の悪化などによりボーナスがカットされたり、今後もボーナスが増える見込みがなかったりする場合は、早めに転職した方が将来的なメリットも大きくなる可能性があります。
株式会社マイナビが実施した「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」(※1)でも、現在転職を検討していて転職経験がある人のうち、過去にボーナスが少ないことが理由で転職したと回答した人は69.1%(※2)と、ボーナスの額が転職理由になった人が約7割います。
(※1 20-50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3カ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)
(※2 (「1番大きな転職理由だった」(32.1%)と「1番ではないが転職理由だった」(37.0%)の合計)
ただし、ボーナスの額だけで転職先を決めると、肝心の仕事が合わずに後悔することにもなりかねません。条件にぴったり合う転職先を見つけたい場合は、転職エージェントなど転職のプロに頼るのも良い方法です。
【出典】株式会社マイナビ「「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」を発表」
【関連記事】「ベースアップ(ベア)とは?定期昇給との違いや役割について解説」
【関連記事】「昇格とは?昇進・昇給との違いや昇格試験合格のポイントを解説」
【関連記事】「昇給とは?昇給制度の種類や仕事選びでの注意点を紹介」
キャリアアップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
【卒業年早見表はこちら】
6.まとめ
20代でもらえるボーナスの平均額は、20代前半か後半かで大きな開きがあります。また、業種や学歴、企業の規模などによって、100万円以上もらえる方もいれば、数万円という方もいます。
ボーナスが少ない企業では毎月の給与を多く設定しているケースもあり、ボーナスの額が即年収に結びつくとは言い切れませんが、ボーナスがない、または減少した場合、特に20代の方は早めに転職を考えた方が良い場合もあります。
紹介したボーナス平均額を参考に、将来のキャリア形成についてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける



