取引先などの関係者に手紙などを送る際には、季節に合わせた時候の挨拶を添えるのが一般的です。時候の挨拶を添えることで、相手に丁寧さと心遣いを伝えられます。
そこで本記事では、日本の多くの地域で冬の気配を徐々に感じるようになる11月に使える時候の挨拶を紹介します。時候の挨拶がどのようなものなのかを含め、上旬・下旬など使う時期に応じた具体的な使用例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】「【例文付き】月ごとの時候の挨拶・結びの挨拶一覧!注意点やコツも解説」
【関連記事】「手紙の書き方を例文で解説!マナー違反をしないための注意点も」
【関連記事】「【例文あり】営業メールの書き方ガイド|シーン別に使える例文を紹介」
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 時候の挨拶とは?
時候の挨拶とは、手紙を送る際に季節や天候の話題に触れながら相手の体調や状況を伺う一文です。本文の前に添える書き出しの挨拶と、本文の終わりに添える結びの挨拶があります。
11月は体感的には秋が終盤となり、暦の上では冬本番に差し掛かる季節です。そのため、時候の挨拶でも「寒」「冬」といった言葉がよく使用されます。そんな時候の挨拶には、どのような役割があるのでしょうか。
1.1. 相手に気遣いを伝えられる
時候の挨拶は、四季の特色が豊富な日本ならではの文化です。時候の挨拶を添えることで、無機質になりがちなビジネスシーンの手紙にも季節感が生まれ、温かみが加わります。
11月は秋が終わりに差し掛かり、冬に向かって寒さが増していく時期なので、寒さによる体調の変化を気遣う挨拶を添えるといいでしょう。また、紅葉や小春日和にかけて相手の繁栄や活躍を願う一文も最適です。
本題に入る前にこうした挨拶を添えることで、相手側も丁寧な印象を受け、次に続く本文へもスムーズに導入できます。(※)
(※なお、仕事の取引先や目上の方ではなく親しい人などに向けて頭語として「拝啓」ではなく「前略」を使う場合は、時候の挨拶や安否の挨拶を省略します)
1.2. メールやLINEでは必要?
メールやLINEといったオンラインツールでは、基本的に時候の挨拶は不要とされています。なぜなら、メールやLINEではできるだけ簡潔に、わかりやすく要件を伝えることが求められるからです。
ただし、いきなり本文に入るのではなく、「いつもお世話になっております」「突然のメール失礼いたします」といった一文を添えましょう。

【関連記事】「11月の季語を一覧で紹介!美しい花を使った有名俳句や時候の挨拶も」
【関連記事】「冬の季語を一覧で紹介!美しい季語を使った有名俳句も解説」
【関連記事】「季語とは?春夏秋冬の季語一覧や有名俳句、時候の挨拶例文を紹介」
【関連記事】「仕事の選び方が分からない場合の対処法|自分に合う転職先探しのコツも紹介」
「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。
【マイナビ転職エージェントのご利用方法はこちら】
2. 挨拶状の構成と送るタイミング
実際に挨拶状を書く場合、どのような構成にしたら良いか悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは時候の挨拶を含めて、挨拶状をどのような順番で書けば良いか、その基本構成を解説します。また、挨拶状を送るタイミングについても解説します。
2.1. 挨拶状の基本構成
挨拶状は、一般的に次の4つの構成から成り立っています。
| 前文 | 「拝啓」「謹啓」などの頭語、時候の挨拶、それに続く相手の健康や繁栄を祝う言葉を書きます。 |
|---|---|
| 主文 | 「さて」「このたびは」などのおこし言葉から、挨拶状で伝えたい主題を書きます。 |
| 末文 | 相手の健康や繁栄を祈る結びの言葉と、「敬具」「謹白」などの結語を書きます。 |
| 後付 | 日付、差出人名、宛名を書きます。(メールの場合、宛名は文書の最初に入れます) |
挨拶状を取引先や仕事の関係者へ送る場合は、上記のように正しい構成を意識して書くことが大切です。
まずは、「拝啓」などの頭語、次に季節に合わせた時候の挨拶を記載します。続いて本文を書き、結びの挨拶で結んだら、前文の頭語と対になる「敬具」などの結語で締めます。最後に、日付や差出人を添えます。
【関連記事】「【例文付き】「拝啓」の意味とは?手紙での使用方法を解説」
【関連記事】「【例文付き】「敬具」の使い方とは?意味や正しい書き位置を解説」
2.2. 挨拶状を出すタイミング
感謝の気持ちを伝える挨拶状は、できるだけ早く出すのがマナーです。
お礼状は品物を受け取った当日、もしくは遅くても3日以内に出すようにしましょう。イベントなどへの招待状は、少なくとも1週間前までに送るのが基本です。
仕事関係では、転勤や転任の挨拶は辞令が出た当日から異動後1〜2か月以内に、社長や役員交代の挨拶は、交代から1週間以内に出すのが一般的です。移転や転居の挨拶は、1ヶ月以内に届けるのが望ましいとされています。
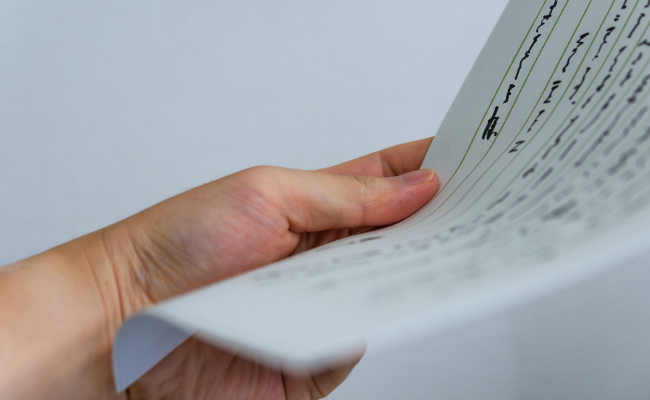
【関連記事】「【例文】ビジネスシーン別お礼メールの書き方や使えるフレーズ集を紹介」
【関連記事】「【例文】初めての相手に送る挨拶メールの書き方!マナーや注意点、言い換え例」
【関連記事】「【キャリアチェンジ向け】転職理由の例文テクニック|PREP法の活用方法も」
【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」
【テーマ別】平均年収ランキング
3. 時候の挨拶は漢語調と和語調を使い分けよう
時候の挨拶には「漢語調」と「和語調」があります。漢語調は硬くかしこまった言い回しのため、主にビジネスシーンや目上の方への手紙で使用されます。
和語調はやわらかく日常的な言い回しが多いので、親しい間柄の方や家族への手紙に適しています。
4. 【漢語調】ビジネスで使える11月の時候の挨拶
ビジネスシーンで使われる漢語調の時候の挨拶は、「〇〇の候」「〇〇の折」「〇〇のみぎり」といった形で始め、そのあとに相手を気遣う言葉などを簡単に添えるのが一般的です。
ここでは、使用する時期に合わせていくつかの例を紹介します。
4.1. 11月全般の時候の挨拶
以下の3つは、11月全般に使える主な時候の挨拶です。
●向寒(こうかん)の候
「向寒」は寒さに向かって季節が進んでいることを意味します。11月7日頃は冬が始まる立冬にあたるため、11月には最適な時候の挨拶です。
●残菊(ざんぎく)の候
本来は10月半ばに見頃を迎える菊が、冬の初めになってもまだ咲き残っているという意味があります。そのため、11月いっぱいは使用可能です。
●霜寒(そうかん)の候
霜が降りるほど寒い時期になったことを意味します。11月頭から12月初旬頃まで使用できる時候の挨拶です。
<例文>
拝啓 向寒の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと心よりお喜び申し上げます。
さて・・・・・・【本文】
落ち葉散りしく時節、皆様のご多祥を心よりお祈り申し上げます。
敬具
4.2. 11月上旬~中旬の時候の挨拶
以下の3つは、11月上旬〜中旬の書き出しとして使える主な時候の挨拶です。
●晩秋(ばんしゅう)の候
暦の上では10月23日頃~11月6日頃までが晩秋とされており、秋の終わりを意味します。11月7日頃の立冬前日までは使用可能です。
●立冬(りっとう)の候
11月7日頃の立冬前後に使用できる挨拶です。この日を境に暦の上では冬が始まるため、寒さや雪というキーワードも徐々に使えるようになります。
●冷雨(れいう)の候
冬が近づき、雨も一層冷たくなる時期という意味です。秋が終わりに差し掛かり、冬の到来を感じさせる11月上旬に使用できます。
<例文>
拝啓 晩秋の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて・・・・・・【本文】
落ち葉風に舞う折、ご自愛専一にお過ごしください。
敬具
4.3. 11月下旬の時候の挨拶
以下の3つは、11月下旬の書き出しで使える主な時候の挨拶です。
●深冷(しんれい)の候
空気がかなり冷たくなり、寒さが深まってきたという意味の「深冷」は、11月7日頃の立冬を過ぎてから、11月下旬までに使用するのが最適です。
●初霜(はつしも)の候
その名の通り、初霜が見られるくらいに寒くなってきたことを意味する挨拶です。日本各地で霜が降りるのは11月中旬〜下旬頃が多いため、その時期に使用するのが適当です。
●霜秋(そうしゅう)の候
こちらも、秋が終わって霜が降りるくらいに季節が進んだことを意味しています。立冬前後から11月下旬に使用すると良いでしょう。
<例文>
拝啓 深冷の候、貴社ますますご発展の由、大慶に存じます。
さて・・・・・・【本文】
師走に向かい何かとご多忙のことと存じますが、引き続きご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具

【関連記事】「【例文つき】ビジネスシーンで使えるお礼状の書き方や注意点を解説」
【関連記事】「【例文つき】お歳暮のお礼状とは?正しい書き方や基本マナーを紹介」
【関連記事】「業界研究まず何から始めればいい?やり方と見るべきポイント」
【関連記事】「転職に向けた業界研究の進め方は?各業界の特徴について解説します」
【年収500万円以上の求人はこちら】
5. 【漢語調】ビジネスで使える11月の結びの挨拶
上記の例文でも一部紹介した通り、本文のあとには季節の話題に再び触れた結びの挨拶を添えます。ただし、書き出しで使用したフレーズとはかぶらないように注意しましょう。
ここでは、ビジネスシーンで使える11月の結びの挨拶を、上旬・下旬に分けて紹介します。
5.1. 11月上旬の結びの挨拶
11月上旬に使える漢語調の結びの挨拶には、以下のようなものがあります。
- 向寒のみぎり、何卒お身体おいといください。
- 夜寒の折、ご自愛専一にご精励ください。
- 小春日和の折、貴社のさらなるご繁栄をお祈り申し上げます。
5.2. 11月下旬の結びの挨拶
11月下旬に使える漢語調の結びの挨拶には、以下のようなものがあります。
- 深冷の候、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
- 木枯らしのみぎり、皆様お風邪など召されぬようご自愛ください。
- 晩秋の折、皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
【関連記事】「11月といえば何?行事・食べ物・花など会話のネタになる風物詩を紹介」
【関連記事】「業界を変える転職を成功させる3つのポイント!職種を変えるケースも解説」
【関連記事】「IT業界とは?5つの業界別に職種やメリット・向いている人を紹介」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】
6. 【和語調】プライベートで使える11月の時候の挨拶
ここからは親しい方へ向けた手紙で使用できる、和語調の時候の挨拶をいくつか紹介します。わかりやすくカジュアルなキーワードを取り入れることで、より親しみのある挨拶になります。
6.1. 11月全般の時候の挨拶
和語調における11月全般に使える時候の挨拶には、以下のようなものがあります。
- 枯葉舞い散る季節となりました
- ゆく秋に寂しさを覚える今日この頃
- 冷気強まる晩秋を迎え
- 吹き来る木枯らしに、冬の到来を実感する今日この頃です
<例文>
拝啓 枯葉舞い散る季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて・・・・・・【本文】
秋晴のすがすがしい日々、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。
敬具
6.2. 11月上旬~中旬の時候の挨拶
和語調における11月上旬~中旬の時候の挨拶には、以下のようなものがあります。
- 暦の上ではいよいよ立冬を迎えました
- 朝夕はめっきり寒くなり、初霜の便りが届く頃となりました
- 紅葉も過ぎ、冬が駆け足で近づいてきました
- 暦は立冬を過ぎましたが、おだやかな小春日和が続いております
<例文>
拝啓 立冬を過ぎ、日ごとに寒さが深まってまいりました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて・・・・・・【本文】
朝晩の冷え込みも厳しくなる時節、お体には十分お気をつけください。
敬具
6.3. 11月下旬の時候の挨拶
和語調における11月下旬の時候の挨拶には、以下のようなものがあります。
- 紅葉は見頃を過ぎ、霜枯れの季節となりました
- 吹き来る木枯らしに、冬の到来を実感する今日この頃
- 吐く息は白くなり、朝夕の冷え込みが身に染みる時節
- 日脚もめっきり短くなり、ひだまりの恋しい季節となりました
<例文>
拝啓 紅葉は見頃を過ぎ、霜枯れの季節となりました。その後、お変わりございませんか。
さて・・・・・・【本文】
本格的な寒さに向かう時節、体調を崩されませぬようご自愛ください。
敬具

【関連記事】「【例文】ビジネスメールの書き出しはどう書く?マナーや例文をパターン別に紹介」
【関連記事】「面接日程メール返信の基本|ケース別例文10選とNG行為」
【年収600万円以上の求人はこちら】
7. 【和語調】プライベートで使える11月の結びの挨拶
ここからは11月上旬と下旬、それぞれの時期にプライベートで使える結びの挨拶をいくつか紹介します。
7.1. 11月上旬の結び挨拶
11月上旬に使われる結びの挨拶は、以下のような文言が考えられます。
- 朝晩の冷え込みは日ごとに増してまいります。お体十分においといください。
- 今年はいつにも増して寒い冬となりそうです。健康にはくれぐれもご留意ください。
- 立冬を過ぎ、いよいよ本格的な冬に向かいます。お体にはどうかお気をつけください。
- 冬支度に忙しい時期とは存じますが、またお会いできるのを楽しみにしております。
7.2. 11月下旬の結びの挨拶
11月下旬に使われる結びの挨拶は、以下のような文言が考えられます。
- 夜の冷え込みが一段と厳しくなっています。ご無理はせず、温かくしてお過ごしください。
- 暦の上ではもう冬ですね。健康には十分留意してお過ごしください。
- 年末に向かい何かとご多忙のことと拝察いたしますが、お体には十分お気をつけください。
- 本格的な寒さに向かう時節、お風邪など召されませんよう気をつけてお過ごしください。
- 今年もいよいよ残り少なくなってまいりました。悔いのない一年になるよう、お互い励みましょう。

【関連記事】「【例文集】ビジネスメールの締めの言葉はどう書く?シーン別、季節別の例文を紹介!」
【関連記事】「【例文】謝罪・お詫びメールとは?社内外別に書き出しから締めの言葉まで解説」
【関連記事】「飲み会お礼メールの正しいマナーとは?上司や取引先宛ての例文を紹介」
【年収700万円以上の求人はこちら】
8. 11月の挨拶文でよく用いられるキーワード
季節の行事や暦上のキーワードを知っておくと、時候の挨拶を考える際にとても役立ちます。ここでは11月の主な行事や、11月という季節に関連したキーワードをいくつかピックアップしました。
8.1. 行事や暦関連のキーワード
11月の主な行事と暦関連のキーワードは以下の通りです。
11月の主な行事
- 七五三(11月15日):子供の成長を祝う行事です。数えで3歳、5歳、7歳の年に神社へ参拝します。
- 酉の市(11月の酉の日):毎年11月の酉の日に開催されるお祭りです。開運招福や商売繁盛を願う熊手が有名です。
11月の節気
- 立冬(11月8日頃):冬が始まる日を指します。木枯らしが吹き、冬の気配を感じ始める時期です。
- 小雪(11月23日頃):雪が降り始める日を指します。積もるほどではありませんが、北国では雪が舞い始める時期です。
8.2. 天候や風物詩に関するキーワード
11月の天候や風物詩に関連したキーワードは以下の通りです。
- 銀杏(いちょう):10月〜11月にかけて黄色く色づく木です。街路樹として植えられていることも多く、木の実は料理にも使われます。
- シクラメン:10月〜3月が開花期であり、冬の代表的な花の一つです。
- 木枯らし:10月中旬から11月にかけて吹く、冷たい北風です。毎秒8メートル以上と定義されています。
- 小春日和:10月下旬から12月にかけて、寒い時期にもかかわらず春のように暖かい日を指します。
- 野分(のわき):秋の終わりから初冬にかけて、野をかき分けて吹くような強い風です。
- 時雨(しぐれ):秋から冬にかけて、降ったり止んだりを繰り返す雨のことです。
- ししゃも:子持ちで脂ものって旬をむかえる季節です。
- 白菜/ほうれん草/ブロッコリー/キウイフルーツ/ざくろ:これらの野菜や果物は11月に旬を迎え、冬の食卓を彩ります。

【関連記事】「初盆・新盆の法要に参列する際のマナーとは?香典や服装などの注意点」
【関連記事】「冬転職のススメ!「冬の転職」を成功させるポイントをチェックしよう」
【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」
メーカーへの転職希望者はこちら
9. まとめ
立冬を迎える11月は、季節が秋から冬に移り変わる時期です。雪が降ったり氷が張ったりする地域は限られますが、時候の挨拶では冬を感じさせる言葉が多く用いられます。
手紙を書く際は、送る相手によって漢語調と和語調をうまく使い分けながら、心のこもった内容にすることが大切です。ここで紹介した例文を参考にして、気遣いや思いやりが伝わる挨拶を添えましょう。

10. 他の月の時候の挨拶
11月以外の時候の挨拶は、下記の記事でご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。
| 各月の時候の挨拶 | ||
|---|---|---|
| 1月 > | 2月 > | 3月 > |
| 4月 > | 5月 > | 6月 > |
| 7月 > | 8月 > | 9月 > |
| 10月 > | 11月 > | 12月 > |
履歴書・職務経歴書などの書類作成は
キャリアアドバイザーがサポートします
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける
【卒業年早見表はこちら】

