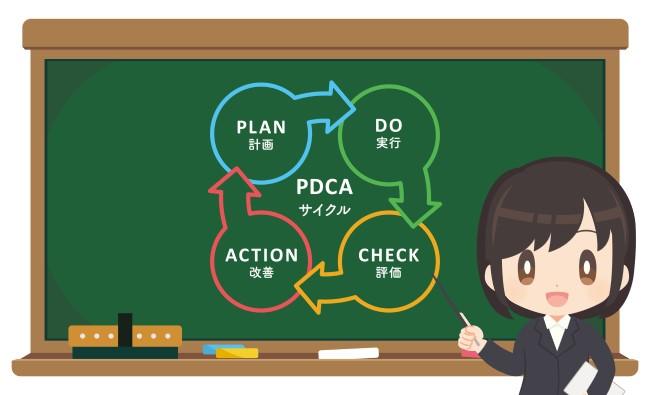企業やチームの拡大成長を目指すうえで役立つのが「KPIツリー」といわれるものです。KPIツリーは、目標に対して必要なアクションを明確化し、チームの方向性を整える効果があります。
今回は、多くの企業で活用されているKPIツリーについて解説していきます。
(※もしかしたら仕事頑張りすぎ!? ... そんな方におすすめ『仕事どうする!? 診断』)
【関連記事】「【マーケティングとは】マーケティングの3要素と4つの手順、成功例を紹介」
1.KPIツリーとは?
KPIツリーとは、KGI(Key Goal Indicator)とよばれる「重要目的達成指数」を頂点に置き、達成に必要な要素であるKPIをツリーの枝葉のように段階的に設置した図のことです。
枝葉の末端にあるKPIから達成していくことで、最終目標のKGI実現を叶えます。
実際に図形化する際には基本的に左側に頂点となるKGIを置き、左から右に向かってKPIを広げていきます。
1.1.まずはKPI・KGIについて知ろう
KPI(Key Performance Indicator)とは「重要業績評価指標」を意味する言葉であり、設定した目標に対する進捗状況を測定するための重要な指標です。
例えば、営業であれば、売上目標の達成率や新規顧客獲得数がKPIとなり得ます。
一方、KGI(Key Goal Indicator)は「重要目的達成指標」を意味する言葉であり、企業や組織にとって最終目的となる数値です。
つまり、KGIは大局的な目的を示す指標であり、KPIはそれを具現化し、具体的な成果や進捗を計測するための指標であると言えます。
1.2.KPIツリーを作る目的や意味
KPIツリーは、掲げた目標へたどり着くための道しるべです。KGI達成のためにどのような要素を満たす必要があるのか、自社に足りないものは何か、日々どのような成果を積み重ねる必要があるかなど、必要なアクションを分析できます。
各KPIの関連性も可視化されるため、KGI達成までの過程で迷うこともなくなります。視覚から全体像の理解が得やすいため、チームメンバーとの共通認識も持ちやすくなるでしょう。
【関連記事】「【コンバージョンとは】コンバージョンをビジネスで活用するさまざまな方法」
【関連記事】「【重要指標MAUとは?】売上改善に活かせる計算方法と注意点」
キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。
2.KPIツリー作成には、KGIが重要
KPIツリーの作成では、適切なKGIの設定が重要です。
KGIにおいては、企業やチームが目指す最終ゴールを定量的な表現で設定する必要があります。数値化が不可能な、また客観的にモニタリングできないようなKGIでは何をもって達成とされるのかが不明瞭であり、KPIの設定も曖昧になりかねません。
KPIツリーはKGIを起因とするため、KGIの設定を見誤ればKPIも意味をなさなくなってしまいます。何をKGIとして設定するかで結果の明暗が分かれることを認識し、最適なKGIを設定しましょう。
【関連記事】「【ビジネス用語一覧】よく使う用語集100選|意味を例文付きで紹介」
【関連記事】「【エンゲージメントとは】SNSや企業活動で重視される理由」
【関連記事】「【データマイニングとは】注目される理由、得られる知見や業界別の応用例などを解説」
【関連記事】「OODA(ウーダ)ループとは?求められる背景やPDCAとの違いについても解説」
3.KPIツリー作成のメリット
では、KPIツリーを作成することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。主な3つのポイントを紹介します。
3.1.指標・目標を明確化できる
一つのKGIを実現するためには多数のKPIを達成しなければなりません。それらのKPIをツリー形式にまとめる過程を経ることで、指標・目標を明確化することができます。各KPIの相互関係も一目瞭然な形で可視化できるため、企業・チーム内で共通認識を齟齬なく持つことが可能となります。
3.2.ボトルネックの早期発見が可能
KPIツリーはKPI達成を妨げるボトルネックの早期発見に有効です。
ボトルネックの発見が遅れる原因は、適切な現状把握や課題認識が不足していることにあると考えられます。KPIツリーで必要なアクションを細分化しわかりやすく可視化することで、素早くボトルネックを発見できるようになり、PDCAも効率よく回せるようになるでしょう。
3.3.具体的なデータが可視化される
KPIツリーでは、最終目標達成までのタスクが細分化されます。それによりピンポイントで精度の高い数値が入手できたり、適切な効果測定が実施できたりします。また、KGI達成に向けたKPIの道筋に見誤りがないかを定期的に振り返り、改善にむすびつけることもできます。
【関連記事】「インプレッション(インプレ)とは? 意味や類似語との違い、関連する指標も解説」
【関連記事】「【ターゲティングとは】ターゲティングの手順やメリットなどについて解説」
【関連記事】「【セグメントとは】セグメントに分ける目的、分けた後にすべき事」
【関連記事】「AIDMA(アイドマ) とAISAS(アイサス)、その他の購入行動モデル含め徹底解説」
【関連記事】「【クッキー(Cookie)とは】利用するメリットとプライバシー保護上の問題点」
4.KPIツリー作成のデメリット
KPIツリーの作成にはメリットが多くありますが、注意点やデメリットもあります。
以下では、考えられるデメリットを紹介します。
KPIツリーを有効に活用して、業務の効率や生産性を上げるために参考にしてください。
4.1.他に優先すべき事があるのに優先順位を見誤ってしまう
前述の通りKPIツリーは明確な目標を提示しているため、目標が分かりやすく共有しやすいというメリットがあります。
しかし一方で、目標の達成を意識しすぎて優先順位を見誤ってしまう可能性があります。
例えば、本来なら顧客を優先に考えるべきサービスや商品であるのにも関わらず、「目標を達成するためにはどうしたらいいか?」といった考えが先行しやすくなるので注意しましょう。
4.2.表現しきれていない要素や問題点を見落としやすい
目標を達成するために必要な要素が一目でわかるので、KPIツリーに沿って行動することで業務の効率や生産性が上がります。
しかし、KPIに表現しきれていない要素や問題点を見落としやすくなるということも意識しておく必要があります。
KPIツリーに頼りすぎて考えることを疎かにしてしまわないよう、社員一人一人が考えて行動する、責任を持って業務にあたるという意識が重要です。
【関連記事】「【インバウンドマーケティングとは】企業の成功事例や手法を徹底解説!」
【関連記事】「【ペルソナとは】ターゲットとの違いやペルソナ設定のメリット・設定方法」
【関連記事】「【D2Cとは】D2Cのマーケティング手法と具体例、メリットとデメリット」
【関連記事】「【マネタイズとは?】意味や使い方、4つのマネタイズ手法を解説」
5.KPIツリー作成のポイント
上記で紹介したメリットは、KPIツリーの作成を適切な形で行うことで初めて享受できるものです。
以下の4つのポイントを踏まえたうえでKPIツリーを作成しましょう。
5.1.四則演算で成り立っている
すべてのKPIは、四則演算(足す、引く、掛ける、割る)を用いて作成されます。たとえば「顧客単価」というKPIの直下にあるKPIは、「商品単価+購入金額」、「オンラインショップアクセス数」というKPIの直下にあるKPIは、「SNS流入+メルマガ流入+新聞広告流入+Web広告流入+自然検索流入」となります。
上記のような論理が成立していないと、KPIツリーの構造に矛盾が生じてしまいます。
これらはエクセルシートの簡単な関数でも行えるため、日々の管理に活用していくのがおすすめです。
5.2.単位に注意する
ここで注意したいのが、ツリーで結びついているKPI同士は同じ単位でなければならないという点です。前項の例でいくと、「顧客単価」の単位は「円」なので、その直下の商品単価や購入金額の単位も円、「オンラインショップアクセス数」の単位は「PV」のため、直下のSNS流入、メルマガ流入、新聞広告流入、Web広告流入、自然検索流入もPVで見ることになります。この単位が統一されていないと、KPIツリーとしての論理は成立しなくなります。
5.3.遅行指標(結果指標)と先行指標を理解しておく
遅行指標(結果指標)とは時差で発生する指標、先行指標とは遅行に先駆けて現れる指標を指しています。
KPIツリーでは、ツリーの上流に近づくほどに遅行指標の傾向が強まります。それは、下流に位置するKPIの成果の積み重ねがツリー上流に位置するKPIやKGIの達成に必要なためです。KPIツリーの作成時は、KGIに近い上流のKPIであるほど遅行指標、KGIから枝分かれし下流のKPIほど先行指標に移行していくという法則が成立しているかを確認しましょう。
5.4.同じ要素を入れないようにする
KPIツリーでは、原則的に同等または類似の要素を含まないようにします。それらの要素があると効率や生産性の低下を招くためです。ケースによってはイレギュラーな手法が採用されることもありますが、効率的にKPIを達成し、その先のKGIを実現するために覚えておきましょう。
【関連記事】「【ハッシュタグとは】マーケティングでの活用法やメリット、分析ツールを紹介」
【関連記事】「【オウンドメディアとは】注目される理由と運営するメリット・デメリット」
【関連記事】「【強調スニペットとは】採用された際のメリットと採用されやすい条件」
【関連記事】「【SWOT分析とは】分析のポイント、応用方法や"町中華"での分析例も解説」
6.KPIツリーの作り方
KPIツリーは大まかに以下の3つの工程で作成可能です。ここまで解説したポイントを忘れずに反映させるようにしましょう。
6.1.KGIを設定する
KGIの具体例としては、売上高や業界シェア率、利益率などが挙げられます。
6.2.KGIを起点とし、分解(細分化)していく
続いて、KGI達成のためにどのような成果が必要なのかを洗い出します。大まかな要素を分解し、その後最小レベルまで細分化していきましょう。それら一つひとつの要素がKPIとなります。KGIを起点とし、ツリーの枝葉として各KPIを配置していきます。
6.3.ロジックツリーにより可視化する
ロジックツリーを使用して、わかりやすく可視化することも大切です。
ロジックツリーとは手順やプロセスを階層的に整理し樹形図化したもので、KPIツリーの可視化には欠かせません。
文字だけでなく、どの段階にどういった目標があるのかを可視化することで、目標達成までのイメージが湧きやすくなります。
数字の管理はエクセルなどの表計算ができるソフトを、項目の洗い出しや可視化にはパワーポイントなど資料作成ができるソフトを使用するのがおすすめです。
【関連記事】「【アフィリエイトとは】アフェリエイト広告のメリットと問題点を解説」
【関連記事】「【GAFAとは】巨大IT企業4社がプラットフォーマーとして特別視される理由」
【関連記事】「【ブルーオーシャン戦略とは】見つけ方から戦略のフレームワークまで」
【関連記事】「【キャズム理論とは】キャズムが生まれる理由と"キャズム超え"のための戦略」
7.KPIツリーの具体例
例えば飲食店のKPIツリーであれば、ツリーの頂点であるKGIは売上であることが多いでしょう。
そのKGIを達成するためのKPIには、客単価や客数、さらにそこから新規とリピーター、予約ありと予約なしなどと枝分かれさせていきます。
もしも、ECサイトであればKGIは売上になることが多いため、そこからサイト訪問数、購入率、顧客単価などを枝分かれさせます。
ただし、開業して間もない企業の場合は、KGIが同じ売上であったとしても、「売上〇〇円」など具体的な数字を設定するのは難しいでしょう。そのため、「前期より売上高〇%アップ」といったKGIがふさわしいと言えます。
このように、KPIツリーに用いるKPIやKGIの項目や数値は、企業の種類や規模によって大きく異なります。
8.まとめ
効率と成果の双方をバランスよく得るうえで、KPIツリーは大きな役割を果たすツールです。目標達成までの工程を分析し図形化することでチームの理解を促し、業務管理や状況把握もスムーズとなります。
一度で過不足なく完璧なKPIツリーを作成することはむずかしいため、はじめは軌道修正を加えながら、KPIツリーの仕組みや扱いに慣れることを目指しましょう。また、いままでにない新たな発見や挑戦につながるヒントを得るためにも、チームメンバーの多角的な視点を取り入れてKPIツリーを作成することにもトライしてみましょう。