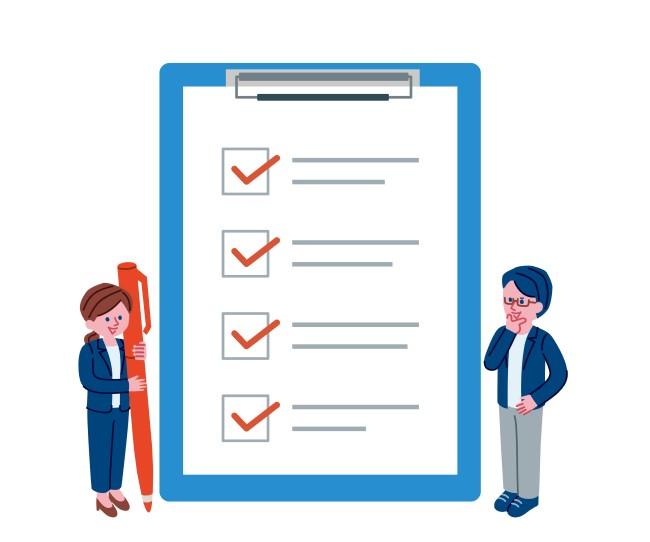書類選考に落ちる主な理由として、書類の不備や自己PRの不足、求人のミスマッチなどが挙げられます。書類選考を通過するためには、完成度の高い応募書類を作成したうえで、企業がどんな人材を求めているのかをしっかり研究することが大切です。
この記事では、書類選考で落ちてしまう主な8つの理由を挙げ、それを避けるために改善すべき具体的なポイントを紹介します。自分の強みをしっかりアピールし、面接など次のステップに進むためのコツをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】「転職のタイミングは何月がベスト?年齢・状況別の見極めポイントも解説」
【関連記事】「【例文あり】面接日程メールの返信マナー|調整が必要な場合の書き方も解説」
【関連記事】「面接結果が遅いと不採用?来ない場合の対処法について解説します」
「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 書類選考で落ちる割合はどれくらい?
マイナビ転職エージェントの調査によると、書類選考の通過率は約30%です。
言い換えると、約70%の割合、つまり10人中7人が一次面接に進めず書類選考で落ちることになります。このことから、書類選考に通過するのは、多くの人が思っているほど容易ではないことがわかります。
さらに、人気のある求人であればあるほど、書類審査は厳しいものになることも理解しておかなければなりません。
なお上記の調査では、一次面接に合格し最終面接に進む確率も約30%で、その中で内定を獲得する確率は50%となっています。
つまり、就職・転職活動において、書類選考と一次面接突破が最もハードルの高いフェーズであると言えるでしょう。
書類選考の通過率については、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】「転職エージェントで内定率、書類選考・面接通過率がアップする秘密は?」
【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉の相場と年収アップの交渉をするコツをご紹介」
【テーマ別】平均年収ランキング
「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。
【マイナビ転職エージェントのご利用方法はこちら】
2. 書類選考で落ちる主な8つの理由
書類選考で落ちる場合、何らかの要因があります。主に考えられる8つの理由を紹介します。
2.1. 書類に不備がある
履歴書や職務経歴書に不備があると、書類選考で落ちてしまう場合があります。
具体的には、必要な記入欄が埋められていない、誤字脱字がある、会社から指示された記載方法が反映されていない、などの不備が考えられます。
適切なルールに沿った応募書類が作成できていないと、「基本マナーがなっていない」「注意力散漫」といったマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。
【関連記事】「【決定版】履歴書の書き方マニュアル|テンプレートのダウンロード」
【関連記事】「転職活動で職務経歴書は必要か?役割を知って転職を成功に導く!」
【関連記事】「【学歴・職歴の正しい書き方】転職の際の書類作成の基本的なルールや注意点」
2.2. 自己PRが不十分
いくら不備のない応募書類を作成できたとしても、自己PRの要素が足りないと採用担当者の心に残りにくく、書類選考で落とされてしまう可能性があります。
書類選考では、応募書類という限られた情報のみで仕事への適性や活躍の可能性を判断されてしまうため、自分の強みや得意なこと、これまでの経験を通じて身につけたスキルなどを適切に記載し、他の応募者との差別化を図る意識が必要なのです。
【関連記事】「【自己PR完全ガイド】例文集・書き方や面接での伝え方」
【関連記事】「【転職】自己PRの書き方とテンプレート集!職業別の例文も紹介」
【関連記事】「【例文あり】職務経歴書の自己PRで効果的にアピールするためのポイントを紹介」
2.3. 抽象的で具体性に欠ける
例えば、「私は責任感があり、さまざまな努力をしてきました」という表現は一見ポジティブに感じられますが、「どんな場面で責任感を発揮したのか」「どういう努力をして結果はどうなったのか」などが書かれていないと、読み手にイメージが伝わりません。
誰にでも当てはまるような事柄や、説得力のない抽象的な表現は避け、自分が実際に体験したエピソードを具体的に記載することが大切です。
【関連記事】「自己PRで長所をアピールする際のポイントと例文」
2.4. 「入社したい」という熱意が伝わらない
まったく同じ年齢・経歴の応募者がいたとした場合、採用担当者が採否の決め手とするのは「どれだけ自社に入社したいと思っているか」という熱意であることが多いです。
採用担当者も一人の人間である以上、応募者の熱い思いに心動かされることも少なくないと理解しておく必要があります。
【関連記事】「【例文付き】志望動機は書き出しが重要!好印象を与える「書き出し」のコツとは」
【関連記事】「転職の志望動機・志望理由の書き方|ポイントや失敗例について例文を用いて解説します」
2.5. 企業が求める人物像とマッチしていない
企業が求める人物像と書類から伝わる人物像とがマッチしていない場合も、書類選考の段階で落ちる可能性があります。
「この人はうちと合わないのでは?」と書類選考の段階で採用担当者が思ってしまうと、その先の選考に進むのは難しくなります。
そのため、企業研究をしっかりと行い、企業側が求めている人物像を把握しておくことが大事です。
【関連記事】「転職の軸とは?軸となる3つの条件や考えるポイントについて解説します」
【関連記事】「「転職したいけど何がしたいかわからない」ときはどうすればいい?解決策やポイントをご紹介」
2.6. すでに他の候補者を採用してしまっている
あなたの書類を見る前に、別の応募者に内定を出してしまっていたということも考えられます。
企業が採用を急いでいたり、企業が求める人物像にぴったりの応募者がいたりすれば、あなたの書類に問題がなかったとしても書類選考で落ちることがあります。
こればかりはタイミング次第ですが、企業への応募は早いに越したことはないと言えるかもしれません。
2.7. 応募条件を満たしていなかった
企業が提示した応募条件を満たしていない場合も、書類選考で落ちる可能性が高いです。
多くの企業では、「必須条件」と「あると望ましい条件」という2種類の応募条件を設けていることが多いです。
「必須条件」に関しては入社時に最低限身につけておかなければならないスキルを指していることから、合致していなかった場合は書類選考で落とされてしまう可能性が高くなります。
「あると望ましい条件」については、その条件にマッチしている応募者がいればその人を優先的に採用するといった意味合いが強いため、必ずしもこの条件を満たす必要があるとはいえません。
企業が採用を急いでいる場合などは、「あると望ましい条件」を満たしていなくても、「必須条件」を満たしていれば採用される可能性も高いといえるでしょう。
【関連記事】「転職活動でやることは何?スケジュール例や選考を有利に進めるためのコツ」
2.8. 転職回数の多さ・離職期間(ブランク)の長さなどの懸念点がある
短期間に何回も転職を繰り返している場合、採用担当者から「適応力や忍耐力に欠けるのでは?」「またすぐに辞めてしまうのでは?」という不安を抱かれてしまう可能性があります。
また、離職期間(ブランク)が長すぎる場合も、「知識やスキルが古くなっているのでは?」「仕事へのモチベーションが下がっているのでは?」と思われてしまうことがあります。
このような懸念を払拭し、前向きな評価につなげるためには、転職の理由や離職期間をどのように過ごしたかを明確に説明することが重要です。
【関連記事】「転職のブランクは不利?面接で空白期間の理由をうまく伝える回答例を紹介」
【関連記事】「転職回数は何回から不利?「多い」と思われない書類の書き方と面接術」
【関連記事】「転職の平均回数はどれくらい?年代別の傾向から転職成功の秘訣までまとめて解説」
【関連記事】「職務経歴書の空白期間(離職期間)はどう記載する?伝え方のポイントと例文」
キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。
「マイナビ転職エージェント」のご利用方法はこちら。
3. 書類選考の際に企業はどこをみているのか
書類選考に落ちることなく先の選考に進むためには、企業視点に立った対策が重要です。書類選考において企業がチェックするポイントを知っておきましょう。
3.1. 基本情報はしっかり記載されているか
名前や生年月日、住所、電話番号などの基本情報が漏れなく記載されているかは、企業が必ずチェックするポイントの一つです。
選考における他の要素とは別に、人間性が表れる部分でもあるため、企業は欠かさずチェックしています。
記入欄を見落として空欄になっていたり、途中までしか記載されていなかったりといったことがないよう念入りにチェックしましょう。
3.2. 自社で活躍できるか人材か
企業は、自社で活躍し貢献してもらえる人材か否かを、まずは書類で見極めたいと思っています。
そのため、入社後のあなたの仕事ぶりや、既存社員とのスムーズな関係構築の可能性を見つけようとします。
仕事への熱意をアピールするだけでなく、記載事項を企業理念や社風に沿った内容にすることが重要となります。
3.3. スキルや経験がマッチしているか
自社で求める経験やスキルを持ち合わせているかどうかもチェックされる点です。
職務経歴書では、社名や職種の羅列だけでなく、携わった業務や成果、培ったスキルなど、具体的な内容が記載されているかがポイントとなります。
3.4. 自社で長期的に働いてくれるか
できる限り長く働いてくれる人を採用したいと考える企業は多いです。それを見極めるにあたっては、前職の勤続年数や退職理由を見る場合があります。
また、たとえ勤続年数が短かったとしても、退職理由が未来につながるポジティブなものであれば、印象が変わってきます。
【関連記事】「長所一覧16選と伝え方例文付き!長所の見つけ方4選やPRのコツも」
【関連記事】「【短所一覧・言い換え例】面接の印象がアップする短所・弱みの伝え方」
【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】
【10~12月限定】
年内の転職を目指す!「秋の無料個別相談会」
4. 書類選考の通過率を上げる8つのポイント
ここからは、書類選考の通過率を上げるためのポイントを8つ紹介します。
今まで書類選考になかなか通らずに辛い思いをしてきた方は、以下のポイントを意識した応募書類の作成を心がけてみましょう。
4.1. 自己分析・企業研究を行う
書類選考に落ちる人の多くは、自分や企業への理解が浅かったり、それをうまく言語化できていなかったりする傾向があります。説得力のある応募書類にするには、自己分析と企業研究をしっかり行うことが大切です。
なお、自己分析は一度きりではなく、環境や気持ちの変化に合わせて複数回行うのがおすすめです。採用担当者から「この人に会ってみたい」と思われるには何が必要なのかを考え、じっくりと自分を見つめ直しましょう。
企業研究は、求人情報や企業のホームページを見るだけではなく、説明会やイベントがあれば積極的に参加し、リアルな情報を集めることが重要です。
それが難しい場合は、同業他社の友人知人に話を聞きイメージを膨らませられると良いでしょう。
また、転職エージェントの利用もおすすめします。
「マイナビ転職エージェント」なら、業界や職種に特化した専任のキャリアアドバイザーがおり、企業の社風や雰囲気、業界の動向など細かな情報を教えてもらえます。
「マイナビ転職エージェント」のご利用方法はこちらとなります。
【関連記事】「企業研究のやり方ガイド!効率よく企業を理解するための5ステップ」
【関連記事】「転職活動に欠かせない自己分析とは?メリットや簡単なやり方を解説」
4.2. 今までのキャリアを整理する
自己分析の精度を高めるため、キャリアの棚卸しをしましょう。
キャリアの棚卸しをすると、経歴やスキルの整理だけでなく、自らの強みや他者から評価されたこと、実現したかった目標などが鮮明になり、応募書類に記載する一つひとつの言葉に深みと説得力が出てきます。
キャリアの棚卸しは、書類選考に落ちる要因の一つである「求人のミスマッチ」への対策にもなるでしょう。
【関連記事】「自分の市場価値とは?市場価値を決める要素や、価値の高め方について解説します」
4.3. 企業に合った自己PRを作成する
応募先企業や募集職種に即した自己PRを作成しましょう。
他社への応募時に使った自己PRを使い回す人もいますが、採用担当者が読めば「どの企業にも同じことを言っているのだろう」ということがすぐに分かってしまいます。
例えば、チームワークを求める企業には以下のような自己PRが適しています。
4.3.1. 自己PR例
前職では長期プロジェクトに参加していたこともあり、協調性やチームワークを大切にしていました。
その際に意識していたポイントは、メンバー同士の密なコミュニケーションや、メンバーの行動や心情に合わせて今自分が取るべき最適なアクションを考えることでした。
その結果、「○○さんのおかげで動きやすくなった」と声を掛けてもらえる機会があり、良好な信頼関係も構築できました。
貴社での業務においても、周囲の方との関係性を大切にしながら、貢献できる人材になれるよう努めて参ります。
企業が求めるものに即した自己PRを作成するためには、企業がどのような人材を求めているかを適切に理解する必要があるため、企業研究をしっかりと行いましょう。
4.4. 具体例を用いて説明する
具体的なエピソードを盛り込むことで、書類選考に合格する確率がアップする可能性があります。
例えば「行動力」をアピールしたい場合は、以下のようなエピソードを添えると良いでしょう。
4.4.1. エピソード例
私の長所は、問題解決に向けた行動力です。前職では当初契約社員で雇用されていましたが、長年見過ごされてきた問題点について社長に改善策を提案しました。
その結果、私のやりたいように進めて良いと認めてもらったためそれを実践に移し、さらに次月からは正社員登用と部署の責任者への抜擢が決定しました。
このような具体例を示すことで、自己PRの説得力が格段に上がります。
採用担当者により具体的なイメージを持ってもらえるような内容を意識しましょう。
4.5. 誤字脱字や日本語のチェックをする
誤字脱字がないか、正しい日本語が使えているかという点は、書類選考に通過するための基本です。
自分の中にある正解や常識には誤りがある場合も考えられるため、固定観念を取り払い、慎重にチェックしましょう。
時間を置いてダブルチェックすると、見落としのリスクも軽減されます。
4.6. 第三者の意見を聞く
書類選考の通過率アップには第三者の意見を参考にすることも有効な方法です。
異なる経験や価値観を持つ第三者の意見からは、自分にはない気づきを得られることがあります。
「もっとこういう言い方が良いんじゃないか」「ここはちょっとわかりにくいかも」など、率直な意見を取り入れると、より完成度の高い応募書類を作成できるでしょう。
4.7. 合否に関わらずPDCAを回す
理想の企業で働くためには、書類選考の合否に関わらずPDCAを回し続けることが大切です。
PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)からなる、ビジネスシーンで多用されるフレームワークです。
転職活動においても、書類審査に合格した会社からは何が評価されたのか、今後応用できる点はあるか、落ちた企業から見て自分の書類はなにがマイナスポイントだったのか、改善点はどこにあるか、といった点を理解し改善を続けることで、書類の精度は向上します。
4.8. 転職エージェントに推薦状を送ってもらう
書類選考の通過率のさらなるアップを目指したい場合は、転職エージェントに推薦状を送ってもらう方法が有効です。
転職エージェントの推薦状とは、転職エージェントから応募先企業に対して、応募者の紹介理由や人柄、強みなどを伝えるためのもので、履歴書や職務経歴書に添えて提出するのが一般的です。
「信頼できる転職エージェントから推薦された人材であれば直接会ってみたい」と考える企業も一定数あるため、書類選考通過の確率アップが目指せます。
転職を考え始めたら、
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
【卒業年早見表はこちら】
5. 書類選考でよくある疑問
ここでは、書類選考においてよくある疑問とその答えを解説します。転職時の書類選考について、また結果に対する返信の必要性も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
5.1. 書類選考には何日かかる?
書類選考の期間は一般的に7日から10日程度が目安とされていますが、状況によってはそれ以上かかることもあります。
例えば、応募者の数が非常に多い場合は、1人ひとりの書類を確認するために時間がかかります。また、担当者が不在となり選考の進行が一時的に止まったことで、結果の通知に遅れが生じることも考えられます。
5.2. 合否の連絡が来ないときは不合格?
通常の書類選考では、「○日頃までに結果を郵送します」「結果は1週間以内を目途にメールにてご連絡します」といった案内があるのが一般的です。しかし、先述したようにやむを得ない事情で遅れが生じ、なかなか合否の連絡が来ないこともあります。
もしも、期日を過ぎても連絡が無い場合は、以下のような内容で採用担当者にメールで確認してみるのも一つの方法です。
件名:書類選考結果のご確認について
株式会社○○
人事部 □□様
お世話になっております。
○○職に応募させていただきました、△△と申します。
このたびはお忙しい中、書類選考にご対応いただき誠にありがとうございます。先日、履歴書および職務経歴書を送付させていただきましたが、選考状況はいかがでしょうか。
催促する形となり誠に申し訳ございませんが、いつ頃ご連絡をいただけるかの目安をお伺いできれば大変ありがたく存じます。もし、何か追加でご提供すべき情報や資料がございましたら、どうぞお知らせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
△△ △△(氏名)
電話番号:XXXX-XXXX-XXXX
メールアドレス:
なお、「連絡は合格者のみ」という条件があるケースで、2~3週間経っても連絡がない場合は不採用の可能性が高くなります。
5.3. 転職は書類選考でほぼ内定が決まる?
転職においては、前職の経験やスキルが重要視されることが多いため、「書類選考だけで、ほぼ内定が決まる」という噂を耳にしたことがある方もいるでしょう。
確かに、中途採用者は即戦力として期待される存在であり、企業が求める職務経歴があれば採用確率はアップすると考えられます。
しかし、業務に関する知識の深さや仕事に対する気持ち、個人の人柄などは、書類選考だけでは判断できません。一旦採用した人材は簡単に解雇できないことを考えると、書類選考のみで合否を判断するのは大きなリスクを伴います。
そういった理由から、転職の際も書類選考のみで内定が決まる可能性は低いと言えます。
5.4. 結果の連絡に返信は必要?
近年、書類選考の結果はメールで送信されてくることも多く、返信するべきか迷う方も多いでしょう。
基本的に、通過の連絡をもらった場合は、簡単なお礼と次回の面接に参加する旨を連絡しておくと、ていねいな印象を与えられます。
一方、「不採用の連絡」「"返信不要"という記載がある」「事務的な一斉送信メール」といった場合、お礼の返信は不要です。
【関連記事】「【例文あり】面接日程メールの返信マナー|調整が必要な場合の書き方も解説」
【関連記事】「面接結果が遅いと不採用?来ない場合の対処法について解説します」
【関連記事】「採用(内定)メールの返信はどう書く?受諾・保留・辞退のケース別例文とコツ」
6. まとめ
書類選考に落ちたとしても、決して悲観する必要はありません。この記事の内容を実践することで、あなたの魅力や能力を認めてくれる企業ときっと出会えるはずです。
履歴書や職務経歴書の文章がうまく書けないという方も、自己分析や過去の書類選考の振り返りを行えば、採用担当者に伝わる言葉が自分の中から出てくるようになります。
必要以上に人と比べず、自分なりのやり方を見つけて、前向きな気持ちで書類選考に挑んでいきましょう。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける
【求人をお探しの方はこちら】