試用期間とは、新入社員の適性を判断するために設定された期間のことです。本採用をする前に試用期間を設けている企業も多くあります。この記事では、「試用期間とはどういうものなのか」「試用期間中の給与や社会保険はどうなるのか」「万が一、仕事内容が合わなかった場合は退職できるのか」などの点について詳しく説明します。
関連記事【仕事辞めたい】よくある理由と会社を辞めたくなったらやるべきこと
関連記事【職務経歴書】短期離職の書き方|退職理由の伝え方や例文も紹介
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける>
1.試用期間とは
試用期間とは、企業などが新規学卒者や中途入社の社員らを雇用する際、試験的にその人材を雇用する期間のことをいいます。ここでは、試用期間の長さや試用期間を設ける目的、研修期間との違いについて解説します。
1.1.試用期間の長さ
試用期間の長さは、3~6ヶ月程度に設定している企業が多い傾向にあります。労働基準法上、試用期間の上限は定められていませんが、長すぎる試用期間は民法90条における公序良俗違反によって無効となる可能性があります。
試用期間については、雇用契約書への記載が義務付けられているわけではありません。しかし、雇用後のトラブルを防ぐためにも、企業が試用期間を設ける場合は、具体的な労働条件を雇用契約書や労働条件通知書に明記しておくことが求められます。
なお、労働者を募集する際は、試用期間について明示することが法的に義務付けられています。
1.2.試用期間を設ける目的
企業はなぜ試用期間を設けるのでしょうか。主な目的としては、以下の2点が挙げられます。
1.2.1.企業と労働者のミスマッチを防ぐため
企業側のメリットとして、履歴書、職務経歴書、適性検査、面接といった採用までの一連の流れでは把握しにくいその人の性格や能力、特性を見極められることが挙げられます。
一方、労働者側のメリットとしては、会社のホームページや求人情報からだけでは知ることができない職場の雰囲気、仕事内容などを、実際に仕事を行うことによって体感できる点が挙げられます。自分に合っている環境か、この先も仕事を続けていけるのかなどについて見極める機会が設けられるのは、大きなメリットといえます。
このように、試用期間は企業側と労働者側双方にメリットがあり、ミスマッチを防ぎやすくする目的があります。なお、試用期間はアルバイトやパート、契約社員など、正社員以外の労働者との雇用契約においても設けられる場合があります。
1.2.2.本採用後に適切な人員配置をしやすくするため
選考プロセスだけでは見えない適性を試用期間中に見極めることで、企業側は本採用後の配属や任せる業務内容を適切に判断しやすくなります。
本人の性格や能力、意向を理解した上で配属を決定すれば、適材適所が実現しやすくなり、生産性の高い組織をつくりやすくなります。
また、働く本人にとっても、自身の特性を活かせる環境で業務に従事しやすくなるメリットがあります。試用期間は、面接などではアピールしきれなかった強みを企業側に理解してもらうためにも有効な期間だとも言えるでしょう。
1.3.試用期間中に企業は何を見ている?
上述したような目的があるため、企業は採用の時点で見極められなかった適性をチェックしています。もちろん企業によって見ている点は異なりますが、たとえば以下のような点が挙げられます。
- 性格(他者への接し方、集団での振る舞い)
- 仕事における得意、不得意
- 自社の仕事に必要なスキルがあるかどうか
- 自社の文化に適応できているかどうか(仕事の進め方や同僚との関係など)
ただし、企業側も自社に適応するまである程度の時間が必要なことは分かっています。そのため、必ずしも最初からこれらすべてが完璧である必要はありません。
特に、企業との相性については能力やスキルとは異なり、実際に働いてみないとわからない部分もあるので、入社前から不安になりすぎなくても大丈夫です。
1.4.試用期間と研修期間の違い
試用期間と同じようなニュアンスでとらえられている言葉に「研修期間」と呼ばれるものがあります。しかし、試用期間と研修期間はまったく別物のため注意が必要です。
試用期間は雇用契約にかかわるものであり、その人物の能力を見極め、正式に自社の社員として迎えられるか会社側が判断するための期間です。そのため、試用期間の有無によって業務内容が左右されることは少なく、基本的に既存社員と同様の業務にあたります。
一方、研修期間は、業務に必要なスキルを身につけるための教育期間を指します。その方法は会社や配属先によって異なり、座学から入る場合もあれば、はじめからOJT(On the Job Training:職務を遂行しながら仕事を覚えること)形式で行う場合もあります。
なお、研修期間の期間についても労働基準法による定めはなく、各社に委ねられています。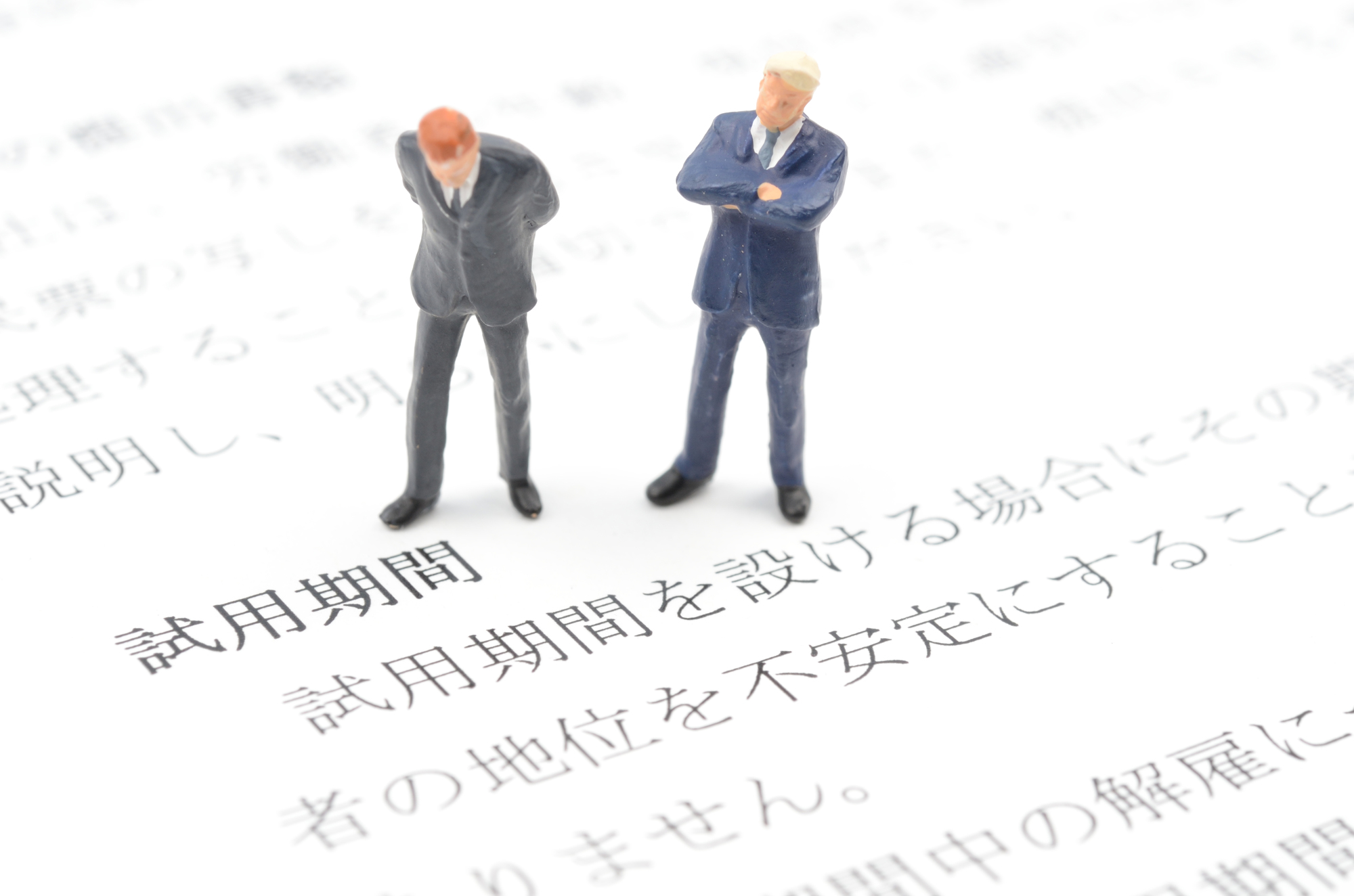
関連記事新入社員研修では何をする?研修の内容や形態などについて解説
関連記事【自分に向いてる仕事がわからない】仕事が向いてないと判断する方法を紹介
キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。
2.試用期間中の給与・社会保険・有給休暇について
試用期間中の給与や社会保険、有給休暇について、本採用されている社員との違いはあるのでしょうか。ここでは、試用期間中の給与と社会保険、有給休暇について解説します。
2.1.給与は本採用より低い場合がある
「本採用されていないうちは、正社員じゃないのでは?」と考える方がいるかもしれませんが、試用期間中であっても労働契約が成立しています。そのため、給与や残業代は支払われなくてはいけません。
ただし、企業によっては、試用期間中は本採用時の給与よりも低い金額を設定している場合があるので、就職・転職する前に雇用契約をしっかり確認しましょう。また、その場合には各都道府県の最低賃金を下回っていないか確認することも重要です。
2.2.社会保険への加入は義務付けられている
試用期間中も従業員であることに変わりはないので、各種保険(雇用保険・健康保険・労災保険・厚生年金)への加入も義務付けられています。
試用期間中だからといって、保険に加入させてもらえないといった不当な扱いを受けるような場合は、会社との話し合いが必要です。
どうしても改善されない場合は厚生労働省の各都道府県労働局など、行政に相談しましょう。
2.3.有給休暇は試用期間の開始から6ヶ月後に付与される
労働基準法によると、有給休暇が付与されるのは「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者」と定められています。
勤務先が試用期間を設けている場合は、「雇い入れの日」=「試用期間の開始日」となるため、正社員の場合、試用期間が始まってから6ヶ月後には10日間の有給休暇が付与されることになります。
万が一、「試用期間が6か月以上あるのに、その間の有給休暇取得が認められていない」「有給休暇の取得要件である継続勤務期間に、試用期間がカウントされない」といった場合は違法となります。
関連記事試用期間中の「社会保険なし」は違法?加入条件や入れない場合の対処法を解説
関連記事試用期間中の給料を詳しく解説!低いと言われる理由や注意点も
3.試用期間中における注意点
ここまでで試用期間とはどういった制度なのかが理解できたと思いますが、実際に試用期間に仕事をする際はどんなことに注意して働けば良いのでしょうか。
3.1.雇用契約書をしっかり確認しよう
まずは、雇用契約書と就業規則にしっかり目を通しましょう。雇用契約書にはあなたが雇用されるにあたっての条件が記載されているため、給与などの待遇面、福利厚生、休日などをしっかり確認する必要があります。
例えば、試用期間中は本採用時よりも賃金が低いこともあると述べましたが、給与などの労働条件が試用期間と本採用時で異なる場合、企業は労働者がそのことを確認できるよう、雇用契約書などに明記しておかなければなりません。また、賞与制度がある場合の試用期間中の扱いについても、同様に明記が必要です。
もしも、試用期間中に契約内容や就業規則と照らし合わせて疑問点が発生した場合は、ためらわずに企業側に確認しましょう。
3.2.意欲を持って仕事に取り組もう
きちんとした勤務態度で仕事を行うことが社会人としての基本であり、無断欠勤や遅刻はもってのほかです。規則はしっかり守り、真剣に仕事に取り組みましょう。出勤してからの業務遂行の流れや電話の取り方などは、その会社ごとによって異なることがありますので、率先して覚えるようにしましょう。
また、個人のスキルだけではなく、協調性やチームワークを乱していないかなども大切な要素です。上司や周囲の先輩方との接し方にも注意しましょう。初めての仕事は誰でも戸惑うことが多いものです。しかし、分からないことを素直に学ぼうとする姿勢や真面目に取り組む姿を見せ、意欲的に仕事に取り組むのはとても大切なことです。
3.3.遅刻や欠勤に気を付けよう
試用期間中に最も評価されるポイントは、仕事覚えが早いことでもミスが少ないことでもなく、人としていかに上司や先輩からの信用を得られるかです。遅刻や欠勤を繰り返したり、そのうえ上司に遅刻の連絡もしていなかったりすれば、当然信頼を得ることはできません。
社会人として決められた事柄を守ることは大前提であると認識し、「起床時間に余裕を持つ」「遅延を想定して1、2本早い電車やバスに乗る」「体調管理に気を配る」など、自分でできる最大限の努力を行いましょう。

関連記事日本の月平均残業時間は? 残業の減らし方やホワイト企業への転職方法
4.試用期間中に起こり得るトラブルとは
試用期間中も本採用時と同様に労働契約が結ばれているとはいえ、中には想定外のトラブルに遭遇するケースもあります。自分で自分の身を守れるよう、あらかじめ起こり得るトラブルについて把握し、万が一に備えるようにしましょう。
4.1.不当な理由での解雇
「試用期間中にミスをすると、即クビになってしまうのではないか」と不安に感じる方がいるかもしれません。しかし、試用期間中であっても労働契約は成立しているため、企業は「会社の雰囲気に合っていない」「業務を行う能力が不足している」といった漠然とした理由で労働者を解雇することはできません。
「経歴詐称」「無断欠勤を繰り返す」などの理由があれば別ですが、万が一正当な理由なく突然解雇を言い渡された場合は、労働基準監督署や都道府県労働局、弁護士などの専門機関に相談しましょう。
なお、試用期間の解雇においても、企業には「30日前の予告」もしくは「解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払い」が義務付けられています。ただし、例外として、試用期間開始後14日以内であれば、これらの義務は免除となります。
関連記事試用期間中でもクビになる?不当解雇になる場合や回避する方法を解説
出典都道府県労働局「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」
4.2.試用期間の延長
試用期間の長さは労働基準法などの法律で定められているわけではありません。平均3~6ヵ月以内、長くても1年以内としている会社が一般的で、万が一それを超える場合は公序良俗違反に該当する恐れがあります。
ただし、従業員の業務状況により会社側がもう少し時間をかけて見極めたいと希望する場合、試用期間が延長されるケースもあります。
試用期間の延長については、「あらかじめ雇用契約書や就業規則などに試用期間の延長が発生する可能性があることやその理由、期間について明記されていること」「延長する正当な理由があること」「延長することへの合意が成立していること」といった要件を満たしていれば違法にはなりません。要件を満たしていない場合は違法となる可能性があるため、専門機関へ相談しましょう。
4.3.試用期間後の本採用拒否
試用期間後での本採用の拒否は解雇に該当します。そのため、前述した試用期間中の解雇と同様、正当な理由なく会社側の一存で本採用を拒否し解雇することは認められません。
参考までに、過去に本採用拒否が認められた事由の一例を紹介します。
- 採用時に提示していた経歴に詐称が発覚
- 出勤率90%未満、無断欠席3回以上の出勤率不良
- 協調性を欠く言動による不適格性の明確化
- 勤務態度、接客態度不良の指導に対する改善が期待できない
上記のように、選考時には知り得なかった事実が判明した場合や、会社側が自社従業員として継続して雇用することが難しい状態であることが客観的に判断できる事由がある場合は、本採用の拒否が認められます。そうしたことに覚えがない場合は、専門機関へ相談するようにしましょう。
4.4.最低賃金以下の給与と残業代の未払い
企業は、試用期間中であっても最低賃金以上の給与を支払う義務があります。最低賃金には、地域ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業に設定されている「特定最低賃金」があり、両方に該当する場合はどちらか高い方が支払われます。
また、残業代についても、所定労働時間を超えて働いた場合は支払われます。所定労働時間は企業が定める労働時間で、所定労働時間は法定労働時間の範囲内で設定する必要があります。法定労働時間は1日8時間・週40時間となっています。
試用期間だからといって、これらの権利が制限されるわけではないので、違法な待遇を受けた場合は労働基準監督署などに相談することをおすすめします。
4.5.雇用保険や社会保険への未加入
雇用保険は、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられています。試用期間中でもこの条件を満たせば、企業は雇用保険に加入させる義務があります。
また、社会保険についても、正社員と同じように働く場合は試用期間中であっても加入が義務です。試用期間を理由に加入を拒否された場合は、違法の可能性があります。
出典厚生労働省「従業員のみなさま | 社会保険の加入条件やメリットについて」

関連記事【正社員と契約社員の違いとは】給与やボーナス、業務内容を解説
関連記事福利厚生とは? 種類の例・メリット・デメリットをわかりやすく解説
今の仕事、会社がつらい場合は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」にご相談ください。
5.試用期間中のトラブルへの対処法
事前に確認した契約内容と実際の働き方に相違があったり、明確な理由もなく解雇を宣告されてしまったりした場合、まずは社内で解決できる道を探しましょう。
それでも埒(らち)が明かない場合、社外専門機関に相談することを検討しましょう。
5.1.会社の担当窓口に相談する
まずは、直属の上司、または人事部などに担当窓口がある場合はそちらに相談しましょう。相談する際には感情的にならず、冷静な態度で事実を元にトラブル内容を伝えてください。
話の切り出しは、「労働条件について確認したいことがあります」などと伝えるのが良いでしょう。
入社面接の際に契約書に記載されていない事柄を担当者から言われていたとしても、その事柄について自分の主張を通すことは難しいでしょうから、あくまでも書類ベースでの話に徹しましょう。
5.2.社外専門機関に相談する
社内での問題解決が困難な場合、社外の専門機関に相談しましょう。
トラブルの内容によって相談する先が異なります。解雇・賃金に関しては労働基準監督署、雇用保険未加入はハローワーク、社会保険未加入は年金事務所がそれぞれ担当しています。
また、これらの機関でもトラブル解決が困難な場合は、弁護士などに相談し、労働審判や労働訴訟も検討しましょう。
ただし、社外専門機関を交えてトラブル解決を行う場合、トラブルが解決しても会社との信頼関係に傷がつく可能性もあるため、その会社に勤め続けるのが難しくなる場合もあります。社外への協力を仰ぐ際には覚悟が必要でしょう。
関連記事退職を考えている時は誰に相談すると良い? 相談する相手や注意点を紹介
関連記事パワハラで困っている人は都道府県労働局に相談を!「個別労働紛争解決制度」が使えます!
6.試用期間中でも退職できる?
実際に働いてみて、「どうしてもこの先この会社で働き続けることができない」と感じてしまうこともあると思います。
しかし、「仕事を辞めたい」と思ってもすぐに退職できるわけではありません。まずは就業規則などでその会社の退職に関する規定を確認しましょう。
労働基準法では、原則退職の申し出から2週間経過すれば労働契約を終了させることができると定められていますが、円満退職を目指すなら会社としっかり相談することが大切です。
また、試用期間中であっても、退職まで働いた分の給料は全額支給されなければいけません。
関連記事試用期間中に退職はできる?申し出る方法や退職を迷ったときの判断基準を解説
関連記事仕事辞めたいは甘え? 甘えと思われる理由と転職前にするべきこととは
7.試用期間中に退職する手順
できるだけスムーズな退職を行うために、辞める意志を固めたら下記の手順で手続きを進めましょう。
7.1.落ち着いて話ができるように直属の上司にアポイントをとる
「お話ししたいことがあります」「大切な話があります」といったように直属の上司に口頭やメールで依頼し、時間を作ってもらうようにします。アポイントメントを取ることによって、会議室などの別室で落ち着いて話すことができます。
7.2.口頭で退職したい旨を伝える
退職したい旨は必ず口頭で伝えます。なぜ退職を考えているのかを、失礼のないよう配慮しながら、感じていることをできる限り誠実に説明します。また、会社の規定に従って具体的な退職日を決めます。必要な保険や税金関連の手続きについても確認しておきましょう。
7.3.書面で退職届を提出する
会社に「退職届」のフォーマットがある場合はそちらを使用します。ない場合は、一般的な退職届のフォーマットに従い、退職理由・退職日付・所属と氏名などを書いて提出します。
7.4.残務処理や引き継ぎを滞りなく行う
試用期間中なので大きな仕事を任されることはないと思いますが、与えられた仕事については責任を持って引き継ぎを行いましょう。自分が行っていた業務についてドキュメントにまとめて上司に提出するのもよいでしょう。
関連記事新卒で会社を辞めたいと思ったら-転職のメリット・デメリットや注意点について解説
関連記事仕事を辞めさせてくれない...法律違反になる?対策や円満退社のコツ
関連記事退職の挨拶マナーは?実際に使えるスピーチやメールの例文もご紹介
8.納得されやすい退職理由と例文
試用期間中の退職理由として納得されやすい理由とはどういったものなのでしょうか。退職を考えるということは会社に対しての何かしらの不満があるのだとは思いますが、くれぐれも会社の悪口や批判になるような理由を並べないようにしましょう。試用期間中の退職理由として納得されやすい例文をご紹介します。
8.1.【職場の雰囲気や社風になじめない】
例文1
「本日まで同僚の方々にはとても親切にご指導いただき、業務を行ってまいりましたが、入社前にイメージしていた社風や職場と異なっており、自分にはどうしても合わないと感じてしまいました。
試用期間中にこのような結論を出すことになってしまい、大変申し訳ないのですが退職させていただきたいと思っております。」
例文2
「試用期間中に大変恐縮ではございますが、退職させていただきたいと思っております。入社前に会社説明会や面接などで丁寧に会社や業界のことをお聞きし、そのお話の中から自分なりに職場環境や雰囲気を思い描いていました。
しかし実際に入社してみて、抱いていたイメージと実際では異なっていることが分かりました。
熱心に指導してくださる同僚の皆さんの期待に応えたいと努力をしてまいりましたが、この先5年先、10年先まで自分が働いている姿がどうしても想像できず、このような結論に至りました。」
8.2.【求めていた仕事内容ではなかった】
例文1
「本日まで同僚の方々にはとても親切にご指導いただき、業務を行ってまいりましたが、入社前にイメージしていた仕事内容より業務が多岐にわたっていることにギャップを感じています。
自分としては多岐にわたる業務より、深く専門的に業務を行っていきたいと考えております。
試用期間中にこのような結論を出すことになってしまい、大変申し訳ないのですが退職させていただきたいと思っております。」
例文2
「誠に勝手ながら、退職させていただきたいと思っております。
今までこの職種の経験がなく初心者として入社いたしましたが、実際に業務を行ってみると想像以上に難しく感じる部分が多くありました。
試行錯誤し努力と経験を重ねていけば今より成長できるかもしれないという希望もありましたが、基礎的な部分の理解にすら追いつけていない状況で、この先長く働き続けるビジョンが描けませんでした。
このような結論となり、誠に申し訳ございません。」
8.3.【家庭の事情により続けることが難しくなった】
例文1
「本日まで同僚の方々にはとても親切にご指導いただき、業務を行ってまいりましたが、急遽(きゅうきょ)夫の転勤が決まり、このまま仕事を続けることが難しい状況となりました。
家族で話し合いを行った結果、夫が単身赴任する形ではなく、私も一緒についていくことにいたしました。
試用期間中にこのような結論を出すことになってしまい、大変申し訳ないのですが退職させていただきたいと思っております。」
例文2
「大変急なお話となり恐縮ですが、退職させていただきたいと思っております。
先日実家の父の体調が思わしくないと連絡があり、その後家族と話し合いを行った結果、今後私が実家で営む飲食店を引き継ぐことに決まりました。
入社したばかりの状況ですので自分の中で葛藤もございましたが、決断するならば試用期間中の早い段階の方が良いと思いこのような結果となりました。」
関連記事仕事を辞める主な理由は?会社を円満に退職するための伝え方を紹介
9.試用期間中の退職は転職に影響する?
試用期間中に退職したことを次の転職活動の際には伝えた方がいいのでしょうか。
9.1.前向きな退職理由であることが重要
試用期間中の退職が転職活動に影響するかどうかは次に受ける会社の考えによって異なります。
ただし、試用期間中の退職を自己申告せずに新しい会社に採用されたとしても、前職で社会保険の手続きを行っていた場合、転職先で再度加入手続きをする際に担当者が気づき、経歴詐称を疑われたり、同じ業界で転職した場合はどこかで情報が出回ったりといったリスクがあり、後々トラブルになる可能性もあります。
そういったことを防ぐためにも、試用期間で退職してしまった会社でも、正直に履歴書や職務経歴書に記載するようにしましょう。
その上で、なぜ退職したかについては面接でしっかり説明し、前向きな退職であったことをアピールするとよいでしょう。また、次の就職先を探す際は、やみくもに書類を送るのではなく、試用期間中に辞めることになったことを踏まえて、再度自己分析及び企業分析を行い、慎重に転職活動をしましょう。
9.2.転職エージェントを利用していた場合はどうなる?
試用期間中など早期に退職する場合には、事前に転職エージェントへ退職の経緯と理由を電話などで連絡した方が親切です。
退職時はもちろんのことですが、その後の再就職を有利に進める意味でも、転職エージェントとの連絡は密に行った方が良いでしょう。各業界の情報収集や応募企業の選定、面接対策など、求職者の理想の転職を叶えるべく最大限のサポートをしてくれます。
退職経緯や理由を踏まえてよりその人に合う会社とのマッチングを行ってくれるため、「こんなはずじゃなかった」というミスマッチのリスクは最小限に抑えられます。

関連記事転職エージェント利用後にすぐ退職するのは問題?会社を辞める前の注意点
関連記事転職活動でまずやることとは?流れ・準備・進め方を分かりやすく解説
転職を考え始めたら、
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
10.まとめ
いかがでしたか?試用期間は企業側だけでなく、働く側も自分に合った仕事なのか、会社環境なのかを見極めることができる期間です。実際に働きながら自分らしく働けるか、成長できる会社なのかをしっかり判断しましょう。
関連記事"転職活動に役立つメールの書き方"おすすめ記事6選! 活動フェーズごとに紹介
関連記事【例文アドバイス】面接日程メールの書き方や返信方法は?調整する際のマナー|転職成功ノウハウ
関連記事面接結果が遅いと不採用?来ない場合の対処法について解説します
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける



