一般的に、試用期間中でも社会保険の加入対象となります。そもそも試用期間とは企業が従業員を本採用する前に、能力や勤務態度を見極めるお試し期間のことです。お試しとはいえ、長期雇用を前提として設けられている期間であり、労働条件は通常の社員と変わりません。本記事では試用期間中の社会保険について、加入条件や未加入の場合の対応を中心に解説します。
【関連記事】「新卒で会社を辞めたいと思ったら-転職のメリット・デメリットや注意点について解説」
「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1 試用期間中も社会保険の加入対象になる?
結論から言うと、試用期間中の労働者は社会保険加入の対象者です。「試用期間中はまだ正式な社員ではない」と思われがちですが、企業と労働者の間では正式な労働契約が結ばれているため、一定条件を満たせば、通常の社員と同じ労働条件が適用されます。
1.1 そもそも試用期間とは
試用期間とは面接だけでは判断できない採用者の資質を、企業が見極めるために設けられている期間です。言わばお試し期間とも言えますが、基本的に長期雇用を前提としており、正式な雇用契約を結んでいるため、給与も労働契約で定められた規定通りに支払われます。
期間は通常3~6ヶ月程度であることが多く、最長でも1年以内とされています。雇用から14日以内は「解雇予告」や「解雇予告手当」の義務はないものの、企業はやむを得ない事由がない限り、従業員を解雇することはできません。
【出典】e-GOV「労働基準法 第十七条」
【出典】e-GOV「労働基準法 第二十条」
【関連記事】「会社の試用期間とは?給料や社会保険、トラブルへの対処法を解説!退職の手順も」
1.2 そもそも社会保険とは
社会保険とは相互扶助の考えに基づき、国民が怪我や病気などで生活に支障が出た際に、給付を受けられるようにするための制度です。緊急時に備える財源を確保するには、多くの国民が参加することが求められるため、条件を満たした国民は基本的に強制加入となります。
社会保険の広義では健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つを含みますが、狭義では健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを「社会保険」、労災保険・雇用保険の2つを「労働保険」と呼ぶのが一般的です。
1.3 社会保険の加入条件
正社員の多くは、基本的に社会保険の加入対象者となると考えて良いでしょう。具体的には、以下の事業所(強制適用事業所)に勤務する一般的な労働者は、強制的に社会保険加入の対象となります。
- 株式会社などの法人事業所、または国や地方公共団体
- 従業員を常時5人以上雇用している、個人の事業所(サービス業の一部、農林業、水産業、畜産業、法務など一部事業所を除く)
なお、強制適用事業所にあてはまらない事業所でも、半数以上の従業員の同意や厚生労働大臣の認可といった一定の条件を満たせば、社会保険加入は可能です。
1.4 試用期間中は社会保険に入れてもらえない?
社会保険加入の義務は、原則として「雇用契約の開始日(入社日)」から発生します。試用期間中であっても、正式な労働契約が成立している以上は、通常の社員と同様の権利が与えられています。
万が一、会社から「まだ本採用ではないから」という理由で社会保険に入れてもらえない場合は、健康保険法第208条に抵触することとなり、会社側には罰則が課せられる恐れがあります。

1.5 パート・アルバイトの社会保険加入条件
パートやアルバイトなどの短時間労働者も、以下5つの条件に当てはまる方は社会保険加入の対象者です。なお、社会保険加入の要件である特定適用事業所の被保険者数は、2024年10月から51人以上に引き下げられ、短時間労働者への社会保険適用範囲が大幅に拡大されました。
- 従業員数が常時51人以上の事業所(特定適用事業所)で勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 1ヶ月の賃金が8.8万円以上である
- 2ヵ月を超える雇用が見込まれている
- 学生ではない
【出典】厚生労働省「従業員数100人以下の事業主のみなさま」
【出典】従業員のみなさま 社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について│厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
【出典】地方厚生局「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?」
1.6 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入条件
前述したように、社会保険は狭義では「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」と「労働保険(労災保険・雇用保険)」とに区分されます。
労災保険は正社員・パート・アルバイト、日雇いなど、雇用形態を問わず全ての方が対象です。労災保険は労働し、賃金を受け取っている全ての従業員が保険給付の対象であり、基本的に被保険者という概念はありません。
一方、雇用保険は労災保険加入者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上の雇用見込みがある方が対象者となります。
【出典】厚生労働省「労働保険(労災・雇用)に 入る義務があります。」
【関連記事】「試用期間中でもクビになる?不当解雇になる場合や回避する方法を解説」
【関連記事】「試用期間中に退職はできる?申し出る方法や退職を迷ったときの判断基準を解説」

2 社会保険加入が対象外となる条件
基本的に、正社員であれば、試用期間中でもほとんどの方が社会保険加入の対象となります。ただし、雇用条件によっては対象外となるケースもあります。社会保険加入が対象外となる条件には、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 日々雇い入れられる人(1ヶ月を超えて雇用される場合は、その日から被保険者となる)
- 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人(2ヶ月を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる)
- 所在地が一定しない事業所で雇用される人
- 季節的業務(4ヶ月以内)に従事する人
- 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に雇用される人
- 国民健康保険組合の事業所に雇用される人
- 後期高齢者医療の被保険者となる人
その他にも、社会保険の種類によって対象外となる条件は異なるため、不安な場合は会社の人事担当者に確認するようにしましょう。
【関連記事】「試用期間中の給料を詳しく解説!低いと言われる理由や注意点も」

3 試用期間中の社会保険未加入は違法?違反した場合の罰則
企業には対象となる従業員を社会保険に加入させる義務があるため、手続きを怠った場合は、罰則が科せられることも考えられます。ここでは、加入義務のある企業が、社会保険に未加入だった場合の罰則について解説します。
3.1 罰則と罰金
企業は従業員を雇用した場合、5日以内に「健康保険被保険者資格取得届」を健康保険組合へ、「厚生年金保険被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所へ提出しなければなりません。これは健康保険法施行規則第24条と、厚生年金保険法施行規則第15条に記されています。
また、健康保険法第208条と厚生年金保険法第102条では、企業が社会保険の手続きを怠った罰則として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められています。
さらに、翌月の10日までに公共職業安定所へ、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。もしも違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられると、雇用保険法第83条第1号に記載されています。
【出典】e-GOV法令検索「健康保険法施行規則 第二十四条」
【出典】e-GOV法令検索「厚生年金保険法施行規則 第十五条」
【出典】e-GOV法令検索「雇用保険法 第八十三条」
【出典】e-GOV法令検索「健康保険法 第二百八条」
【出典】e-GOV法令検索「厚生年金保険法 第百二条」
3.2 追徴金と延滞金の支払い
厚生労働省によると、労働保険に関しては最大2年さかのぼって追徴金が徴収されるとされています。また、健康保険と厚生年金保険に関しても、必要に応じて立入検査が実施され、職権により遡って加入手続きを行ったうえで、保険料額が決定される可能性があります。
さらに、いずれの保険でも納付期限までに保険料の納付が確認されない場合は、事業所に督促状が送付されます。それでも未納付が続く場合は、健康保険・厚生年金保険は年8.7%、雇用保険・労災保険は年14.6%の延滞金が科されることになります。
【出典】厚生労働省「成立手続を怠っていた場合は」
【出典】日本年金機構「延滞金について」
【出典】厚生労働省「労働保険料」
【出典】地方厚生局「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?」
【関連記事】「試用期間中の退職は履歴書に書くべき?理由別の書き方も紹介」
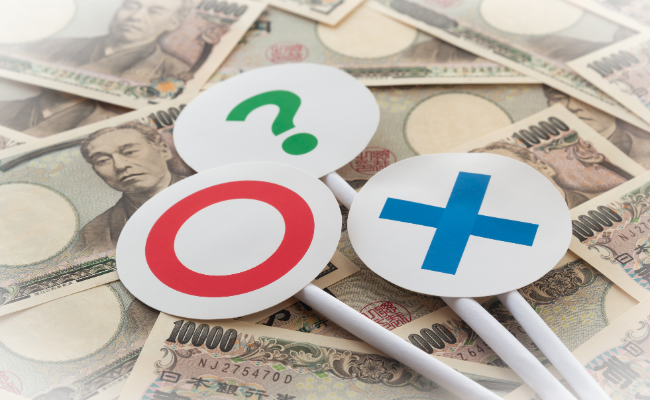
4 「試用期間中は社会保険なし」と言われたときの対処法
先述したように、試用期間中であっても条件を満たしているのであれば、社会保険の対象となります。しかし、会社から「試用期間中は社会保険に加入できない」「そもそも社会保険がない」と言われた場合はどうすればいいのでしょうか。
4.1 社会保険の加入条件を確認する
まずは、社会保険の加入条件を確認し、もしも条件を満たしているのであれば、なぜ加入できないのかを人事担当者に問い合わせましょう。会社によっては、「2ヶ月間の試用期間を設けている場合、本採用となる3ヶ月目から加入すれば問題ない」と誤った解釈をしているケースもあります。
確かに、社会保険が対象外となる人の条件には、「2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人」という項目がありますが、これは2ヶ月以内という有期雇用の場合であり、2ヶ月を超えての雇用が見込まれるのであれば、契約当初から加入しなければなりません。
4.2 国民健康保険と国民年金保険に加入する
もしも、「加入条件を満たしていなかった」「勤務先が強制適用事業所ではなかった」という場合は、自分自身で国民健康保険と国民年金保険に加入する必要があります。市区町村役場や年金事務所で早めの手続きを行いましょう。
4.3 転職を視野に入れる
加入条件を満たしているにもかかわらず、会社から「社会保険には加入できない」と言われた場合は、会社が違法行為を行っている可能性があります。ただちに会社へ申し入れを行い、それでも応じてもらえないときは年金事務所に相談しましょう。
しかし、社会保険の管理がずさんな会社は、経営面や待遇面にも不安が残ります。将来のことを考えれば、早めに見切りを付けて新たな転職先を探すのがおすすめです。
【関連記事】「"ブラック企業での勤務経験者"は7割超、ブラック企業の特徴1位は!?」
【関連記事】「転職活動でまずやることとは?流れ・準備・進め方を分かりやすく解説」
5 試用期間中の社会保険でよくある質問
ここでは試用期間中の社会保険でよくある質問をいくつか紹介します。保険証や退職時の対応についても解説します。
5.1 保険証はいつもらえる?
保険証は企業が届出書を提出してから、約1週間ほどで企業に発送されます。企業は従業員を雇用後5日以内に届出書を提出することが定められているため、その期間を入れても通常は10日前後で受け取れることが多いでしょう。
5.2 試用期間が短くても加入は必要?
試用期間の長さにかかわらず、長期雇用が見込まれる場合は社会保険に加入しなければなりません。たとえ、試用期間が1週間であっても、その後2ヶ月を超えて継続雇用されるのであれば、入社当初から加入の義務があります。
5.3 試用期間中の社会保険加入は辞退できる?
社会保険は基本的に強制加入のため、条件を満たしているのであれば加入を辞退することはできません。2ヶ月を超えて働く場合は、試用期間であっても社会保険に加入する必要があります。
5.4 試用期間中でも家族を扶養に入れることはできる?
試用期間中でも社会保険に加入する義務があるため、扶養制度を利用することができます。なお、扶養制度の利用には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)
- 被扶養者の収入が被保険者(あなた)の収入の半分以下
扶養の手続きを行いたい場合は、被扶養者の収入を確認したうえで会社に申請しましょう。その際、被扶養者の源泉徴収票や非課税証明書などの提出を求められる可能性があります。
5.5 試用期間中に退職した場合はどうなる?
試用期間中に退職した場合、社会保険の切り替えを行わなければなりません。健康保険に関しては「任意継続健康保険に加入する」「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」のいずれかを選択します。
また、厚生年金保険の資格も喪失するため、国民年金への切り替えも必要です。いずれも定められた期間中に、自ら手続きを行わなければならないため注意しましょう。
なお、雇用保険の解除は会社側が行いますが、雇用保険による失業手当の受給資格は、「離職前の2年間に1年以上の被保険者期間があること」とされています。そのため、1年未満の試用期間中に退職した場合は、失業保険を受け取れない可能性が高くなります。
【出典】全国健康保険協会「退職後の健康保険について」
【出典】日本年金機構「会社を退職した時の国民年金の手続き」
【出典】厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
はじめての転職には、
「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
6 まとめ
試用期間であっても、長期雇用を見込んだ労働契約を結んでいるのであれば、契約当初から社会保険に加入しなければなりません。たとえ試用期間が短くても、条件を満たしている場合は加入の対象となります。
社会保険の加入対象条件や加入対象外の条件は、それぞれの保険によって異なります。2024年10月からは短時間労働者への適用が拡大されるなど、法律も時代とともに変化しているため、条件にあてはまっているかは都度確認してみることが大切です。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける



