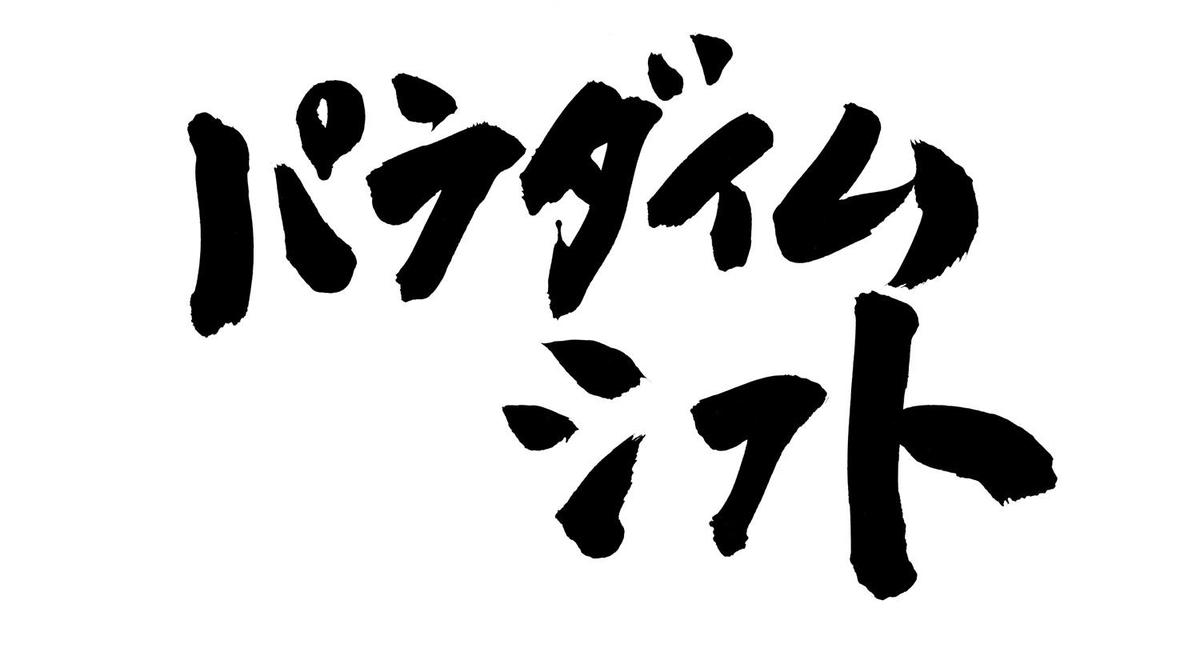「パラダイムシフト」という用語を聞かれたことがあると思いますが、変化の激しい現代においてはパラダイムシフトに対応できることが個人や組織に必要とされます。パラダイムとは、パラダイムシフトの意味や事例、パラダイムシフトに対応することが重要な理由について解説します。
(※仕事辞めたい、会社がつらい...悩んでいる方は『仕事どうする!? 診断』の診断結果もご参考にしてください)
【関連記事】「【ビジネス用語一覧】よく使う用語集100選|意味を例文付きで紹介」
1.パラダイムとは
パラダイム(Paradigm)とは、その時代の規範となるような思想や価値観のことです。
ギリシャ語で「配列」を意味するパラデイグマ(Paradeigma)に由来した言葉で、米国の科学史家であるトーマス・クーンが、自著の『科学革命の構造』の中で使用した言葉です。
【関連記事】「エビデンスとは?意味とビジネスシーン別の例文を簡単に解説」
【関連記事】「【マーケティングとは】マーケティングの3要素と4つの手順、成功例を紹介」
今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。
2.パラダイムシフトとは
パラダイムという言葉は、「パラダイムシフト」という言葉でよく使われます。
パラダイムが変わるという意味で、その時代の規範となる考え方や価値観が大きく変わることを指します。
例えば、中世では地球は不動で、天体だけが動くという天動説が信じられていました。しかし、コペルニクスなどが観測データに基づき、地球は太陽の周りを公転していると考えた方がデータが合理的に解釈できることから、地動説を唱えました。
しかし、当時の宗教的な解釈や常識からは受け入れ難い考え方であるため、大きな反発を受けました。一方で、地動説の考え方では、天体の観測データが理解しやすくなるため、天文学は大きく発展することになりました。
このように、その時代に信じられている当たり前の常識が変わることがパラダイムシフトで、パラダイムシフトが起きるとその分野を超えて他の分野にも大きく影響し、世の中が変わることになります。
一方、以前のパラダイムと新しいパラダイムとを比較して、必ず新しいパラダイムの方が優れているとも限らない、というのも大きなポイントです。
【関連記事】「【ペルソナとは】ビジネスにおける意味やメリット、設定方法を解説」
【関連記事】「【マネタイズとは?】意味や使い方、4つのマネタイズ手法を解説」
【関連記事】「「定量」と「定性」の違いとは!?--ビジネスで活かせる「定量」「定性」分析」
3.ビジネスシーンでのパラダイムシフトの事例
パラダイムシフトは固定観念にとらわれていては起きないために、ビジネスの世界では積極的にパラダイムシフトが起こることを求める人達や組織も存在します。
革新的なアイディアによって市場が変わるため、そこに大きなビジネスチャンスが生まれるからです。
すでにビジネスの世界ではいくつものパラダイムシフトが起きてきました。
3.1.所有から共有へ
自動車というのは従来自分で購入して所有するのが一般的でした。しかし、90%以上の時間は停車しており、社会全体で見ると遊休資産になっていました。
そこに登場したのがカーシェアリングという考え方で、自動車を社会で共有しようとする考え方が広がったのです。
これにより、シェアカー(時間単位でレンタルできるレンタカー)やライドシェア(車移動のついでに乗客を乗せ、経費の一部を負担してもらう)など、新しいサービスが登場しています。
3.2.ハードディスクからクラウドへ
情報を保存しておく場所は従来自分が所有するハードディスクなどが一般的でした。しかし、インターネットが普及し、1人で複数のデバイスを使うようになると、インターネット上のストレージ=クラウドを利用することが増えてきました。
クラウドに保存をすることで、デバイスとハードディスクを接続することが必ずしも必要でなくなり利便性が向上しました。
他者と情報を共有する場合も、リンクを送るだけで共有可能となり、利便性が向上しました。クラウドの登場により、多数のデバイスを使い分けられるようになり、また、業務の仕方もオフィス、自宅、外出先を選ばずに仕事ができるようになりました。
さらに、関係者で情報を共有したり、オンラインで共同作業したりできるようになりました。
3.3.利益追求から社会貢献へ
企業とは原則的には利益を追求する集団ですから、少しでも利益を増やすことが目的です。
しかし、社会が成熟してくると企業の成長余地も乏しくなるため、利益をあげることが他者の利益を奪う場合が相対的に多くなり、企業の目的の前提に疑問が持たれるようになりました。
特に日本の場合、2011年に起きた東日本大震災が人々の考え方を大きく変えました。
利益を追求しても災害によって企業の業績は一気に悪化します。利益よりも社会貢献を軸に考えた方が、企業経営を長く保つことができるという考え方が広がりました。
例えば、食品販売をする企業が、利益追求のために食品を販売するのではなく、食品を必要としている消費者に商品を届けるという社会貢献をしていると考えるようになることで、企業と消費者の関係性が大きく変わるきっかけにもなってきています。
【関連記事】「【コンバージョンとは】コンバージョンをビジネスで活用するさまざまな方法」
【関連記事】「【GAFAとは】巨大IT企業4社がプラットフォーマーとして特別視される理由」
【関連記事】「【スキームとは】ビジネスでの意味と使い方を解説!簡単に言い換えるなら?」
【関連記事】「【例文アドバイス】面接日程メールの書き方や返信方法は?調整する際のマナー」
4.パラダイムシフトに対応できる組織とは
パラダイムシフトは小規模なものであれば日々起きていますし、大きなものでも現代では10年に1回ぐらいのペースで起きていると考えられます。
例えば、2007年に登場したスマートフォン、2022年に登場したChatGPTは、パラダイムシフトのきっかけをつくりました。
パラダイムシフトが短期間に起きる現代では、組織あるいは個人の双方とも、パラダイムシフトが起きても耐えうるようになる必要があります。
パラダイムシフトに耐えうる組織とは次のような4つの特性を備えています。
4.1.あらゆることに柔軟に対応できる
企業の中には企業文化、その企業なりの価値観があります。それは素晴らしいことで継承すべき特質です。しかし、その価値観と異なる価値観と出会った時に、柔軟な対応ができるかどうかが重要です。
よくあるのは、新しい価値観を従来の価値観という物差しで評価をして、軽視したり、排除したりしてしまうことです。
その企業の中では従来の価値観が最も価値のあることと考えられがちですが、その考えがあまりに強すぎると、企業の価値観以外のものをすべて排除してしまうような頑迷な組織となってしまい、次第に時代からずれた組織になっていってしまいます。
新しい価値観が組織に浸透してきてもそれを排除するのではなく、何が従来の価値観と異なるのか考え、必要であればうまく取り入れて組織を強化をしていく姿勢が求められます。
4.2.環境の変化に敏感になる
強い組織は環境の変化に敏感でなければなりません。
小さなことであっても社会や環境の変化をすぐにとらえ、それがどのような影響をもたらすのかを予測し、それに対して自分たちはどのように対応すべきなのかを議論できる姿勢を取り続けることが必要です。
そうした姿勢がない組織は、環境が変化しても自ら変わることができず、恐竜のように滅びていく可能性があります。
環境の変化を見逃さないように、組織として常にアンテナを張っておくことが必要です。
4.3.問題意識を持ち続ける
環境の変化をとらえるには情報源を確保しておくことも重要ですが、最も重要なのは常に問題意識を持ち続けていることです。
例えば、日々の業務の中で、「なぜ定型文のような書類を何枚も大量に作成しなければならないのか?」という問題意識を持ち続けていれば、書類作成を大幅に減らすことができるデジタル技術や、定型書類を生成してくれる生成AIなどの情報を得た際に、その情報の価値を瞬時に正しく判断することができます。
情報源を確保していても問題意識がなければ単なる情報としてしかとらえることができず、情報の価値を見誤る可能性があります。
日頃から、組織の中で「どのような問題が存在しているか」を議論し、組織の中で問題意識を共有していることが重要です。
4.4.価値観の異なる人とコミュニケーションする
価値観が異なる人と話をすることは、時として摩擦を引き起こしてしまう可能性もありますが、一方で強い刺激を受けることもできます。
ちょっとしたことであっても考え方が異なれば話の端々にひっかかる点が出てきますが、これが重要なのです。
同じ価値観を共有する人との会話にはひっかかることが少なく、摩擦や対立を引き起こすことも少ないため心地よく感じることも多いですが、大きな刺激は受けにくいです。
強靭な組織とは、組織を運営するために必要な価値観には同意しつつも個人としては異なる価値観を持った人が多く集まっている組織です。
これに対し、硬直化した組織とは、組織の価値観に染まりきって、それとは異なる価値観を持つ人を排除してしまう人が多く集まっている組織といえます。
【関連記事】「【ニッチとは】ニッチ戦略のメリット・デメリット、ブルーオーシャン戦略との違いも解説」
【関連記事】「インプレッション(インプレ)とは? 意味や類似語との違い、関連する指標も解説」
【関連記事】「【ブルーオーシャン戦略とは】見つけ方から戦略のフレームワークまで」
【関連記事】「【例文あり】面接結果の合否連絡が遅い・来ない場合の対処法を解説」
5.まとめ
パラダイムとは、その時代の規範となるような思想や価値観のことです。
ビジネスの世界においても、価値観が変わる時に企業が成長する機会が生まれます。
そのため、パラダイムシフトに対して対応できる組織体制や企業文化を築いていくことが必要になります。
従来主流とされてきた考え方とは異質な考え方を受け入れる組織づくりが重要です。
【関連記事】「OODA(ウーダ)ループとは?具体例でわかりやすく解説!」
【関連記事】「KPIツリーとは? 作り方のポイントやメリット・デメリットを紹介」
【関連記事】「AIDMA(アイドマ) とAISAS(アイサス)、その他の購入行動モデル含め徹底解説」