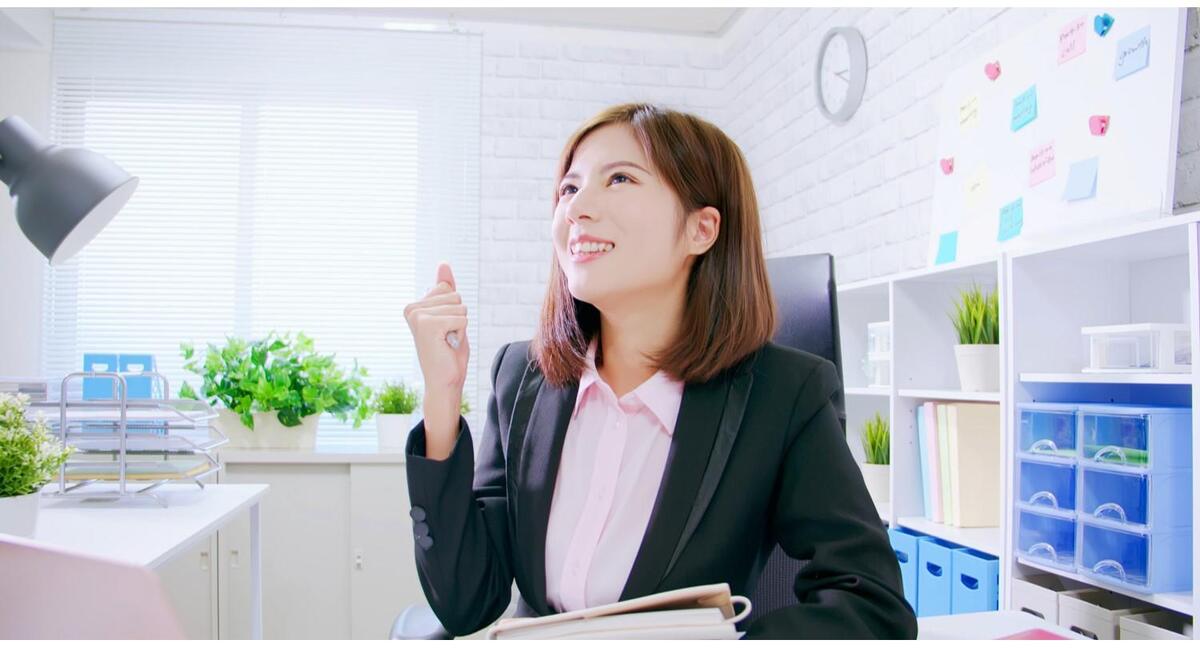多くの企業で目標管理(MBO)が導入されており、社員は組織の成果を高めるために、業務上の目標やキャリアの目標を設定し、その進捗を定期的に報告することが日常業務として根付いています。
一方で、「目標の立て方がわからない」という声も少なくありません。そこで本記事では、「SMARTの法則」を活用した仕事の目標の立て方を紹介します。(Misa)
「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. なぜ、仕事では目標を持たなければいけないか
なぜ、仕事で目標を持つことが求められるのでしょうか。
仕事をするうえで目標を設定すると、個人の仕事が組織全体の目標と連動し、より効果的に成果を上げることができます。近年、多くの企業で目標管理(MBO)が広く普及し、組織のマネジメントや人事評価に活用されています。
また、組織や部門の目標を個人に落とし込むことで、個人の役割や期待される成果が明確になり、仕事の方向性もブレにくくなります。こうした背景から、一人ひとりに目標設定を求められているのです。
1.1. 目標があるとどう変わるか
仕事で目標を持つと、優先すべきことが明確になり、効率よく仕事を進められます。具体的な目標を設定することで、行動計画が立てやすくなり、無駄な時間や労力を減らせるのも大きなポイントです。
また、目標を達成することで得られる達成感がモチベーションの維持につながるだけでなく、スキルや経験も積み重なり、自身の成長を実感しやすくなります。
こうした個人の成長と効率化が仕事のやりがいや満足感を高め、結果的にチームや組織の成果向上にも良い影響を与えます。
【関連記事】「KPIツリーとは? 作り方のポイントやメリット・デメリットを紹介」
【関連記事】「「転職したいけどわからない」を解決!ケース別の対処法とは」
今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。
2. 目標設定できない人の共通点
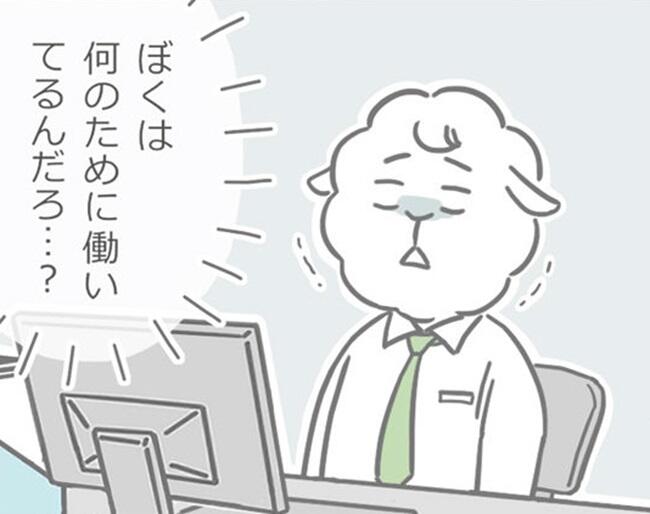 イラスト:斉田直世 漫画の続きはこちら>
イラスト:斉田直世 漫画の続きはこちら>
「仕事には目標が大切」ということは理解していても、なかなか目標が設定できない人もいます。
目標が立てられない人には、以下のような共通点があることが多いです。
- そもそも仕事に対するモチベーションが低い
- 自分の役割や立ち位置がはっきりしていない
- 将来のビジョンやなりたい姿を想像できていない
詳細な目標を立てる前に、まずは仕事に対する意識の向上を図ったり、役割の確認を行ったりすることが大切です。
【関連記事】「やりたい仕事がない人向け|見つからない原因と5つの対処法を解説」
【関連記事】「20代|やりたい仕事がないのはなぜ?原因と転職を成功させるポイントを解説」
【関連記事】「仕事のやりがいがない理由を分析しよう!前向きに仕事をするためには」
2.1. よくあるつまずき方と対処法
目標設定でつまずく原因は人それぞれですが、よくあるパターンと対策を知っておくことで、苦手な人でもスムーズに目標を立てやすくなります。
まず、明確な目標がなく何をすればいいか分からない場合は、「今週中に資料の下書きを仕上げる」や「上司や先輩に仕事の進め方を聞いてみる」など、小さな行動から始めてみましょう。
また、目標が高すぎて続かない場合は、「売上10%アップ」のような大きな目標を「今月の顧客訪問数を増やす」など達成しやすい段階に分けるのがポイントです。
モチベーションが続かない場合は、目標の意味や自分にとってのメリットを見直すのも効果的です。
3. わかりやすい目標の立て方とSMARTの法則
目標管理(MBO)が定着した企業では、効果的な目標設定のための教育がおこなわれますが、それでも目標を立てるのが苦手な人もいます。そうした場合、多くは自分の所属部門やチーム内での自分の役割を理解できていないことが原因です。
所属部門の業務や役割を理解し、自分に期待される役割が把握できると、目標設定の第一歩である「定性目標」をイメージしやすくなるでしょう。
(1)定性目標を立てる
定性目標とは、質的に表現される数値化されない目標で、目指すべき状態を示します。目標達成に必要な行動を示すため、「行動目標」と呼ばれることもあります。
(例)
- 顧客満足を高め、リピート受注を増やす
- 業務を改善し、コストを削減する
(2)定量目標を立てる
定量目標とは、目指すべき状態を数値化し、具体的に設定する目標のことです。数値化することで、実現に必要なプロセスが明確になり、具体的な行動計画を立てやすくなります。
(例)
- 新規顧客を月2件ずつ獲得する
- 消耗品、事務用品のコストを20%削減する
【関連記事】「「定量」と「定性」の違いとは!?--ビジネスで活かせる「定量」「定性」分析」
(3)「SMARTの法則」で精査する
SMARTの法則は、1981年にジョージ・T・ドランによって提唱された目標設定のフレームワークです。作成した目標が「SMART」の各項目に当てはまっているかを確認し、適切な目標かどうか判断します。
現在、一般的に使われているのは、以下の定義です。
- Specific(具体的):5W (Who、What、When、Where、Why)が盛り込まれている
- Measurable(測定可能):指標を用いて数値化されて、効果測定ができる
- Achievable(達成可能):現実的に達成できる内容である
- Relevant(関連性):目標を達成することでどういった成果がもたらされるか
- Time-bound(期限つき):具体的な期限が設定されている
この定義は提唱者や出典の違いによって異なることがあります。もともと「A」はAssignable(割り当て可能)、「R」はRealistic(現実的)を指していました。
時代や企業の実情に合わせて、理解しやすさや運用しやすさを重視したさまざまなバリエーションのSMARTが広まっていきました。
4. 【仕事別】使える個人目標の例文を紹介
職場によっては、定期的に個人目標を発表・提出する必要があり、特に新人の方は悩むこともあるでしょう。
そこで、業種別に具体的な目標例を紹介します。
【製造業】
作業効率を見直すことで工場の稼働率を10%上げる。
【接客業】
お客様アンケートに週1回目を通し、自分の接客で改善可能な点を見つける。
【事務職】
重要な書類は他者にWチェックを依頼してミスを0にする。
【営業職】
新規訪問数を増やすとともに、先月の売り上げを10%上回る。
【エンジニア職】
プロジェクトの納期達成率を95%以上に維持する。
【クリエイティブ職】
新規プロジェクトのコンセプト案を月に3件提出する。
このように、業種によって個人目標の立て方は異なるため、配属先の部署や担当業務を踏まえて目標を考えることが重要です。
5. 目標を持つことで、仕事の効率とやりがいがアップする
具体的な目標を立て、実施計画を作成することで、目的意識がはっきりします。目的意識があれば、目標達成のための自律的な思考が生まれ、誰かの指示を待つのではなく、自分で目標達成のプロセスをイメージしながら効率的に行動できるようになるでしょう。
また、組織全体・部門単位・チーム単位で目標を共有することで、組織内のビジョンを理解しやすくなり、やりがいも見つけやすくなります。
さらに、定量的な目標設定によって成果の測定が容易になり、合理的に仕事の成果を評価できます。成果と評価を紐づけることで、人事評価の公平性や納得感が高まり、やりがいの向上にもつながるでしょう。
【関連記事】「仕事のやりがいとは?具体例や見いだせない理由、見つけ方を解説」
【関連記事】「「転職したいけどわからない」を解決!ケース別の対処法とは」
【関連記事】「転職は「逃げ」ではない!より自分に合う会社に転職するために」
【関連記事】「転職エージェントは相談だけでも利用できる?メリットや注意点を徹底解説」
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける
原稿:Misa
ITベンチャーで企画、人材開発、広報などを経て独立。現在はコンサルタント、ときどきライター。ライターとしては、ビジネス系を中心に、アニメ・マンガ、車から美容・健康まで何でもチャレンジ中。