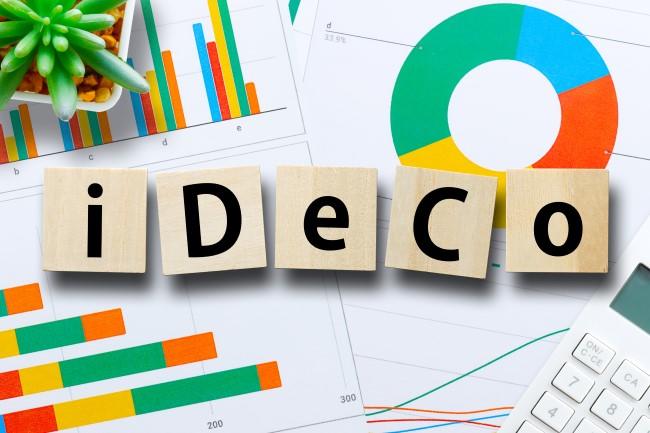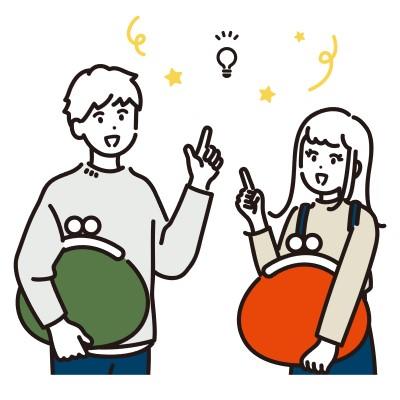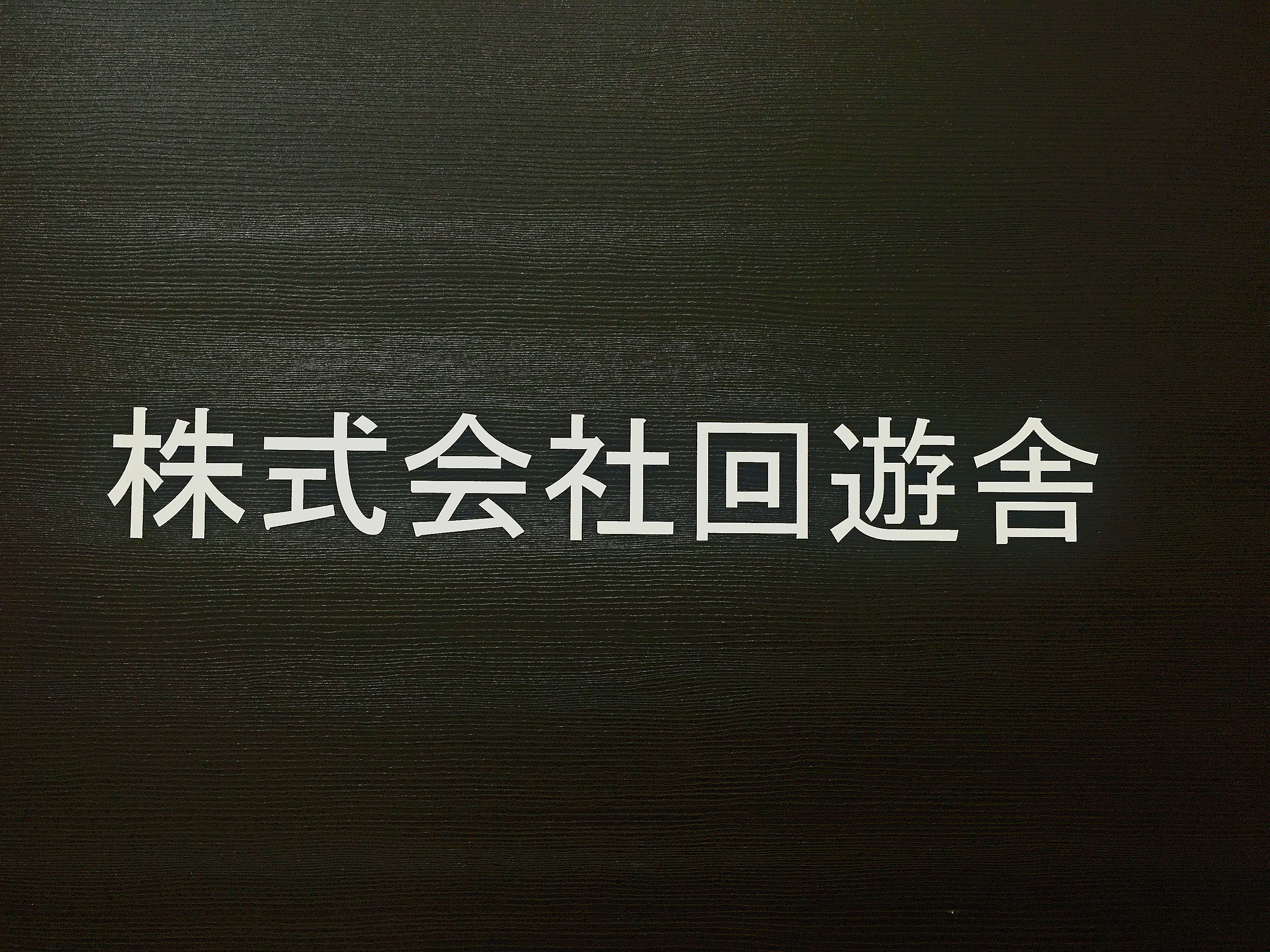さまざまな税制上のメリットが得られる「個人型確定拠出年金(iDeCo)」は、転職や退職をした場合でも、基本的にそれまで積み立ててきた資産を引き継ぐことが可能です。
ただし、転職先に企業年金があるかどうかといった条件によって、上限額や必要な手続きが異なる可能性があります。この記事では、iDeCoの引き継ぎに関する転職先による違いや、移換の手続きなどについて解説していきます。
【関連記事】「新NISAとは? わかりやすく解説、デメリットや注意点も詳しく解説! (1)」
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける>
1.iDeCoは引っ越し可能
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で掛金を拠出し、老後資金を積み立てるための日本の私的年金制度です。運用益が非課税になるなど税制上のメリットが大きいため、老後資金を効率的に準備したい方にとっては嬉しい制度と言えます。
そんなiDeCoには、転職や退職をした場合にそれまでの運用資産を持ち運べるという「ポータビリティ制度」があり、前職と同じように積み立てを継続することができます。
ただし、転職先や条件によっては、掛金の上限を変更する必要や継続加入ができない可能性もあるため注意が必要です。
まずは、転職によってどのような手続きが必要になるのかを解説します。
【関連記事】「テレワークで通勤手当がなくなった!--コロナ禍の定期券や交通費の疑問にお答え」
今の仕事、会社がつらい場合は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」にご相談ください。
2.転職によるiDeCo移換で必要な手続き
iDeCo加入者が転職をした場合、必ず手続きが必要になります。
iDeCo加入時に「事業主の証明書」を提出しますが、勤め先が変更になると、この書類を転職先に新たに作成してもらう必要があります。
転職先の企業が発行してもらったこの「事業主の証明書」に加えて「加入者登録事業所変更届」を金融機関に提出します。
また掛金が変わる場合には、「加入者掛金額変更届」の提出も必要です。
なお、企業型DCのある企業に転職し、iDeCoを解約して企業型DCに加入し直す場合は手続き方法が異なります。
このケースの場合、転職先への入社日が決まったら、iDeCoを解約するために、「加入者資格喪失届」を運営管理機関に提出します。企業型DCへの加入手続きについては勤務先によって異なるため、転職先の担当者の指示に従いましょう。
またiDeCoの資産を移換する場合は、移換手続きが必要になるため、転職先に問合せて書類を準備してもらいます。
なお、「無職になったらiDeCoも止めたい」という方もいますが、原則としてiDeCoは60歳まで資産を引き出すことができないため、「掛け金の減額」や「積み立ての停止」で対処する必要があります。
3.転職先によるiDeCoの継続方法
「企業年金があるのかないのか」「企業年金の種類は何か」など、転職先の状況によってiDeCoの継続方法は異なります。ここでは、iDeCoをどのように継続するのか、それぞれのケースごとに解説します。
3.1.転職先に企業年金がない場合
転職先に企業年金がない場合、そのままiDeCoを継続することが可能です。掛金の上限額は月額2万3,000円です。
3.2.転職先に企業年金がある場合
転職先に企業年金がある場合は、企業型DCなのか、確定給付企業年金DBなのかによってiDeCoを継続可能かどうかが変わります。
3.2.1.企業型DCの場合
以前は、年金規約の定めにより、iDeCoと企業型DCの同時加入が認められていないケースが大半でした。しかし、2022年10月の制度改正によって、企業型DC加入者がiDeCoに加入する要件が緩和されました。
これにより、今までiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者も、以下の条件を満たすことでiDeCoに加入できるようになりました。
(1)各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えていないこと
(2)掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること
(3)企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと
もしも、iDeCoの資産を企業型DCに移換したい場合は、iDeCoの加入者資格喪失手続き及び、資産移換手続きが必要です。
3.2.2.確定給付企業年金DBの場合
企業年金には、企業DC以外に、従業員が受け取る年金給付額があらかじめ約束されている「確定給付型企業年金(DB)」があります。
転職先にDBがある場合は、そのままiDeCoの継続が可能です。ただし掛金の上限額は月額1万2,000円となっています。
3.3.公務員・自営業者・専業主婦(夫)になった場合
公務員や自営業者に転職した場合、また専業主婦になった場合は、それぞれ掛金の上限に違いがあります。
3.3.1.公務員になった場合
転職して公務員になった場合、そのままiDeCoの継続が可能です。その場合、掛金の上限額はDBと同じく月額1万2,000円となっています。
3.3.2.自営業者になった場合
転職して自営業者やフリーランスになった場合、そのままiDeCoの継続が可能です。自営業者におけるiDeCoの掛金の上限額は、国民年金基金の限度額とあわせて月額6万8,000円となっています。
3.3.3.専業主婦(夫)になった場合
仕事をやめ、専業主婦(夫)になった場合、そのままiDeCoの継続が可能です。この場合の掛金の上限額は月額2万3,000円となっています。
【関連記事】「【手取りとは】額面給与との違いや計算方法、手取り額が減少している理由を解説」
キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。
4.iDeCoの変更で生じるメリット・デメリット
転職でiDeCoを変更した場合、いくつかのメリットとデメリットが生じます。ここでは、iDeCoを企業型DCに移換する場合、またiDeCoと企業型DCを併用する場合に生じるメリット・デメリットを解説します。
4.1.iDeCoを企業型DCに移換する場合
転職先に企業年金DCがある場合は、iDeCoを辞めて企業年金DCに資産を移換することもできます。iDeCoを企業型DCに移換するメリットは、何と言っても掛金や事務費用の個人負担がなくなることです。また、上限額も企業型DCの方が高いので、将来のリターンも大きくなる可能性があります。
ただし、企業型DCの場合、会社が委託した金融機関が扱っている運用商品の中から選ばなければならず、選択肢が狭まる点はデメリットと言えます。
4.2.iDeCoと企業型DCを併用する場合
掛金の上限など一定の条件を満たしていれば、両者を併用することも可能です。運用益が非課税であるiDeCoと企業型DCを併用すれば、他の投資に回すよりも効率的に老後資金を準備できます。
一方、iDeCoは掛金や事務手数料は自己負担であり、企業型DCのみに比べると負担が増える点はデメリットです。また、転職が多い方は必要な手続きが多くなるため、いつまでに手続きを終わらせるのかをしっかり確認しておく必要があります。
【関連記事】「【消費者物価指数とは】「そもそも何?」から5年ぶりの見直し内容まで解説」
5.転職でiDeCoの手続きをしないとどうなる?
転職や退職に際してiDeCoの手続きをするのが面倒だと思われる方も多いかと思いますが、手続きをしないまま放置していると自身の資産が減ってしまうといったデメリットが発生する可能性があります。
自分がどのケースに該当するのか確認したら、コールセンターに電話をして必要書類を用意してもらい、手続きを進めるのがスムーズです。
手続きをせずにいた結果、より手続きが複雑で面倒になってしまうこともあるので、できるだけ早く手続きを済ませることをおすすめします。
5.1.資産が減少する可能性がある
先述したように、手続きを行わずに転職前の企業型DCから国民年金基金連合会に自動移換されてしまった場合、移換時にかかる各種手数料が資産から引き落とされます。
また、iDeCoの加入資格を失った場合や掛金の上限額が低くなった場合に手続きをしないでいると、超過分の掛金は返金されるものの手数料が引かれることになります。
手続きをせずにいて加入者資格の有無を確認できない期間が発生すると、掛金の引き落としが一時停止される可能性があります。
手続きを行い資格が確認できれば引き落としは再開されますが、停止していた期間分の追納はできません。
引き落としが停止され積立ができなかった期間は職所得控除を計算する際の勤続期間としてカウントされないため、将来的に受給額が減少する可能性があります。
5.2.受給可能年齢が遅くなる可能性がある
自動移換されている期間は加入期間にカウントされません。
自動移換期間が発生したことで受給要件となる加入期間に満たなくなってしまう場合、本来受給できるはずだった年齢よりも遅れてしまう可能性があります。
6.企業型DCの加入者が転職する際の注意点
iDeCO加入者が転職する場合の手続きについて説明しましたが、合わせて企業型DCの加入者が転職する場合についても確認しておきましょう。
企業型DCに加入している人が、企業年金がない企業に転職した場合、新たにiDeCo口座を作成することでこれまで積み立てた資産を移換することができます。
一方、転職先に企業年金がある場合、新たな企業型DCに移換します。この場合はiDeCoとの併用が企業の規約で認められていてもiDeCoへの移換はできません。
なお、企業型DCに加入していた人が転職などをして、資産をiDeCoや企業型DCに移換する場合、移換手続きは6ヶ月以内に行う必要があります。
この手続きを6ヶ月以内に行わないと、資産は現金化されて国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。
自動移換されると、資産運用はされず、自動移換の際の手数料や管理手数料が資産額から引かれてしまうため、注意しましょう。
【関連記事】「【年末調整の保険料控除とは】控除の種類、税負担が軽くなる仕組みを解説」
年収アップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
7.まとめ
転職をした場合でも、これまでiDeCoで積み立ててきた資産を引き継ぐことができる場合が多々あります。
ただし、転職先によって引き継ぎの際に必要になる手続きが異なるため、自分がどのケースに当てはまるのかをしっかりと確認しておきましょう。
【関連記事】「【金融リテラシーとは】資産を守るため最低限身に着けたい知識などを解説」
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける