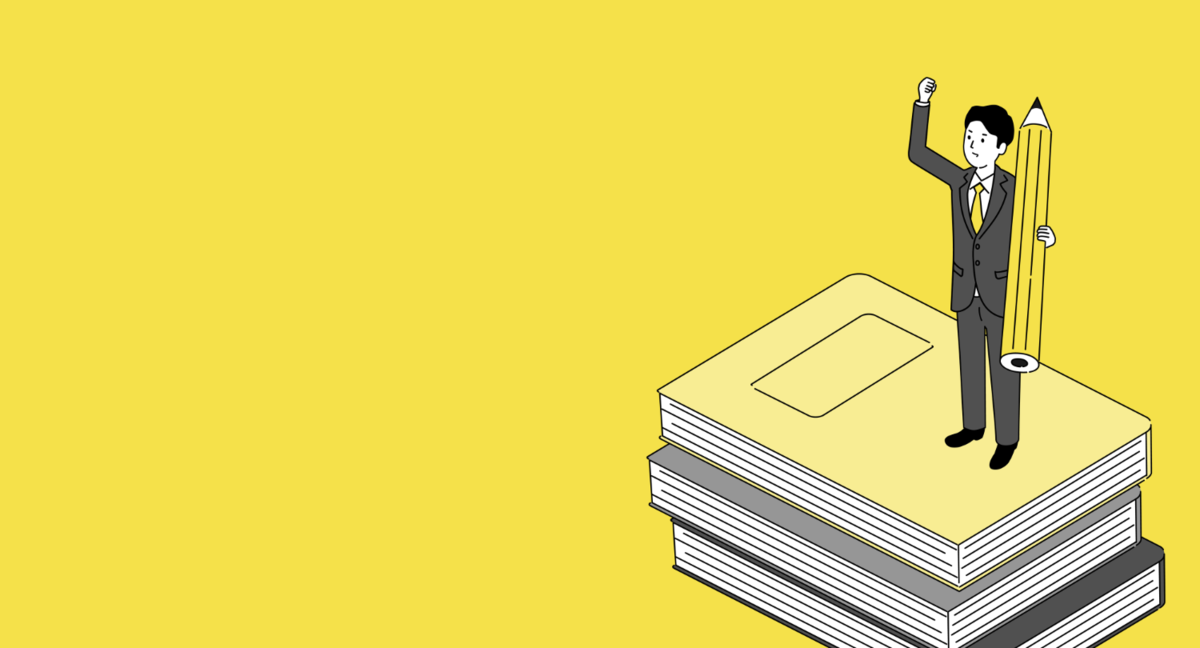資格取得の勉強方法には、参考書や過去問の活用、セミナーへの参加などがあります。資格取得は今後のスキルアップやキャリアアップにも有効なので、自分の実力やスケジュールに合わせた学習計画を立てることが大切です。
本記事では、資格を取得するメリットや種類、試験に合格するための効果的な勉強方法を紹介します。また、資格ごとの難易度や選び方についてもまとめました。自分にとって必要な資格や、取得のためにすべきことが明確になるでしょう。
【関連記事】「「転職したいけどわからない」を解決!ケース別の対処法とは」
「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >
1. 資格取得のための勉強方法
資格取得には、参考書や動画サイト、スクールなどで知識をインプットし、過去問や模擬試験でアウトプットすることが有効です。この流れをバランスよく繰り返すことで、知識が定着しやすくなります。
以下では、具体的な勉強方法を6つのポイントに分けて解説します。
1.1. 参考書を活用する
新しい知識のインプットには、参考書の活用がおすすめです。資格勉強の参考書には馴染みのない専門用語が多く、理解するまでに多くの時間がかかることも少なくありません。
まずは一通り目を通して全体像を把握するイメージで読み進めましょう。次に冒頭に戻って再度目を通すと、難しく感じた用語もスムーズに頭に入りやすくなります。
このように何度も繰り返し参考書を読むことで、少しずつ専門的な知識や難しい用語も定着していきます。
1.2. 動画で学ぶ
参考書などの文字情報だけでなく、動画や音声教材があればさらに記憶に残りやすくなるでしょう。動画はスマートフォンで簡単に視聴できるため、移動中や身支度の間、家事をしながらでも学習が可能です。
帰宅後の〇時~〇時までは参考書や過去問を使用して勉強し、それ以外の時間に動画学習をするといったように、時間を決めて使い分けるといいでしょう。
1.3. 資格スクールや予備校に通う
「自分一人では途中で挫折してしまう」「とにかく合格したい」という場合は、資格スクールや予備校、通信講座の受講を検討しましょう。
近年では、さまざまな団体や企業から通信講座やスクールなどのサービスが提供されており、自宅でオンライン受講が可能なものもあるため、用途に合わせて活用しましょう。
1.4. セミナーや勉強会に参加する
セミナーや勉強会に参加することで、その分野に精通したプロフェッショナルや、実務経験を積む講師から指導を受けられます。
「独学では難しい」「スクールや予備校に通う余裕がない」という場合は、単発でおこなわれるセミナーや勉強会、講習会などに参加するのも一つの方法です。
また、セミナーや勉強会で出会えることもあるため、情報を共有し合える仲間を作れる可能性もあります。
1.5. 過去の問題を解く
効率的に資格試験の勉強を進めるには、過去問を活用するのがおすすめです。過去問を解くことで、問題量や出題形式、難易度、時間配分など試験全体の傾向をつかみやすくなります。
まずは数年分の過去問を一通り解いて、自分の弱点を洗い出します。次に、間違えた問題をノートに書き出して、解答や解説を読み込んで再度解くことで理解を深めます。
過去問を繰り返し解き、新たな弱点を可視化して1つずつ克服していくことがポイントです。
1.6. 模擬試験を受けてみる
資格によっては、本試験前に模擬試験を実施されることもあります。難易度や試験時間、問題量など本試験を想定した内容となっているので、合格ラインに達していれば、安心して本番を迎えられるでしょう。
合格ラインに届いていない場合は、苦手な分野や単元を絞って集中的に学習することができます。
模擬試験を受けることで、資格勉強の進捗状況を可視化できるので積極的に挑戦しましょう。
なお、模擬試験が実施されない場合や試験会場が遠方で受験できない場合は、過去問で模擬試験のような状況を作って挑戦してみるのも1つの方法です。
 【関連記事】「社会人にも勉強は必要?メリットやおすすめのジャンル・資格を紹介」
【関連記事】「社会人にも勉強は必要?メリットやおすすめのジャンル・資格を紹介」
2. 資格を取得するメリット
資格を取得することで、自分のスキルを証明したり、キャリアアップにつながったりするなど、多くのメリットがあります。特に昇進や転職の際には、資格の有無が評価を左右する重要な要素となることが少なくありません。
ここでは、資格取得で得られるメリットを4つ紹介します。これらを理解しておくことで、資格勉強に対するモチベーションを高く保つことができるでしょう。
2.1. スキルや能力の証明になる
資格はその人自身のスキルや能力の証明になるため、転職や営業などで自分をアピールする際に有利です。
また、資格取得によって能力を裏付ける根拠にもなります。
例えば、「私は情報システムやセキュリティ関連のIT知識を身に付けています」よりも「私は、ITパスポートを取得しているため、IT関連と情報処理に関する基本的な知識はすでに有しております。」と伝える方が説得力が高まります。
2.2. スキルアップにつながる
資格を取得すれば、ある特定の分野の知識が身に付き、自分の能力を向上させることができます。新しい知識や技術を手に入れられるので、自己成長はもちろん、チーム・組織・会社全体を大きく変革させられる可能性があるでしょう。
一口に「資格」といっても、さまざまな種類があり、得られるスキルも多岐にわたります。知識や技術だけでなく、経験やマインドなどの成長も見込めるため、自分に必要性の高いものを見極めることが大切です。
2.3. キャリアアップを目指せる
資格を取得し、現状よりも高いスキルが身に付けば、キャリアアップにつながる可能性があります。企業が求めるスキルや技術を習得することで、より良い条件で活躍できるかもしれません。
会社の制度として、資格取得によって昇進や昇給などができれば、モチベーションアップにつながるでしょう。
キャリアアップにおすすめの資格もあるので、昇進や昇給を望んでいる場合は、記事後半を参考にしてください。
2.4. 仕事の幅が広がる
スキルアップをすることで、普段こなしていた業務を効率的におこなえるようになる可能性が高まります。さらには、パフォーマンス向上効果も見込めるため、ワンランク上の業務も担当できるかもしれません。
専門性を高めて仕事の幅が広がれば、会社からの信頼を得られ、新しい業務を任されるチャンスにつながる可能性もあります。また、挑戦したい仕事や部署異動を打診する発言力を得られるケースもあります。
転職を検討している場合は、特定の資格を応募条件として設けている企業への応募も可能になるので、より視野を広げられるでしょう。
 【関連記事】「社会人におすすめの資格27選!資格の選び方や勉強方法なども紹介」
【関連記事】「社会人におすすめの資格27選!資格の選び方や勉強方法なども紹介」
【関連記事】「「転職してよかった」と思える転職を目指そう!成功事例から学ぶポイント」
3. 資格の種類
資格にはさまざまな種類があり、以下のように大きく4つにわけられます。
| 種類 | 特徴 | 主な資格 |
|---|---|---|
| 国家資格 | 国の法律に基づいた資格 | 医師、弁護士、税理士、行政書士、教員、キャリア・コンサルティング技能検定など |
| 民間資格 | 民間企業・民間団体が独自で設定した資格 | TOEIC、証券アナリスト、アロマテラピー検定、医療秘書技能検定、ベンダー資格(MOS)など |
| 公的資格 |
各省庁が認めた資格 |
簿記検定、秘書検定、メンタルヘルス・マネジメント検定など |
| 国際資格 |
他国でも通用する資格 |
調理師免許、米国上級秘書資格(CAP)、米国公認会計士(USCPA)など |
「国家資格」は、国の基準に基づいて認定されており、比較的高い信頼性があることが特徴です。なお、技能レベルを評価する国家検定制度である「技能検定」も、国の法律に基づいて設定されています。
「民間資格」は、民間企業や団体などが社会のニーズにあわせて独自の審査基準を設けて任意で認定する資格を指し、「公的資格」は文部科学省や経済産業省などの特定の官庁や大臣が認定する資格です。
「国際資格」は、複数の国家の合意により定められる資格で、取得すれば海外でも通用するスキルを有していることの証明になります。
資格の種類の特徴と実施している団体・組織を知ったうえで、取得すべき資格を検討しましょう。
 【関連記事】「20代必見!転職に有利な資格やキャリアアップにおすすめの資格」
【関連記事】「20代必見!転職に有利な資格やキャリアアップにおすすめの資格」
4. 資格の勉強をする際のポイント
資格の勉強は、手あたり次第に進めるのではなく、戦略的に進める必要があります。具体的には、次の6つのポイントを押さえて資格勉強に励みましょう。
4.1. 1日の勉強時間を決めておく
資格の勉強には、1日の勉強時間と勉強するタイミングをあらかじめ決めておくことが大切です。
計画性のない学習は知識が定着しにくいため、反復学習ができるように、勉強スケジュールを立てて計画的に進めましょう。
例えば、「夕食と入浴を済ませたら、寝る前の時間を使って毎日3時間勉強する」というように日常生活に組み込むことが重要です。
勉強を後回しにせず、自分で決めたルールを守れるようにご褒美を用意するなどの工夫をすると良いでしょう。
4.2. 目標を設定しておく
最終目的が「試験に合格する」だけではなく、その前段階で小さな目標をいくつか立てておきましょう。
具体的には、中間目標として「〇月〇日に模擬試験を受けて〇点を獲得する」「〇月〇日までに過去問のミスを減らして合格ラインに達する」など、現実的な目標を立てます。
モチベーションの低下を防ぎ、進捗状況を正しく把握するため、中間目標を設定するのは有効な方法です。
4.3. 取得までのスケジュールを引いておく
試験合格までのゴールから逆算してスケジュールを立てれば、計画的に勉強を進められます。
まずは、合格ラインに達するために必要な勉強時間を算出し、1日の目安となる学習時間を設定しましょう。次に1週間単位で学習目標を決めておきます。
1日あたりの学習時間は、その日の体調や仕事の忙しさなどに応じて変動しても良いですが、週ごとの学習目標にズレが生じないように心がけましょう。
4.4. 完璧を求めすぎない
学習をおこなう際は、完璧を求めすぎないことが重要です。例えば、「各分野で満点を取らなければ次の章に進めない」など、完璧な理解を求めてしまうと時間が足りなくなるかもしれません。
また、完璧を求めすぎると、達成できない場合に理想と現実のギャップに苦しみ、モチベーションが下がる可能性もあります。
満点を目指すよりも、自分の実力やスケジュールに合わせて無理なく学習を進めましょう。
4.5. 分からないままにしない
勉強中に分からない部分は、放置せずに解決してから次に進みましょう。
つまずいた箇所を後回しにすると、その分野での高得点を取りにくくなります。しかし、関連する問題が出題される場合があるので、諦めずに一つずつクリアしていくことが重要です。
理解できなかった分野は再度学習し直し、習得できるような余裕のあるスケジュールを立てておきましょう。
4.6. 適度に休憩を取る
資格取得に向けて、「平日は〇時間、土日は〇時間勉強する」というような計画を立てるケースも多く見られますが、余裕のない計画は挫折につながりやすいため、休憩時間もスケジュールに含めることが大切です。
適度な休憩は、脳と身体をリフレッシュさせることができるので、モチベーションや集中力アップにもつながるでしょう。
 【関連記事】「社会人におすすめの資格27選!資格の選び方や勉強方法なども紹介」
【関連記事】「社会人におすすめの資格27選!資格の選び方や勉強方法なども紹介」
5. 資格別の難易度
ここでは、おすすめの資格とそれぞれの特徴や難易度について解説します。どの資格を取得すべきか迷っている方は、難易度と自分が確保できる学習時間、必要なスキルなどを照らし合わせながら検討しましょう。
5.1. 簿記
簿記とは、企業の経営活動を計算・整理して帳簿に記録する技術のことを指します 。資格の正式名称は、「日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験」です。
経営成績や財政状態を明らかにする技能のことで、業種・業態問わずさまざまな企業で必要とされます。なお日商簿記には、初級・3級・2級・1級という4つの級に分けられており、受験資格は設けられていません。
商工会議所の受験者データ(統一試験)によると、直近の3級の合格率は42.4%、2級は22.2%、1級は14%です。
5.2. ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナー(FP)は、税金・保険・投資・住宅ローンなどライフプランに関するお金の知識を証明できる資格です。
認定機関である日本FP協会の公式サイトでは、ファイナンシャルプランナー(FP)のことを「家計のホームドクター」のような存在と記述しています。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、3級・2級・1級の3つの級に分類され、2025年9月現在の合格率は下記の通りです。
| 学科試験 | 実技試験 (資産設計提案業務) | |
|---|---|---|
| 3級 | 85.4% | 85.6% |
| 2級 | 44.4% | 48.8% |
| 1級 | 82.4% |
|
1級は年に1度(9月)に実施されるため、2024年9月のデータを記載しています。
【出典】日本FP協会「実施試験結果データ(受検者数、合格者数等)」
5.3. 行政書士
行政書士とは、行政手続きを専門とする法律関係の国家資格です。行政書士は、官公庁に提出する書類などの作成業務や、書類提出手続きの代理業務、相談業務などを担います。
「最近10年間における行政書士試験結果の推移」によると、合格率は令和2年度以降高くなっていることが分かりました。
| 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 59,832人 | 47,785人 | 6,165人 | 12.90% |
| 令和5年度 | 59,460人 | 46,991人 | 6,571人 | 13.98% |
| 令和4年度 | 60,479人 | 47,850人 | 5,802人 | 12.13% |
【出典】行政書士試験「最近10年間における行政書士試験結果の推移」
5.4. 医療事務
医療事務とは、病院やクリニックなどの医療機関で受付・会計・診療報酬請求業務を担う仕事です。
医療事務は民間資格にあたり、「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク(R))」や
「医療事務管理士(技能認定振興協会)」などさまざまな種類が存在します。
医療事務管理士(技能認定振興協会)の合格率は、50%前後と記載されています。各資格によって難易度や身に付くスキル、特徴が異なるので、リサーチしたうえで検討しましょう。
【出典】技能認定振興協会「医科 医療事務管理士®技能認定試験」
5.5. 中小企業診断士
中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対して診断や助言を行う専門家です。
国家資格なので、「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣によって登録されます。運営管理や企業経営理論のほか、財務・会計などに関する専門知識を身に付けられます。
「中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移」によると、直近4年間の第一次試験の合格率は、以下の通りです。
| 第一次試験 合格率 | 第二次試験 合格率 | |
|---|---|---|
| 令和6年度 |
27.5% |
18.7% |
| 令和5年度 |
29.6% |
18.9% |
| 令和4年度 |
28.9% |
18.7% |
| 令和3年度 |
36.4% |
18.3% |
【出典】J-SMECA 中小企業診断協会「中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移」
5.6. 宅地建物取引士
宅地建物取引士とは、公正かつ円滑な不動産取引をサポートする専門家を指す国家資格であり、主に不動産の売却や賃貸契約などの業務を担うことができます。
不動産適正取引推進機構が公表している「令和6年度宅地建物取引士資格試験結果の概要 」によると、合格率は18.6%でした。
宅地建物取引士は年間約20万人が受験する人気資格ですが、合格できるのは3万人ほどです。
【出典】不動産適正取引推進機構「令和6年度宅地建物取引士資格試験結果の概要 」
5.7. ITパスポート
ITパスポートは、ITに関する基本的な知識を証明できる国家試験です。ITに関するスキルに加え、ビジネス用語や経営知識も身に付くので、取得を目指すビジネスパーソンも多くいます。
令和7年8月度の合格率は48.8%で、例年40〜50%台が多いため、比較的難易度は低めと言えるでしょう。
【出典】IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「【ITパスポート試験】統計情報」
5.8. Microsoft Office Specialist(MOS)
Microsoft Office Specialist(MOS)とは、Word・Excel・PowerPointなどの操作スキルを証明できる国際資格です。取得することで業務の効率化につながり、就職・転職時に有利になる可能性があります。
試験は、「一般レベル(アソシエイト/スペシャリスト)」と「上級レベル(エキスパート)」の2種類に分けられます。MOSの合格率は非公開です。
【出典】Microsoft「マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)」
5.9. 社労士
社労士とは、企業で採用から退職までの労働・社会保険などに関する問題、年金相談といった業務を担う専門家です。
社会保険労務士試験の受験資格は、学歴や実務経験、厚生労働大臣が認定した国家試験合格といった3つの受験資格が必要です。
厚生労働省が公表する「第56回社会保険労務士試験の合格者発表」によると、43,174人が受験し、合格率は6.9%であり、難易度の高い試験であることが分かります。
【出典】厚生労働省「第56回社会保険労務士試験の合格者発表」
【関連記事】「履歴書に書く資格がない場合はどうする?書き方やアピール方法を解説」
6. 資格の選び方や注意点
取得したい資格を選ぶ際は、自分の環境や状況、目的に合わせた選び方が大切です。ここでは、資格の選び方や注意点を4つに分けて紹介します。
6.1. 今の仕事に必要な資格か考える
スキルアップやキャリアアップを資格取得の最終目的としている方は、今の仕事で活用できるかどうかの確認が必要です。
また、会社によっては「有資格者=給与が上がる」という制度を導入していないケースもあるため、会社が求める資格であるのかを事前に調べたうえで挑戦しましょう。
6.2. 自分が将来どうなりたいか考える
自分が理想とする将来像から逆算して、必要なスキルを身につけるのも1つの手段です。例えば、「現在は経理事務として働いているが、将来的には医療事務員になりたい」という場合は、医療事務の資格取得を目指すと良いでしょう。
また、現職と大きくかけ離れていても、資格を取得することで転身できる可能性もあります。まずは3年後の自分の姿を想像しながら、理想像を紙に書き出して言語化してみると、必要な資格が見えてくるかもしれません。
6.3. 資格の難易度や勉強時間はあるか考える
取得する資格によって、難易度や必要な学習時間が異なります。自分がどの程度の時間を資格の勉強に充てられるのかを考えてから、現実的に可能なものを選択しましょう。
また、これまでに資格を取得した経験がない方は、短期間で合格できるものを選ぶと良いかもしれません。
資格の難易度が高くなれば、その分参考書やスクールなどの費用、受験費用も高額になる可能性があるので併せて確認しておきましょう。
6.4. 資格を取得するための方法を調べる
実務経験の有無や、短大・大学卒業以上など取得条件が設けられている資格があります。資格によっては試験日が数年に一度だったり、試験会場が遠方で出向くのが困難だったりするケースもあります。
また、資格取得後も定期的な登録手続きが必須、あるいは継続学習で単位を取得する必要があるなど、更新に費用が発生するかもしれません。
資格の勉強をはじめる前に、要件や条件を満たしているのかをチェックすることが大切です。
スキルアップを目指すなら
まずはプロにご相談ください
マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >
7. まとめ
資格を取得することで、スキルアップやキャリアアップにつながり、理想の働き方を実現できる可能性があります。
まずは理想とする将来像を明確化させて、自分に適した資格を見つけることが大切です。
資格取得のための勉強は、中間目標を立てて計画的に着手し、効率的かつ着実に合格を目指しましょう。
\転職するか迷っていてもOK/
マイナビ転職エージェントに無料登録して
転職サポートを受ける