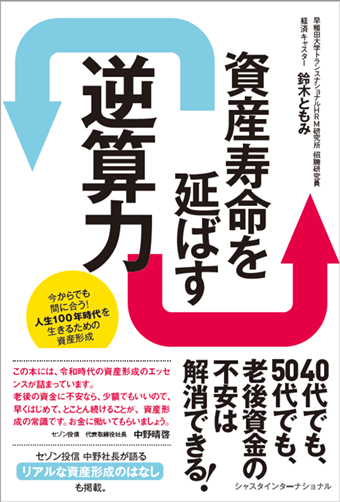平家物語は作者不明とされていますが、実在した歴史上の人物が数多く登場します。紫式部の『源氏物語』は、登場する貴族たちの名前も人物像も、今の私たちの社会や生活とは別次元の世界が表現されている作品です。
一方、『平家物語』は、今の私たちの社会や組織のあり方、仕事人としての覚悟など、相通じる場面がいくつも出てきます。
そのまま自分たちの身近な出来事として共感したり、参考となったりするような物語やエピソードが存在するのです。
また、『平家物語』に描かれている12世紀は、長い日本の歴史のなかでも、貴族社会から武士社会へと転じる大きな変貌を遂げる時代でもありました。今の日本もめまぐるしい国際情勢の変遷や急速なグローバル化、デジタル化という新たな潮流を迎えています。
様々な観点で『平家物語』から学び得ることは数多くあると言えそうです。
今回は、『平家物語』のなかでも哀話の筆頭格と言え、あの織田信長が好んだ伝統芸能「幸若舞」の一節として知られる『敦盛最期』を取り上げ、現代の生き方や日常と照らし合わせつつ考えてみたいと思います。
古典講師歴37年、大学受験生を始め、若い世代に向けてわかりやすい古典解説と、古典作品の魅力を伝え続けている中西光雄先生に詳しくうかがいました。
--------------------------------------------------------------------------
[平家物語より『敦盛最期』]
【あらすじ】
一の谷で敗北した平家軍は総崩れとなり、海を渡って退却した。源氏の武将・熊谷直実は、敵の大将と一騎打ちするため、海岸で待ち伏せしていた。
そこへ、美装の一騎が現れ、沖の船めがけて海に馬を乗りいれた。
熊谷は大声で「貴殿は大将とお見受けした。敵に背を向けて逃げるとは卑怯千万。戻られよ」と、叫ぶ。すると武者は引き返した。
熊谷は自分の馬を武者の馬に押し並べて、むんずと組みついて、どうっと馬から地面に落ちた武者を押さえつけて、首をかき切ろうとした。ぐっと相手の甲を仰向けにし、顔をのぞきこむと、その年齢は十六、七ほど、薄化粧をし、お歯黒を染めた若武者である。ちょうど我が子小次郎と同年くらいで、大変な美顔であった。
「いったい貴殿はどんな身分の方か。名乗られよ。お助けいたそう」
「そう言うそなたは何者か」
「名乗るほどでもないが、それがしは武蔵の国の住人、熊谷次郎直実と申す」
「それなら、そなたにとって、この私は極上の相手だ。名乗らなくとも、首を取ってから人に聞いてみよ。知っている者が必ずいよう」
それを聞いた熊谷は、
「あぁ、実に立派な大将だ。この人一人討ち取ったとて負けと決まった平家が勝つはずもない。またお討ち申さなくとも勝ちと決まった源氏が負けるはずもない。小次郎が軽傷を負ったのでさえ、この直実は親として胸を痛めたのに、この人の父は我が子が討たれたと聞いて、いかばかりか嘆くことであろう。あぁお助けしたいものだ」
と思い、後ろをきっと振り返ると、源氏の土肥、梶原が五十騎ほど率いてこちらに向かっていた。
熊谷は涙をおさえて
「お助けしようと思ったが、わが軍勢は雲霞のごとくおります。貴殿を見逃がすことはないでしょう。人の手におかけするぐらいなら、同じくは、この直実の手によってお討ちし、のちの供養をいたそう」
と告げた。すると若武者は、
「ただ、早く早く首を取れ」と答えた。
熊谷はあまりにも哀れで、どこに刀を立てていいものやら、目がくらみ、気も遠くなり、前後不覚に陥ったが、そのままでいるわけにもいかず、泣く泣く若武者の首を斬った。
「あぁ、弓矢を取る武士の身ほど情けないものはない。武芸の家に生まれなければ、
このようなつらい目に会うこともなかったものを。非情にも討ってしまった...」
と、熊谷は袖を顔に押し当てさめざめと泣いた。
やがてそうもしてられないと、鎧直垂を切り取って、それで首を包もうとしたところ、若武者が錦の袋に入れた笛を腰に差しているのに気づいた。
「あぁ、いたわしい。今日の明け方も城内で管弦を奏していたのはこの人たちだったのだ。今、我が軍に束国の軍勢が何万騎もいるであろうが、いくさの陣に笛を持つ人などいるはずもない。身分の高い貴人はやはり風雅なものだ」
と感心して、義経のもとにこの笛を持参してお目にかけたところ、居並ぶ参謀たちもみな涙を流した。
のちに聞けば、この若武者は、修理職大夫、平経盛の子息で大夫敦盛、当年十七歳であった。
それが契機となり、熊谷は出家の志を強く固めた。
この笛は、笛の名手であった敦盛の祖父の忠盛が鳥羽天皇から賜ったものであると言う。その笛の名は小枝と言った。
狂言綺言も仏道に入る機縁となるとは言うものの、この笛の一件が、熊谷が仏道を
仰ぎ讃える原因(ゆえん)となったのは、心に響くものがある。
--------------------------------------------------------------------------
――前回の解説で、『平家物語』は日本人の感情のコレクションであることを教えていただきました。そのなかでも、『敦盛最期』は哀話の筆頭格として知られ、落涙最多の物語であると言えるのかもしれません。
『敦盛最期』は『平家物語』においてどのような位置づけにあり、またどのようなメッセージが込められている作品なのでしょうか?
一の谷の合戦は、源平合戦における平家の敗北を決定づけた戦いでした。源氏の内部抗争により、劣勢からの立て直しをはかった平氏でしたが、難攻不落といわれた一の谷の陣を、小さな兵力しか擁しない源義経軍によって打ち破られ、敗走することになったのです。「鵯越の逆落とし」の場面は特に有名で、勇気をふりしぼって断崖絶壁を馬で滑り降りる源義経とその家臣たちから、次々にヒーローが誕生します。軍記にとって、もっとも華やかで記憶に残る名場面といってよいでしょう。その中にあって、青年武士・平敦盛が初陣で殺害される『敦盛最期』の話は悲劇としかいいようがなく、人の生と死について多くの示唆を与えてきました。能『敦盛』、幸若舞『敦盛』、文楽・歌舞伎『一谷嫩軍記』など、多くの芸能の題材となったのも当然といえます。

――『平家物語』は軍記物語、つまり戦争の物語です。「死にざま」を描くことは同時に壮絶な死に至る「生」を照射することであるとも解釈できます。人の死が身近であった時代だからこそ「生きざま」「死にざま」の潔さが、若干17歳の若武者・敦盛にも備わっていたと言えるのでしょうか?
第一回で取り上げた那須与一は、肝の据わった若き武士で、高度な弓矢のテクニックによって一躍ヒーローとなりました。一方、平敦盛も、誇りと覚悟をもった若き武士です。初陣で敵に首を掻かれるという、まことに悲劇としかいいようのない状況にあって、敦盛は従容として自らの死を受け入れているように見えます。自らの命そのものよりも大切な価値、大義に殉ずる覚悟を敦盛は持っていた。そしていざという場面で、少しも動じることなく生を全うするのです。その潔さに、敦盛と同じ年頃の子を持つ熊谷直実も感涙を禁じ得ない。だからこそ自らの手で敦盛の首をとったのでした。まことに、私たちの心の琴線に触れてくる愁嘆場です。しかし、ここで流される涙は、老少不定や逆縁を悲しむ涙ではありません。自らの命を越える大義に生き、大義の前で従容として死んでゆく若者への深い共感の涙なのです。敦盛は、武士としてのプライドに殉じたのでしょうか。むしろ死の美学を憧れとしていたのでしょうか。そうではありません。彼は、死を越える生の大義を知っていたからこそ、死を怖れなかっただけなのです。そういう意味で、敦盛の生きざまは世俗的なものでなく、宗教的な感覚に貫かれていたといってよいでしょう。だからこそ、この一件ののち、熊谷直実は出家して仏道に入るのです。ことわざの「武士は食はねど高楊枝」のような形骸化したプライドや、『葉隠』の「武士道といふは死ぬことと見つけたり」のような冷静な死の哲学ではなく、強烈な「生」の実存が敦盛の姿には投影されているように思います。
――前回、「平清盛は権力者としてのロール(役割)を生きているという自覚が持てない人物であった」という解説がありました。一方、この物語において、敦盛も熊谷も自身のロール(役割)を最期まで果たし切っているように感じます。現代のビジネスシーンにおけるロールと、この時代におけるロールの位置づけや価値に共通することはあるのでしょうか?
「身の程意識」という言葉は、ネガティブに使われがちです。『源氏物語』の明石の君は、光源氏から惜しみなく自身に注がれる愛情に対して、「取るに足らない」「つまらない」と自己卑下を繰り返します。それが「身の程意識」ですが、「かしこきもの」=畏怖・尊敬の対象としての光源氏との関係性が、彼女のすべてだからからそう表現されるのです。平敦盛や熊谷直実らすぐれた武士は、もちろん「身の程」をわきまえていました。出自・身分や武芸のスキル、そして教養の高さが、彼らの「身の程」を決定してゆく要素です。封建君主との契約も常に意識しなければなりません。しかしその上で、すぐれた武士は、自分の生を成り立たせている普遍的な大義、命より大切なものの存在を知っているからこそ、自らの「身の程」と折り合いをつけて生きてゆけたのだとも思います。自らが世の中を取り仕切っているという清盛のような万能感とは逆の、世界の摂理の中で生かされているちいさな自己=「身の程」を自覚しているからこそ、自らのロールを社会から与えられたものとして全うできる。この感覚は、現代のビジネスパーソンにも共通する生の技術ではないでしょうか。宗教が後退した現代で「大義」を語ることはたいへん難しいことですが、「命の尊さ」であれ「地球環境」であれ「公共性」であれ「エシカル」であれ、自分にとっての「大義」を探し続けることが、自らのロールに自覚的になる唯一の方法のように思います。
――今、私たちを取り巻く環境において、リモートワークやテレワークが増えたり、仕事の量や質に変化があったりと、今後の自身の立場や将来に不安を抱く方も増えています。自身のロール(役割)を失うことへの戸惑いや不安はいつの時代も同じだと思うのですが、『平家物語』を通して得られる教訓はありますでしょうか?
今回の新型コロナウイルスの蔓延によって、私たちの生活や労働のスタイルは大きな変化を経験せざるをえないでしょう。ウイルスによる直接的な生命の危機が過ぎ去ったのちも、私たちには深い恐怖心と猜疑心が残るに違いありません。社会の分断がより明らかになり、ビジネスのあり方も、働き方も大きな変質を余儀なくされるはずです。『平家物語』が描く戦乱は有事です。そして現在の世界もまた有事そのものです。『平家物語』から私たちが教訓を得るとしたら、それは戦乱の中にあって、「ポストウォー」=戦後の世界を常に思い描くことだと思います。敦盛と同じく、一の谷の戦いで死んだ平忠度は、藤原俊成の弟子で歌人でしたが、都落ちの前に俊成のもとに赴き、自分の詠んだ歌を師に託します。戦乱が終わり、平和が訪れたら勅撰和歌集が編纂されるだろう。そのときに、私の歌を一首でよいから、「詠み人知らず」として入集させてほしいとの願いを添えて。俊成は、戦乱が収束したのち、自らが編集にあたった『千載和歌集』に平忠度の歌を掲載しました。
さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな
戦乱はいつか終わります。私たちもいつかは死にます。しかし、死を越えた価値が、「大義」があることを見据えて、変化を怖れず前向きに生きる。『平家物語』は、そのようなことも私たちに教えているように思います。
--------------------------------------------------------------------------
古典講師プロフィール
中西光雄氏
古典講師。音楽研究にも精通。1960年、岡山県生まれ。
国学院大学大学院博士前期課程修了。博士後期課程中退。(元河合塾専任講師)。
専門は日本文学・日本政治思想史。著書に『蛍の光と稲垣千頴』(ぎょうせい)、
共著に『唱歌の社会史』(メディアイランド)、『高校とってもやさしい古文』(旺文社)など。
著者プロフィール

鈴木ともみ(すずきともみ)氏
経済キャスター、国士館大学政経学部兼任講師、ファイナンシャル・プランナー、日本記者クラブ会員記者。
早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員、多様性キャリア研究所副所長。
埼玉大学大学院人文社会科学研究科経済経営専攻博士前期課程を修了し、経済学修士を取得。地上波初の株式市況中継TV番組『東京マーケットワイド』や『Tokyo Financial Street』(ストックボイスTV)にてキャスターを務める他、TOKYO-FM、ラジオNIKKEI等、ラジオ番組にも出演。国内外の政治家、企業経営者、ハリウッドスター等へのインタビュー多数。