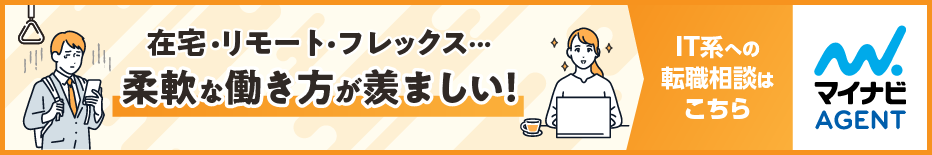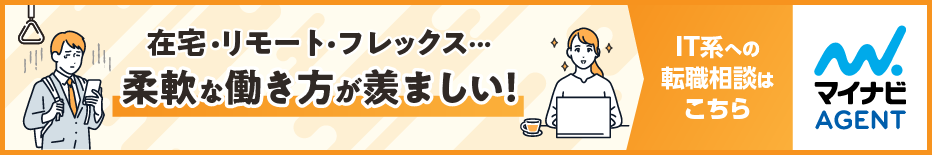ここ最近になって良く聞く「DX」という単語、当たり前のように使う人も現れてきて、今更詳しく聞けない雰囲気を感じているかもしれません。
DXは"Digital Transformation(Trans=X)"の略というのは聞き飽きたかもしれませんが、直訳するとデジタル変革、意訳すると「デジタル技術を活用して変革を起こすのだ!」といったところでしょうか。実はDXの画一的な定義は存在しません。様々な組織・個人がレポートや発言の中で「私の考えるDX」を示しています。ただ、範囲を絞っていけばある程度の解釈に落ち着いていくものでもあると思っています。
今回はそんなDXについて、前編・後編に分けて解説をしていきます。前編では概要として「DXとは何か」、「DXを進める意義」、後編では具体的に「DXの進め方」、「DX時代に求められる人材」について解説します。この記事が一人でも多くの方々の理解の一助となれば幸いです。
1.DXとは--学者が発表した概念から
DXは2004年、スウェーデンのウメオ大学の教授であったエリック・ストルターマン氏によって発表された論文「INFORMATION TECHNOLOGY AND THE GOOD LIFE」の中で初めて提唱された概念とされています。原文はかなり難解ですが、文章およびその後の同氏の発言を勘案すると「情報技術が進むことにより現実世界とデジタル世界が不可分に融合していく、その継続的な融合が全ての人々の生活に影響を与えていく」といった内容となります。
例えば、今や、音楽・映画はインターネット上のサーバにデジタルデータとして保管されており、インターネット配信(ストリーミング)という形で好きなタイミングで楽しむことができるようになりました。私も2つのサービスを契約しており、自宅にある数千枚のCDやDVDを利用することはなくなりました。多くのお金を投じて購入したCDやDVDの利用価値がなくなることは悲しいのですが、今ではインターネット配信の価値も感じており、総合的に見て、個人的には良い影響と捉えています。
ただ、一連のサービス体験の中で、使われている仕組みの存在に気をとめる人は少ないでしょう。どのような技術が使われているのか、なぜこの価格で抑えられているのか、提供した個人情報はどうなっているのか、もしかしたら私たちの個人情報が意図せぬ相手に渡り悪用されているかもしれません。これはよくよく立ち止まって考える必要がある点だと思いますが、情報技術の活用、顧客視点による利便性追求、変革のみに囚われると、個人情報の問題のように悪い影響が私たちの生活を脅かすかもしれません。
現実世界とデジタル世界が不可分に融合した世界の分かり難さが生む危うさ、持続可能で社会に受け入れられる変革の大切さについてストルターマン氏は警鐘を鳴らしています。「デジタル技術を活用して変革を起こす」ことにとどまらず、人間の生活に対する影響の光と影の存在にまで言及しているのが、同氏による概念の特徴だと思います。

2.概念から具体的なDXへ
前項で見てもらったように、ストルターマン氏の概念は抽象度の高い内容となっています。同氏も認めているように、ここからどのようなDXが展開されるかは各国、各企業がおかれた状況よって異なっていきます。従って、DXという単語の使い手(立場、思惑など)や文脈によって意味するところは異なっていきます。商売に利用するためだけに、拡大解釈して利用する人も出てくるでしょう。これがDXを理解するうえでの障壁となっています。
例えば、ドイツにおいてはGDPに占める製造業の割合が大きいこともあり、DXは製造業を中心に展開されていきます。2011年にドイツ政府は「Industrie4.0(第4次産業革命)」という製造業の未来構想を打ち出します。ざっくり言えば「スマート工場の実現」ですが、具体的には、製造設備をネットワークに接続、さらに各工場をネットワークで結び、AIなど先端デジタル技術の利用により生産性を高め、多様化した顧客の要求に応じて製品を1個から生産できるという「マス・カスタマイゼーション」というものがあります。これが本当に実現できれば、世界市場において競争優位を築き、第二次産業革命時のような強いドイツの復活が実現するかもしれません。しかしながら、実際にはそんな理想通りには進んでいないとの報告もあり、自国の製造業を売り込むためのプロモーションとして利用している思惑も見え隠れしています。

3.日本におけるDX
日本も負けてはいられません。2015年に政府は「Society5.0」という社会の未来構想を打ち出します。内閣府のホームページには「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」とあり、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く未来社会を描いています。

まだ漠然としていますね。さらに範囲を絞っていきましょう。経済主体には家計・企業・政府とありますが、DXを考える上では特にサービスを提供している企業・政府にどうやら関係がありそうです。政府のDX(電子政府など)もありますが、ここからは私たちに身近な企業に焦点を絞り、企業におけるDXを紐解いていきたいと思います。
4.日本企業におけるDX--これまでの情報システム投資、既存システムの問題
まずは、企業がおかれた現状から理解していきましょう。2018年に経済産業省が「DXレポート」を発表していますが、これが企業のおかれている現状を理解する上で役に立ちます。レポートの中では、DXを進める上で企業が持つ既存の情報システムが足枷になっているとしていて、早急な見直しが必要であると報告しています。国が企業のシステムに口を出すのは異例なことですが、現状に対する相当な焦りが見て取れます。
多くの企業は、自社システムを情報サービス企業(ベンダ企業)に外注して作ってきました。企業の要望は、社内調整が容易なこともあり、現状の業務に合わせてゼロから作り上げるシステムであり、ベンダ企業側も開発要素が多いほど売上を確保できるため、それに迎合してきました。結果的に、これまでのシステム投資においては「既存業務をITにより置き換える」ことが目的となっていました。
システムが完成した後は、企業の外部・内部環境の変化に合わせて機能追加やカスタマイズが繰り返され、肥大化していきます。一方で、ITエンジニアやノウハウの多くは外注先のベンダ企業側に蓄積されるという構造的な問題、企業側有識者の退職などによりシステムはブラックボックス化していきます。その結果、IT予算の8割が既存システムの運用・保守に奪われているという現状があります。この問題を放置するとさらに、セキュリティの欠陥、古い技術を扱う技術者の不足といったものが顕在化し、負のスパイラルに陥っていきます。後述するDXを推し進める上で既存システムの問題処理(それによる投資予算の確保)は待ったなしの状況です。
5.日本企業におけるDX--変革のDX
経済産業省が発表している各種レポートにおいては、DXの定義を「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としています。
デジタル技術についてはこれまでも活用されてきました。銀行の窓口業務をATM、鉄道の改札業務を自動改札といったように、人が行っていた業務をコンピュータやネットワークといったデジタル技術を活用して置き換えてきました。ただ、前項の通り、これまでは主に既存業務をITにより置き換えることが目的でした。
これに対してDXは変革がキーワードです。既存業務ありきで考えるのではなく、顧客・社会のニーズと活用できるデジタル技術を鑑みて、どのような製品・サービスを提供するか、どのように競争優位を築くかというアプローチで考えていく必要があります。
クラウド・IoT・AIといった先端デジタル技術を活用するのがDXといった表現も一部見受けられます。確かにこのような技術を活用することで次の展望(例えば、データをクラウド上に集約することで、クラウド事業者が提供しているAIエンジンを安価に活用することができるなど)を描きやすくなるという側面はあります。ただ、デジタル技術の内容というよりは、デジタル技術を活用した製品・サービスの変革、ビジネスモデルの変革、それを支える業務・組織・プロセス・文化・風土の変革、それによる競争優位・利益の確保がDXの本質となります。

6.日本企業におけるDX--進めるうえでの課題
ここ数年、経営者の大号令「AIを使って何かやるのだ」を受けた検証プロジェクトが数多く生まれました。ただ、本格的なDXへとつながらないのが日本企業の課題と言われています。
そもそも、DXを推し進めるということは、製品・サービスのターゲットや提供する価値、オペレーション、経営資源の見直しなどが必要であり、新規事業を興すに近しいエネルギーが必要となるため、すべての試みが成功するわけでもないと思います。
ただ、先端デジタル技術に囚われ、全社・事業戦略のない中でDXを期待するのは根本的な問題なので、ここは変わっていく必要があるでしょう。
その上で、DXを推進できるDX人材(後編で解説予定)が必要なのですが、残念ながら圧倒的に不足しているのが現状です。また、最終的なシステムのゴールが定まらない中で試行錯誤しながら作り上げていくことになるため、企業とベンダ企業間の契約内容や開発手法の見直し(アジャイル開発の導入など)も必要となってきます。
また、守りの存在であったシステム投資ですが、今後は攻めの投資として経営者の強いリーダシップのもとDXを推し進める必要があります。これまで、システム開発規模が大きくなるほど、仕様通り、予算通り、納期通りに作ることが重要視され、ベンダ企業が多くのリソースを動かせることは提供価値の1つとなっていました。ただ、これからのDX時代においては、経営者と伴走し、企業の製品・サービスの価値向上にいかに寄与できるかを考え、いかにソリューションを提供できるかが価値になってくると意識を変える必要があります。
7.DXを企業が進める意義
企業が進める意義は主に以下の2点です。
1.(ネガティブ)進めないと既存のシステムが重荷になる
2.(ポジティブ)競争優位を築き競合に打ち勝つことができる
「DXレポート」では2025年の崖と表現していますが、既存システムの問題を放置することにより今まで以上に運用・保守費用が高騰していきます。また、多くのエンジニアは新しくて将来性のある技術に携わり経験を積みたいと考えますので、人材確保も難しくなり、目が届かなくなったシステムは弱くなっていきます。このような負の連鎖により、ますます未来への投資に使えるお金が無くなっていきます。
しかしながら、既存のシステムを上手にリノベーション、負担を軽くし、そこで生まれた余剰を使ってDXを推し進めることで、競合が簡単には真似できない仕組みを手にすることになり、競争優位が生まれます。
身近なDXの具体例としては、マクドナルドのモバイルオーダーが分かりやすいかもしれません。マクドナルドを食べたい、でも週末の行列を考えると二の足を踏むといった経験を持っている方も多いと思います。モバイルオーダーは現場で働くクルーからすると既存の業務の変更や、短期的にみると業務量の増大につながるかもしれず、抵抗したい内容かもしれません。ただ、顧客からすると二の足を踏まずにマクドナルドを選ぶ理由の一つになります。まさに顧客のニーズに寄り添い、デジタル技術を活用してサービスに変革をもたらしたものだと言えるのではないでしょうか。これはマクドナルドの競争優位につながりましたが、さらにこのモバイルオーダーのデータを蓄積・分析することにより需給バランスを最適化できる可能性があり、それが実現されればますます競争優位が強固なものとなっていくと予想されます。
8.まとめ
前編では「DXとは」、「DXの意義」について紹介しました。
ストルターマン氏の概念が放ったシグナルは約15年の時を経ていよいよ強いものとなりました。日本企業がDXを成し遂げて甘い果実を得るためには、抱えている既存システムの問題、人材や環境など各種課題を着実に解決していく必要があります。その中で、ITエンジニアも大きな変化を迫られているのかもしれません。
後編では「DXの進め方」、「DX時代に求められる人材」について紹介していきます。
【会社概要】株式会社BFT
東京、名古屋にてシステムインフラの強みを活かした基盤構築自動化サービスやIT技術の教育サービスなどを展開している。
WEBサイトはこちら。